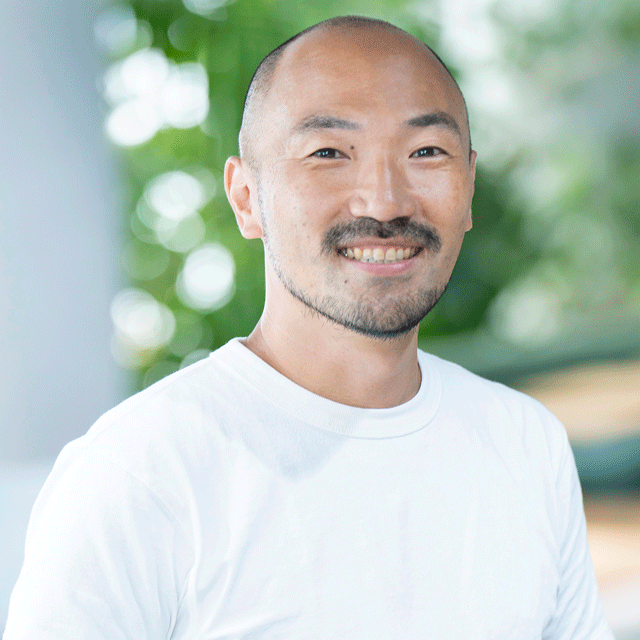企業活動において「サステナビリティ」の重要性は高まる一方です。自社とステークホルダーのサステナビリティをどう考え、どういったアクションを起こしていくかは、最重要課題の1つであると言えます。
そして今、DXに代表されるさまざまなトランスフォーメーションがテーマになる中で、「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)」に対する注目も高まってきています。SXとは一体何なのか、SXを自社に取り入れるにはどうしたらいいのか。本記事では、株式会社電通PRコンサルティング サステナブル・トランスフォーメーションセンターに所属する石井裕太氏と横川愛未氏にインタビュー。SXを推進する最前線にいる2人から、SXの定義や導入のポイント等について、現場ならではのリアルなお話を聞きました。
SXとは「存続に値する会社へと変革すること」
Q.石井さんと横川さんは、電通PRコンサルティングの中でも「サステナブル・トランスフォーメーションセンター(SXセンター)」という部署に所属しています。シンプルな質問ですが、このSXセンターとは何をするチームなのでしょうか?
SXについて、さまざまな説明があるかと思いますが、日本においては2020年8月、経済産業省の「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」が「社会のサステナビリティと企業のサステナビリティを同期化し、長期の時間軸の中で、社会課題を経営に取り込むことで企業の稼ぐ力を強化していくこと」としてSXを提唱し、広がったような気がします。
私たちは、そのSXを「存続に値する会社への変革」と捉えています。つまり、「事業で利益を得る」と「社会課題を解決する」を両立できる、存在意義のある企業へと変革すること、と定義しています。
そう捉えたときに、企業が社会とより良い関係を築く「パブリックリレーションズ(PR)」を生業にする私たちがSXを推進する意味が出てくると考えています。例えば、PRの手段の1つであるCSRの「Responsibility(責任)」は、社会の課題にきちんと対応(Response)するだけの力(Ability)を企業が持ち合わせているのかを示すことを意味します。さまざまな社会課題が構造的に複雑化する現代において、それに応えられる企業であるかどうか。これらをしっかり示していくための活動です。そこにはコミュニケーションも重要な活動になる。だから、私たちがSXと向き合う必要があると考えています。
これを踏まえて、私たちのチームがどのようなことをしているかというと、「社内外のステークホルダーから選ばれ続ける会社になるために、顧客企業に伴走する」ということです。事例を1つご紹介すると、とある企業の「ダイバーシティ研修プログラム」の開発にご一緒しました。発端は、その企業にお勤めのセクシャルマイノリティの社員が「会社は多様性を尊重すると言うが、経営層も社員もLGBTQ+のことをきちんと理解していないのではないか」という課題意識を持ち、それを社内に提言したことでした。そしてまず社内向けにアライ(=LGBTQ+の理解者・支援者)を育成する研修プログラムを、当事者の社員と外部のNPOと一緒に開発したのですが、これが好評だったことを受け、取引先や自治体など社外にも広く無償で提供する、ということになったのです。そして、メディア報道などを通じてその取り組みが知れ渡り、結果的にステークホルダーからの評価が高まりました。一方、社内においては「多様性を正しく理解しよう」という姿勢が行動につながり、事業のブランディングや新規事業の開発にも展開されていくようになった。こういったさまざまなインパクトを社内外に生み出し、企業が社会課題を持続的に解決していけるサイクルづくりに伴走させていただいて、まさに一緒にやっていく、というようなことを実践しています。

Q.石井さんたちが所属するSXセンターは2022年の1月に発足したと伺いました。組織としては新しいのですが、もともとそういったニーズや依頼はあったのでしょうか?
その理由は2つあって、1つは時代的な背景ですね。2016年頃からSDGsが普及し、「宣言はしたものの、具体的に何をしたらいいか分からない」というご相談をいただくようになりました。まずはパーパスをきちんとつくり、自社の社会的存在意義を言葉に落とし込んで社内外に浸透させたい。そして、最近では「人的資本経営」、つまり「人材をコストではなく資本(投資)として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる」ことを実装させたい。そして、そのアクションや生み出した社会的インパクトが、しかるべきステークホルダーにきちんと伝わるような、攻守一体型のコミュニケーションを展開したい。こういった相談が増え続けています。
そしてもう1つの理由は、当社が15年前から取り組んでいる「パラスポーツ支援」が評価されたからだと思います。私たちがパラスポーツの世界に飛び込むきっかけになったのは、2007年に、パラアスリートの大日方邦子(冬季パラリンピック アルペンスキー金メダリスト)が当社に入社したことなのですが、その大日方と社員有志が、PRの知見を生かしてパラスポーツの普及・発展に向けて自主的に取り組み始めたのです。具体的には、競技団体や選手、報道や企業の関係者を巻き込んで、「パラスポーツメディアフォーラム」という勉強会を7年間で32回開催し、パラスポーツに関する報道や企業支援の活性化に貢献してきたんですね。そして、社会的なインパクトを生み出した取り組みとして、国内外で評価(※1)を頂いたことも、ご相談が増えている背景にあります。このアクションもまた、先ほどご紹介した「ダイバーシティ研修プログラム」と同じで、1人の社員の課題認識が起点ですね。
PRエージェンシーならではの、SXを推進する3つの視点
Q.サステナビリティやSXといった領域がホットなトピックであるということは、そこにはさまざまなプレーヤーが存在している、ということだとも思います。その中で、石井さんたちのSXセンターというチームの強みは何でしょうか?
1つ目のPは、People。その企業のESGアクションは、「社員」が起点になっているかどうかです。もちろん、企業トップによるメッセージ発信は大前提として大事ではあるのですが、その企業の「らしさ」を体現するのは、1人ひとりの社員が思いをもって取り組んでいるというファクトです。社員や店頭スタッフの「神対応」がSNSで拡散されニュースになるような時代だからこそ、社員の発言や行動が企業のブランディングに大きく影響します。
2つ目のPは、Partnershipです。自治体や学校、企業などとの「連携」を通して、より大きな社会的インパクトを生み出していくことで、世の中の共感を得ていきます。中でも、NPOや社会起業家など現場の最前線にいるさまざまなソーシャル・イノベーターとの連携は、複雑化する社会課題の根本に切り込み、その企業しかできないアプローチが価値になります。
そして3つ目のPは、PESOですね。Paid、Earned、Shared、Ownedの各メディアを全体最適化し、ステークホルダーに魅力的に伝わるコミュニケーション活動にまで落とし込むことです。これは社外向けだけではなく社内向けも非常に重要で、サステナビリティ領域についての取り組みは社員全員のモチベーションやエンゲージメントに大きな影響を与えます。
私たちは、これら「3つのP」を起点に、企業本位になりがちなESGに対して、ステークホルダーが共感できるアクションづくりとコミュニケーションをお手伝いしています。
「コミュニケーション」と「アクション」の両輪でSXは進んでいく
Q.本質的なところを考えてみたいのですが、そもそもSXとは、今の企業にとって本当に必要なのでしょうか?うがった視点で言うならば、「SXに注力すれば、企業成長につながるのか?」という質問になるかもしれません。
Q.SXに取り組もうとしている、あるいは取り組んでいるけれどうまくいっていない、という企業に共通の特徴や課題はありますか?

「事業推進」と「社会課題解決」を両立し、「存続に値する企業」へ。それがSXの本質だと、SXセンターの2人は語ります。目先の売り上げや話題づくりにとらわれることなく、中長期的な目線をもって責任を果たしていくことが、結果として企業の成長を促すことにつながっていくのかもしれません。
後編では、SXを推進するためのアプローチ方法や、マインドセットの部分をより深く掘り下げていきます。
本記事を読んで、SXに関して具体的なアクションを起こしたいという方はもちろん、既に何か取り組みをしているがアップデートしたい、よりシンボリックな取り組みをしたい、などお感じになりましたら、ぜひCONTACTからお声がけください。
※1 PRアワードグランプリ2021、PR Awards Asia 2022、Golden World Awards 2022など受賞