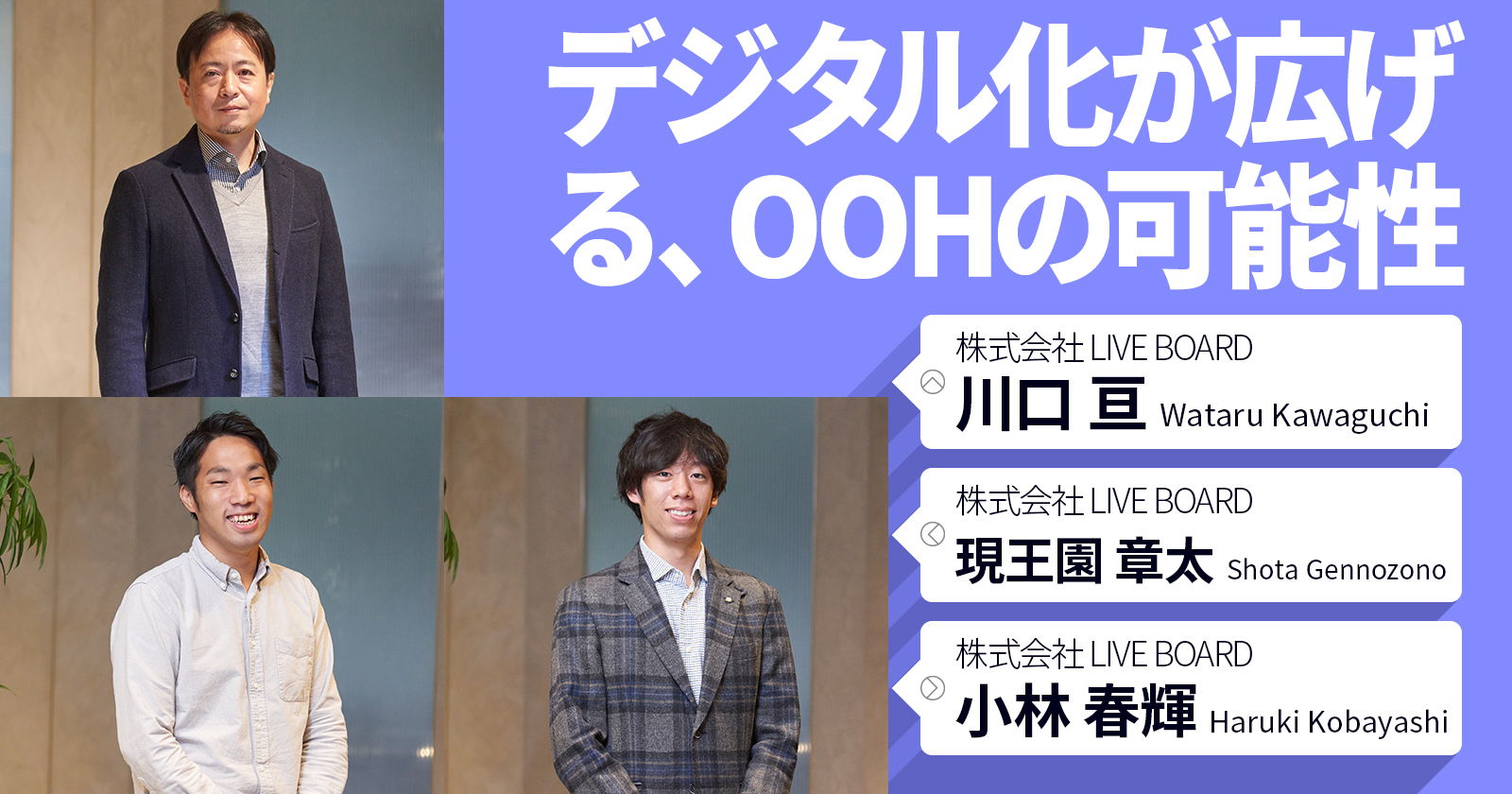広告に関わったことがあれば「OOH(Out Of Home:屋外広告)」という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。では、「DOOH=デジタルOOH」についてはいかがでしょうか。OOHは、広告の形態としては歴史が深く、そういった意味ではトラディショナルなものだと思っている方も多いかもしれません。しかし、デジタルサイネージの普及によって、OOHの可能性は大きく広がっているのです。
そこで本記事では、デジタルOOHを専門に扱う、株式会社 LIVE BOARD(ライブボード)の川口亘氏、現王園章太氏、小林春輝氏にインタビュー。OOHが「デジタル」になってどう進化したのか、そして企業からはどのような相談が来るのか、といったリアルな現場の話を聞きました。全ての広告担当者はもちろんのこと、マーケティング担当者にとっても、デジタルOOHの現在地をあらためて知るためにお役立ていただければ幸いです。
OOHが「デジタル」になって、できることが大きく広がった
Q.最初に、「LIVE BOARD」とはどのような会社なのか、ご説明いただけますか?

私たちは、約80個のデジタルOOHを保有していて、それらの販売事業者でもありますが、他事業社が運営しているデジタルOOHとも連携させていただいており、総数で言えば1万6000面程度を取り扱うことが可能。「デジタルOOHのプラットフォーマー」としての機能を果たしているといえます。
Q.今でこそ、街中でさまざまなデジタルサイネージを見かけるのは当たり前になっていますが、かつてOOHが「デジタルOOH」に進化した時には、どのくらいのインパクトがあったのでしょうか?
さらに最近は、「3D広告」「巨大広告」とか、これまでにないインパクトを出せるような広告枠も登場してきています。新宿に「巨大な三毛猫」が現れた、という広告について聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
一方で、それを見る生活者視点に立っても変化は起こっています。先ほどのような3D広告などは、明らかに「今までにない新しい表現」として見えていますが、実は意識していないところでも変化が起こっています。例えば、気温によって広告素材が変わっている、というケース。その分、その時の気持ちにフィットした広告が掲出されているので、見ても不快ではなく自然に入ってくる、というケースがあるのです。「屋外で見る広告への不快感が減ってきている」という感覚に、「言われてみれば確かにそうかもしれない」と、思い当たる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

やはりデジタルならではの「リアルタイム性」はポジティブな効果を発揮していると思います。同じ場所のデジタルOOHでも、朝は「行ってらっしゃい」と書いてあり、夜に帰ってくると「お帰りなさい、お疲れさま」とメッセージが変わっている。これだけでも、世の中に対して非常にポジティブな効果をもたらしているのではないでしょうか。
また、単純に「汚れにくい」ので、それだけでも印象はいいですよね。やはり古かったり汚れたりしている広告がいつまでも出ていると、見ていて気持ちのいいものではありませんし、その商品やサービスのイメージも悪くなりかねません。
「ターゲティング」や「プランニング」と「公共性」の両立がDOOHの魅力
Q.古くからある形態のOOHが「デジタル化」するという、そのアナログとデジタルがミックスしている感じ自体も非常に興味深く感じています。
同時に、「出会う場所」にも意味が出てきます。「渋谷の真ん中で見た」ということは、単に「広告を見た」だけではなくて、「なんか流行っているものだ」「渋谷を訪れる層に人気があるんだ」といった印象も同時に与えます。「何を見たか」だけではなく「どこで見たか」「いつ見たか」といったことにも意味が出てくるのは、OOHが元々持っていた価値ですし、デジタルOOHになってその魅力はますます高まっていると思います。
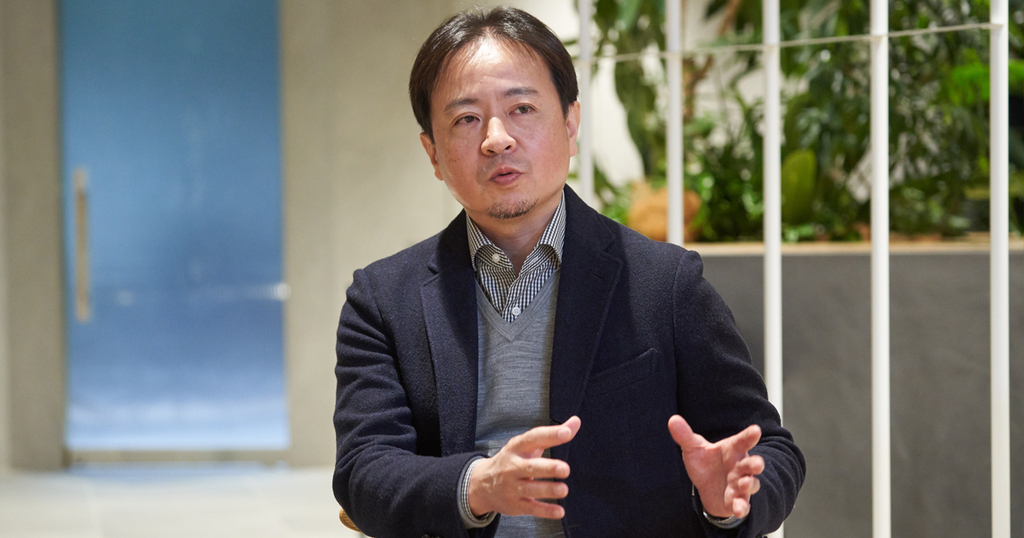
長きにわたって人々に親しまれてきた、OOHという広告形態。それが技術革新により、デジタルOOHへと進化を遂げました。リアルタイムに情報の出し分けを行えるようになったことで、「多くの人に見てもらえる」だけではなく、「見る人の気持ちに寄り添う」ことまでもが可能となっているのです。
続く後編では、デジタルOOHの活用例を「データ活用」などの観点から事例とともに紹介しつつ、LIVE BOARDが描く広告の未来についても詳しく聞いていきます。
本記事を読み、「自社でもデジタルOOHを導入したい」「デジタルOOHを活用した、先進的な事例をもっと知りたい」など、関心を持っていただいた方は、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせはCONTACTから。