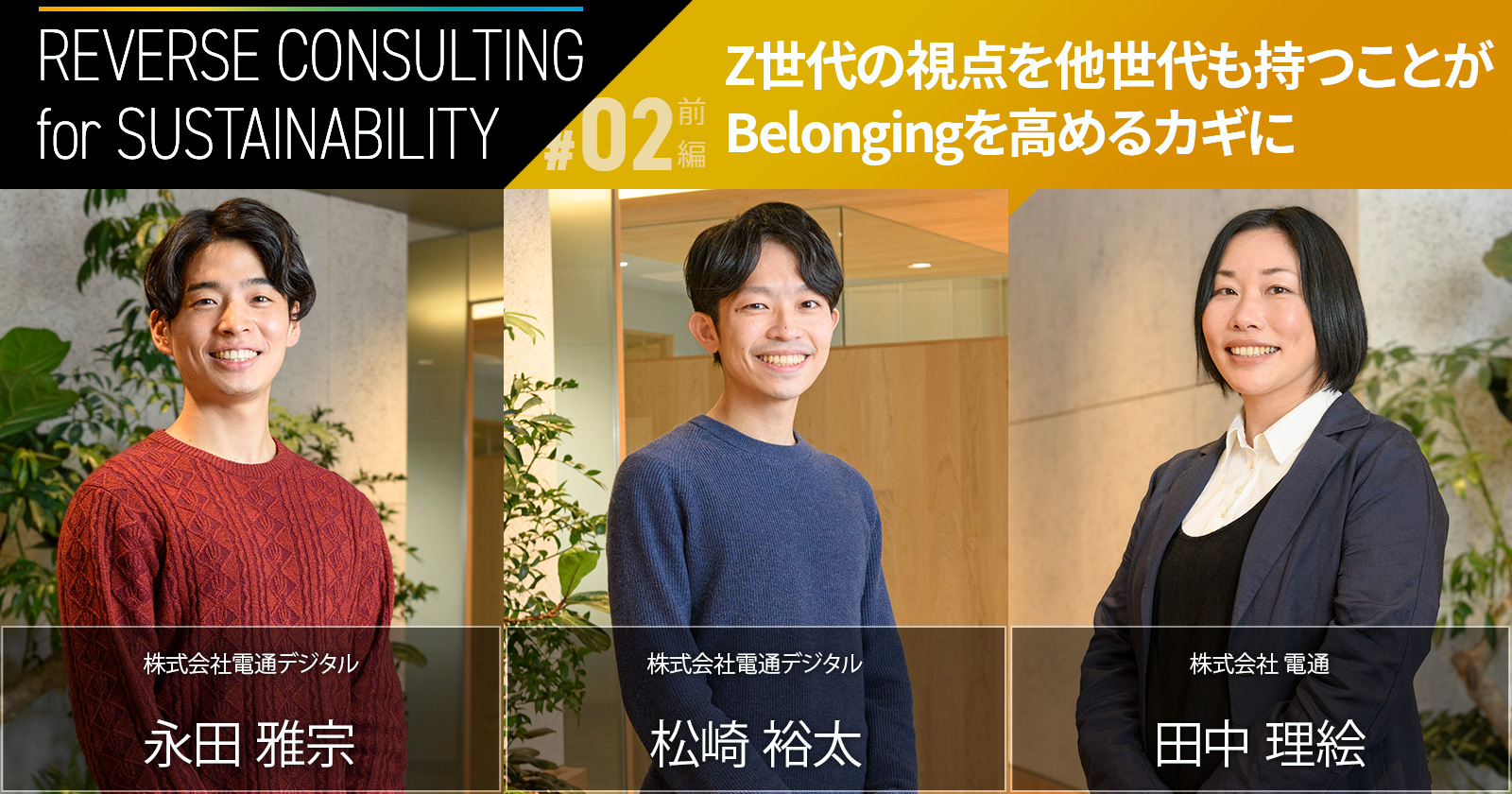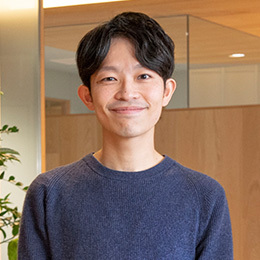電通ジャパンでは、サステナビリティ・ネイティブと呼ばれるZ世代と共に企業のサステナビリティを推し進めるサービス、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」をリリースしました。このサービスに携わる、株式会社電通デジタル「YNGpot.™」共同代表の松崎裕太氏と、コンサルタントを務める永田雅宗氏、そして株式会社 電通 サステナビリティコンサルティング室の田中理絵氏が昨今人事・経営分野で注目されるDEI&BのB(Belonging:帰属意識)についてZ世代視点で読み解き、語り合います。
Z世代の「好き」を生かすカルチャーは、サステナビリティ推進のドライバーに
田中:電通デジタルの「YNGpot.™」は、デジタルネイティブ世代がメンバーにいて、入口のインサイトリサーチと出口の効果検証だけでなく、企画開発の全てのプロセスを「Z世代視点で行う」ところに特長がありますよね。これをサステナビリティ領域のビジネスにすると「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」にそのままつながっていくので、ぜひこれまで進めてきた知見をお伺いできればと思います。まずはYNGpot.™の活動について教えていただけますか?

松崎:前提として、YNGpot.™ではZ世代という区切り方以上に、デジタルネイティブ世代という捉え方を大切にしています。人の行動様式や価値観は、情報量と共に大きく変わりました。結果、ビフォーデジタル世代とアフターデジタル世代の間で、行動様式や価値観の差異が生じていますから、Z世代という世代論よりも「デジタルにどういう関わり方をしているか」という切り口で考えているんです。
田中:デジタルネイティブ世代の視点で行う事業コンサルティングには、どういう特長があるのでしょうか。
松崎:デジタルネイティブ世代が自分たちの不平・不満を解消するために望むサービスや商品には、当たり前かもしれませんが、デジタルを基点にしたものを求めることが多く、企業はそのニーズに適した新規事業や新サービスを、次々に起こしていく必要があります。ただ一方で忘れてはいけないのは、彼らはデジタルを通して、多くの人々の生活とつながることができる世代。自分の満足のために、他者の不幸を見て見ぬフリをできない世代でもあるんです。ですので、サービスを考えるときには、もちろんデジタルネイティブ世代当事者の満足も重要ではありますが、彼らの周囲にいる他者の幸福や、次の世代が率いる社会の幸福まで、どのようにしたら両立できるのか」という視点で、デジタルサービスを開発することや、プロジェクト推進することを大切にしています。
田中:「自分の好きなことを起点に他人の幸福のきっかけもつくりたい」は、Z世代にインタビューをすると、伺うことが多い考え方ですよね。「地球環境のためにというより、最初は自分が好きだから始めました」という言葉が出てくると、Z世代のチェンジメイカー(社会変革・社会課題解決に取り組む人)らしさを感じます。以前、松崎さんと一緒にウェビナーを開催しましたが、その際に登壇いただいた大学生も、「まずやりたいこと・ワクワクすることをやる」と話していたのが印象的で。
松崎:事業を進めるのも、結局は「人」なので、お客さまに満足いただくためにチームが頑張ることはもちろん重要ですが、チームの中にいる自分たちが欲しい、またはチームメンバーの身近な誰かの役に立つと心から信じられるものを楽しんで作り、そこにお客さまを巻き込んでいくという順序の方が、よりデジタルネイティブ世代の良さが生かせるのではないかと思います。
そのためには、顧客企業さまも自社のメンバーも、プロジェクトチームにいる1人ひとりを「労働力」として見るのではなく、まずは人として尊重し合うことが重要。全ての人がマイノリティーな一面を持つ時代ですから、できれば誰もがリーダーシップを取れるチーム状態をつくり、多様な視点から意見が出るチームをつくることが望ましいです。それに加えて、サステナブルな視点を併せ持つことや、社会の変化に柔軟に対応していく姿勢もあれば、さらに良いと思います。
そのためには、顧客企業さまも自社のメンバーも、プロジェクトチームにいる1人ひとりを「労働力」として見るのではなく、まずは人として尊重し合うことが重要。全ての人がマイノリティーな一面を持つ時代ですから、できれば誰もがリーダーシップを取れるチーム状態をつくり、多様な視点から意見が出るチームをつくることが望ましいです。それに加えて、サステナブルな視点を併せ持つことや、社会の変化に柔軟に対応していく姿勢もあれば、さらに良いと思います。
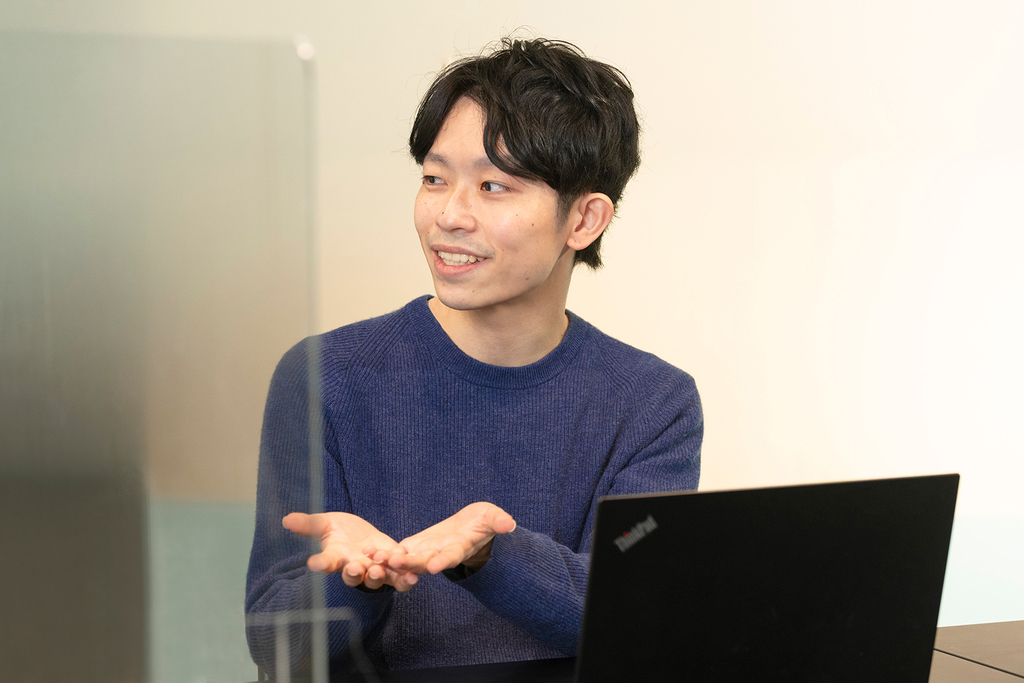
田中:それはすごく、昨今注目のDEI&Bの観点と関連しそうです。DEI(Diversity、Equity、Inclusion)は企業の観点ですが、B(Belonging)は個人の観点と言えます。企業のリソースとしての労働力という捉え方ではなく、「個人の生活や人生の中に、仕事のために使う時間があり、仲間との関係性もある」と捉えることで帰属意識が高まるし、結果として場の安心感につながり、主体性が高まることで、創造性や生産性も高まりますよね。
そう考えると、DXもサステナビリティも、第1回の久志さんの発言にもありましたが、会社ではなくて人を中心に捉え直すことに行き着きそうです。サステナビリティ領域のコンサルティングについてもお考えを聞かせていただけますか?
そう考えると、DXもサステナビリティも、第1回の久志さんの発言にもありましたが、会社ではなくて人を中心に捉え直すことに行き着きそうです。サステナビリティ領域のコンサルティングについてもお考えを聞かせていただけますか?
松崎:DXもサステナビリティ推進も企業変革と捉えると考え方は同じで、現場の担当者や社員が「本気で導入したいかどうか」で成功の可否は決まると思っています。役員陣はもちろんのこと、プロジェクトリーダーから現場社員までを含めた全員が「本気感」を持ち、同じ「ありたき理想像」を見ていないと、DXやサステナビリティの推進が「目的化」されてしまう。だからこそ、Z世代を中心としたデジタルネイティブ世代にはすごく可能性があると思っています。彼らはデジタルやサステナビリティを「自然なもの」として受け入れていますし、さまざまな角度から意見を見ることができる世代ですから。
リモートワークの普及によりサードプレイス化したオフィスで、社員のBelongingを育むには
田中:永田さんご自身もZ世代ですが、松崎さんの言う「Z世代だけではなく、他世代も巻き込むインクルージョン」が行われるにはどんなことが大事だと思いますか?
永田:先ほど話に出ていた「自分の好きなことを起点に、他人の幸福のきっかけもつくる」ということは、私も経験しています。これは電通デジタルでの例ですが、私の趣味でやっていたことが、会社から認められ、社内のカルチャーの1つとして、いろんな年代・職種の人の交流のきっかけになった、ということがあります。
田中:具体的にどんなことをされているのでしょうか。
永田:電通デジタルには、2018年度から「サークル制度」があります。スポーツや音楽など、共通の趣味嗜好を通じて交流を深めるコミュニティーです。私はその中でコーヒーサークルを設立し、代表を務めています。元々は、カフェに行って飲み比べをしたり、プロのバリスタを社内に呼んでイベントを開催したりしていたのですが、今ではサークルメンバーが交代でバリスタとしてカウンターに立ち、コーヒーをふるまうように。総務とも連携して、部署や年代の垣根を越えてさまざまな社員がコーヒーを飲みに集まる、公式の社内イベントになりました。
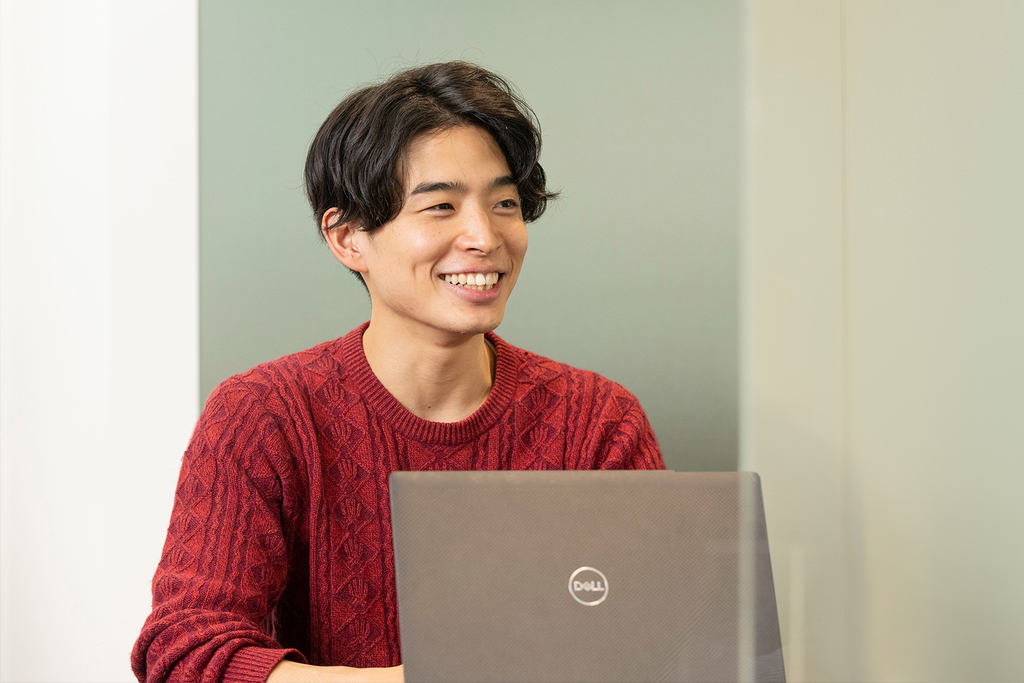
田中:私も先日電通デジタルの手話サークルに参加させていただいたのですが、そこには社外の方も複数いて、年齢層もバラバラで、とても開かれた豊かな場を体感しました。コーヒーサークルもあるんですね。毎月社内で入れたての美味しいコーヒーが飲めるのはうらやましいです。そういうボトムアップの取り組みは、一部の人だけで盛り上がるとか、「常連さん」ばかりが集まって他の人は入りにくい、といったことも起こりがちですが、そのあたりはいかがですか。
永田:1回のイベントで平均130人くらい飲みにきてくれますが、毎回同じ人ではなく、初めまして、という人も多いです。バリスタ側に多様性を持たせているので、私より年上の人もいれば年下の人もいて、さらには部署も違うんです。それぞれの知り合いが集まったとしても、カウンターで隣に座る人は年齢も所属もバラバラ。バリスタがコーディネーターになって、隣り合った人同士を紹介し合うこともあって。コーヒーが抽出されるまでの待ち時間があるのもつながるきっかけとしていいのかもしれません。注文が重なったときは「もうちょっと話しながら待ってて!」と言うこともありますが、全く問題なく受け入れてくれますね。そういう時間は、一見、無駄にも思えるかもしれませんが、サステナブルな組織をつくるためには重要だと思うんです。

田中:効率や定量的なKPIを重視しているデジタル専業会社などにおいて、ネットワーキングできる新しいカルチャーや、デジタルデトックス時間を作ろうなど、社内イベントに積極的という流れが大きくなってきている印象があります。効率良く分業するだけではなく、人とつながる感覚を持てるチームの方が心理的安全性が高く、仕事のパフォーマンスも高いという研究もありますね。
松崎:そうですね。とはいえ、「社員同士を仲良くさせないといけないから、そのためにパーティーやイベントを開く担当をアサインしよう」となってしまうと、目的と手段が逆転して、失敗するケースが多いように思います。業務として交流を「やらなければいけないもの」にしてしまうと、運営側が疲弊してしまう。特に、Z世代は「みんなを喜ばせるために自分が犠牲になる」ではなく、「自分が好きなことをやって、自分が満足する。その結果、周りも喜んでくれたらいいよね」みたいな空気感の方が受け入れやすいと思います。コミュニティーは作るものではなく、結果としてできあがっていくものなので、目的と手段を取り違えないことが最重要なのではないでしょうか。
田中:その辺りが難しいですね。現場で自発的に好きにやってほしいけれども、たくさんの人に参加してもらうには、業務時間としてやってもいいという会社からのお墨付きもいる。コーヒーイベントにおける会社からの支援は、どのように進められていますか。
永田:まず、「オフィスの一番目立つど真ん中の場所を使っていい」と許可してもらい、会社公式のイベントとして告知もしてくれて、さらにはコーヒー豆代などの費用を払ってくれました。あとは社長が飲みに来てくれることも大きいです。「若手が勝手にやっている」と線引きするのではなく、積極的に参加してくれます。電通デジタルのオフィスは2022年に日経ニューオフィス賞で「経済産業大臣賞」を受賞しているのですが、カジュアルで話しやすい「ラウンジ」というコンセプトがあるので、みんなでコーヒーを飲むという文化は空間設計にもマッチしたのではないでしょうか。
田中:業務で忙しいのにコーヒーなんて入れている場合か、と言われないのでしょうか。
永田:私がバリスタ担当社員のシフトを組むのですが、そのとき仕事で忙しい人は無理にシフトに入れないようにすれば問題ないですね。
田中:サークルには年上の社員もいるとおっしゃっていましたが、会社の先輩にシフトを指示するケースもあるのではないかと思います。そこに抵抗はありませんでしたか。
永田:それは、気にしたことがないですね。普段の業務でも年齢の上下は誰も気にしていないと思います。
松崎:もちろん企業にもよりますが、最近ではある意味、オフィスがサードプレイス化している側面もありますよね。例えば、家をファーストプレイスと捉えてみると、これまでは職場がセカンドプレイスだったと言えると思います。そんな中、リモートワークによって、どこでも仕事ができるようになると、業務をオンライン上で完結できるようになってきました。確かに、対面で実施しなければいけないタスクもありますが、そういった場合を除いて、あえて物理的にオフィスに行く理由は何だろうと考えてみると、今まで以上に働く環境の気分転換や、目的のない会話から生まれる発見、職場での誰かとの偶然の出会いなど、サードプレイス的な要素を求めて出社する側面が強くなっていると思います。結果、職場に行く感覚は、以前のコワーキングスペースやカフェに行く感覚に近くなっているのではないでしょうか。
田中:部署の分断という課題に対するベストプラクティスが注目される中、Z世代の永田さんが企画推進するコーヒーイベントは、電通デジタルが大事にするカルチャーを体感でき、コーヒーを入れる人も、飲む人もリフレッシュして、しかも社内でこれまで交流のなかった人と話すきっかけにもなっています。まさに社内貢献と自己表現の両立ができ、インクルージョンにもつながっている好例ですね。
会社で、社員が好きなことや得意なことで自己表現できる機会が持てることは、社員のBelongingを高め、それが1人ひとりのパフォーマンスを高めることにつながり、社内の新しい人間関係をつくり、その関係の質が長期的なビジネス成果にもつながっていくと思います。Z世代を起点に他世代を巻き込むDEI&Bのカルチャー醸成は、まさにサステナビリティをかなえる事業変革・事業成長の原動力となり、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」の核となる領域です。会社の組織文化は、マインドセットが変わるだけで大きく変わる。費用対効果のレバレッジが効きやすく、若いZ世代がキードライバーになるとあらためて感じました。
会社で、社員が好きなことや得意なことで自己表現できる機会が持てることは、社員のBelongingを高め、それが1人ひとりのパフォーマンスを高めることにつながり、社内の新しい人間関係をつくり、その関係の質が長期的なビジネス成果にもつながっていくと思います。Z世代を起点に他世代を巻き込むDEI&Bのカルチャー醸成は、まさにサステナビリティをかなえる事業変革・事業成長の原動力となり、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」の核となる領域です。会社の組織文化は、マインドセットが変わるだけで大きく変わる。費用対効果のレバレッジが効きやすく、若いZ世代がキードライバーになるとあらためて感じました。
DXもサステナビリティ推進も、現場が「本気で導入したいかどうか」で決まり、その際、Z世代の「自分の好きなことを起点に他者の幸福のきっかけもつくりたい」という動機が会社で公式に支援されれば、他世代への刺激にもつながるかもしれません。
今回は電通デジタル社内でZ世代社員が推進する、多世代インクルージョンにつながる事例についてご紹介しました。後編では、顧客企業のサステナビリティ推進にZ世代の意見が刺さった事例についてお話ししていきます。
事業構想に行き詰まりを感じている、Z世代との対話やアイデア共創などに関心がある、そんな方は、ぜひ一度「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」や、電通グループの取り組みにご注目ください。お問い合わせはCONTACTから。