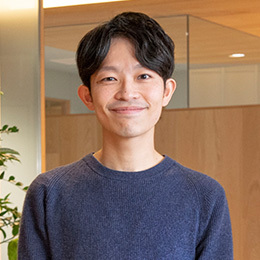環境、人権の意識が高まる中、あらゆる企業にとってサステナビリティの推進は、避けては通れない経営課題です。電通ジャパンでは、サステナビリティ・ネイティブと呼ばれるZ世代とともに企業のサステナビリティを推し進めるサービス、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY 」をリリースしました。このサービスの概要や立ち上げの背景について、Z世代のトレンドを発信するNEW STANDARD株式会社代表取締役の久志尚太郎氏、株式会社電通デジタル でデジタルネイティブルームを設立した松崎裕太氏、そして株式会社 電通 サステナビリティコンサルティング室 ディレクターで、電通Team SDGsコンサルタントの田中理絵氏が語り合います。本記事は、全3回にわたる連載の第1弾としてお届けします。
サステナビリティ推進に、Z世代の視点が欠かせない理由とは 田中: 連載の1回目ということで、久志さん、松崎さんたちと一緒になぜこのサービスを作ったのかお話をするところから入りたいと思います。まずは、それぞれのお仕事と、普段サステナビリティやZ世代とどのように関わっているのか、ご紹介ください。
株式会社 電通 田中 理絵氏 久志: NEW STANDARDは、2014年創業のスタートアップ企業で、デジタルメディア事業や、企業やブランドのトータルプロモーション、課題解決などを手掛けています。私たちは、ミレニアル世代やZ世代のスペシャリストとして、彼ら、彼女らが抱く価値観や考え方を、メディアを通じて発信してきました。2022年にはこうした知見を集約し、次世代の価値観やサステナビリティなど、社会的トレンドに関する調査・研究・発表を行う「
NEW STANDARD THINK TANK 」も始動しています。
私自身は高校生時代をアメリカで過ごし、ヒッピーカルチャーに漬かって育ちました。世界中のエコビレッジやサステナビリティ系のコミュニティーを巡る旅をしていました。
田中: 久志さんは、サステナビリティに関してはここでは語りつくせないほど濃い経験をお持ちで、ご自身のバックグラウンドを今のお仕事に生かされています。日本でサステナビリティ関連のビジネスをされている方って、久志さんをはじめ海外在住経験者が多いという印象がありますね。ご自身の海外経験も踏まえて、日本のサステナビリティ関連の現状をどのようにお感じになられていますか?
久志: 日本は、欧米と比べるとやはり遅れていると感じます。日本人は、自然を尊ぶ感覚を非常に強く持っているものの、自然環境を守っていく、より良く改善していくための具体的な方法論やルールが、社会全体に形式知として広がっていないことに大きな問題があると思います。
田中: 私もサステナビリティに関するグローバル調査を3年続けてきましたので、日本の課題はずっと感じていました。松崎さんはどんなお仕事をされていますか。
松崎: 電通デジタルにはZ世代の当事者を巻き込んだ事業変革のコンサルティングの需要の高まりを受け、2019年より「
YNGpot.™ 」という社内横断組織があります。私もその一員だったのですが、2021年にYNGpot.™での実績と、さらなる需要の高まりを受け、ミレニアルズやZ世代などのデジタルネイティブ世代が暮らしやすい社会やサービスを創造するコンサルティングを行う組織として、専門チーム「
デジタルネイティブルーム 」を正式に部署化しました。
田中: サステナビリティについてもお仕事のスコープにされているのでしょうか。
松崎: 事業構想においては、10年後、20年後といった中長期的な視点が欠かせないので、結果として「サステナビリティ」というテーマを避けては通れません。また、デジタルネイティブ世代の生声を事業に反映する中で、消費を含めた彼らの幅広い行動とサステナビリティ意識が深く結び付いていることも分かってきました。その結果、最近ではサステナビリティが関わる仕事が必然的に多くなってきています。
株式会社電通デジタル 松崎 裕太氏 田中: Z世代にとってサステナビリティは、表面的なエシカル行動として現れるのではなく、ベースの価値観に無意識に入っている感じですよね。健康意識、ルーツ回帰、節約で中古品を買う、DIY、農業や緑を生活に取り入れたいとか、コロナ禍を経たニューノーマルが来る前からそういう傾向があって。
松崎: その他にも「オーセンティシティ(誠実さ)」も大切ですね。企業の存在意義(パーパス)はもちろんのこと、誠実な企業姿勢や、透明性の担保された情報開示などもすごく重要だと考えている世代。また、社会環境変化の激しい時代に生まれ育っているため、新たなライフスタイルを取り入れることにも柔軟ですね。そのため、彼らは社会がより良い方向に進む選択を、当たり前のようにできる力を持っている印象があります。
田中: そういったZ世代の行動傾向は、サステナビリティを意識した社会トレンドと完全に重なっていますよね。私は、デジタルやグローバルの仕事でZ世代の話を聞くことが多かったのですが、どのビジネス課題でも彼らの話は役に立ちました。Z世代の世界の捉え方は、若者トレンド研究の対象としてではなくて既存の社会の枠組みを捉え直すバイアスブレイクになると実感しました。
年長者が若者に学ぶ、「リバースメンタリング」という考え方 田中: では、サービス名である「REVERSE CONSULTING」という言葉の意味について、久志さんからご説明いただけますか?
久志: サステナビリティや新しいテクノロジーを前提とした価値観が築かれていく中で、これまでのいわゆるトップダウン型とは逆に、若い世代から学んでいく「リバースメンタリング」という取り組みに注目が集まっています。REVERSE CONSULTINGは、そのリバースメンタリングを軸に、若い世代と対話やセッションをしながら、未来を築いていこうということですね。企業が考える「企業目線の未来」ではなくて、「生活者目線、Z世代目線の未来」を目指しています。
NEW STANDARD株式会社 代表取締役 久志 尚太郎氏 田中: 今はリスキリングという言葉も浸透して、新しい社員教育やキャリアパスに取り組む企業も多くなりました。海外で数年前から流行していたリバースメンタリングやモダンエルダーは、日本企業にも入ってきているトレンドなのでしょうか。
久志: 日本でも、若い世代のトレンドがビジネスに直結しているようなデジタルやインターネット関連業界・化粧品業界では、新しいスタンダードになってきています。
田中: リバースメンタリングを取り入れる企業の方が、「成長する」「売り上げが伸びる」のでしょうか。
久志: 実証された結果を見たわけではないですが、世界中で広まっているのはそのためでしょう。サステナビリティへの考え方も同様で、SNSやAIの使い方など、若い世代が「当たり前」として捉えていることを、企業としてきちんと理解し、目線を合わせていくことが重要になってきます。
田中: 「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」はまさに、サステナビリティに関するサービスや事業開発をZ世代と共に考え、進めていく取り組みです。コンサルティングの入り口として4つのメニューを提供しています。
「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」サービス概要 田中: メニューがシンプルなので「これまでのZ世代ソリューションと何が違うの?」「どこがサステナビリティと絡むの?」と思われる方も多いのではないかと考え、今回はサービスが求められる背景についてお話させていただきました。
「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」というサービスが誕生した背景には、Z世代との共創が事業構想に有効というコンサルティング現場での手応えがありました。実践のヒントとなるのは「リバースメンタリング」というアプローチ。サステナビリティ対応を機会と捉え経営戦略に反映するために、Z世代の視点で既存の枠組みを捉え直し、将来世代のマイナスをプラスに変え、それが収益に結び付くよう事業の再構築をするコンサルティングサービスです。
後編では、Z世代と共創する上で重要なポイントや、これからのサステナビリティの在り方について、さらに掘り下げていきます。
事業構想に行き詰まりを感じている、Z世代との対話やアイデア共創などに関心がある、そんな方は、ぜひ一度「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」や、電通グループの取り組みにご注目ください。お問い合わせはCONTACTから。
https://transformation-showcase.com/articles/290/index.html
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。