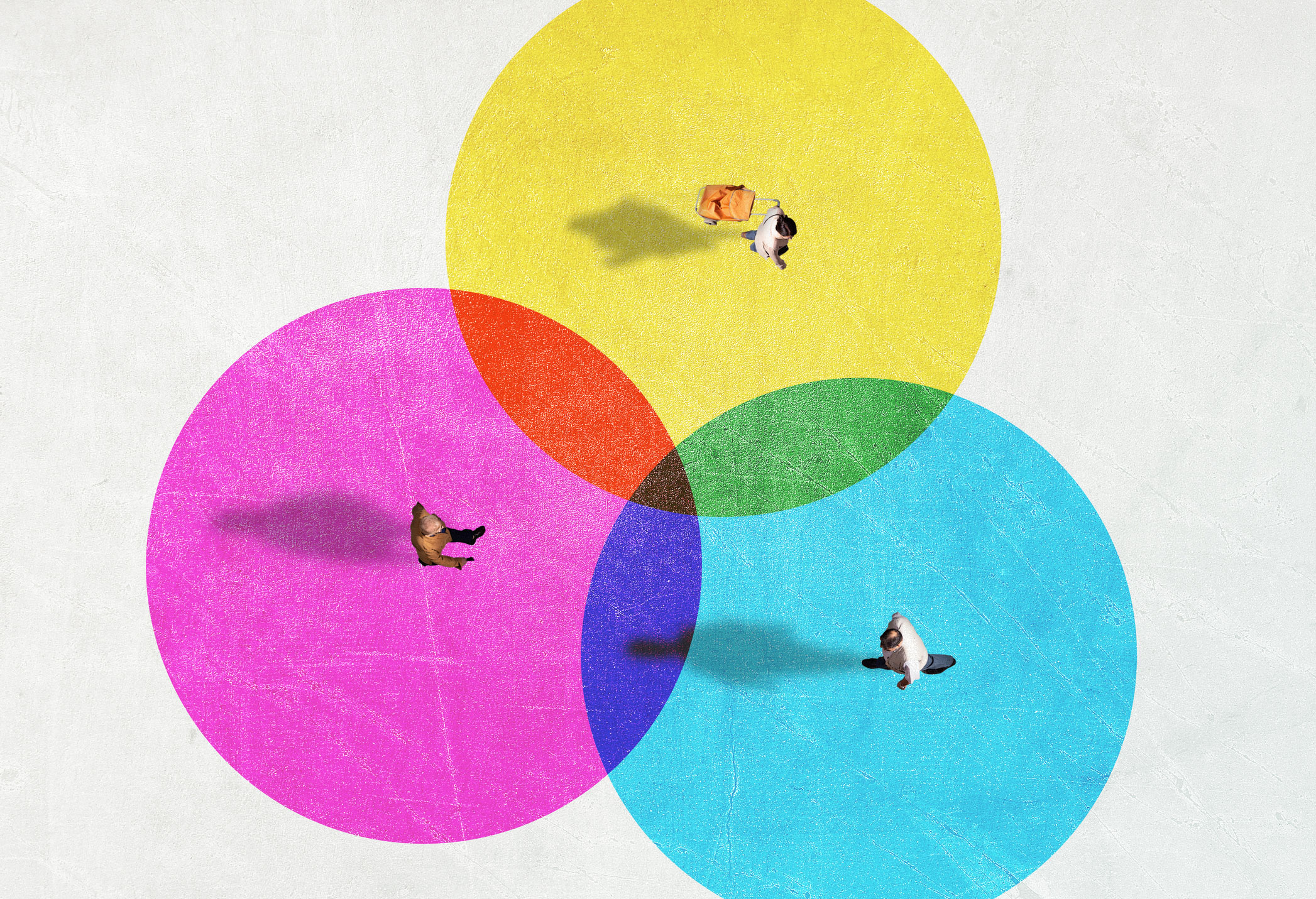サステナビリティやSDGsといった概念が広がる中で、世界全体が「カーボンニュートラル」に向かって動き出しており、企業にはこれまで以上に環境に配慮した対応が求められています。そうした中で、今注目されているキーワードの1つが「サーキュラー・エコノミー」です。この記事を読んでいる方の中には、「そもそも、サーキュラー・エコノミーって何だろう?」という方もいれば、「言葉は知っているけど、自社でどう取り組んだらいいだろう?」という課題を抱えている方もいるでしょう。あるいは、「環境対応は進めなければいけないと感じているが、どこから手をつければいいのか分からない」など、より具体的な視点で解決策を模索している方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、「電通Team SDGs」の SDGsコンサルタントである堀田峰布子氏に、サーキュラー・エコノミーの基本や導入ステップ、取り組む際に注意すべきことなどを聞いています。まだ日本ではなじみが薄いと言われるサーキュラー・エコノミーについて、理解を深めたい方のお役に立てれば幸いです。前後編の2回に分けてお届けします。
サーキュラー・エコノミーは資源を循環させていくビジネスモデル
Q.まず、サーキュラー・エコノミーの話を始める前に、堀田さんのキャリアについてお話しいただけますか。かなり多様な経験をしていらっしゃると思うのですが。
堀田:はい。現在は株式会社 電通で働いていますが、もともとは大手メーカーで通信機器のプロダクトデザイナーをしていました。その後、通信事業会社に移って、デザイン全体をディレクションしたり、決定したりするような立場で仕事をし、その次はグローバルな通信機器メーカーに入社してまたプロダクトデザインやプロダクトブランディング、マーケティングを担当しました。
学生の時から「素材」の授業があり、「素材」についてはいろいろと勉強してきましたし、メーカーで働いたことで、モノづくりや設計のこと、工場がどうなっているか、といったことについての経験値も得ることができました。通信業界では、「通信×デザイン」ということに広く取り組みました。後でお話ししますが、サーキュラー・エコノミーを社会に実装する上では、ユーザーから不用品などを「回収」したりしなければいけない。そのためにはインセンティブを設けて、アプリなどによってユーザーに届ける、というようなことも必要になってきます。通信業界での経験はそういう今の仕事にものすごく生きているな、と感じます。
私は、「ビジネスデザイナー」という肩書で仕事をしているのですが、その土台となっているのは、「国内大手メーカー」と「グローバルメーカー」、モノを作って売る「メーカー」とサービスで稼ぐ「通信事業者」というように、ビジネスモデルや環境が異なる多様な企業で培った経験です。
そして現在は電通にいるわけですが、自分の中では、今までの「つくる」という領域から、「つたえる」という領域へと越境してきたと思っています。やはり現代は、良いプロダクトやサービスをつくったから使ってもらえる、買ってもらえるという時代ではないと思うんです。むしろ、「つくる」時から、「つたえる」ことを考える。「つたえる」ことから逆算したモノづくりをする、という視点を持てば、体験は大きく変わってくるのではないかと。
一方で、「つたえる」こと、つまりコミュニケーションだけを改善しても、顧客企業の経営課題を解決することはできません。ですから、コミュニケーション視点をしっかりと持った上で、モノづくりやUXの領域に踏み出していくことが大事なのではないかと思っています。最近は、顧客企業の研究所と仕事をする機会も増えてきました。研究成果をいかに具現化してビジネスへとつなげていくか、という取り組みを行っています。
Q.それでは、堀田さんにあらためて伺います。そもそもサーキュラー・エコノミーとはどういった考え方なのでしょうか?
堀田:サーキュラー・エコノミーは、直訳すると「循環型経済」です。国際的なサーキュラー・エコノミーの推進機関であるエレン・マッカーサー財団では、その3大原則を
- 廃棄物や汚染をなくす設計(Design out waste and pollution)
- 製品や素材を使い続ける(Keep products and materials in use)
- 自然のシステムを再生する(Regenerate natural systems)
と定めています。
従来は、廃棄物を再利用したりリサイクルしたりして、できるだけ長く使っていく「リサイクリング・エコノミー」が推進されてきました。サーキュラー・エコノミーはこれをさらに発展させた仕組みです。製造段階から、不要になった製品や素材などを回収して再利用することを前提として設計し、新たな資源の投入を最小化。限られた資源を使い続け、廃棄を最小限にするビジネスモデルです。
資源を無駄にしないための方法として、これまでは、「リユース(Reuse:捨てずに何度も使う)」「リデュース(Reduce:ゴミの量をなるべく減らす)」「リサイクル(Recycle:使い終わったものを再資源化する)」の「3R」が重要だと言われてきましたが、サーキュラー・エコノミーにおいては、これに加えて、さらに「リペア(Repair:修理しながら使い続ける、および最初からそういう設計になっている)」や「リフューズ(Refuse:廃棄の元になるものを最初から買わない・もらわない)」といった「5R」の取り組みも重視されます。さまざまなアプローチによって限りある資源を有効に活用することで、サーキュラー・エコノミーを構築することができるのです。

サーキュラー・エコノミーが注目されている理由とは
Q.なぜ今、サーキュラー・エコノミーが注目されているのでしょうか?
堀田:サーキュラー・エコノミーの実現を目指すということは、環境負荷を抑えることになるので、SDGsの実践やサステナブルな社会を志向するために有効なアプローチとなるから、という面もあるのですが、さらに重要なのは、これが企業にとって新たなビジネスを生むチャンスになるという点です。今、世界全体が「カーボンニュートラル」に向かって動いています。その中で例えば化石燃料をやめて再生可能エネルギーを使おう、ということになる。これは産業にとっては大転換が起こるわけですね。EUでは既に国境炭素税(CO2排出量に応じて輸入品に対して課される税)の導入を表明しているので、これはもう今までと同じようなモノづくりビジネスが立ち行かなくなる、という可能性があるわけです。
そんな中でサーキュラー・エコノミーというモデルが広がってきた。これによって、例えば、今までは「売って終わり」だったビジネスが、「ユーザーから回収して再利用」というモデルに変わる。ここに大きなイノベーションが存在します。つまり、サーキュラー・エコノミーを推進することで、時代の要請に合わせて環境負荷を低減していくと同時に、自分たちのビジネスモデルを進化させ、今までとは異なる形で収益を上げられるようになる可能性が高まるのです。いかに時代の変化に合わせて自分たちのビジネスにイノベーションを起こすか、と考えたとき、サーキュラー・エコノミーが示すビジネスモデルは大きなチャンスを与えてくれます。
とはいえ、電通・電通総研が行った「サステナブル・ライフスタイル意識調査2021」では、「サーキュラー・エコノミーの内容を理解している」と回答した日本人の割合は約8%という結果でした。日本では本格的な取り組みはまだこれからと言えるのではないでしょうか。

従来の「リサイクリング・エコノミー」や「3R」をさらに進展させて、資源を循環させることを前提としてビジネスを設計していくのが、サーキュラー・エコノミー。環境負荷を減らすためだけでなく、ビジネスにイノベーションを起こすきっかけになり得るものとして、注目を集めています。後編では、サーキュラー・エコノミーの実現のために、企業としてどのような取り組みができるのか、具体的なステップや注意点についてお伝えします。