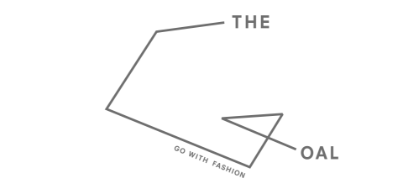ここ数年で一気に浸透し、人々が「取り組むべきテーマの1つ」として意識するようになったSDGs(持続可能な開発目標)。「電通Team SDGs」が2018年より定期的に実施している「SDGsに対する生活者調査」では、2021年の「SDGs認知率」は54.2%と、前年からほぼ倍増しました。特に若い世代において、SDGsが浸透していることが明らかになっています。
そうした動きを受けて、ファッションやラグジュアリーブランドに高い専門性を持つ広告会社である株式会社ザ・ゴールの牛尾雄大氏、川崎莉奈氏、増野朱菜氏に、「ファッション業界とSDGsとの接点」をテーマにインタビュー。前編に引き続き、後編ではファッション業界が抱える矛盾や今後の行く末について、さらに深く掘り下げます。
ファッション業界自体が、さまざまな矛盾を内包している?

Q.前編の最後では、ファッション業界における動物愛護や環境負荷の問題について、一概に「何が良くて何が悪い」とは言い切れない、難しい問題であるとのお話がありました。単純な正解が見つからない状況の中、それぞれのブランドはどういうスタンスを取ればよいのでしょうか?
増野:はっきり言ってしまえば、洋服などのファッション製品は、食料品とは違って必ずしも「必需品ではない」という面があります。絶対に必要だから買う場合もありますが、「娯楽としての購買」という面もありますし、そういった意味ではSDGs的な視点から見たときに、矛盾をはらんだ世界であるとも言えるわけです。そして、ファッションの特性の1つとして、「常に新しいものを求めていく」「トレンドを生み出していく」という面もあります。
前編で労働環境の問題を挙げましたが、例えばH&Mは、透明性(トランスペアレンシー)に非常に力を入れています。H&Mにそれができるのは、やはり資本の力が強力だからという面もあるわけです。ファストファッションだからこそ、他のブランド以上に透明性を担保できる。となると、ファストファッションが問題だということもなかなか一概には言えないんじゃないかと思います。
牛尾:そういった中で、ブランド側も悩んでいるのではないかということは感じています。そもそもSDGsって、わざわざアピールするものではないのかもしれないですよね。スウェーデンの環境活動家であるグレタ・トゥーンベリさんは、気候変動問題のシンボルとなる一方で、例えば関係者が飛行機に乗っただけでたたかれてしまう。全てをさらけ出しながら、同時に「善」であり続けることはとても難しい。だから、「こういうことに取り組んでいます」だけではなく、「ここはまだできていない」を開示した方がいいのではないかとも思うんです。事実を隠そうとする方が問題なのかもしれません。
Q.ファッション業界としても、自分たちが矛盾をはらんでいる存在だということを前提とした上で、振る舞いやコミュニケーションを考えているということでしょうか?
増野:そうですね。確かにジュエリーブランドなどは、「自分たちが扱っているこの宝石は倫理的に採掘されたものだ」ということをしっかり伝えてアピールしています。きちんと自主基準を作ってそれを守ることで、自分たちの存在を守っているといえるかもしれません。
ほかにも、「プレオーダー」の比率を増やして無駄な生産を減らしていこうとか、コレクションの回数を減らしていこうといった取り組みをしているブランドも増えてきています。ファッション業界自体が、自分たちのサステナビリティを模索していると言えるのではないでしょうか。
ファッション業界を目指す若い世代とのやり取りで感じたこと
Q.先日、ファッション業界を目指す学生たちに向けて、「ファッション×SDGs」をテーマに講演されたと聞きました。若い世代の人たちは、よりSDGsへの関心や興味が高いというデータもありますが、実際にお話ししてみてどう感じましたか?
増野:確かにSDGsのような考え方に敏感に反応して、いろいろなことを考慮すべきと考えている学生もいましたね。ただこうした日本の反応は、ヨーロッパなどと比べるとちょっと違いがあるかな、と思う面があるのも事実です。
私はロンドンでファッションを学んだのですが、そこでは独自のフィロソフィーやクリエーティビティ、何よりも「自分のオリジナルのものを作って人に届ける」ことを重視した教育が行われている印象があります。そうした土壌があると、「魅力的なものを作る」ことと、その中で「サステナビリティを取り入れる」という2点を共存させることが、当然だという空気があるんです。
一方、日本ではファッションの教育というと「家政学」というか、服の作り方とか実技的な内容を学ぶことが中心的になっている気がします。そうした違いから、SDGsに対する反応や実際のアクションには、日本と欧米では温度差があるんじゃないかと感じました。もちろんこれは個人的な印象なので、間違っているかもしれませんが。
川崎:中里唯馬さんというデザイナーの方が最近取り組んでいらっしゃる「Face to Face」というプロジェクトが、非常に面白いなと思います。お客さまのシャツを預かって、その人の趣味は何か、服を着てどこに行きたいかなど対話を重ねた上で、唯一無二の新しい服として仕立て直すというプロジェクトなのですが、これこそまさに「リメイク」を超えた「アップサイクル」だな、と。ファッションとしてのアート性や文化性とサステナビリティとが非常に高い次元で共存していますよね。
牛尾:ビジネスとして捉えても、売上を上げるためにはたくさん売った方がいい。そのために価格をなるべく安くして、買ってくれる人を増やしていく。生活消費財ならそれでいいのかもしれませんが、ファッションというのは、逆に「作り過ぎない方がいい」ということもあります。例えば、「100足限定のスニーカー」はプレミアム価格で売れますよね。ビジネス的にも優れているし、無駄に多く作ることもありません。サステナビリティという視点に立つと、安易に安く売ってはいけない。そういった視点を持てるか、ということが求められていると感じています。
世界水準でファッションの仕事をするために、必要な姿勢とは?
Q.なるほど。確かに、「技術としていい服を作れる」とか「質の良いものを低価格で提供できる」ということも重要ですが、ファッションという特性を考えると、根底にある想いは何なのか、あるいはどういうスタンスで世の中と関わっていくのかという部分こそが重要だし、これからファッション業界に入っていく次世代の人たちには、そこをぜひ自分なりに考えてほしいということですね。
牛尾:偉そうなことを言っていますが(笑)、これは実は自分たち自身に向けても日々忘れないようにしていることなんです。というのも、私たちザ・ゴールという会社が、グローバルで展開しているブランドとお仕事をさせていただくとなると、「じゃあ、ザ・ゴールはSDGsやサステナビリティという領域にどう向き合っているのか」を問われます。彼らと同じ土俵に立ったときに、自分たちはきちんと課題を理解しているのか、そしてそれにふさわしい取り組みをしているのか。
これからもファッションやコミュニケーションの世界で仕事をしていくのであれば、業界の皆さんと向き合っていけるだけの知識と実績が必要だと、まさに私たち自身が向き合っている課題でもあるんです。ブランドの皆さんに取引相手として認められ続けるよう、私たちこそ信念とスタンスを持って仕事をしていかなければいけないと感じています。
現場の最前線で活躍する3名のインタビュー、いかがだったでしょうか。ファッション業界は、嗜好性や情緒性が高いからこそ、商品を通じてブランドのフィロソフィーがダイレクトに反映されます。その中でSDGsという今どきのテーマがどう取り入れられ、表現されているのかというテーマに迫りました。その中で、むしろSDGsが広がる前から、ファッション業界が抱える課題や矛盾に自ら向き合ってきた歴史があることが見えてきました。
しかしこれはファッション業界に限ったことではなく、今後あらゆる業界、あらゆるビジネスについても同様のことが言えるのではないでしょうか。そもそも自分たちは何を作り、何を世の中に提供しようとしているのか。そして、世の中のトレンドや流行に関係なく、自分たちのビジネスを見直したときに、もし何らかの矛盾を抱えていたとしたら、周りから指摘される前に自分たちとしてどうそれに向き合っていくのか。そこに確固たる信念を持つものだけが、自社のビジネスをサステナブルに続けられるという時代が、すぐそこにやって来ているのかもしれません。
※所属・役職は取材当時のものです。