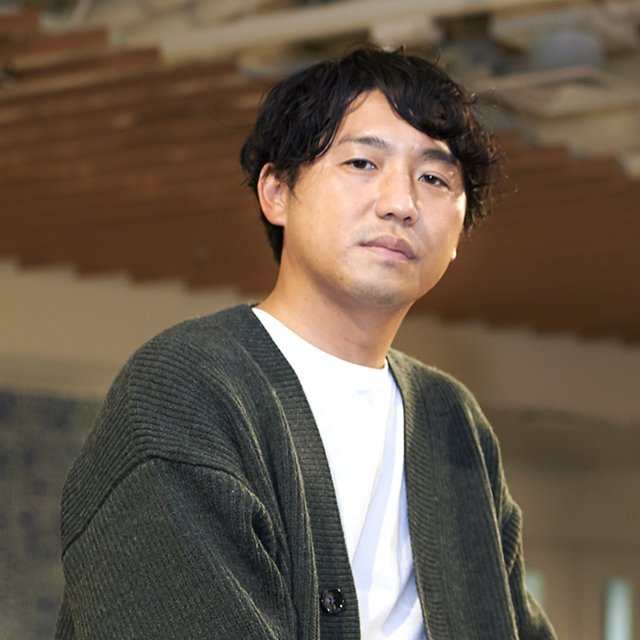新型コロナウイルス感染症の影響で、かつてないほど活況を呈しているEC市場。以前よりECビジネスに取り組んできた中小企業に加え、オフラインを主な活動の場としてきた大手メーカーも新たに参入するケースが相次いでいます。とはいえ、「参入すればすぐに売れる」というほど簡単に運ばないのがECの世界。お客さまとのエンゲージメントを強化し、LTV(ライフタイムバリュー)を高めるために、各社はさまざまな角度から試行錯誤をしているのが現状です。
そこで今回は、そんな激しい変化を続けるECの世界にスポットを当て、「ECの最新トレンドや成功のポイント」を徹底解剖。話を聞くのは、国内有数のデジタルマーケティング企業として知られる株式会社CARTA COMMUNICATIONSの加藤潤一氏と西奈津紀氏です。企業のEC参入や強化を支援するチームに所属し、多くの知見を持つ両氏に、ECビジネスに携わる人間が知っておくべき要点を語ってもらいます。インタビュー後編となる今回は、オンラインでビジネスを展開していくにあたっての心構えや具体的手法に迫ります。
「EC新規参入組」が陥りやすい罠とは?

Q.コロナ禍の影響として、メーカーがECに参入するようになってきました。とすると、CARTA COMMUNICATIONSには、そういった「EC新規参入組」からの相談も増えているのでしょうか?
加藤:はい。もともとオフラインだけのビジネスをしていたけれど、コロナ禍をきっかけにオンラインにも進出したいというご相談は増えています。オンラインを始めると一口に言っても、考え方によっては「今実践しているのと同様のビジネスを、もう1つ立ち上げる」とも言えるわけです。実際に手を出してみても、会社の体力が足りないとか、体制的に対応し切れていない、結果的にやるべきことをやり切れていない、というケースは多いと感じます。だからこそ、私たちのやれることも多いのではないでしょうか。
Q.その意味では、ECに慣れていない顧客企業も増えているのかなと思いますが、そのような企業が「履き違えているポイント」があるとしたら、どういった点なのでしょうか?
西:なかなか言いづらいのですが、「オフラインでも売れているんだから、オンラインでも売れるだろう」「オフラインでこれだけシェアがあるから、オンラインでも売れるはず。なのに、なんで売れないの?」というケースが意外とあります。特に大手メーカーになればなるほど、その傾向は強い気がします。でもECでは、これまでも「オフラインで手に入らないものほどオンラインで購入する」という流れがあったわけです。ですから、ただECをやれば売れるというわけではありません。
逆に、ずっとEC中心で売り上げを上げてきた中小企業には、「これくらいチャレンジしないとダメなんだ」という気持ちの強さがあるように感じます。ECという世界の中で、有名になるための努力を徹底的にできているかどうか。オフラインでは「棚」に制限がありますが、オンラインではその制限がありません。その中で有名になったり、モールでランキング上位に行くのは、オフラインとは違う努力が必要です。
例えば、「レビュー」を書いてもらえるように努力しているか。普通に商品を出しているだけでは、そもそもレビューを書いてもらえないのが当たり前です。その中でお客さまにレビューを書いてもらい、評価してもらうにはどうすればいいのか?私は、「レビューにすべてが隠されている」と言えるほど、レビューを重要視しています。まずお客さまにレビューを書いていただけるような関係性を作り、次にそのレビューの声にきちんと応えられるよう努力する。こうした関係は、完全に1対1のとても人間くさい関係です。オンラインの方が、むしろお客さまの1つ1つの声を真摯に受け止め、きめ細かく対応していくことが重要と言えますね。
加藤:私がECビジネスに取り組むお客さまに感じているのは、とても基本的なことですが、「投資回収」の考え方をしっかり理解していただきたいということです。ECビジネスは、オンラインで売り出したら初月から売り上げがどんどん上がる、というものではありません。やはりECはリピート比率など、お客さまのLTVが大事になってきますので、獲得コストを徐々に下げていきながらリピート購入で回収していくという構造は、昔から変わらないと思います。そこを見誤ると、そもそものビジネスの進め方を誤ってしまうのではないでしょうか。
自ら「EC事業者」になることで得られたノウハウとは
Q.皆さんのチームでは、EC事業者を支援するためのノウハウを蓄積するために、自らEC事業者となってビジネスを実践していると聞きました。具体的にどのようなことをしているのでしょうか?
加藤:とある製薬メーカーと連携して、「HAUT(オウ)」というメンズスキンケアブランドを立ち上げ、商品をECで展開しています。まさに「事業者の目線」を自分たちも体験することで、EC支援サービスのあるべき姿をつかんでいこうという想いで実践してみました。いざ自分たちが当事者としてECビジネスを展開してみると、ああこれは大変だな、ということがよくわかりました(笑)。
「EC支援」というと、きれいなサイトを作るとか広告を運用するという、デザインやプロモーションの領域が中心的になりがちだと思います。でも、前編でも申し上げているように、ECの本当に大切なところは、物流や在庫管理、カスタマーサポートなど、お客さまにいかにストレスなく商品を受け取って喜んでいただくか、そしてリピーターになっていただくかなんです。つまりその領域を支援できなければ、本当の意味でECでの売り上げアップを実現することはできないかもしれない。それが、自分がEC事業者になって得た大きな気づきでした。
もう1つの気づきは、「ECだけに閉じていると、どこかで行き詰まる」という感覚を得たことです。やはりデジタル施策だけでは認知が取り切れない。永遠にInstagramの広告を運用していても、いずれCPA(顧客獲得単価)は高騰していく。そのときに、いかにオフラインでの展開を活用できるかが重要になってきます。これもやはり、「自らやってみてわかった」重要な発見だったなと思います。
D2Cブランドの立ち上げからEC運用まで、一気通貫でサポート
Q.そのような、まさに「当事者としての体験」も踏まえて皆さんが提供するサービスが、「Commerce Container(コマース・コンテナ)」ですね。最後に、このサービスの概要について簡単に教えてください。「EC領域支援のワンストップサービス」とのことですが、具体的にはどのようなソリューションなのでしょうか?
加藤:はい。このサービスは、Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングという日本の3大モールへの出店からオウンドサイトにおけるEC展開まで、その全てを支援するサービスです。
モールに出店したいというニーズに対しては、それぞれのモールに合わせた販促戦略の立案から参入市場の分析、自社と競合の分析、サイトの制作、SEO対策、広告展開による流入増など、あらゆる面で支援します。特にモールでの展開時に重視しているのは、それぞれのモールが実施する「セール」のタイミングに合わせて売り上げを伸ばすような取り組みを行い、それを通常期の底上げにつなげていくことです。
3大モールと言いましたが、例えばAmazonであれば、ランキングやコメントが非常に重要になるので、そのための取り組みを実践していきます。楽天の場合、メーカーが自社商品の売り上げを上げるために、楽天に出店している店舗を支援する広告を展開する、といったことも実践できます。また、Yahoo!ショッピングについては、私たちは「Yahoo!コマースパートナー認定」を取得しており、商品の仕入れを含め、出店そのものを代行することも可能です。
オウンドサイトでECを展開したいというニーズに対しては、例えばShopifyを活用した支援を実践します。Shopifyは世界最大のECプラットフォームであり、私たちは「Shopify Plus パートナー」に認定されていますから、その取り扱いに精通しており、特徴を最大限生かした展開を行います。
ほかにも、最近はInstagramのショッピング機能(Instagram Shop Now)を活用する方法も広がってきています。この場合は開設から運用まではもちろんのこと、SNSアカウント運用とも連動した取り組みをご提供できます。
このようにECの立ち上げから運用を一貫して支援できるのが「Commerce Container(コマース・コンテナ)」というサービスなのですが、ただこのサービスをご提供するだけではなく、ECの運用においてD2Cブランドの立ち上げから顧客企業と一緒になって展開していくような取り組みも始めています。その場合、戦略策定はもちろんのこと、特に重要になるのがフルフィルメントの領域です。フルフィルメントとは、一般的には「ECで商品が注文されてからエンドユーザーに商品が届くまでに必要となる業務全般」のことを指しますが、具体的に言えば、物流・配送とか、受注管理、在庫管理、カスタマーサポート領域などの業務です。私たちは、このフルフィルメント領域まで含めてサービスを提供します。
Q.なるほど。それだけフルパッケージで提供できるサービスであれば、まさに「今、力を入れて広げていきたいソリューション」ではないかと思うのですが、皆さん自身が「Commerce Container(コマース・コンテナ)」を積極的に営業しているのでしょうか?
加藤:はい、さまざまな顧客企業にご提案しています。例えばアパレル業界のOEM企業などは、「自社ブランドを作って販売したい」というニーズをお持ちで、そういったところからのご相談は増えています。商品を作る能力は高いのですが、それを「ブランド」として立ち上げて展開していくのはあまり得意でないというケースが多く、そこで私たちのソリューションが生きてくるのではないかと思っています。
西:私たちはもともとWeb系メディアの広告商品を販売していたこともあり、媒体社との関係が深いというのも特徴の1つです。その中で最近は、媒体社からも相談を受けるケースがあります。例えば「ライター講座」を展開するなど、自分たちが持っているソフトコンテンツやノウハウをECに展開していこうという動きなのですが、このように商品開発から力を合わせてやっていくのも、私たちが取り組んでいる領域です。
CARTA COMMUNICATIONSという会社は結構柔軟性があって、それこそ自分たちがEC事業者になってしまうというようなことにも挑戦する会社です。ですから「ECでの売り上げを上げる」というゴールに向かって、型にはまることなく、どんな領域でもどんな施策でもやれることを考えて実践することができるんです。「EC支援」をうたっている会社は数多く存在しますが、その中ではこの柔軟性や幅広さこそが私たちのユニークネスではないかと思っています。
ECビジネスを成功させるためには、お客さまとの「1対1の関係」をどれだけ想像できるか、「N=1」の想いにどれだけ応えられるかが重要だという点は、ECの本質を突いているのではないでしょうか。つまりECの本質とは、「お客さまとのダイレクトなビジネス」であり、商品が届く瞬間、そしてその後も含めて満足していただけるような関係を1人ひとりと築いていく、その積み重ねであるということです。
逆に言えば、それまで流通などの別事業者に任せていた「ダイレクトな接点」を、自分たちでマネジメントできるということでもあります。それはむしろ、「今までできなかったことができるようになるチャンス」だと言えるかもしれません。これからECに本格参入する方も、既にECに取り組んでいる方も、あらためて「お客さま1人ひとりの想いに応えられているか」という点に立ち戻って、自分たちの取り組みを見直してみてはいかがでしょうか。