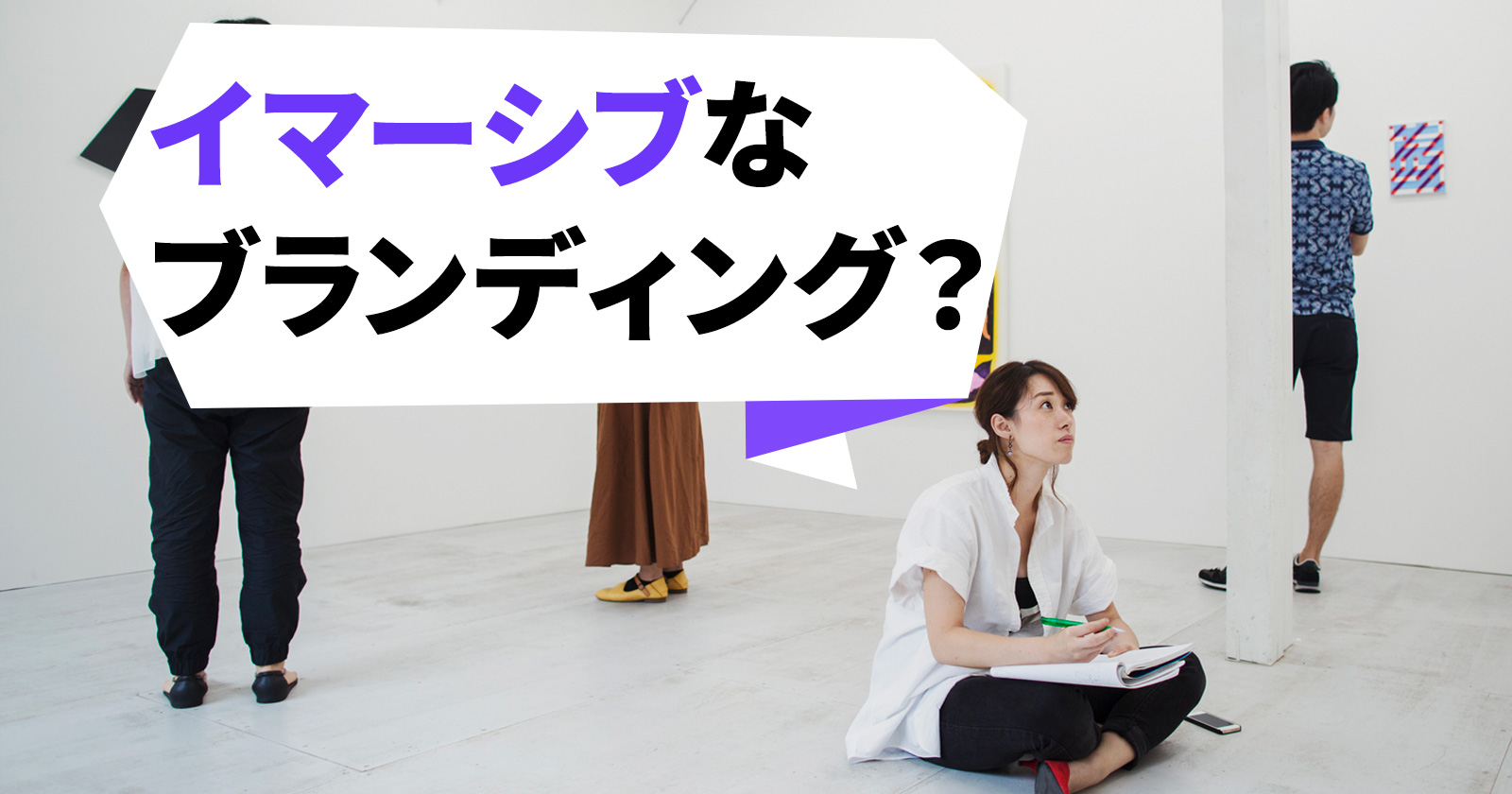テクノロジーの進化により、もの・ことの表現手段が多岐にわたっている現代。中でも、VRやメタバースをはじめとした、ユーザーに「没入感」を与える「イマーシブ」なコンテンツに注目が集まっています。消費の面でも「体験すること」に価値を置いた商品・サービスが広がりつつあることから、ユーザーとの最初の接点となるコミュニケーションや情報発信に「イマーシブ」の要素を取り入れることは、ビジネス戦略上、重要であると考えられます。
そこで今回は、自社のマーケティング/ブランディング戦略を日々模索する方々に向けて、「イマーシブを意識することは、自社ブランド力向上のきっかけになり得るか?」というテーマの下、新しいコミュニケーションのあるべき姿やその可能性を探っていきます。
もの・ことに「没入した状態」を示す、「イマーシブ」という言葉
近ごろ、耳にする機会が増えた「イマーシブ(immersive)」という言葉。「没入感」を意味し、人がコンテンツや空間などに「浸っている状態」そのものを指します。誰しも読書をしたり、テーマパークを歩いたりしている最中に「時間を忘れた」経験があるのではないでしょうか。それほどまでにある1つのもの・事象に没入している状態が「イマーシブ」です。
最近は、「パーソナライズ」「自動化」「体験型」「計測可能性」といった言葉とともに、コミュニケーションの将来を左右するキーワードとして語られることが増えていますが、もともとはマーケティング用語ではなく、ゲーム、美術館、劇場などのエンターテインメントにおける演出やその体験を形容する言葉として使われていました。
例えば、従来の展覧会では、世界的な名画などの静止した展示物を閲覧、観覧するスタイルが一般的です。一方、近年各国で開催されている「イマーシブミュージアム」では、デジタル技術を用いて作品を空間に投影して動かしたり、観客が作品の中に入り込み、その世界をリアルに体感したりするような展示が行われています。
「イマーシブシアター」と呼ばれる体験型の演劇作品も人気です。代表的なのは、ニューヨークで上演されている「Sleep No More」。ホテル全体が劇場になっており、観客は複数のフロアを自由に移動しながら役者の演技を間近に見ることができます。演目が続いているホテルに宿泊し、観客自身が物語の登場人物となってその世界を構成できるような作品など、客席に座って見るのとは違う、体験の深度を追求した没入型の作品が次々に登場してきています。
このほかにも、イマーシブコンテンツは多岐にわたって存在します。具体例を2つご紹介します。
事例1:数百台のコンピューターとプロジェクターを用いた、デジタルアート施設
国内外で多くのファンを獲得しているのが、巨大なデジタルアート空間と庭園を組み合わせたミュージアムです。骨格センサー、圧力センサーなどで来場者の動きをリアルタイムに感知し、投影する映像を変化させることで、体と作品世界との境界を感じさせない新しい体験を提供しています。
事例2:3D表現を駆使した市街地体験サイト
イマーシブコンテンツはアート作品だけにとどまりません。開発中の新しい街を疑似体験できる不動産会社のWebコンテンツでは、ブラウザ上でWebプログラミングが行えるシステムを導入し、ユーザーのマウスの動きやスマートフォンを操作する指の動きに応じて、街を自由に移動したり、360°全ての方向から閲覧したりすることができます。
「体験価値」が高まっている今こそ、「イマーシブな体験提供」を意識する時

このように、アートやエンターテインメント作品をはじめとしたさまざまな領域において、「イマーシブ」な体験を意識した多様なコンテンツが生まれています。では、そんなイマーシブの要素を、広告をはじめとするコミュニケーションや情報発信などに取り入れることで、マーケティングの分野にどのような効果をもたらすのかを考えていきましょう。
ものを手に入れることが豊かさであった高度経済成長の時代が過ぎ、大量生産されたものが世の中にあふれ、ニーズが多様化しているのが現代です。何を選べばいいのか分からず、他者の評価をそのまま受け入れ受け身の消費をする人も少なくなく、ものから心の充足を得られにくくなっている面もあります。
そんな中、近年は「体験経済の拡大」がよくいわれるようになりました。「モノ消費」から「コト消費」への移行が進み、体験そのものに価値を見出す人が増えているのです。「体験こそがアイデンティティの源泉である」という考え方や、「人やコミュニティとのつながりを強め、人生を豊かにしたい」という欲求の高まりは、VRやARを含む「コト消費」が活性化する以前から示唆されていました。
さらには1998年の時点で、B.J.パインⅡ氏とJ.H.ギルモア氏の共著『経験経済』において、「企業は顧客が印象・記憶に残る経験を提供するべきであり、その記憶自体が製品になる」と言及されています。ものとしての商品を提供するだけではもはや価値として弱く、そこからどのような体験を生み出せるかが、今後の経済において重要になることが予測されているのです。
実際、デジタルネイティブ世代の消費動向を読み解くと、「ものを通じて他者とのつながりを深めたい」という希望を持っていることが分かります。ものの先に体験を見いだす彼らをターゲットとしたブランド・商品を提供している場合は、ますます体験価値の設計にも力を入れていくべきだと言えるでしょう。この世代の消費動向については、こちらの記事で詳しく解説しています。
そうした消費行動を促すための広告に、体験に深く踏み込めるイマーシブな要素を取り入れることは必然の流れと言えるのではないでしょうか。実際、ある研究では、広告への没入度が高まるとその説得効果も高まることが示唆されています。
近年はテクノロジーの発達とともに「ユーザーが何を求めているか」を探ることが徐々に容易になってきました。AIの分析を通して、ユーザー1人ひとりにとっての最適な体験をデザインする「パーソナライズ」の技術や、その効果を計測する「計測可能性」も高まっています。「ユーザーが求める体験」を提供していく意識が、コミュニケーション設計においても求められていると言えるでしょう。
イマーシブを生み出すアプローチはさまざま。自由な思想がビジネス向上の一手に

前章では、消費傾向の変化から体験価値の提供が重要性を増す中で、それを仲介するコミュニケーション設計においてもイマーシブを意識することが重要であることを確認しました。それでは、イマーシブをキーワードに、具体的にはどのようなマーケティングやビジネスを展開していくべきなのでしょうか。
最近、商品・サービスの購入に至るまでの体験に付加価値を付けることで、顧客満足度の向上を目指す取り組みが増えています。例えば、そうした取り組みの1つとして、商品やブランドの世界観に合わせた没入感のある体験を演出できれば、競合他社との違いをより強く訴求したり、ブランドイメージを鮮明に印象付けたりすることにつながるのではないでしょうか。顧客との最初の接点となる広告などの情報発信から、実際に商品を買うまでのさまざまな接点を一貫した体験と捉え、その世界に深く入り込めるような設計にすることは、今後のビジネスにおいて必要不可欠な視点と言えるでしょう。
没入感を強めたコミュニケーション施策の一例としては、「ゲーム内広告」が挙げられます。ゲームはもともと没入感の強いコンテンツです。そのゲーム内で風景として登場する看板などに、私たちが暮らす現実世界の商品(食品や日用品など)が映し出されていたらどうでしょうか。ゲームの登場人物とプレイヤー間の境界線がさらに曖昧になり、もっと没入感が強まるのではないでしょうか。特に近年はゲーム内の微細な部分まで精緻に描写することが可能になっているため、今後のさらなる進化と浸透が期待できます。
メタバースに代表されるような体験を重視したサービスにおいては、没入感を阻害しない仕掛けやコミュニケーションが重要です。物理法則に縛られないメタバース空間では、「現実ではできない体験」も容易に実現できます。そのときに「現実世界から操作している」のではなく、あくまで「メタバース空間で行動している」とユーザーに認識してもらうためには、その操作性を向上させることはもちろん、ゲーム内広告のように、あえて「現実的な要素」を融合させることも効果的ではないでしょうか。そうした意味で、メタバース空間の没入感を阻害せず、むしろその体験を深めていけるようなイマーシブな広告展開の方法論や情報発信のあり方を考える価値は大いにあると言えるでしょう。
その一方で、「イマーシブなコミュニケーション」は必ずしもデジタル技術を用いて実現されるものとは限りません。例えば、アパレルブランドの世界観を精緻に表現したリアル店舗もその1つと言えます。ブランドの世界観や蓄積された時間性といった感覚的なものが物理的に表現された空間に身を置くことで、顧客はブランドが描き出すストーリーと一体化し、より深くその魅力を感じ取ることができるはずです。それを実現するためには、まずはブランドイメージを言語化すること。そして、実働を担うスタッフたちとの認識の齟齬を限りなく減らした上で、店舗設計やインテリア選びに着手することなどが必要になってくるでしょう。
冒頭で挙げたミュージアムやシアターの例は、「イマーシブそのものを提供する場」ですが、マーケティングに資するコミュニケーションにおいてはそのエッセンスをいかにくみ取り、商品やブランドの魅力を表現していくかがカギを握ります。「イマーシブ」をヒントにブランディングや今後のビジネス展開を考えていくことで、次に目指すべき世界が一足先に見えてくるかもしれません。
アート展や劇場など、エンターテインメント業界を中心に使われていた「イマーシブ」という言葉は、今や日常的な消費の領域にも影響を与えつつあります。没入感が強い広告ほど説得力が高まることを示唆する研究結果もあるように、デジタル・リアルを問わずイマーシブな体験をコミュニケーションにうまく取り入れることは、売り上げアップや自社ブランディングの向上につながると考えられます。そうした時代の流れに適応した「これからのコミュニケーションの在り方」とはどのようなものなのか、考えてみると面白いのではないでしょうか。
今後、没入型コンテンツの重要性はますます高まっていくでしょう。電通グループにはコンテンツに没入感を付与するための、さまざまな知見・ノウハウが揃っています。「ユーザーを魅了するブランド世界を作るには?」「まずは広告から“イマーシブ”を取り入れてみたい」。そんな方は、お気軽にCONTACTよりお声掛けください。