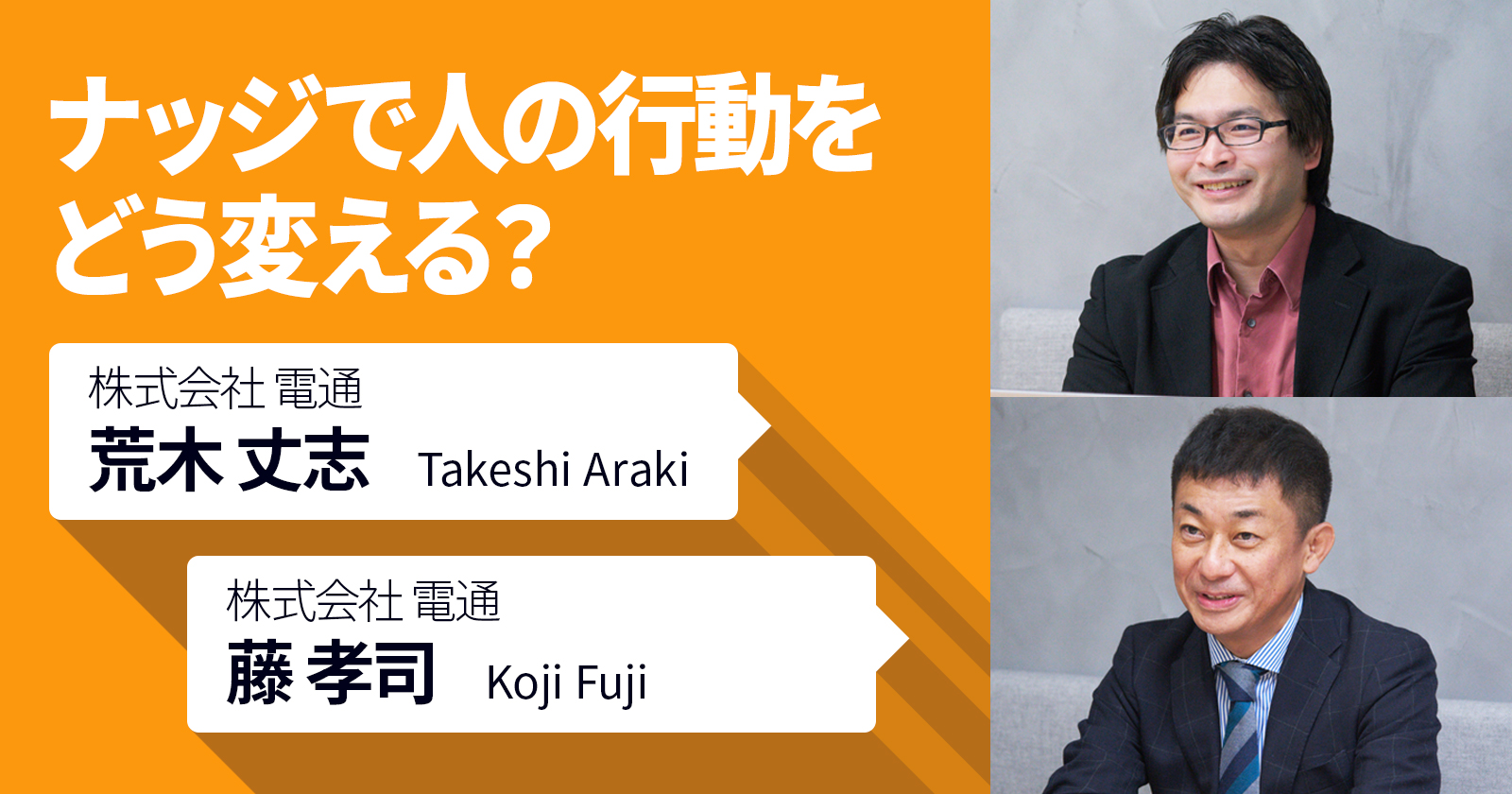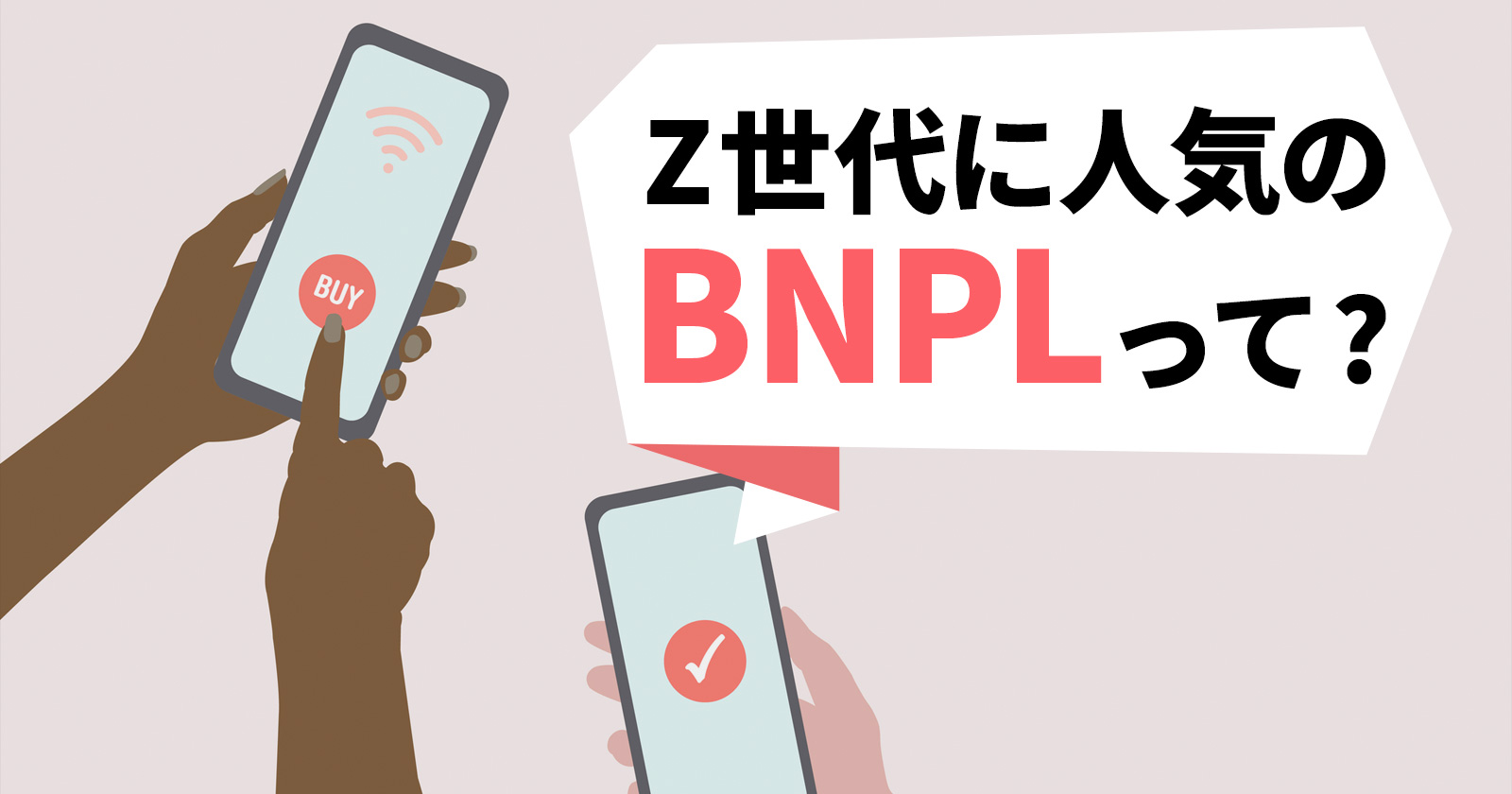2022年10月より、電通グループは、顧客企業・団体のカーボンニュートラル社会に向けた取り組みを支援する「dentsu carbon neutral solutions」の提供を開始。「Transformation SHOWCASE」でもこちらの記事で紹介しました。
「dentsu carbon neutral solutions」では、カーボンニュートラル実現支援コンサルティングから最先端技術とのマッチング・社会実装支援、社内・社外への発信までトータルにサポートするだけでなく、各企業・団体のステータスに合わせてカスタマイズしたメニューを提供しています。中でも、注目を集めているのが行動経済学に基づいた手法である「ナッジ(Nudge)」を活用して脱炭素型ライフスタイルへの行動変容を促す取り組み。
「dentsu carbon neutral solutions」のプロジェクトリーダーである株式会社 電通の荒木丈志氏と、長年にわたって環境・エネルギー問題と向き合ってきた株式会社 電通の藤孝司氏にインタビューする後編では、ナッジを活用した脱炭素行動促進について詳しく話を聞きました。
映像制作におけるCO2排出量を削減する新たな取り組み
Q.「dentsu carbon neutral solutions」は、幅広いプログラムを備えていますが、その中の一例として、荒木さんは、「カーボンニュートラル実現には社内向けのコミュニケーションが大事」というお話をされていました。他にも、今後重要となりそうなソリューションをご紹介いただけますか?

今、電通グループにおいても、サプライチェーンのCO2排出量の可視化を求められています。その際、メディアだけでなく制作プロダクションも一緒になって、カーボンニュートラルを進めていくことが重要となります。そのきっかけになるのが、映像制作カーボンカリキュレータです。
海外では、既にメディア制作物のCO2排出量を計測するカリキュレータが活用されていますが、代表的なツールはイギリス製で、日本の実情に合っていないという声も耳にします。そこで、電通グループの株式会社電通クリエーティブX・株式会社電通クリエーティブキューブと株式会社東北新社・ヒビノ株式会社の4社共同プロジェクト「メタバース プロダクション」が発足され電通グループとしてもその取り組みと連携し、映像制作における温室効果ガス排出削減量を算出し、バーチャルプロダクションへのシフトを推進する「映像制作カーボンカリキュレータ」を開発しました。この動きを拡大することが、電通グループからのメッセージになるのではないかと思います。メディアもプロダクションも巻き込みながら、電通グループとしてCO2排出量の削減に取り組んでいく。他の業界でもまだ類を見ない取り組みなのではないでしょうか。
人の行動をより良く変えるため、そっと背中を押す「ナッジ(Nudge)」手法

Q.藤さんがドライバーになると感じている特徴的なソリューションは何でしょうか。
もともと電通グループは、コミュニケーションやマーケティングに実績のある企業です。コミュニケーションによって人の新しい行動を生み出すことは、私たちのコア事業とも言えるでしょう。実際、今までにいろいろなクリエーターが映像などのコンテンツを通じて、人の行動や価値観にメッセージを届けてきました。
こうしたクリエーターのコンテンツを行動経済学の理論に置き換えて説明すると、BI-Tech(ナッジをはじめとする行動インサイトとAI/IoTなどの技術の融合)のように、これまでとは違う伝わり方になるのではないかと思います。電通グループとしても行動科学的なソリューションを組み合わせることで、顧客やさまざまなステークホルダーに対してこれまでとは違ったコミュニケーションアプローチをご提供できるのではないかと。
Q.ナッジは、さまざまな分野で活用されていて、最近のホットワードでもありますよね。あらためて、ナッジについて説明していただけますか?
もともと「ナッジ(Nudge)」とは、「肘でそっとつつく」「注意を引く」といった意味です。多額の経済的インセンティブや罰則といった手段を用いるのではなく、「人が意思決定する際の環境をデザインすることで、自発的な行動変容を促す」のが特徴。行動変容をそっと促すナッジは、しばしば母ゾウが子ゾウを鼻で優しく押し動かす様子に例えられます。代表的なのは、「バンドワゴン効果」(多くの人が支持するものに対し、より多くの支持が集まること)、「ヴェブレン効果」(高価な商品を手に入れること自体に特別な消費意識・欲求が生まれること)など。普段電通のクリエーターが考えるコミュニケーションの多くも、ナッジのフレームに当てはまり、意識せずに自然とナッジ手法に則ったクリエーティブ開発を行っています。
ナッジは、1つひとつの効果は小さいかもしれませんが、広く適用することで費用対効果が高くなるため、公共施策への応用が進んでいます。2010年にはイギリスのキャメロン政権が、2015年にはアメリカのオバマ政権が政府内にナッジ・ユニットを設立。この動きは各国でも広がり、日本でも2017年に日本版ナッジ・ユニットが設立されました。また、世界銀行、ハーバード大学といった非政府組織でも、ナッジなどの行動インサイトを採用した組織を設置する例が増加しています。
Q.具体的には、どのような場面でナッジが活用されているのでしょう。
例えば、多くの人はデフォルト(初期設定)のまま選択する傾向がある。そのため、臓器移植のドナー登録率が高い国は、「臓器移植をする」という選択肢に最初から〇を付けておき、「移植の意思がない人はチェックを外してください」という形で意思を確認しているという統計結果もあります。
他にも、松竹梅と3種類のメニューがある場合、人は真ん中の竹を選ぶ傾向があるという「極端回避性」、「100万円得します」と言うよりも「100万円損します」と言われた方が行動を起こしやすいという「損失回避性」なども、ナッジアプローチの一種です。たくさんの商品を並べるより、ある程度種類を絞った方が購入率が高いというのも、マーケティングでよく使われるアプローチですね。さまざまなことがルール化され、学術的に証明されたエビデンスに基づいているのが特徴です。
「ナッジ」による行動変容で、カーボンニュートラルを促進
Q.環境分野では、どのようにナッジを活用しているのでしょうか。
そこで環境分野では、例えば家庭に届くエネルギーレポートの中に「あなたの電気使用量は周りに比べてこれだけ上回っています」「この地域の住民の80%は、エアコンを扇風機に変えています」と記載すると、「みんなと同じようにもっと省エネしなければ」と行動変容につながるのです。これを社会規範と言います。
Q.ナッジの理論を環境領域でも取り入れるようになったのは、どのような経緯だったのでしょうか。
日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現には私たち1人ひとりの行動変容を進めないと絶対に達成できません。短期的な視点ではなく、2040年、2050年を見据えて長期的に取り組むことが重要。最近、持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)、その中でも気候変動教育(Climate Change Education)を求める声が高まっていますが、私はナッジアプローチを教育に結び付けることが今後さらに重要ではないかと考えています。子どもの時から2050年やそれ以降の日本、世界のことを意識できるように、SDGsや海洋問題も含めて次世代教育プログラム開発などにも積極的に取り組んでいます。
Q.海外では、既にBI-Techの成功事例はあるのでしょうか。他国での実績について教えてください。
関係府省庁や地方公共団体、産業界や有識者などからなる産学政官民連携の日本版ナッジ・ユニット(BEST:Behavioral Sciences Team)も発足していますが、民間企業とこの領域でさらに連携を深めればより大きな行動変容を引き起こせるはず。私たちもその輪に参画して、より良い社会につながる流れを生み出していくことに少しでも貢献できればと考えています。
生活者起点でカーボンニュートラルを捉えるBtoCソリューション
Q.「dentsu carbon neutral solutions」においても、ナッジを用いた施策を提案しているのでしょうか。
例えば、どうしたら省エネ家電に買い換えてもらえるのか。家庭のCO2削減が進んでいくのか。EVに乗り換えてもらえるのか。車を使わず、自転車やシェアサイクルの利用によってCO2排出量を減らすにはどうすればいいのか。こういったテーマについて、現在は、カーボンニュートラルにつながるBI-Techのエビデンスを蓄積しているところです。さまざまなプレーヤーと共に、電通グループとして理想的なコミュニケーションモデルを構築し、社会実装につなげていきたいですね。
Q.「dentsu carbon neutral solutions」は、2022年10月にローンチしたばかりです。こんなクライアントにご相談いただきたい、こんな困りごとの解決を考えたい、というメッセージをお願いします。
また、「dentsu carbon neutral solutions」は、電通の強みである生活者視点を入れ込んだカーボンニュートラルソリューションです。生活者に関する調査、ナッジを活用した行動変容など、生活者起点でカーボンニュートラルを捉えることができます。これからtoC向けの取り組みを始めたい、でも何をすればいいのか分からないという企業の方からご相談いただけると、私たちとしてもいろいろな気付きが得られるのではないかと思います。

電通グループのコアな部分であるコミュケーションは人々の行動を変えるものですが、それは行動変容を促すナッジと同様です。電通が得意としてきたクリエーティブなコミュニケーションに、行動経済学のアプローチを組み合わせることで、さらに説得力を持って人々の行動変容を促し変えていくことができるでしょう。カーボンニュートラル実現に取り組む企業、あるいは人々の行動を変えることで社会課題の解決を図ろうとする企業や自治体の方にも、参考にしていただきたいと思います。
今、マーケティングにおいて注目されている「ナッジ」ですが、これは脱炭素社会実現に向けても非常に重要なアプローチとなっています。どんなにメッセージを発信しても、生活者1人ひとりがその行動を変えなければ、脱炭素社会は実現しません。電通グループとしても、「ナッジ」に注目しさまざまな取り組みや検証を実践していますが、多くのプレーヤーがみんなで取り組むことで、得られる効果も大きくなります。脱炭素のような地球規模のテーマに向き合うには、企業間連携・自治体なども巻き込んだ大きな連携が必須。「自社を変える」ことはもちろん、それらの行動を通じて「社会全体の変革に貢献する」ために何ができるのか、私たちも問い続け、動き続けたいと思います。
カーボンニュートラルに関する生活者調査、インナーコミュニケーション支援、ナッジによる行動変容促進、映像制作カーボンカリキュレータなど、幅広いソリューションを提供する「dentsu carbon neutral solutions」。カーボンニュートラル実現に向けたあらゆるご相談に応じていますので、ぜひお気軽にCONTACTよりお問い合わせください。