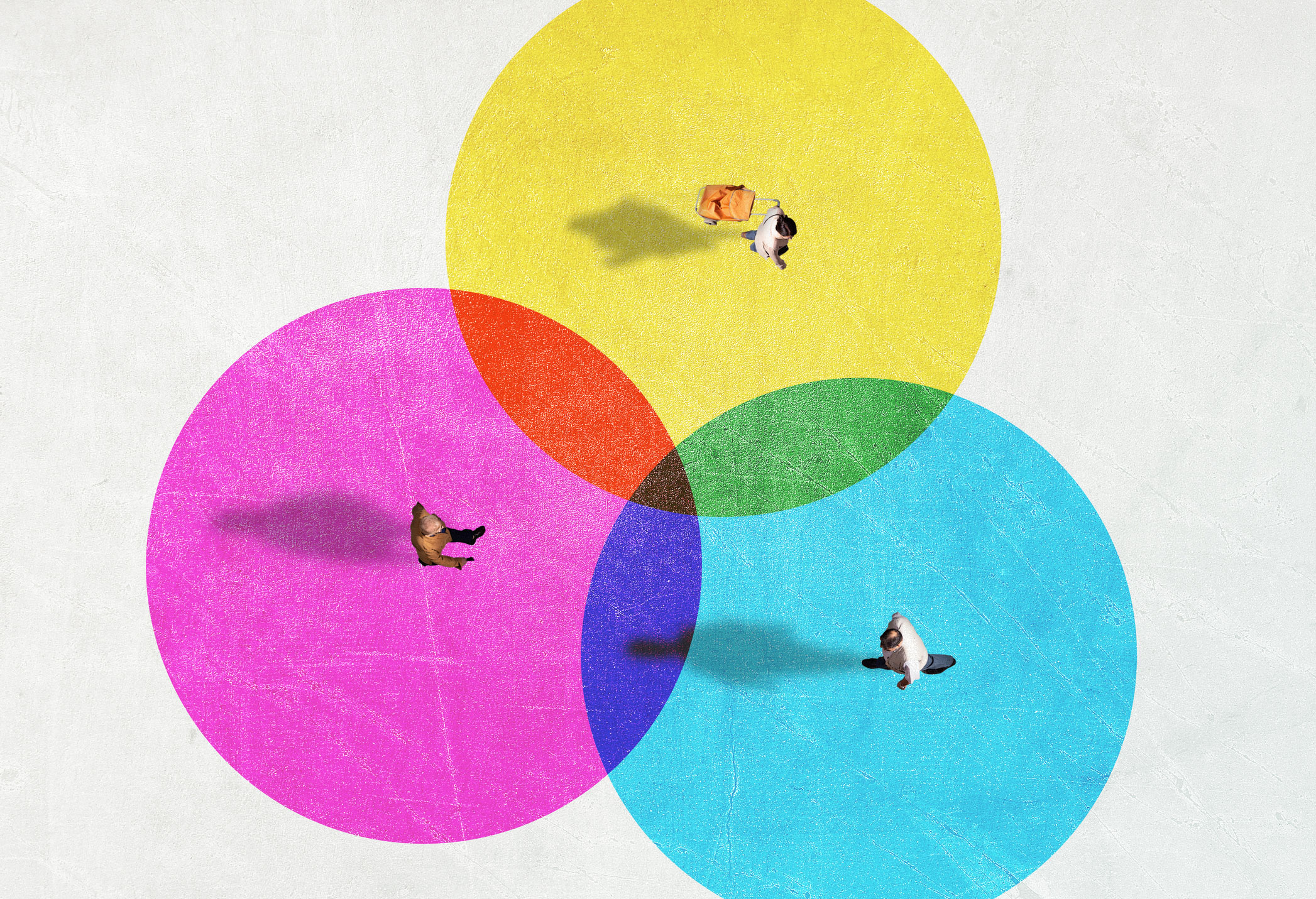「ナッジ」とは、人々がより良い選択をするよう、そっと背中を押すこと。強制ではなく自発的な行動変容を促す、行動経済学に基づいた手法です。マーケティング戦略や社会政策など、さまざまな場面で応用されているナッジ。その活用事例を紹介するとともに、マーケティングに取り入れる際のポイントを解説します。
より良い選択を行うよう、そっと背中を押す「ナッジ」のメカニズム
ナッジ(nudge)とは、「軽くひじ先でつつく、背中を押す」という意味の英語です。2008年、シカゴ大学の行動経済学者リチャード・セイラーと法学者キャス・サンスティーンは、共著『実践 行動経済学』を出版。この本で提唱されたのが、選択を制限したり、経済的インセンティブを与えたりせず、ちょっとしたきっかけによって自発的に良い選択をするよう促す「ナッジ理論」です。同書は全米でベストセラーとなり、リチャード・セイラーはこの理論が評価され、2017年のノーベル経済学賞を受賞しました。
では、「背中を押す」とは具体的にどういうことなのでしょうか。マーケティングの世界でいえば、下記のようなケースが挙げられます。
商品やサービスのプロモーション企画をクライアントに提案する際、展開規模や予算に応じて複数のプランを用意することがあると思いますが、その際に一番高品質なプランから「松・竹・梅」とランク付けするように、分かりやすく差を付けたプランを提案することはないでしょうか。
例えば、
- 理想ではあるが長納期・高コストなプラン
- 最低限の内容でまとめ、コストも最小限のプラン
- AとBの中間で内容的にもコスト的にもバランスの取れたプラン
を用意したとします。
この場合、実は提案する側は「Cのプランを選んで欲しい」と考えていることが多いものです。Cと似たプランを並べるのではなく、あえて極端な選択肢としてAやBのプランを用意しておくことで、その中間であるプランCへとそれとなく誘導する。これも、ナッジ理論を活用した「背中を押す」方法の1つです。
そもそも行動経済学とは、「人間は必ず合理的な行動をする」という考えに基づく経済学とは異なり、「人間は感情の影響を受けて、必ずしも合理的ではない行動を起こす」という前提により、心理学的なアプローチで人間行動を研究する学問。つまりナッジは、人の心理にそれとなく訴え掛けることで、意思決定や行動をデザインする手法と言えます。
あなたの身近なところでも活用されているナッジ理論

ナッジは、社会政策やマーケティング戦略、UI/UX設計など幅広い領域で活用されており、自分の意思で選んだつもりの選択肢も、実は気付かぬうちに誘導されていたというケースは日常でもしばしば起きています。
中でも有名な事例が、オランダ・アムステルダムのスキポール空港。この空港では、トイレの清掃費削減のために、男性用小便器の排水口付近にハエの絵を描きました。すると利用者は、ハエを目がけて用を足すようになり、小便器の周りの飛沫汚れが減り、清掃費が80%も減少したそうです。的があると狙いたくなるという人間心理を利用した、ナッジの活用例と言えるでしょう。
国内でのナッジ活用事例
日本国内の各省庁でも、ナッジは活用されています。環境省では2017年からナッジ・ユニット「BEST」(Behavioral Sciences Team)を設置し、CO2排出削減をはじめ、さまざまな分野でナッジの活用を促進。最大全国50万世帯に2年間にわたり、毎月の電気・ガス使用量や省エネアドバイスを記した「省エネレポート」を送付したところ、CO2排出量の2%削減が2年間継続しました。また、GPSセンサーで車両の加減速等を計測し、その評価をランキングとして表示するアプリを開発。運輸業に携わるドライバーに同調性や社会規範を意識した行動変容を促すことで、最大14.5%の燃費改善・CO2排出量削減につながりました。
現在では他の省庁にも横展開され、厚生労働省では予防医療促進に向けたがん検診の受診率向上、経済産業省では省エネ製品の買い替え需要促進や中小企業向けの事業承継促進にナッジの活用が検討されています。
マーケティングの効果を上げるナッジ活用法

より良い選択をするよう顧客を促すナッジは、マーケティングとも相性の良い手法と言えるでしょう。マーケティングにナッジを生かすポイントは、基本の6原則やフレームワーク「EAST」を取り入れることが重要とされています。
ナッジの6つの基本原則
ナッジの提唱者であるリチャード・セイラーとキャス・サンスティーンは、ナッジのスペル「NUDGES」になぞらえて6つの基本原則を掲げています(※1)。
N:インセンティブ(iNcentives)
金銭的なインセンティブなどを支払うことはナッジではないが、その選択をする人やコストを払う人、利益を得る人にとってそれぞれどのような動機付け(インセンティブ)があるのかを分析することが重要。
U:マッピングを理解する(Understand mappings)
その選択を行うことで何が起きるのか、対応関係を明確にする。そうすることによって、望ましい行動が取れない場合は、その原因を確認できる。
D:デフォルト(Defaults)
多くの人は特にこだわりがなければ、デフォルト(初期設定)のまま選択するので、選んでほしい選択肢を、最初から提示しておく。
G:フィードバックを与える(Give feedback)
選択がどのような結果につながったのかを伝えることで、行動の効果を実感させる。
E:エラーを予期する(Expect error)
多くの人が起こしやすいミスを予測して、あらかじめ対策を打っておく。
S:複雑な選択を体系化する(Structure complex choices)
多くの選択肢がある場合、より良い選択肢が見つけやすくなるよう工夫する。
デジタル領域における業務でUI/UXの設計に携わる方であれば、Webページなどのナビゲーション類が煩雑にならないように整理し、ユーザーにとって最適な選択肢を選べるように設計することを日頃から心掛けていると思います。そのために、上記のような原則は当たり前のように実践しているかもしれません。こうしたポイントを取り入れることによって、ユーザーの意思決定を後押しし、実際に行動するまでそれとなく誘導することができるのです。
ナッジを構成するフレームワーク「EAST」
またイギリスのナッジ・ユニットは、ナッジを構成するフレームワーク「EAST」を提唱しています(※2)。これは「Make it Easy」「Make it Attractive」「Make it Social」「Make it Timely」の各要素の頭文字を取った用語であり、4要素を満たすことで効果的なナッジを設計できるとされています。
Make it Easy(E):簡単に
選択肢を絞る、わかりやすい表現を用いるなど、意思決定のプロセスを減らして行動のハードルを下げる。
Make it Attractive(A):魅力的に
人を惹きつける魅力的な選択肢やインセンティブを用意する。
Make it Social(S):社会的に
人は、周囲の人々と同じような行動を取る傾向があるため、「これだけ多くの人がこちらを選択しました」といった社会規範を意識させることで、行動に影響を与えることができる。
Make it Timely(T):タイムリーに
行動を起こすタイミングは、人によって異なる。その人にとって、適切なタイミング、優先順位の高い時期に選択肢を提示することが大切。
もちろん、過度に魅力を訴求したり、多勢であることをうたって同調を強く促したりすることは逆効果になることもあり、場合によってはユーザーの離反を招きかねません。あくまでも「軽く肘でつつく」程度のアプローチで効果を生むことが、ナッジを生かした行動と体験のデザインと言えるでしょう。
マーケティングにおけるナッジの活用事例
では、こうした原則はマーケティング施策において、どのように活用されているのでしょうか。代表的な例を紹介します。
・ おすすめメニューの提示
飲食店のメニューが多すぎると、何を注文すればいいか悩んでしまうことはないでしょうか。そこで基本6原則の「複雑な選択を体系化する」に基づき、メニューに「おすすめ」と記載しておくと、顧客を誘導できるでしょう。同様に、スーパーマーケットなどの小売店でも「店長のおすすめ」「人気No.1」といったPOPを付けることで、その商品の購入を促すことが期待できます。
・ ポイントカード
飲食店などでは、リピート率を高めるためにポイントカードを発行することがあります。例えば、スタンプを10個集めるとコーヒーが1杯無料になる場合、10個に近づくにつれて来店頻度が上がるそうです。12個のスタンプが必要なカードに最初から2個のスタンプを押しておくと、来店頻度が高くなったという実験結果も。6原則の「デフォルト」や「インセンティブ」の効果と言えるでしょう。
・ 行先を「おまかせ」できる旅行キャンペーン
ある航空会社では、旅のプランニングを億劫に感じる顧客に向けて、マイルで利用できる「おまかせツアー」を用意しています。申し込みをすると、4つの候補地の中からランダムで行き先が決定。行き先がどこになるかわからない、ミステリーツアーのようにユニークなプランは、旅行に行く前からワクワクできる楽しさを提供しています。さらに、「行先を決める」という顧客の労力をできるだけ小さく抑えた上で、新たな発見への興味や期待を高め、旅という行動を促します。
カスタマーサクセスにもナッジは不可欠
サブスクリプションサービスなどのように、顧客と継続的に関係を構築するビジネスにおいては、顧客満足度を高めるカスタマーサクセスが重要です。顧客と信頼関係を築き、顧客が自ら選んだサービスに満足してもらうためにもナッジを活用できます。
ある自動車保険会社では、悪天候の予報が出ると「明日、大雨災害が起こる可能性があります。もし、あなたの自動車に傷などがついた場合は、保険の対象になるかもしれないので申請してください」と連絡を入れるそうです。これは、6原則の「エラーを予期する」にあたり、短期的には自社の収益性が下がるかもしれませんが、長期的な顧客のロイヤルティを高めることができます。
また、複数のプランがあるサービスでは、6原則の「複雑な選択を体系化する」に基づき、パーソナライズされたもの、あるいは選ぶべきポイントがより分かりやすいプランを提案することで、顧客の満足度は高まるでしょう。顧客の獲得だけでなく、サービスの継続利用においてもナッジは有効な手法なのです。
ナッジをマーケティングに活用すれば、消費者をより良い選択に導き、顧客満足度を高めることができます。その一方で、悪用によって消費者が被害を受けることも。高い倫理観を持ち、人々や社会を良い方向へ導くナッジの活用法を考えることが重要です。
※1 出典:『実践 行動経済学 健康、富、幸福への聡明な選択』(リチャード・セイラー、キャス・サンスティーン著、遠藤真美訳/日経BP /2009年)
※2 出典:EAST: Four Simple Ways to Apply Behavioural Insights(The Behavioural Insights Team/2010年)