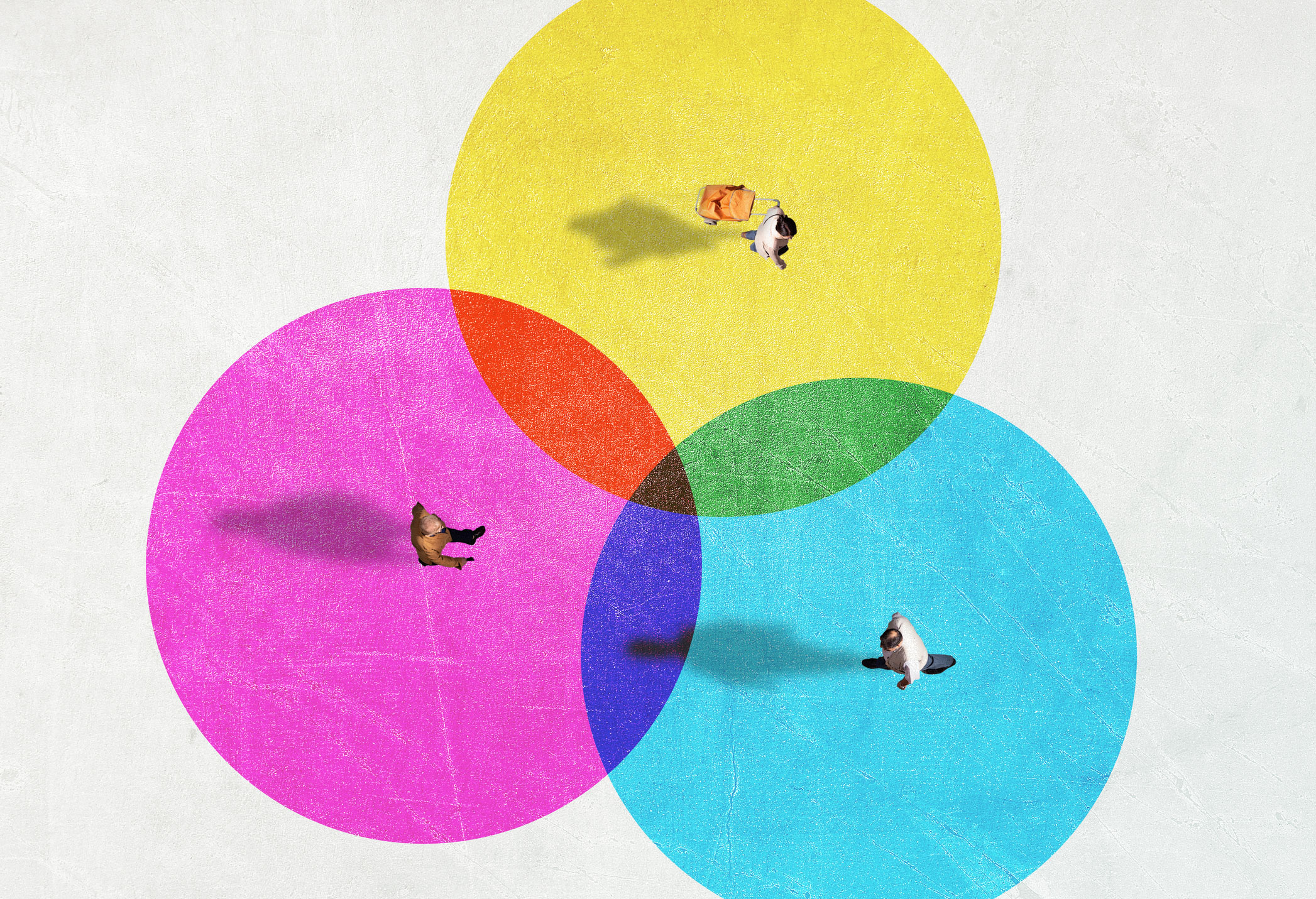家電をはじめ、製造業、輸送業、医療など幅広い分野で活用されているIoT。農業においてもIoTの活用が進み、日本の農業が抱える課題の解決に役立っています。IoT、AI、ロボティクスなど先進技術を活用した「スマート農業」について解説するとともに、農業とそれを取り巻くビジネスの可能性について考えていきます。
IoTは農業の活性化のカギとなる
IoT(Internet of Things)は、あらゆるモノをインターネットあるいはネットワークに接続する技術。モノをインターネットにつなぐことで、モノから情報を取得したり、モノを制御したりといった仕組みが可能になります。日本語では「モノのインターネット」と訳されるのが一般的です。
インターネットにつながる機器と言えば、まず思い浮かぶのがパソコンやスマートフォンでしょう。それ以外にも、家電製品、車、建物、医療機器などさまざまなモノをインターネットにつなぐことで、これまでにないサービスや価値が生み出されています。
IoTを農業に取り入れるメリット
農業においても、さまざまな場面でIoTが活用されています。これまでの農業は、熟練者の経験や勘、長年培ってきた技術に頼ってきました。しかし、IoTを活用することで、経験豊富な熟練者のノウハウをデータ化・見える化すれば、新規就農者でも高いレベルの農作業を行えるようになります。さらに、作業の効率化が進めばより広い農地を管理できる上、未経験の若者や体力に不安のある女性の農業への参入障壁も低くなり、農業の活性化につながるでしょう。では、農業におけるIoTの活用事例を紹介します。
・スマートフォンによる水管理システム
センサーにより水田の水位を観測し、農業従事者がスマートフォンなどで給水バルブや落水口を遠隔操作または自動制御できるシステム。水管理を最適化・省力化することができる。
・生育データに基づくスマート追肥システム
ドローンや農機に搭載したセンサーで、農作物の生育状況を測定。データに基づいて、最適量の肥料を計算・散布する。誰でも簡単に追肥作業を行うことができる上、収穫量の向上、品質安定にもつながる。
・AIを活用した自動収穫機
AIによって収穫に適した農作物を認識し、自動で収穫する機器。最適なルートを自動走行し、葉や枝に隠れた作物も見つけるため、収穫や運搬作業に掛かる人手を減らすことができる。
・熟練農業者技術の「見える化」
熟練農業者の高度な技術をスマートグラスで撮影し、データ化。AIでデータを解析し、新規就農者が装着するスマートグラスに、適切な作業指示をリアルタイムで表示する。技術の「見える化」により、未経験者であっても熟練者の作業のポイントを効率的に学ぶことができる。
IoT、AI、ロボティクスなど先端技術で日本の農業問題を解決

農業にIoTなどの先端技術が活用されるようになった背景には、日本の農業が抱える問題が横たわっています。農業従事者が年々減少、高齢化も進行し、荒廃農地や耕作放棄地も増加。にもかかわらず、依然として人手に頼らざるを得ない作業、熟練の技術が必要な作業が多く、労働力不足は深刻な問題となっています。さらに、安価で品質が良い海外農産物の輸入増加、気候変動などの環境変化もあり、農産物生産量は低下し続ける事態に。今後、日本国内で十分な農産物を確保できなくなることも懸念されています。
農林水産省が推進する「スマート農業」とは
IoTをはじめとする先端技術は、日本の農業が抱えるこうした問題を解決する可能性を秘めています。農林水産省では、IoT、AI、ロボティクスなどの先端技術を活用し、農業の省力化や生産物の品質向上を図る「スマート農業」を推進。農家に先端技術を導入し、効果を実証する「スマート農業実証プロジェクト」も進んでいます。IoTで取得したデータを分析し、農作物の生産量を向上させたり、異常気象などのリスクを予測したりすることで、戦略的かつ効率的な農業を実現することが期待されています。
例えば、作物の良し悪しを判断する、選果のプロセスでAIを活用。きゅうりなどは長さや太さ、色つや、質感、凹凸や傷、病気の有無などによって等級が変わるため、出荷する際はそうした条件によって仕分けをする必要があり、従来はその選別を熟練の作業者が手作業で行っていたため、手間がかかっていました。そこである農家では、等級ごとに用意された膨大な量のきゅうりの写真をAIに学習させることで、自動選果を実現したのです。
こうした農作物の仕分け方は品目によって異なるのはもちろん、同じ品目でも地域や各農家によって違いがあるため、ある農家で専用のハードウェアを開発したとしても、他の農家ではそのまま使えない場合もあり、その使用範囲は限定的なものとなるかもしれません。しかし、ソフトウェアの品質を向上させることや、多くのデータを学習させて野菜を見分ける精度を高めていくことで、より広範に応用することも可能になるでしょう。
IoTが変える農業ビジネスの未来
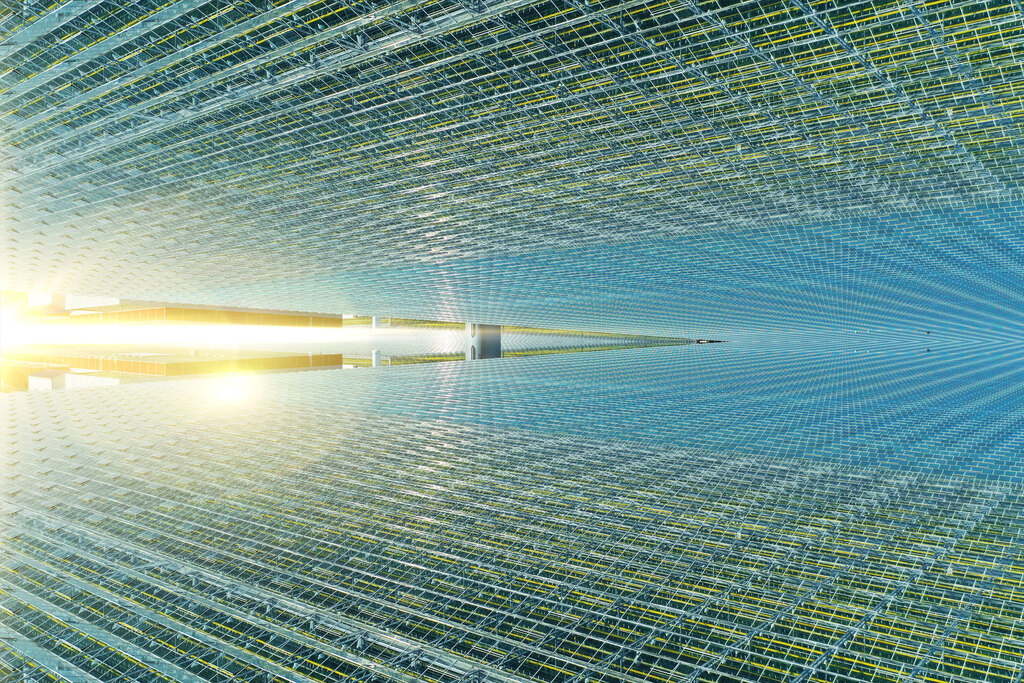
2009年の農地制度改正により、農業生産法人ではない一般企業もビジネスとして農業に参入するケースが増えています。外食産業や食品関連企業が、原材料の安定的確保、トレーサビリティ(商品の生産から消費までの過程を追跡できること)確保のため、農業に関わることも。また、農業と製造業や小売業などを融合し、高付加価値なブランド商品を販売し収益を高めていく「6次産業化」も農林水産省が推進しており、果樹農家が高級フルーツジュースを製造・販売するといった事例が見受けられます。農家が法人化し、農作物の生産から商品開発、工場運営まで一貫して行うケースも少なくありません。企業の参入や農家の法人化により、農業はこれまで以上に収益性の高さ、高付加価値化が求められるようになっているのです。そのためには作業の効率化や、データに基づいた営農戦略が不可欠でしょう。
こうした流れを受け、最新の植物科学と先端技術を駆使した農業向けソリューションを提供するベンチャー企業も誕生。水田や畑の環境情報や作物の生育状況を常時モニタリングできるIoTセンサー、水田の水位・水温管理を行うセンサー、農作業を記録して情報共有するクラウド型営農管理システムなど、農業に特化したセンサー技術の開発を進め、農家を支援しています。
また、農業ビジネスには、農作物の生産だけでなく、農業機械・農薬・肥料などの農業資材、品種改良、農産物の流通・加工なども含まれます。こうした領域でも、IoTで得られるデータが活用されています。株式会社電通国際情報サービスにより開発された、ブロックチェーン技術を活用したスマート農業データ流通基盤「SMAGt(スマッグ)」は、地域農産品の生産履歴から出荷、流通、販売までを記録し、トレーサビリティを向上。消費者に農産品の安全性や生産者のこだわりを伝えることができ、地場農産品のブランド化、食品偽装の防止にも貢献。輸出規制に対応したデータを効率的に取得できるため、輸出拡大にも役立っています。
農業ビジネスの今後
ここまで解説したように企業の参入により、農業ビジネスのスマート化は加速し、日本の農業が抱える課題解決にもつながっています。今後も農業や農業周辺事業に先端技術が活用され、ビジネスの発展に寄与するものと思われます。
こうした未来を見据え、JAXA(宇宙航空研究開発機構)では、人工衛星を農業ビジネスに利用する取り組みも始めています。例えば、災害や資源監視を主目的とした衛星を利用し、東南アジア諸国の水稲作付面積を推定するプログラムを開発。農業統計データの収集にも役立てられる見込みです。さらに、気候変動や水循環を把握するための「環境監視衛星」が取得したデータから、水稲の作況を判断するための農業気象情報提供システム「JASMIN」も開発されました。気象状況を広域かつリアルタイムで把握することで、作物の作況判断に役立てることを目指しています。こうした衛星データを生かせば、将来的には気候変動による収穫量の変動なども予測できるようになり、食料不足の解消など地球規模の課題解決にもつながるかもしれません。
農業従事者の高齢化、人手不足、気候変動など、さまざまな課題を抱える農業ビジネス。IoTをはじめとする先端技術は、こうした課題を解決する切り札と言えます。付加価値の高い農作物を生産し、収益性を高めるにも、今後の農業ビジネスにIoTは不可欠なものになるでしょう。
さらに、スマート農業の在り方から、あらゆる産業の活性化に役立つヒントが見つかるかもしれません。農業に限らず、IoTと産業をどのように結びつけるか、あるいは、「食」をはじめとする人の生活に不可欠な商品・サービスをいかにより良くし、ビジネスとして発展させていくか。スマート農業の進化を知ることが、そうした課題の解決を図るための示唆を与えてくれます。
また、ビジネスにおいて効率化や生産性の向上に取り組もうとする場合、普遍的・一般的な方法論を当てはめようとしがちです。しかし、スマート農業が「収穫を効率的に行いたい」「生産量を安定させたい」といった、現場の具体的な悩みや願いを解決することで発展していったように、現場で直面した1つひとつの課題を解決することにこそ、真に必要なソリューションを見出すための糸口があるのかもしれません。