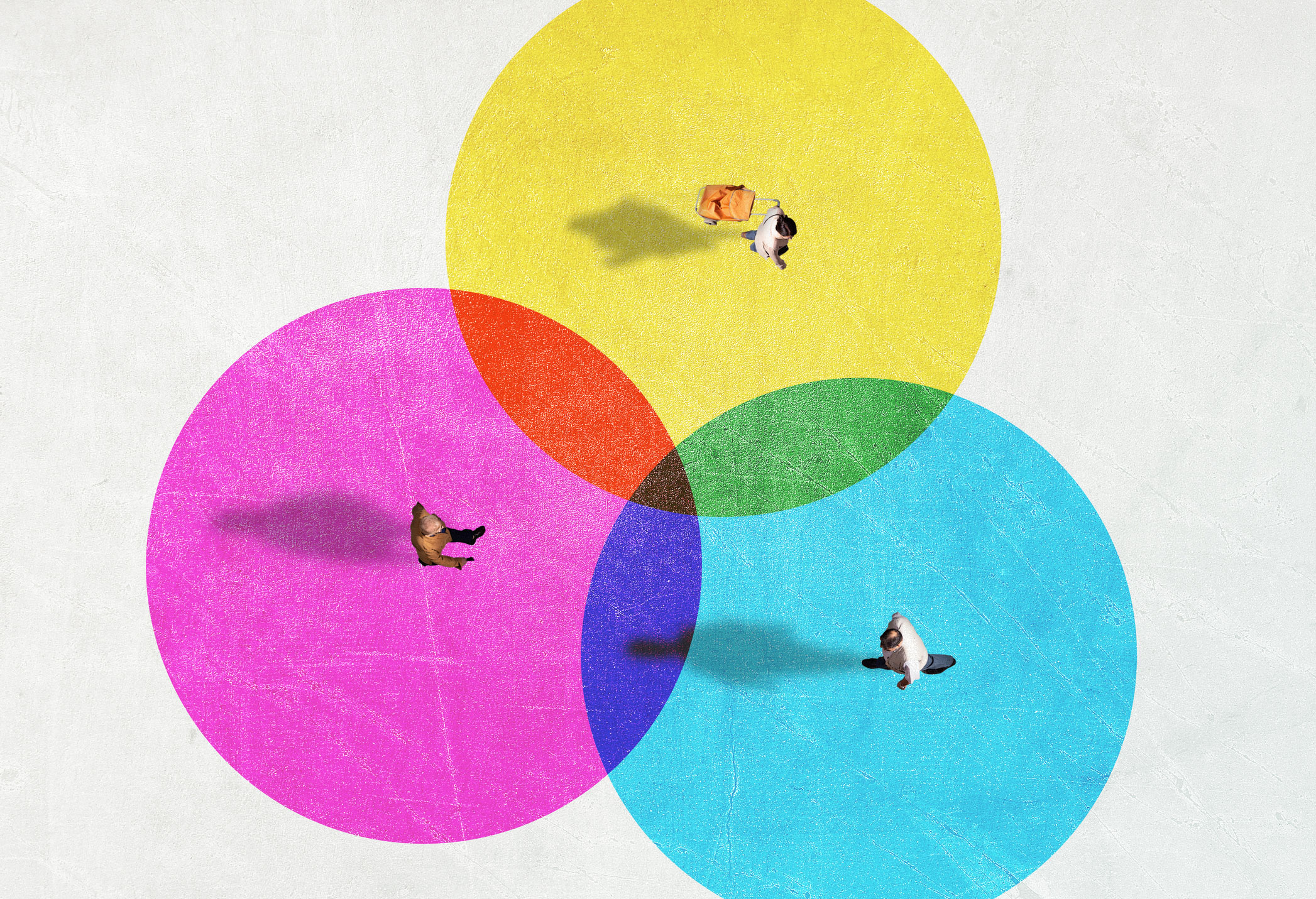株式会社電通デジタルは、2022年1月に「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査(2021年度)」の結果を発表しました。その概要についてはこちらの記事で紹介していますが、DXを推進しながらも「顧客の期待に応えられていない」と感じている企業が4割近くもいる、という結果が注目されています。そこで本記事では、この調査を担当している電通デジタルの外山遊己氏に、調査結果から見えてくる企業の課題や、DXを成功させるポイントなどについて詳しく聞きました。
時系列で見えてくる、企業の「DX推進課題」の変化

Q.「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査」は、そもそもどのような調査なのでしょうか?
外山:この調査は、2017年から継続的に実施しています。調査対象者は「従業員数500人以上の国内企業所属者」で、かつ役職が「経営者・役員クラス、本部長・事業部長/部長クラス、課長クラス、係長・主任クラス」の人たちであり、合計3,000サンプルに対して調査を行っています。2017年当時は、まだ日本国内において、企業のDXの進捗状況を聞くような調査はあまりなかったですし、しかもそれが「従業員数500人以上」という大きな規模の企業に対する調査となると、それなりに貴重だったのではないかと思います。
毎年同じ調査項目を設けて時系列で結果を比較するパートと、「その時ならでは」の質問をするパートがあって、最新の2021年度調査では、「新型コロナウイルス感染症」「SDGs」「個人情報保護法」といった時事的なトピックについて聴取しています。
Q.今回の調査結果では、「自社が“変化する顧客の期待に応えられていない”と感じている企業が4割近くに上る」という結果が特にハイライトされています。2017年からこの調査に関わっている外山さんは、今回の結果を見てどのようにお感じになりましたか。
外山:調査が始まった2017年から、「DXへの着手状況」や、「DXの取り組み内容」については聴取してきました。当然と言えば当然ですが、DXに取り組んでいると回答する企業は年々増えていて、2021年度調査では、81%の企業が既にDXに着手していると回答しています。さらに、その取り組み内容も変化してきていて、当初は「ツールを導入した」「データ活用を始めた」というレベルだったのが、ここ1〜2年では、「新規事業をローンチする」とか「既存事業をさらに拡大する」といった、具体的なビジネスをつくる動きにシフトしていこう、という流れが加速しているのが見て取れます。
そして、こうした動きと呼応するように、多くの企業から、DXを推進する上での課題感として「DX人材がいない」「社内での育成や教育ができない」「組織づくりからやらなければいけない」といった課題が挙げられるようになってきました。
これは私としても肌感覚に合っているな、と感じています。というのも、私が所属する電通デジタルに寄せられるご相談の内容も、かつては「マーケティング領域にデジタルを活用したい」といった話が多かったのですが、最近は「新しいサービスや事業の設計を支援して欲しい」とか「新事業のローンチに向けた業務のサポートが欲しい」、「事業変革に向けた新しい組織をつくりたい」という、より革新的な内容が増えてきているな、と感じているからです。今回の調査では、それを定量的に可視化できたのではないかと思っています。
DX推進のためには、「全社課題」として経営層からコミットすることが重要
Q.DXは着実に実践されつつある。それでも、実は「顧客の期待に応えられていない」と感じている企業が多数存在している。そこにはどのような問題があるのでしょうか?
外山:社会全体でDXの重要度がどんどん高まり、着手している企業もどんどん増えているのに、その一方で、「顧客の期待に応えられていない」と回答している企業が4割もいる。これが今回の調査における大きな発見の1つでした。では、顧客の期待に「応えられている」と回答している企業と、「応えられていない」と回答している企業は何が違うのかというと、それがまさにDXの進展度合いと比例しているという傾向が出ています。
DXが進展している企業はどんなことをしているのか。これは、一見遠回りに思えても、パーパスやミッションをきちんと定める。さらに、経営層と連携して進めているということが見えてきます。DXを推進するには、社内でもいろいろな部署の協力が必要ですし、部署の壁を越えた権限を持って進めなければいけないケースが多いからです。ですから、経営層のコミットがあることは重要です。
あるいは、「さあDXを進めるぞ」ということになって、新規事業開発のために新たに部署をつくっても、既存の部署からの協力がなかなか得られない、というようなことはよく起こります。他の部署からすれば、「自分たちだってやらなきゃいけない業務がたくさんある中で、積極的に協力する余裕やメリットがない」となってしまう。その状況を打破しなければなりません。
とはいえ、新型コロナウイルスの感染拡大によって、この流れは変わってきていると思います。コロナ禍でリモートワークなどが増加した状況においては、やはりDXはビジネスの効率化を図る上でも有効です。加えて、今までと同じビジネススタイルが実践できない中で、「デジタルチャネルでのビジネスを頑張らないといけない」「デジタルマーケティングによってリードを取らないといけない」といった業務変革や事業変革の課題から逃げられなくなったわけです。全社一丸となって取り組む体制になっているかどうか、DXを進めるのに必要な組織や人材がそろっているかどうか、ということが成功のポイントになります。
DX推進のネックの1つであるDX人材不足については、「リスキリング」という考え方も最近注目されるようになってきています。リスキングとは、今後新たに発生する業務に役立つ知識やスキルを社員に習得させようとすること。経済産業省の資料(※)でも、DXのためには「一部の人材だけではなく、全社員がデジタルスキルを習得することが必要」「高報酬が必要なデジタル人材を外部から採用するだけでなく、内部の人材を育成することが有効」といったことが述べられています。つまり、DX推進においては、外部人材に頼るだけでなく、自社の事業に精通している人材に、必要なスキルや知識を身につけてもらえる環境を整えることが求められるのです。
DXを進めていくと、実際に効果が出ているのか、どのくらい定着しているのかなど、さまざまな課題が出てくるでしょう。これはある意味では必然的な結果とも言えます。単なる「デジタル化」では意味がない。いかにそれを社会や生活者の期待や課題に応えるための事業の変革、サービスの創造へとつなげられるか。そういったDXの実行に関する課題が浮き彫りになってきているという点で、日本企業のDXは次のフェーズへと移行しているのかもしれません。しかも、コロナ禍の影響で社会構造は大きく変化し、DXのスピードも加速しています。あらためて自社のDXの効果を冷静に評価し、もし問題があるのであれば、DXの進め方自体を見直してみてはいかがでしょうか。
(※)出典:経済産業省 第3回 デジタル時代の人材政策に関する検討会「今後に向けた取組(案)について」(2021年3月)