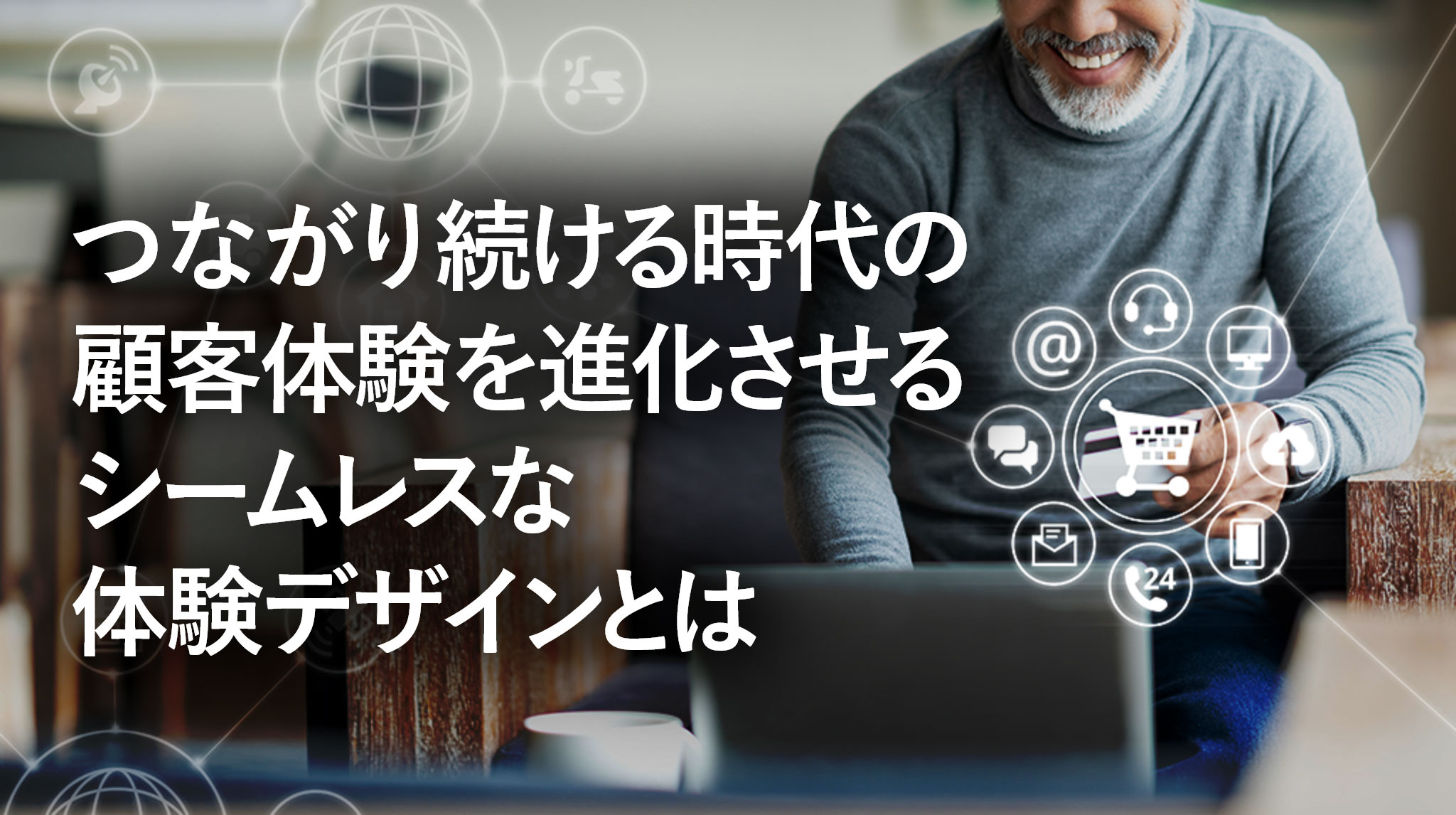数あるSNSの中でも、日本において代表的な存在の1つであるTwitter。もちろん企業マーケティングでも重要なツールとして使われています。では、Twitterを運用する上でのコツや注意点はあるのでしょうか。そこで話を聞いたのが、企業のSNSプランニングを手がけてきた株式会社電通デジタルの崔廷銀氏。前編では、Twitterというメディアの特徴や運用の基本的な心構えなどについてお伝えしました。後編となる本記事では、より具体的にTwitter運用のコツについて解説します。
「Twitter=バズる」だけではない。アルゴリズムを味方にする運用を

Q.崔さんは、さまざまな企業のSNS運営をサポートしていますが、今Twitterに関して寄せられる相談としてはどんなものが多いのでしょうか?
崔:最近多いと感じるのは、メインのTwitterアカウントは既に持っているものの、プロジェクトや新商品に合わせてサブアカウントを立ち上げたいというケースです。もちろん、これからTwitter運用を本格的に始めるケースも多いですし、Twitterが一気に伸びた7、8年前にアカウントを立ち上げたものの、効果を実感できなくて一度止め、その後やはり再開しようと相談されることもあります。
ただ、やはりTwitter案件のご相談を受けるとき、もっとも多く目標にされ、言及されることとして「バスりたい」と言われるケースが多い。もちろんそれを叶えられるのがTwitterの魅力ですが、「Twitter=バズる」だけではないとわかっていただくことも必要です。一時的なバズではない、ユーザーとの「継続的なコミュニケーション」が必要な案件もあります。そしてそれは、後々のバズを生む上でもきわめて重要なんです。
Q.なぜ「継続的なコミュニケーション」がバズを生むために重要になるのでしょうか。
崔:その理由は、Twitterの時系列だけではないアルゴリズム表示によるホームタイムラインにあります。ここでいうアルゴリズムとは、各ユーザーのタイムラインにどんなツイートを表示するかという仕組みです。
アルゴリズム表示ではユーザーがアカウントのツイートに「いいね」やリツイートなどのアクションをしないケースが続くと、Twitter側で「ユーザーはこのアカウントをあまり好んでいない」と判断し、フォロワーであってもツイートを表示しない場合が増えるのです。すると、「ここぞ」というバズを狙いたいときに、大切なメッセージがフォロワーへ届かないことも。だからこそ、普段からユーザーを巻き込む継続的なコミュニケーションでエンゲージメントを上げていく必要があります。
Q.つまり、継続的なコミュニケーションを取らないと一度獲得したフォロワーとの関係が途絶えてしまう可能性があるわけですね。
崔:そうですね。Twitterを含む、最近のSNSではコミュニケーションを頻繁に行い、ずっとつながっている関係を作ることが大切なんです。人間関係もそうですよね。何年も連絡のなかった人が急に「元気?」と連絡してきたら、うれしさよりも「急にどうしたんだろう」という不信感を抱いてしまうことがあるんじゃないでしょうか。ですから、日常的にコミュニケーションを取り、忘れさせない関係づくりが必要。そして「ここぞ!」というときにバズを生む設計が今のTwitter活用には求められます。
では、具体的にどれくらいの更新頻度が良いのかというと、アカウントの役割やそれにひも付く商品などによって異なりますが、基本は週1回以上のツイートが目安になるのではないでしょうか。そのくらいの更新頻度を持続できると、ユーザーと継続的にコミュニケーションが取りやすいと思っています。ただ、更新頻度は、そのアカウントから発信したい情報の量などによっても変わるので、あくまでも参考までに。
長く運用するには「3大エンゲージメント」以外の反応も大切にする
Q.Twitterを運用する中では、効果測定も必要になってきます。その場合、どんな数値を評価指標にするのでしょうか?
崔:企業が最終的に目指す「KGI(重要目標達成指標)」にもよるのですが、一般的にはフォロワー数の伸び方や各ツイートに対するエンゲージメントで評価するケースが多いですね。エンゲージメントの評価方法は企業によって異なるのですが、1ツイートに対して、フォロワー数の何%が反応したか、あるいはフォロワー以外を含め、そのツイートに触れたユーザー全体の何%が反応したか、といった基準を設定することが多い傾向です。
多くの方は、Twitterにおけるエンゲージメントといえば「いいね」「リツイート」「返信」の3つを思い浮かべると思います。私はこれを「3大エンゲージメント」と呼んでいますが、ユーザーがツイートに対して示す反応は実はこれだけではありません。例えば、ツイート内に添付された画像や動画をタップしたり、ハッシュタグやURLを見たりするのも1つの反応であり、エンゲージメントとしてTwitter側では計測できています。
Twitter運用では、とにかく3大エンゲージメントの数字を伸ばそうとしがちですが、ユーザーと「継続的なコミュニケーション」を行う上では、3大エンゲージメント以外の反応も評価に含めることが大切になるのです。
Q.なぜ3大エンゲージメント以外の反応も見るべきなのでしょうか。
崔:全てのツイートで3大エンゲージメントを多数獲得するのは簡単ではありません。3つの数字にこだわりすぎると、「いいね」やリツイートが少ないツイートは「エンゲージメントが悪い」と判断されてしまうので、ツイートのパターンが限られてしまったり、回数を減らしてしまったりすることがある。しかし、「いいね」や「返信」の数は少なかったとしてもツイートに含まれたURLにユーザーが遷移したり、動画をちゃんと見てもらえたりするならば、それは意味のないツイートにはならないですよね。「いいね」だけでなく、そのツイートがユーザーと何かしらエンゲージメントできたのかを含めて考える思考が必要なんです。3大エンゲージメントが大きくなるツイートのみに絞ることは、結果的にツイートの内容がワンパターンになり、加えて、先述のようにアルゴリズムのもと「一度獲得したファンとの関係が途絶える」リスクも発生しかねません。だからこそ、さまざまな評価指標を設定して、長期的に、幅広い方法でユーザーとコミュニケーションできる環境を作ることが大事なんです。
Q.最後に実践的なことを教えてください。Twitterで継続的なコミュニケーションをする場合、具体的にはどんなツイートをすればよいのでしょうか。
崔:ツイートする内容は、日常の何気ない話題で構いません。ただしポイントがあります。それは、ツイートの中にユーザーが反応できる余地を含めることです。例えば「今日はいい天気ですね。みなさんはどう過ごされますか?」といった形で、最後にユーザーに質問を投げかける。あるいは、ツイートに画像を添付し、あえてその画像の中に重要な情報を入れることでユーザーの画像タップを促すなど。ユーザーのアクションを予測して、アクションをとりやすいツイートを作る、ということを心掛けます。
そうして日ごろのコミュニケーションでユーザーとのエンゲージメントを獲得したのちに、キャンペーンや新商品発売といった「ここぞ」のタイミングで、バズを狙ったツイートを行います。日常的なコミュニケーションと、「ここぞ」というときのバズを狙ったコミュニケーション、その2つの設計をしていくことで、「ただ一人でツイートするだけ」にならない、ユーザーを巻き込むTwitter活用ができるかと思います。
Twitterというとバズを意識しがちですが、一過性のバズだけでなく、何気ない日常のツイートやコミュニケーションも重要になっていることが分かりました。バズを狙うためには日々の継続的なツイートが大切とのこと。最新のTwitter運用では、継続的なコミュニケーションからどうバズへつなげるのか、その設計図を描くことがポイントになりそうです。