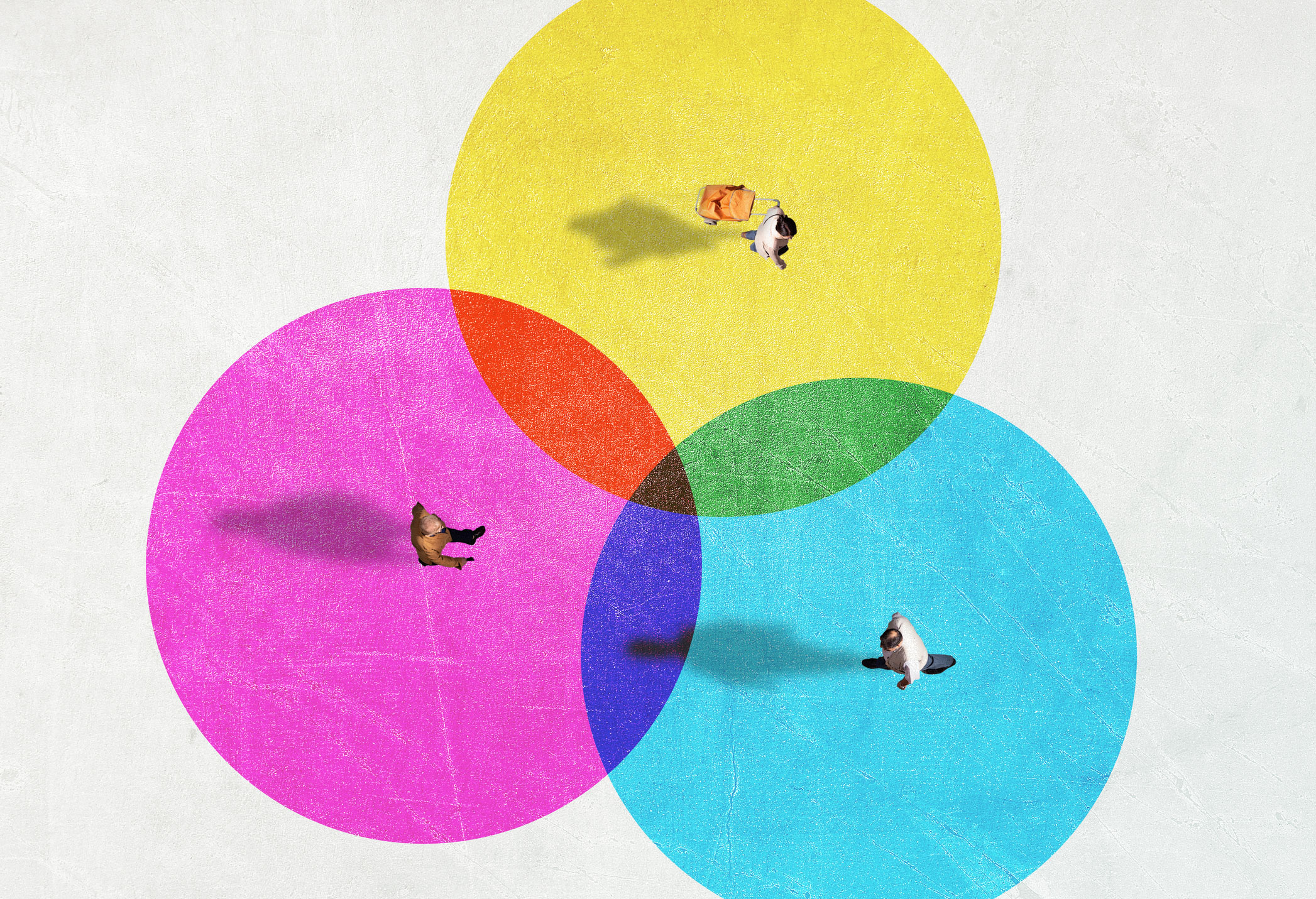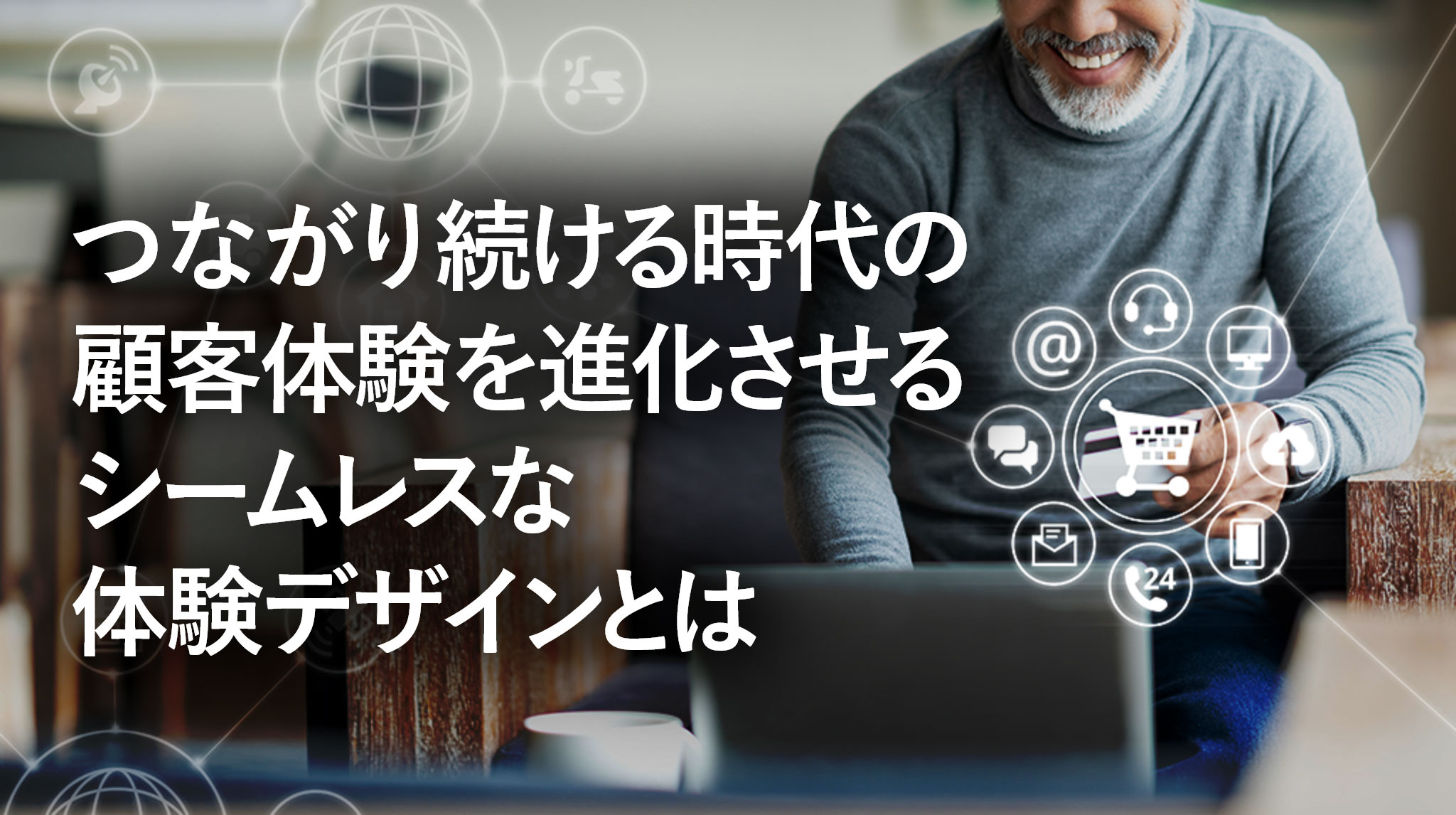「インスタ映え」という言葉が定着するなど、近年、強い存在感を放っているInstagram。写真や動画を中心としたSNSであることは周知の通りですが、「映える商材がないと向いてないでしょ?」「売り上げにつながるような施策は難しいのでは?」と、いざマーケティングの実務レベルで考えると導入に疑問を感じる担当者もいるのではないでしょうか。ところが、実は企業マーケティングの観点で見逃せない、そのほかの特徴もあるようです。そこで今回は、幅広い企業のInstagram運用やディレクションを手がける株式会社電通デジタルの江草香苗氏に、あらためてInstagramというSNSの特徴や運用のポイントを前後編の2回に分けて聞いていきます。
雑誌のように情報をキャッチアップする場所であり、かつコミュニティ形成の場

Q.近年、Instagramから流行が生まれることも増えていますが、あらためてどんなSNSなのでしょうか?
江草:Instagramは多くの人が想像する通り、ビジュアルやイメージに対して関心の強い人、心を躍らせる人が集まる場所だと思います。ただし、最近はきれいな写真を見ようとするだけでなく、情報ツールとして活用している企業や個人も増えています。
「マガジンライク」という表現が近いと思うのですが、まるで雑誌をペラペラとめくるように情報をキャッチアップできる場所に変わってきたのではないでしょうか。さらにInstagram内では、コミュニティも形成されるので、そこに対して反応を生み出せれば、ビジネスチャンスが発生しやすい場であるとも言えるでしょう。
もう1つ、Instagramの見逃せない特徴が、購買にもつなげやすいことです。Instagramには商品タグやショップ機能などコマース関連の機能があり、投稿した商品画像からECサイトなどへシームレスに遷移することが可能です。購買までの導線をつくれますし、さらに購入したユーザーが商品の写真を投稿し、クチコミにつなげるという良いサイクルも生まれやすい。
いわゆる「パルス型消費(何気なくスマートフォンなどで情報を見ているうちに、瞬間的に買いたい気持ちが芽生え、そのまま購買行動を起こすこと)」が成立しやすいプラットフォームだと思います。
Q.SNSで認知を得るだけでなく、その先の購買に結びつけられるのが大きな利点ということですか?
江草:そうですね。とはいえ、Instagramと消費の関連がフォーカスされたのはわりと最近の印象です。商品タグ機能がInstagramに導入されたのは、日本では2018年からですが、その後、新型コロナウイルス感染拡大の影響やショップ機能の導入もあり、2020年頃からさらに注目を浴びました。
というのも、コロナ禍でアパレルショップがショップ機能やインスタライブを活用して、店頭に来られない方の商品購入につなげるブランドなどが話題になったからです。また、コスメ商品の使い方やメイクのHow toをインスタライブで説明しながら購買につなげる方法も普及。こういった動きをきっかけに広まった印象があります。
Q.ということは、購買につなげる面ではまだまだ開拓期であり、企業の相談も増えているということでしょうか?
江草:エンゲージメントから購買へつなげる導線設計を戦略的に描けているアカウントはまだ多くなく、最近はそういったプランニングをご相談いただくことも増えています。もちろん、Instagramによってファンを増やしたい、自社に愛着を抱いてもらいたいという相談も依然としてありますね。
通信など無形商材を扱う企業もアカウントを運用。成功への分かれ道はどこに
Q.Instagramを活用している企業の業界や分野についても教えてください。以前は女性向けファッションやコスメが中心のイメージでしたが、変化しているのでしょうか?
江草:確かにファッションやコスメも多いですが、今はそれ以外も、幅広いジャンルで使われています。私が携わっている企業アカウントだけでも、飲料や通信、BtoBなど多岐にわたります。
Q.通信などの無形商材を扱う企業は、Instagramをどんな風に活用するのでしょうか?
江草:ブランドイメージの発信や、企業に対する愛着形成です。通信や金融は、目に見えない商品を扱う「無形商材」の分野。ですので、通常の広告では、サービスのメリットや優位性を説明するなど、機能訴求がメインになりがちです。しかし、そういった広告では、ブランドイメージの発信や愛着形成を行いにくい面があります。
そこで“第2の手”としてInstagramを活用します。例えばターゲット層が興味を引くような“映える写真”でエモーショナルに情報を提示したり、それこそマガジンライクにターゲットが知りたい Tipsを伝えたり。それによってブランドイメージをアップさせることにチャレンジしている企業が多いですね。
また、日常に役立つライフハックを発信する、自社が行っているCSRの活動を紹介するなど、無形商材のブランドに対して情緒的なイメージを持たせたり、ポジティブな印象を与えたりということも可能です。
Q.企業のマーケティングを考える上で、Instagramと相性の良い商材やジャンルはあるのでしょうか?
江草:あくまで個人的な意見ですが、やはり“写真映えしやすい”商材やジャンルは相性が良いと思います。ファッションやビューティー、インテリア、車などはもちろん、食べ物や旅行も向いているでしょう。一方で、先ほど話したように通信や金融といった無形商材を扱う分野のブランディングアカウントも増えていますよ。
もう1つ、相性が良いと思うのはポジティブな表現がマッチする商材。なぜならInstagram自体がポジティブな投稿が多く、ネガティブなものはあまり見かけないからです。Instagramに広告を載せるなら、不安をあおるようなネガティブ系の広告より、ポジティブな表現の方が親和性は高いのではないでしょうか。
Q.企業がInstagramの運用をうまく行うポイントはどこにあると思いますか
江草:ブランドイメージをきちんと伝えられるかが、成功への大きな分かれ道だと思います。そのためには、ブランドのコンセプトを明確に決め、それに根付いた投稿をしていくこと。また、投稿のトンマナがブレないこと。企業、個人にかかわらず、こういったことが守れているアカウントはInstagramユーザーに対して影響力を持ちやすい。それが継続できれば、骨太に成長する可能性が高まるのではないでしょうか。
Instagramはできることがたくさんあります。商品をきれいに見せる、ショッピングに誘導する、ハッシュタグを使って盛り上げる、インフルエンサーを起用するなど、展開できるコンテンツや打ち手は多数。しかし、それら全部を実施すればうまくいくということでは決してないと思います。
Q.江草さんは幅広い企業のInstagram運用に携わっていますが、既に開設済みの企業アカウントに関わる場合、まずどんな部分をチェックして、どうアドバイスしていくのでしょうか。
江草:最初にチェックするのは、今話したブランドイメージやコンセプトなど、アカウントが伝えたいことが明確になっているかどうか、です。
この部分が明確になっていたら、その先で抱えている課題の対策を考えます。といっても、課題はアカウントごとにさまざまで、解決策も多岐にわたります。例えば「フォロワーが増えない」という課題なら、エンゲージメントが低いことなどが原因として考えられるでしょう。「新規ファンの流入を増やしたい」というときは、広告やインフルエンサーの起用などを提案します。
そのほか、「ファンはいるけれど購買に結びつかない」という課題の場合は、購買までの導線設計を見直しますし、そもそものエンゲージメントの低さが理由であれば、コンテンツとユーザーの親和性を上げる施策を考えます。
Q.中には課題が明確になっていない、あるいは、そもそも「運用がうまくいっているのかわからない」というケースもあると思います。その場合はどう対応していくのですか?
江草:一例ですが、競合比較の分析ツールを使って、まずは自社のアカウントの立ち位置を確認していただきます。その結果をもとに目標を設定して、現状で足りない点や必要な施策をあぶり出していきます。電通デジタルにはInstagram運用に強いスタッフが多数在籍しており、私だけでなくアナリスト など、さまざまな分野に強みを持つメンバーも交えながら、現状把握から目標設定、施策の実行までをサポートしていく形です。
写真や動画を使って企業のイメージ向上や愛着形成に活用されている一方で、購買に結びつけやすいという特徴も持つInstagram。マーケティングにおいては、幅広い活用の可能性がありそうです。続く後編では、運用に必要なクリエーティブディレクションの考え方や、さまざまな機能の「使い分け」についても聞いていきます。