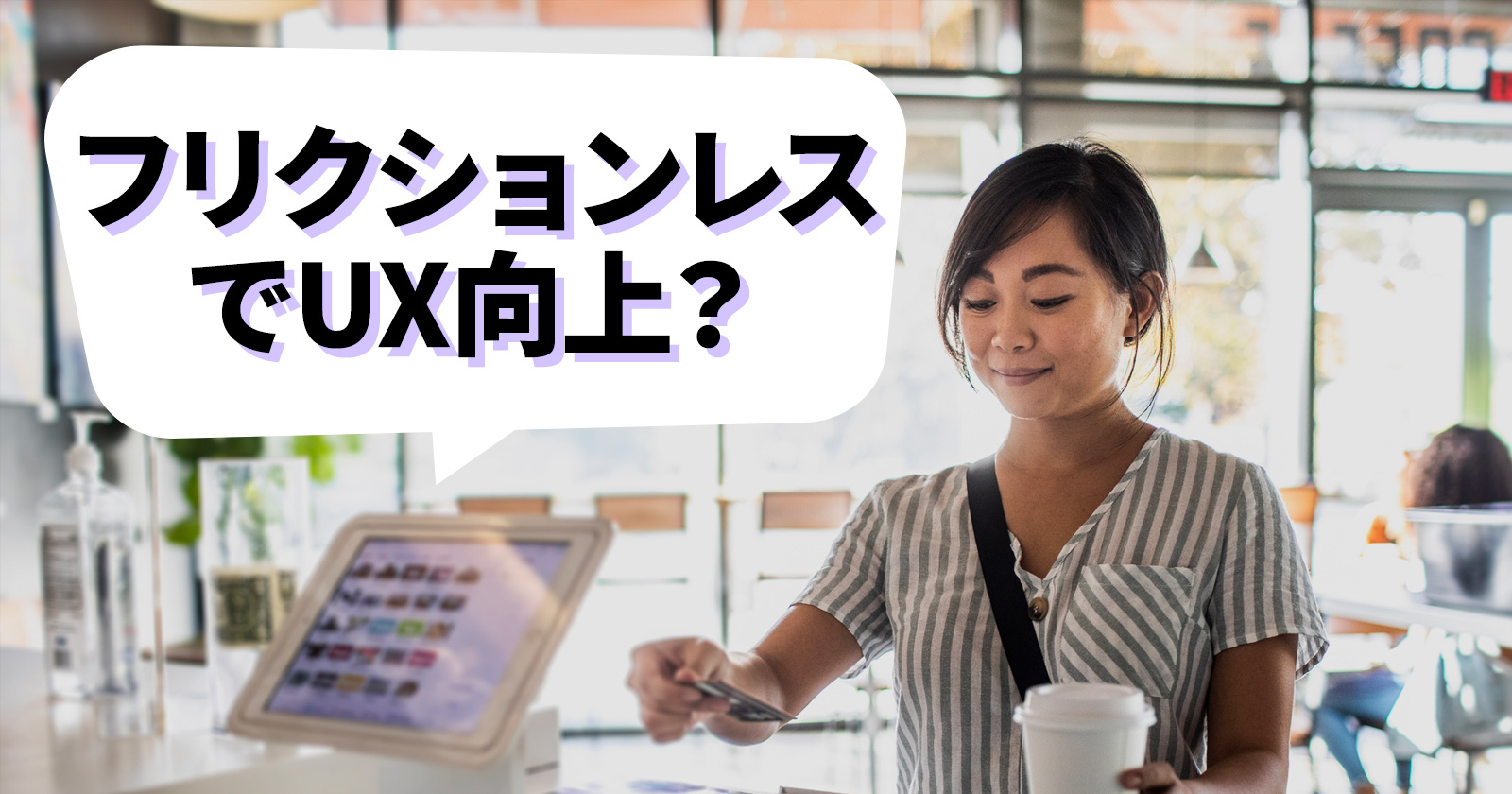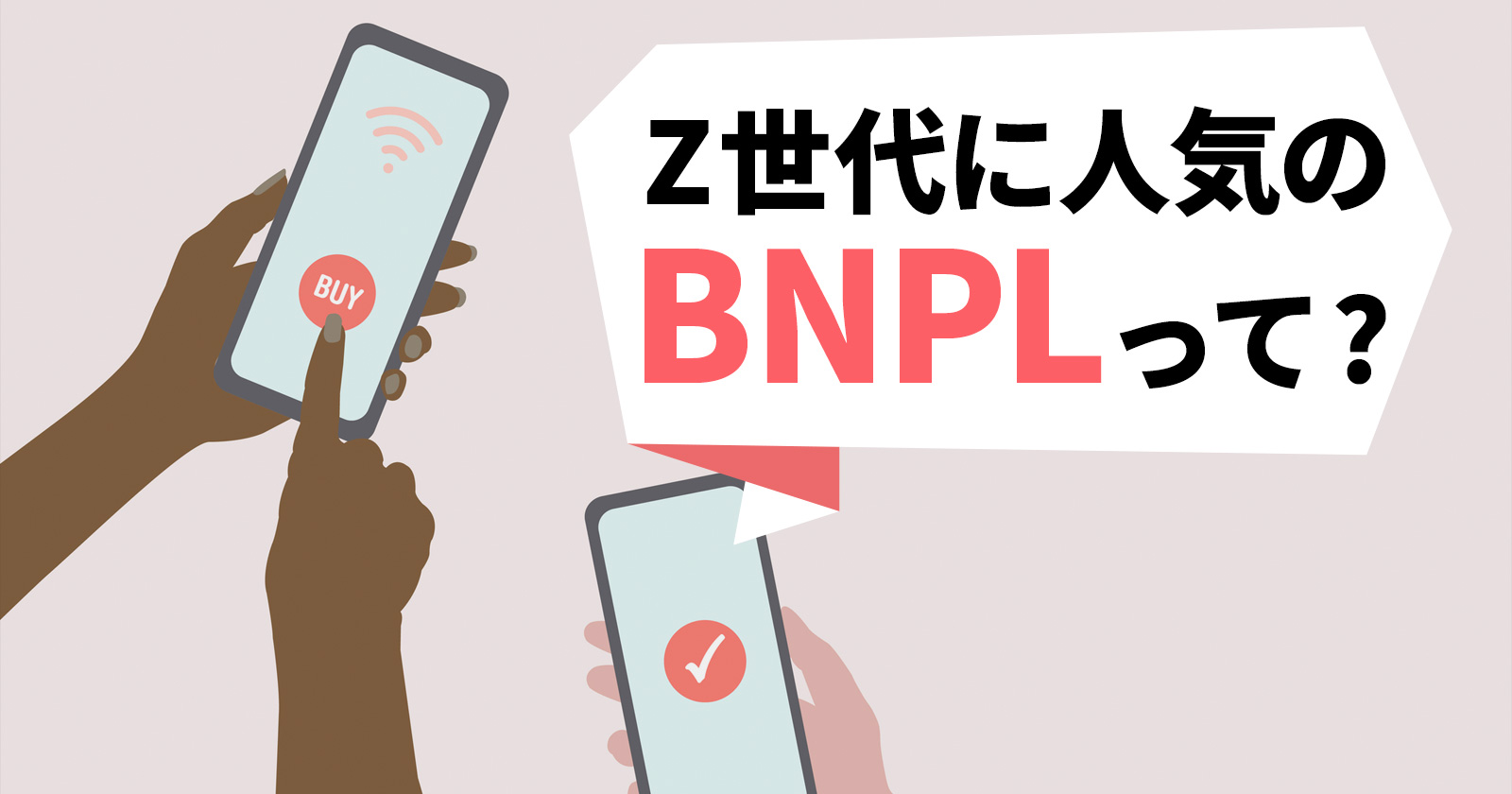非接触決済の普及やECショッピングの活況など、コロナ禍によって人々の消費行動は大きく変化しました。それと同時に、顧客が感じる「フリクション(購買体験における煩わしさ)」の傾向も変化。特に近年、多くの顧客が買い物に求めるようになったのが「速さ」です。スピード感を持って商品を購入できるかどうかは、「買う・買わない」の決断を左右する重要な要素になっています。
こうしたフリクションレスな購買体験の重要性は、EC事業だけにとどまらず、さまざまなビジネス領域へと波及しています。そこで今回は、「顧客の満足度を上げるためのヒントは?」「自社サービスの価値を向上させる糸口は?」といった課題意識を持つ方に向けて、フリクションレスを取り巻く現状を解説。「フリクションレスな購買体験の設計は、EC以外の業種においてもサービス価値向上に寄与するか?」というテーマの下、フリクションレスによるUX(ユーザーエクスペリエンス)最適化のヒントを探ります。
今、人々が求める「フリクションレス」な購買体験とは?
コロナ禍における外出制限や衛生観念の変化は、キャッシュレス決済の拡大やECサイトの利用率の上昇など、顧客の購買行動にも大きな影響を与えました。そうした状況の中で、最近注目を集めているキーワードの1つが「フリクションレス」です。
マーケティングの分野で用いられるフリクションレスとは、顧客が商品を購入するときに「フリクション=摩擦」を感じない状態を指します。フリクションレスをサポートする「非接触決済」などの手法については、こちらの記事でも解説しています。
では、買い物における「摩擦」とは何でしょうか。それは「商品の寸法が分からない」「返品交換の手続き方法が分かりにくい」など、商品を購入する過程で顧客が感じるさまざまな「ストレス」と言い換えられるでしょう。フリクションレスな体験を実現するには、障害物を取り払うように、購入時に生じる疑問点をあらかじめ除いておくことが重要になります。
なぜなら疑問が生じれば、それを解消するための「時間」や「手間」がかかるからです。ECショッピングが一般化したことで、顧客はスマートフォン1つあれば、自分の都合の良いタイミングで、その場ですぐに商品を購入できるようになりました。買い物に時間的・地理的な制約が少なくなった分、「待つこと」「時間がかかること」に対する忌避感は増大しているのが現状です。
米国Vertical Web Media社のWebメディア『Digital Commerce 360』と市場調査会社のBizrate Insights社が2019年に共同で実施したオンラインショッピング利用に関する調査によると、配送リードタイムの短縮に加え、ユーザーは「効率的な購入手続きプロセス」や「検索結果の改善」も望んでおり、あらゆる観点で顧客がECショッピングに「速さ」を求めていることは明らかです。
決済周りの精緻な設計が、フリクションレス実現の第一歩

買い物における「速さ」を意識し、フリクションレスな購買体験を創出していくことは、ECショッピングをはじめとしたコマース事業の拡大を図る上で非常に重要です。
例えば、ECサイトで商品を購入するとき、多くの人が気になるのが返品やキャンセルに関する情報ではないでしょうか。それらはFAQページに明示されていることが多いものの、全てのユーザーがそこまでたどり着き、返品・キャンセルポリシーを読むわけではありません。「返品可能な条件は?」「返品のための配送料はどちらが負担するの?」「返品の受付期間は?」など、さまざまな疑問点を解消できなければ、購入自体をやめてしまうこともあるでしょう。
さらに、実際に返品を行うとなると、クレジットカードや電子マネーを利用していた場合には、返金手段が限定されるケースもあります。特に電子マネーは返金処理に対応していないものも多く、現金での返金となったり、返品そのものが行えなくなったりすることもあるようです。
それはECサイトに限らず、実店舗での買い物にも当てはまるでしょう。商品が高額であるなら、疑問点を店員に確認できなかった場合、購入を諦めてしまう確率はなおさら高まります。そうした離脱を防ぎ、商品を確実に購入してもらうには、必要な情報へのスムーズなアクセスや過不足のない情報提示、購入に関する手続きの簡略化など、購入直前のフリクションをいかに解消できるかがカギを握ります。
実際、そうしたフリクションレスに向けた施策は、さまざまな形で行われるようになってきています。幾つか事例を見ていきましょう。
事例1:RFIDタグ利用によるセルフレジ決済
「レジの混雑」というフリクションの解消に役立っているのが、RFID(Radio Frequency IDentification)タグを利用したセルフレジ決済です。RFIDは、電磁波を用いて非接触でデータのやりとりが行えるシステム。バーコードなどとは異なり、商品を1つひとつスキャナーにかざす必要がなく、複数のタグを一括で読み込めるのが特長です。セルフレジはもちろん、有人レジにおける打刻時間の短縮にも効果を発揮しています。
事例2:宿泊施設でのスマートロックの導入
ホテル宿泊時につきものなのが、チェックイン手続きの手間やルームキー管理の煩わしさ。最近は、スマートフォンのアプリで宿泊手続きを済ませられたり、それをそのままルームキーとして使えたりするスマートロックの導入も進んでいます。
事例3:タブレットの活用/モバイルオーダー
飲食店で導入されているタブレットを用いた注文形式は、オーダーの際に店員を呼ぶことに抵抗を感じる顧客のフリクション解消に役立ちます。また、スマートフォンなどを利用して、飲食店に到着する前に注文・決済を行うモバイルオーダーも、食事の待ち時間や飲食店での滞在時間の短縮につながります。なお、モバイルオーダーなどの「事前注文サービス」については、こちらの記事でも解説しています。
こうした事例から読み取れるのは、デジタル化やIT技術の活用がフリクションレスの実現には欠かせないということ。特に注目したいのが、購買フローの最終段階にあたる「決済」です。財布から現金を取り出し、紙幣や小銭を数え、お釣りを受け取る‥‥‥という支払い時の煩わしさを解消する「キャッシュレス決済」は、フリクションレスを代表する体験と言えるでしょう。キャッシュレス決済の導入にあたっては、手軽に後払い・分割払いができる「BNPL(Buy Now, Pay Later)」をはじめとした決済手段の拡充や、非接触かつ短時間で処理が完了するシステムの開発も、重要な検討材料となります。
加えて、前述したように、決済後のプロセスである「返品」にまで配慮した設計にできれば、購入のハードルをより一層下げることができるでしょう。例えば、ECサイトで衣料品を購入するときに起こりがちなのが、「サイズが合わない」「思っていた色味と違う」といった問題ですが、ある大手通販サイトでは、商品を無料で受け取り、試着後に購入するかどうかを決められるサービスを導入しています。これは、返品におけるフリクションを払拭した好例と言えるでしょう。
大きな顧客体験の変革は、小さなフリクションの解消から

続いてフリクションレスの考え方が、今後のビジネスの活性化にどのように応用できるのか、考えていきましょう。
顧客体験の改善を考えるとき、「ポジティブな体験をいかに増やせるか」という視点はもちろん大切です。しかし、積み重ねたポジティブな体験がネガティブな体験1つで台無しになるケースも少なからずあり、「ネガティブな体験をいかに減らせるか」という視点も決して蔑ろにはできません。フリクションレスとはまさに後者に注目したアプローチです。ユーザーの購買行動の障壁になるようなネガティブな要素を取り除き、快適な購買体験を提供するための地盤作りのような役割を果たします。
こうしたフリクションレスの取り組みの有効性は、小売業における購入や決済プロセスだけにとどまらず、その他のビジネスや窓口業務などにおいても力を発揮する可能性を秘めています。
コロナ禍で導入が進んだ「リモート診療」や保険の「オンライン加入」は、その好例でしょう。リモート診療は、体調が悪い中で病院まで足を運んだり、長時間診察を待ったりする「通院のハードル」というフリクションを、診察のオンライン化によって解消できる手法。時間の確保や移動の手間といった煩わしさの解消だけでなく、産婦人科の受診などプライバシーへの配慮が求められるケースにも有効な施策と言えます。
他にも、北海道・千葉県・京都府・山口県で試験的に始まった「運転免許更新のオンライン講習」も、フリクションレスの一例と言えるでしょう。免許更新に必要な講習をオンラインで事前に受講できる仕組みで、免許センターで手続きにかかる時間を短縮できます。特に地方の場合、郊外にある免許センターまで公共交通機関を乗り継いで足を運ばなければならないことも多く、時間の確保に苦労している人は多いのではないでしょうか。こうした地方特有のフリクションレスの実現は、地方に住むハードルを1つ取り払うことであり、地方創生への一手となり得るかもしれません。
自社のEC事業においても、他業種のサービスにおいても、フリクションレスと聞くと大規模なシステム改修を伴い、時間やコストがかかるイメージを抱くかもしれませんが、必ずしもそういうわけではありません。待ち時間や混雑を解消するような小さな工夫が、大きなUX向上につながることもあります。
大事なのは自社の顧客を理解し、少しずつ着実に改善方法を考えること。まずは、商品・サービスの提供や受け渡しは「待たなければならないもの」「足を運ばなければならないもの」といった固定概念を取り払うことが、その第一歩となるのではないでしょうか。EC事業だけでなく幅広い業種において、慣例化していたフリクションの解消は、UX向上のチャンスと捉えることができます。今回ご紹介した事例の中に、ビジネスにおけるサービス価値向上のヒントがあるかもしれません。
顧客が買い物に求める「速さ」に対応するには、商品購入に関する疑問点や懸念材料など、ネガティブな要素を先回りして取り除いておく、気配りの行き届いた設計が重要です。そのためには、顧客が日ごろから感じている小さなストレスにいかに気付けるかがポイントとなるでしょう。そうしたフリクションレスの考え方は、ECや実店舗を持つ小売事業だけでなく、教育や福祉など人々に無形のサービスを提供するビジネス、消費者とは直接接点は持たなくても、生活インフラやテクノロジーで社会を支えるBtoB事業など、実はあらゆる分野に応用できるのかもしれません。価値を付け加えていくのではなく、価値の損失を防ぐというフリクションレスの考え方を、自社ビジネスのUX向上の足掛かりとして取り入れてみてはいかがでしょうか。
フリクションレスのほか、「非接触決済」や「BNPL(後払い決済)」「BOPIS(店舗受け取りサービス)」なども、UX向上を考える上での注目キーワードです。顧客にとことん寄り添ったUX設計、私たちと一緒に考えてみませんか?お問い合わせはCONTACTから。