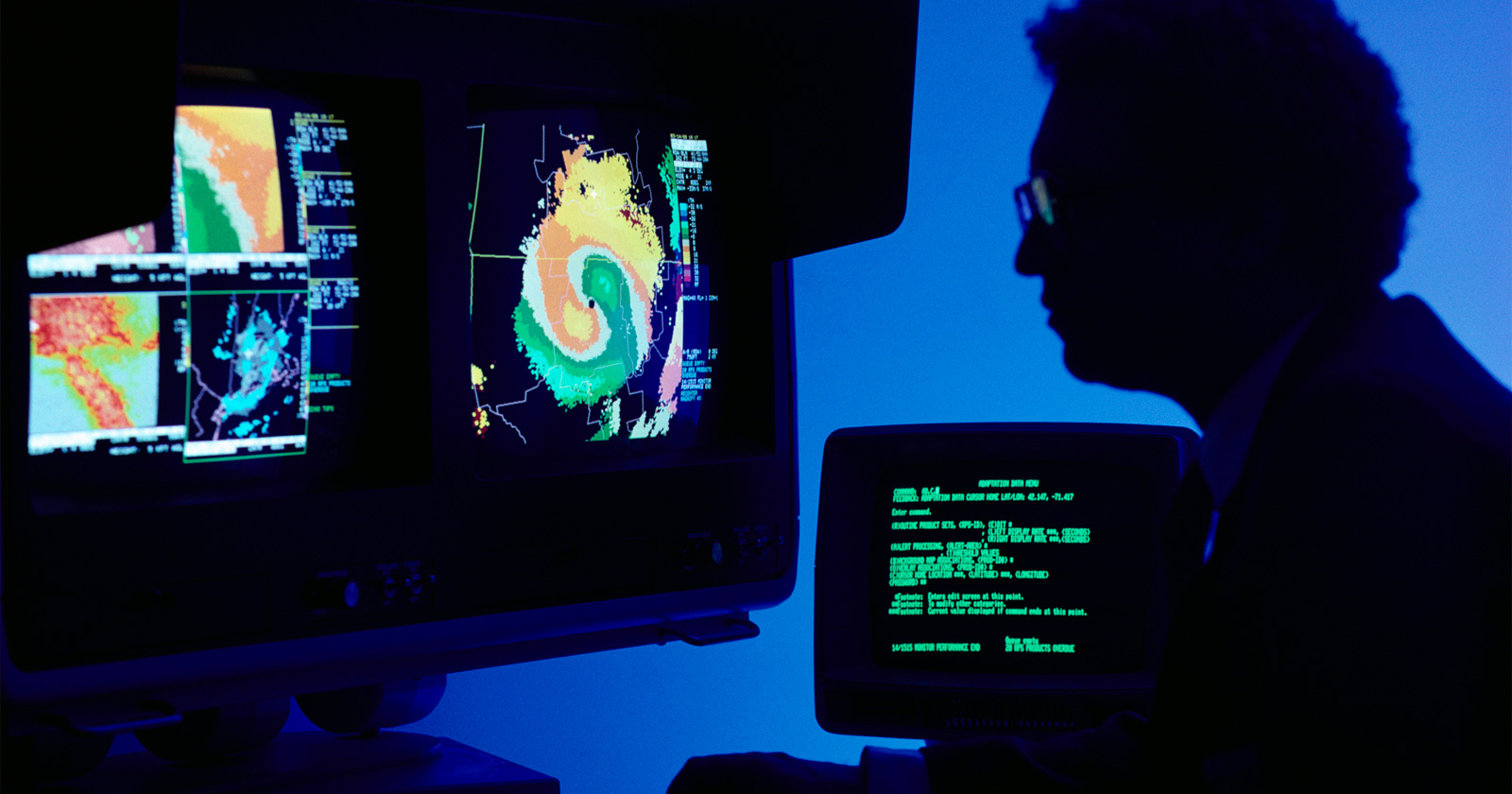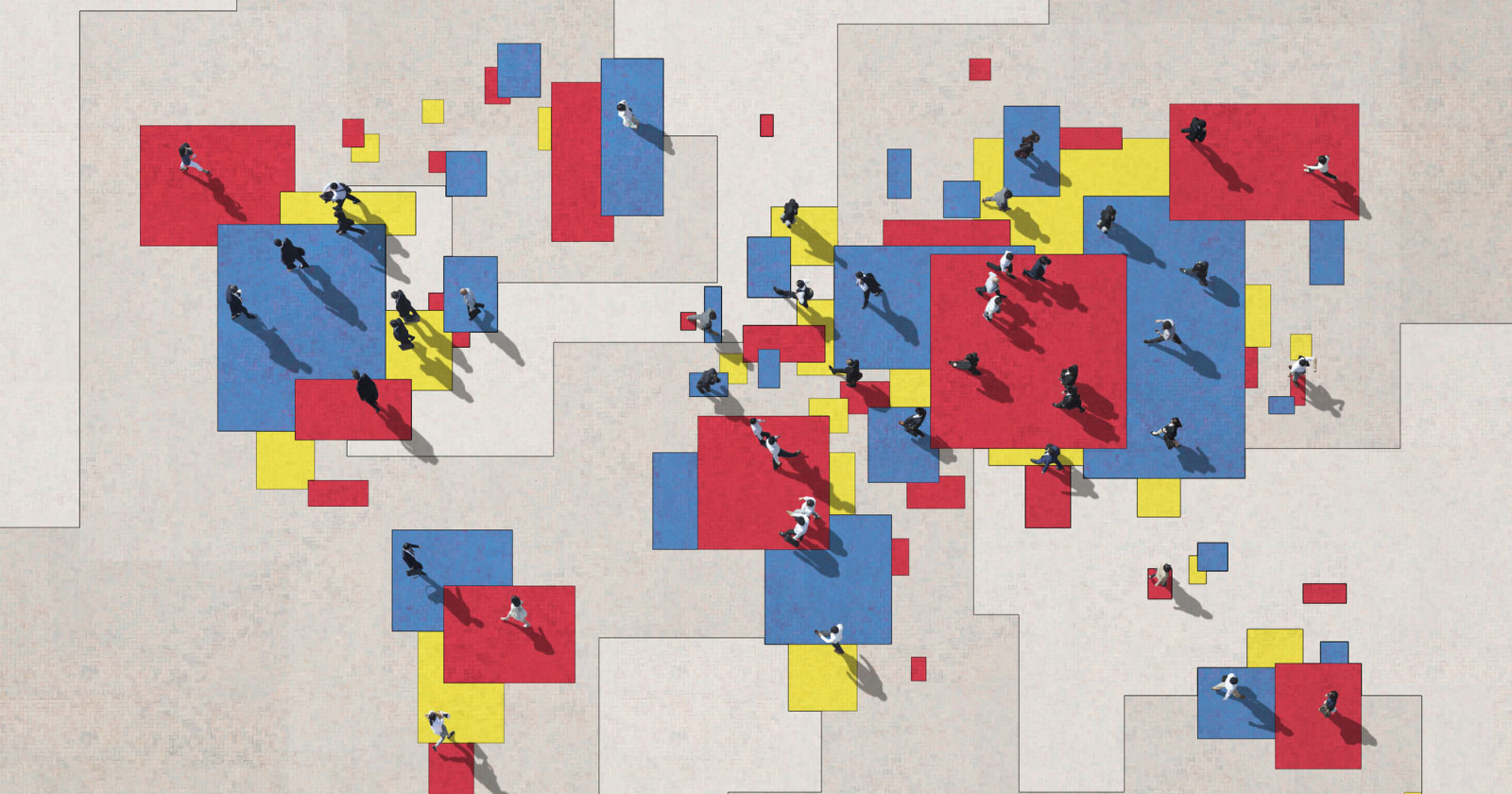コロナ禍によってニューノーマル時代を迎えた今、私たちの消費行動も大きな過渡期に直面しています。変化の1つとして挙げられるのが、オンラインショッピング・宅配サービス・キャッシュレス決済といった非接触型経済活動の活発化。「コンタクトレスエコノミー」と呼ばれるこの経済活動は今後、技術やサービスをさらに進化させ、消費スタイルの主流へと成熟していくことが予想されます。
であるならば、顧客にエフォートレスな体験(努力を必要としない良質な顧客体験)を提供するためには、コンタクトレスエコノミーのCX(カスタマーエクスペリエンス)はどうあるべきなのでしょうか。次世代のCXについて考察しながら、非接触だからこそ重要なCX設計のポイントを探ります。
コンタクトレスエコノミーは、「あったら便利なもの」から「なくてはならないもの」へ
新型コロナウイルス感染症の拡大以降、財布から現金を取り出したり、店頭で商品を手に取ったりする機会が減ったという実感はないでしょうか。直接手で触れることなくモノやサービスを売り買いする経済活動全般を、「コンタクトレスエコノミー(非接触経済)」と呼び、ECサイトでの購入やキャッシュレス決済もこれに含まれます。この新たな経済活動は、長引く景気の低迷で落ち込んだ店頭消費をカバーするものとして加速度的に広がっており、国内外で熱い注目を集めています。
まずはコンタクトレスエコノミーを「在宅消費」と「家庭外での非接触型消費」の2タイプに分けて見ていきましょう。
在宅消費(タッチポイントは家庭内)
在宅消費とは、これまで家庭外だった消費者のタッチポイントが家庭内に移行した消費活動のこと。2008年のリーマンショック以降に拡大し、コロナ禍で外出を控えるようになってから、さらに増加しました。食品や日用品といった消費財のインターネット通販、宅配サービス、デジタルコンテンツの活用にとどまらず、オンライン教育やバーチャルバンキングなどの金融サービス、オンライン診療などのヘルスケア分野と、幅広い領域で急速に拡大しています。
家庭外での非接触型消費(タッチポイントは家庭外)
これまで家庭の外で消費していたタッチポイントはそのままに、デジタル技術やサービスの発展によって登場したのが家庭外での非接触型消費。キャッシュレス決済・非対面での接客・セルフレジなど、スーパーをはじめとした小売業やレストランなどの飲食業で急速に浸透しつつあります。
「在宅消費」「家庭外での非接触型消費」の双方とも、衛生観念の向上や行動様式の変化など、消費者側のニーズとテクノロジーの進化が一体となって、購入体験がアップデートされたことが分かると思います。
デロイト トーマツ グループが作成した報告書「非接触経済の台頭 |コンタクトレス・エコノミーがもたらすCOVID-19危機後の世界」によると、アジア太平洋地域における在宅消費の市場規模は、2025年までにこれまで(2020年11月現在) の約2倍にあたる3兆ドルに達すると見込まれています。家庭外での非接触型消費も含めると、それをはるかに上回る伸びになるでしょう。まさにコンタクトレスエコノミーは、これからの時代を担う新たな消費スタイルとなりつつあるのです。
シンプル・簡単・スピーディー。既存のCXをアップデートして、さらなる体験価値向上を実現

では、コンタクトレスエコノミーは具体的にどのような発展を見せているのでしょうか。その実態は、「コンタクトレスエコノミーの登場で、CXはいかに進化したか」という観点から見ることが重要だと私たちは考えます。そこで、現在CX領域が目覚ましく進化している「家庭外での非接触型消費」を中心に、事例を見ていきましょう。まずは、既存のCXを非接触型にアップデートした例です。
セミセルフレジ、アプリ決済
家庭外での非接触型消費としてまず思い浮かぶのは、飲食店や小売店におけるセルフレジやアプリ決済という方も多いでしょう。店員が商品をスキャンし、顧客が精算機で会計を行うセミセルフレジは、コンビニエンスストアやスーパーなど多くの店舗が既に導入しており、レジの混雑解消と多様な決済方法への対応に役立っています。
交通機関の非接触ディスプレイ・非接触センサー
交通系ICカードなど、いち早く非接触型アプローチを行ってきた鉄道会社では、自動券売機のタッチパネルを触らずに操作できる非接触センサーも導入しています。さらに、乗客の問い合わせに応対する非接触ディスプレイを設置し、駅係員が遠隔から乗客を案内する実証実験をスタート。航空会社では、手荷物預け機に非接触センサーを設置する実証実験を開始しています。
不動産会社のオンライン内見、調剤薬局の宅配ロッカー
不動産会社のスタッフが現地に赴き、映像を通して希望者に物件を紹介する「オンライン内見」は、コロナ禍以前から実施されていたものの、ここ数年で利用者が急増。冷蔵機能付きの宅配ロッカーを設置して、処方薬を非接触で受け渡す調剤薬局の実証実験も始まっています。
これらの事例から読み取れるのは、コンタクトレスエコノミーは「衛生的だから」「人込みを避けられるから」という理由だけで広がったわけではないということ。既存のCXを「シンプル・簡単・スピーディー」にアップデートしたからこそ、顧客の支持を得られたと言えるのではないでしょうか。
コンタクトレスな消費体験を創出するには、CX全体を見渡す視野が必要
では次に、テクノロジーの進化によって新たなCXを創出したサービスの事例を見ていきましょう。
無人店舗
コンビニエンスストアやスーパーでは、スマートフォンやAIを活用した認証技術、センサー、カメラなどの導入により、レジ業務を廃した店舗が増加中です。飲食店では、顧客がスマートフォンで注文を行うモバイルオーダーシステムや配膳ロボットを導入するケースも出てきています。
百貨店の非接触AI採寸システム
大手百貨店の紳士服売り場では、顧客と販売員の接触を必要としない、非接触AI採寸システムを導入。スマートフォンアプリに簡単な情報を入力し、正面と側面の全身写真を撮影するだけで高精度に採寸。自分の体にぴったりの服を購入できます。
デリバリーロボット
物流業界やデリバリー事業においては、自動走行による宅配ロボットの実証実験も進んでいます。公道走行に向けては今後、法整備が必要ですが、実用化もそう遠い話ではないかもしれません。
これらの非接触型サービスは、顧客に新たな体験をもたらすだけでなく、サービスを提供する事業者側にも人手不足の解消や、スタッフの安心・安全の確保など多くのメリットがあります。中でも注目すべきは、バックヤード管理と物流の効率化でしょう。
例えば、コンビニエンスストアやスーパーの無人店舗では、POSデータや性別・年齢といった顧客情報など、従来型店舗と同様のデータを得られるだけでなく、顧客が一度手に取った後で棚に戻した商品など、購入に至るまでの細やかな行動も分析できるように。こうしたデータとAIなどの最新技術とを組み合わせれば、商品の在庫確認と発注、配送を自動管理できるようになります。
コンタクトレスエコノミーのCX設計にあたっては、このように顧客の満足度を高めるために「物流→バックヤード→商品の購入→商品の受け取り」までを含めたトータルなプロセスをデザインするという姿勢が重要ではないでしょうか。場当たり的に非接触化を導入するのではなく、バックヤードも含めてCXをリデザインすること。そのような視点を持てば、戦略的なコンタクトレスエコノミーの実現が可能になります。
コンタクトレスエコノミーの台頭により、以前は注目されていなかった新たな顧客セグメントも浮き彫りになっています。インターネット通販よりも実店舗での購入スタイルを好みつつ、スムーズな会計を望む客層がその1つ。こうした顧客は、非接触型による安心・安全に加え、消費を通して「情緒的で付加価値の高い体験」を求めています。テクノロジーを駆使しつつ、彼らに充実した購入体験を提供するには何が必要かという視点に立ってCXを設計すれば、コンタクトレスエコノミーをよりいっそう洗練させることができるでしょう。
顧客をエフォートレスに導くことができる次世代のCXとは

では、前章で触れた「バックヤードも含めたCXのリデザイン」のポイントを、別の角度から見ていきましょう。
コンタクトレスエコノミーでは人の介在が少ないことから、顧客とのタッチポイントとなる「フロント」に加え、顧客の問い合わせ窓口となる「コンタクトセンター」も念頭に置いて、CXを設計する必要があります。フロントにおいては、上質なデジタル体験をいかにして作り出すか。コンタクトセンターにおいては、電話・メール・チャット・FAQなどさまざまなチャネルを通じて、いかに顧客の不安や疑問を解消するか。この両輪でCXを向上させて初めて、顧客にエフォートレスな体験を提供できると言えます。
フロントおよびコンタクトセンターを両輪で回して顧客の満足度を高める具体的な道筋は、企業や商品・サービス、環境に応じて異なります。しかし、いずれにも共通するのは、顧客の声にじっくりと耳を傾ける姿勢が大切だということです。フロントおよびコンタクトセンターで集めた顧客データや要望を丹念に精査し、CX向上の方向性を探ること。また、そこから見えてきた改善策を、新しいテクノロジーで実現できないか検討すること。こうしたアプローチが求められているのではないでしょうか。
コンタクトレスエコノミーのCX設計においては商品・サービスの購入時に「シンプル・簡単・スピーディー」を実現するとともに、購入の前後を含めた消費行動全体で、顧客にエフォートレスな体験を提供することが大切であることを見てきました。導入には相応のコストがかかるため、自社が扱う商品・サービス、顧客層、提供したい価値などを踏まえた上で、戦略的に検討する必要があります。顧客の声を聞き、顧客とのタッチポイントを見直し、新たなテクノロジーを活用する。これらのポイントを踏まえつつ、自社に合ったデザイン戦略を立ててCXを設計してみてください。