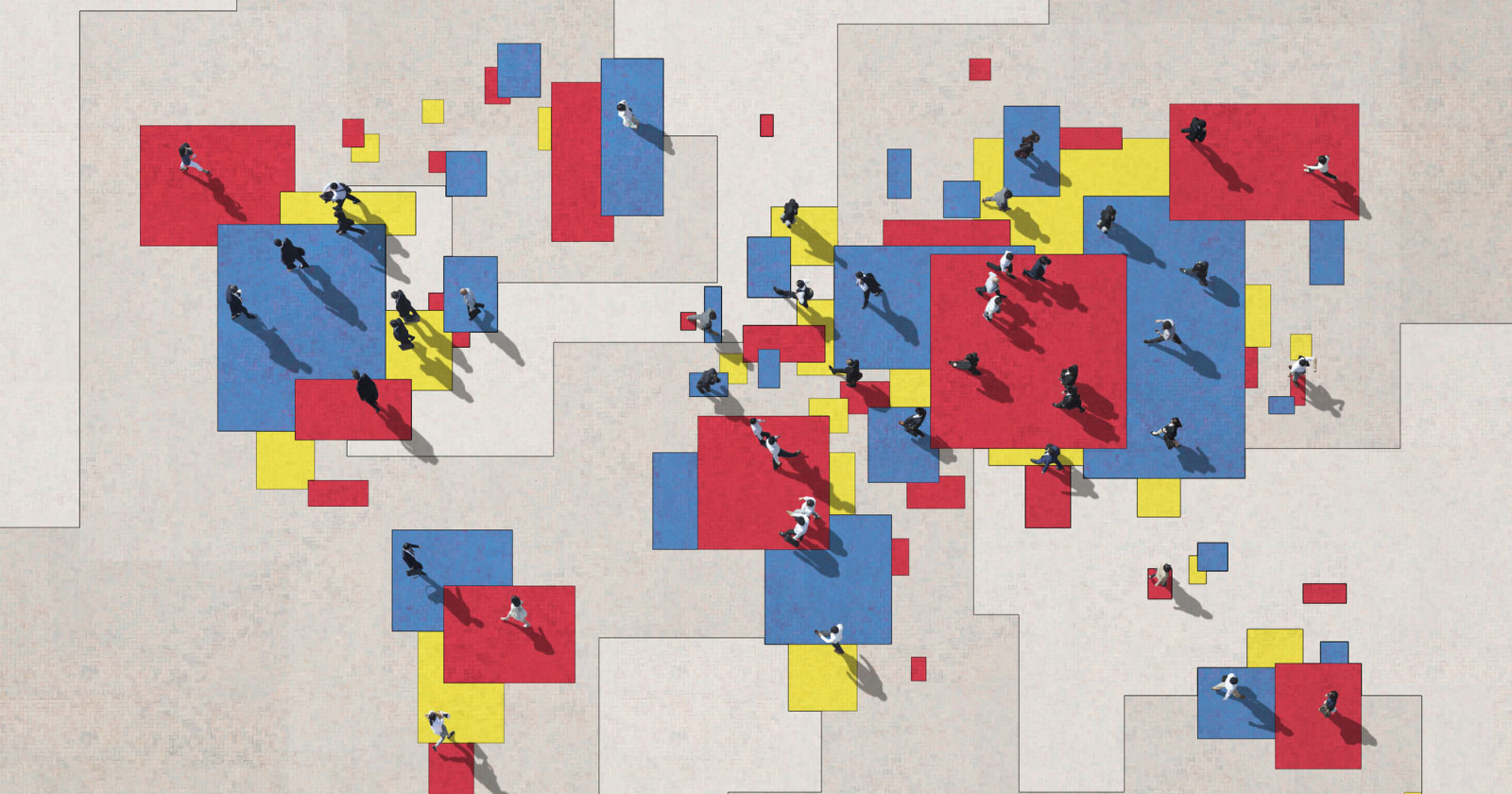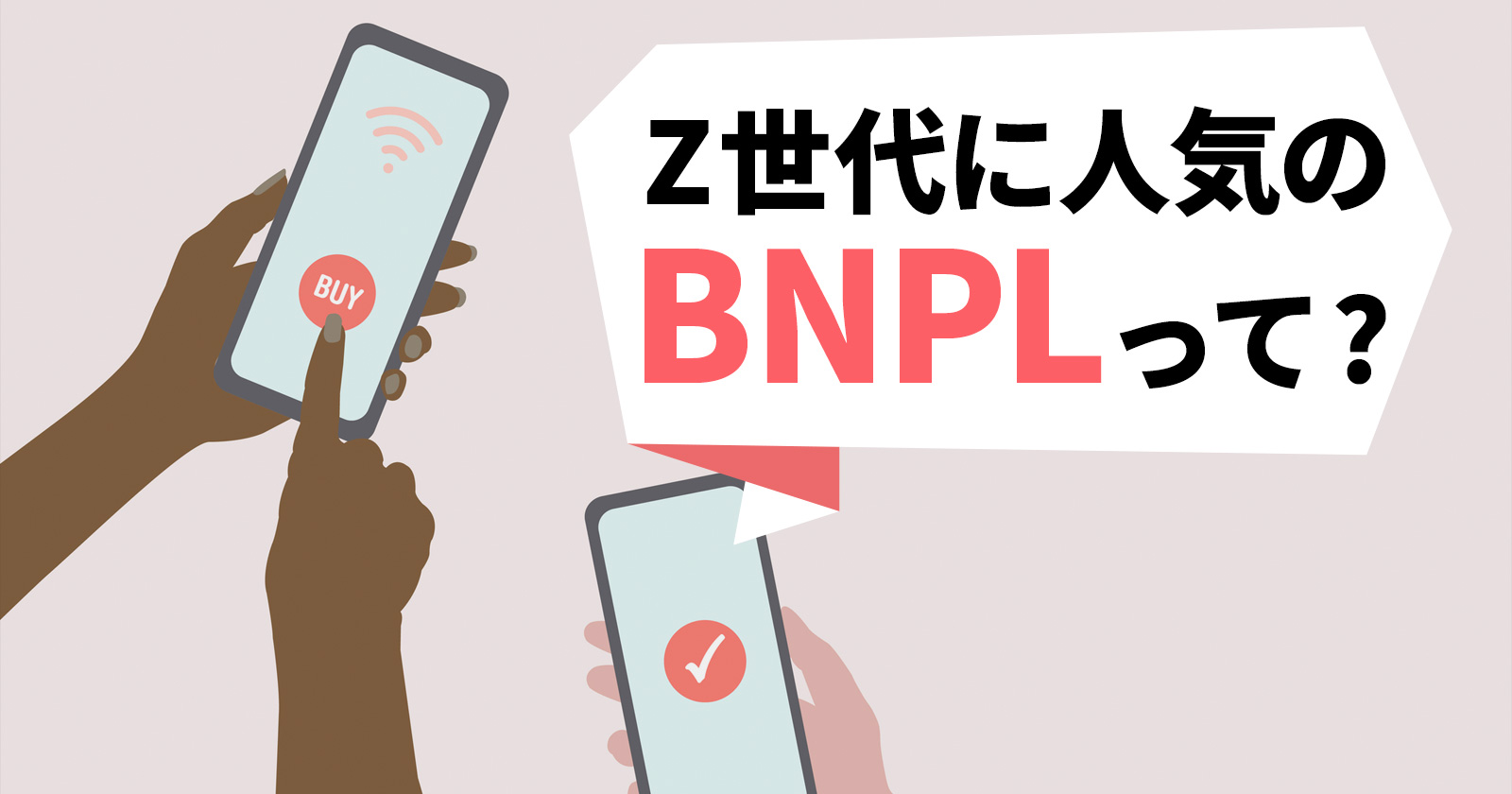中国や東南アジアなどを中心に、さまざまな機能を集約した「スーパーアプリ」が広く普及しています。現在、日本でも複数の機能をまとめたアプリは存在しますが、アジアのように、国民生活の全域で使われるようなスーパーアプリは登場していません。故に、「スーパーアプリってよく聞くけどどういうものか知らない」という方もいらっしゃるかもしれません。今後、日本でもこのようなアプリは生まれるのでしょうか?
今回は、「アジア諸国でのスーパーアプリの成功パターンは、日本市場においても応用可能か?」という視点から、今スーパーアプリが再注目されている理由や日本におけるスーパーアプリの可能性を考察。また、ユーザーニーズに応えたサービスを開発する方法について、スーパーアプリの発想に学びます。
「スーパーアプリ」は日常生活に必要な機能を集約し、顧客体験を向上
多種多様なアプリが開発されている現代。種類が豊富過ぎて、スマホの中がアプリでいっぱいになってしまう人も多いのではないでしょうか。そんな中、中国や東南アジアなどの新興国では、スーパーアプリという新たなスタイルのアプリが発展しています。
スーパーアプリとは、日常生活のあらゆる場面で活用できる統合型アプリケーションのこと。搭載されているサービスには、例えば以下のようなものが挙げられます。
- チャットなどの送受信や通話機能
- SNSなどのコミュニティ機能
- 決済、EC機能
- 音楽、ゲーム、漫画などエンタメ機能
- チケット予約機能
- 配車サービス機能
スーパーアプリ内にあるこれらのサービスは、それぞれ「ミニアプリ」と呼ばれます。さまざまな機能がミニアプリとしてスーパーアプリに集約されているので、サービスごとに個別のアプリをダウンロードしユーザーデータを入力する手間や、スマホ容量の圧迫、機能ごとにアプリを使い分ける煩わしさなどから解放されます。つまりスーパーアプリとは、従来のスマホアプリが持つ不便性を解決し、顧客体験を向上させてくれるサービスなのです。
さらに、アプリを提供する側も、さまざまなサービスを横断してユーザーデータを取得できるため、よりニーズに合ったサービスを開発・提供しやすくなるでしょう。また、スーパーアプリであれば、一度ダウンロードして、あるサービスを使い始めてもらえれば、そこに搭載されている他のサービスも利用してもらいやすくなるといったメリットもあります。
とはいえ、スーパーアプリも万能ではありません。「一部の不備が全てのサービスに影響してしまう」「プログラムが増えることでレスポンスが低下しやすくなる」などの課題もあります。メリットを生かしつつ、これらの課題をどう解消していくかも今後のスーパーアプリには求められるでしょう。
スーパーアプリの海外事情。中国や東南アジアで爆発的に普及した理由とは

ユーザーにとっても、サービス提供側にとっても多くのメリットがあるスーパーアプリですが、海外や日本での現状はどのようになっているのでしょうか。また、スーパーアプリが普及している国にはどのような特徴があるのでしょうか。現状を踏まえて考察します。
冒頭でも触れたように、中国や東南アジアではスーパーアプリが広く普及し、生活に欠かせないものとなっています。
中国のスーパーアプリで有名なものは、コミュニケーションアプリの「WeChat」と、決済アプリの「AliPay」の2つです。これらは、元々はシンプルな機能だけを持つアプリでしたが、外部企業と連携したり、さまざまな機能を拡充したりして発展してきました。中国はモバイル決済の比率が世界一高いと言われていますが、その中でもこの2つのアプリの存在感は大きく、「AliPay」はシェアの50%以上でシェア1位、「WeChat」は約40%で市場2位(2019年時点)、つまり2社でモバイル決済のシェアの約9割を占めています。もはやスーパーアプリが生活インフラの一部となっていると考えられます。
東南アジアでは、配車サービスから発展した「Grab」と「Gojek」がスーパーアプリの2強となっています。「Grab」は配車のほか宅配やEC、フードデリバリーなどのサービスを備え、ASEANの総人口の約1/3のダウンロード数を誇ります。「Gojek」も18以上のサービスを持ち(2020年4月時点)、東南アジア最大の決済アプリ「Go Pay」を提供する、巨大な電子マネープラットフォームとなっています。
日本でも、いくつかのコミュニケーションアプリやECプラットフォーム、キャッシュレス決済アプリなどが機能を拡充し、スーパーアプリ化を推進する動きが始まっています。しかし、現時点では、数社の独占状態になったり、生活に必要な機能が全て集約された国民的アプリとなったり、といった中国や東南アジアのような爆発的な広がりはありません。
同様に、欧米でも生活のインフラとなるようなスーパーアプリは定着していません。その理由の1つとして考えられるのは、デジタルデバイスの普及プロセスです。日本や欧米では、まずパソコンが普及し、次にタブレットやスマートフォンなどのモバイル端末が広がっていきました。その過程で、時代の流れやユーザーのニーズに応じて、個別の機能に特化したアプリが新しいサービスと結びつきながら生まれていったため、結果として独立したサービスが乱立。その点、中国や東南アジアなどの新興国ではインターネットやスマートフォンの普及が一気に進んだため、多くの機能を搭載し生活のシーン全てで活用できるスーパーアプリは利便性が高く、浸透しやすかったのではないでしょうか。
また、先進国では、新たな技術やサービスが登場する際に既存サービスと摩擦が生じたり、法制度などの改正が必要だったりと、普及までに時間がかかるケースが多いと言われています。新興国ではこうした制約が少ないため、先進国が通ってきた発展のプロセスを飛び越えて急速にサービスが普及する「リープフロッグ型」と呼ばれるタイプの発展を遂げることがあります。スーパーアプリの急速なシェア拡大もこうした「リープフロッグ型」の一例と言えるのではないでしょうか。
さらに、中国や東南アジアにおいて特徴的な点は、各種メディアを傘下に収めるメディア・コングロマリットが絶大な影響力と経済力を持っていることです。この環境によって、大企業が多様なサービスとインフラを一気呵成に提供する基盤を整えやすく、成功したアプリのスーパーアプリ化を促し、インフラの一部と言えるような普及につながったと考えることもできます。
スーパーアプリが日本で発展・利用拡大できる可能性はあるか?

ここまで、日本や海外におけるスーパーアプリの現状を紹介してきましたが、最後に、今後日本でスーパーアプリが発展する可能性について考察します。
現在の日本は、多くの独立したアプリが乱立しており爆発的に広まる「リープフロッグ型」のサービス普及は難しいと考えられています。そのため、中国や東南アジアのような国民的なスーパーアプリは生まれにくいかもしれません。
しかし、特定の経済圏やターゲット層といったスモールコミュニティに対するアプローチなら、日本でもスーパーアプリ的な存在を開拓する余地があるのではないでしょうか。例えば、保育園・幼稚園と保護者との情報共有システム、地域で利用可能なクーポンなどは既にありますが、このような利用者の生活に密着したサービスや重要度の高い機能を中心に周辺の機能を拡大していけば、ターゲット層への普及は見込めるかもしれません。
実際に、「Gojek」や「Grab」も、ローカルのターゲット層に合わせたサービスを展開することで発展してきました。「Gojek」は配車サービスからスタートし、地元のパートナー企業と連携しながら、宅配サービスや買い物代行、洗濯代行などローカルの顧客ニーズに合わせたサービスを広げました。「Grab」も、カンボジアならトゥクトゥクの配車サービス、シンガポールではドリアンの配送サービスなど、ローカライズしたサービスを展開しています。
つまり、機能を先に提供するのではなく、ローカルの顧客ニーズに合わせてサービスや機能を拡大していくことが、スーパーアプリの成功要因と言えるのではないでしょうか。
日本における地域アプリの例
「地域のニーズに合わせたサービス展開」という視点から日本国内の動きを見てみると、スーパーアプリとまでは言えないものの、各地で多彩な取り組みが始まっています。
・事例1:会津財布
スーパーシティを目指す会津市では、地域ウォレットとして「会津財布」アプリを採用。電子マネーとして使えるほか、キャッシュレス決済サービスとの連携、レシートの電子化サービスやデジタルクーポンの発行などの機能があります。さらに、コロナ禍の中でミニアプリとしてワクチン接種記録の確認サービスを搭載するなど、地域のデジタルプラットフォームになりつつあります。
・事例2:広島広域都市圏ポイントアプリ
広島広域都市圏とは、広島市の中心部から約60km圏内にある25の市町で構成される地域のこと。「広島広域都市圏ポイントアプリ」は、この地域に導入されたポイント事業「広島広域都市圏ポイント」や、キャッシュレス決済機能をメインに、クーポン発行、抽選応募、ポイントを利用した寄付・支援など、ポイントを中心としたさまざまな機能を搭載。ターゲット層を絞り込み、ニーズに応えた展開をしています。
上記の事例は地方都市における例ですが、都市部でも世田谷区を対象とするデジタル商品券・地域通貨「せたがやPay」のようなアプリも出てきています。今後は街の規模や特性に合わせた、より多様なプラットフォームが生まれていくかもしれません。
日本や欧米では独立したサービスがそれぞれのアプリを提供しているため、中国や東南アジアなどのように爆発的な普及には至っていませんが、地域やターゲット層などを絞り込み、ローカルな顧客ニーズに寄り添った機能を備えたアプリ・サービスを展開していけば、日本でもスーパーアプリのような統合型アプリケーションの成功の芽はあるかもしれません。また、地域に特化したスーパーアプリ的なサービスは、地方創生やスマートシティ化などにもつながると考えられます。
スーパーアプリは、ユーザーの利便性を向上するとともに、地域経済の活性化や社会課題の解決を図る手段としても可能性を秘めているのではないでしょうか。