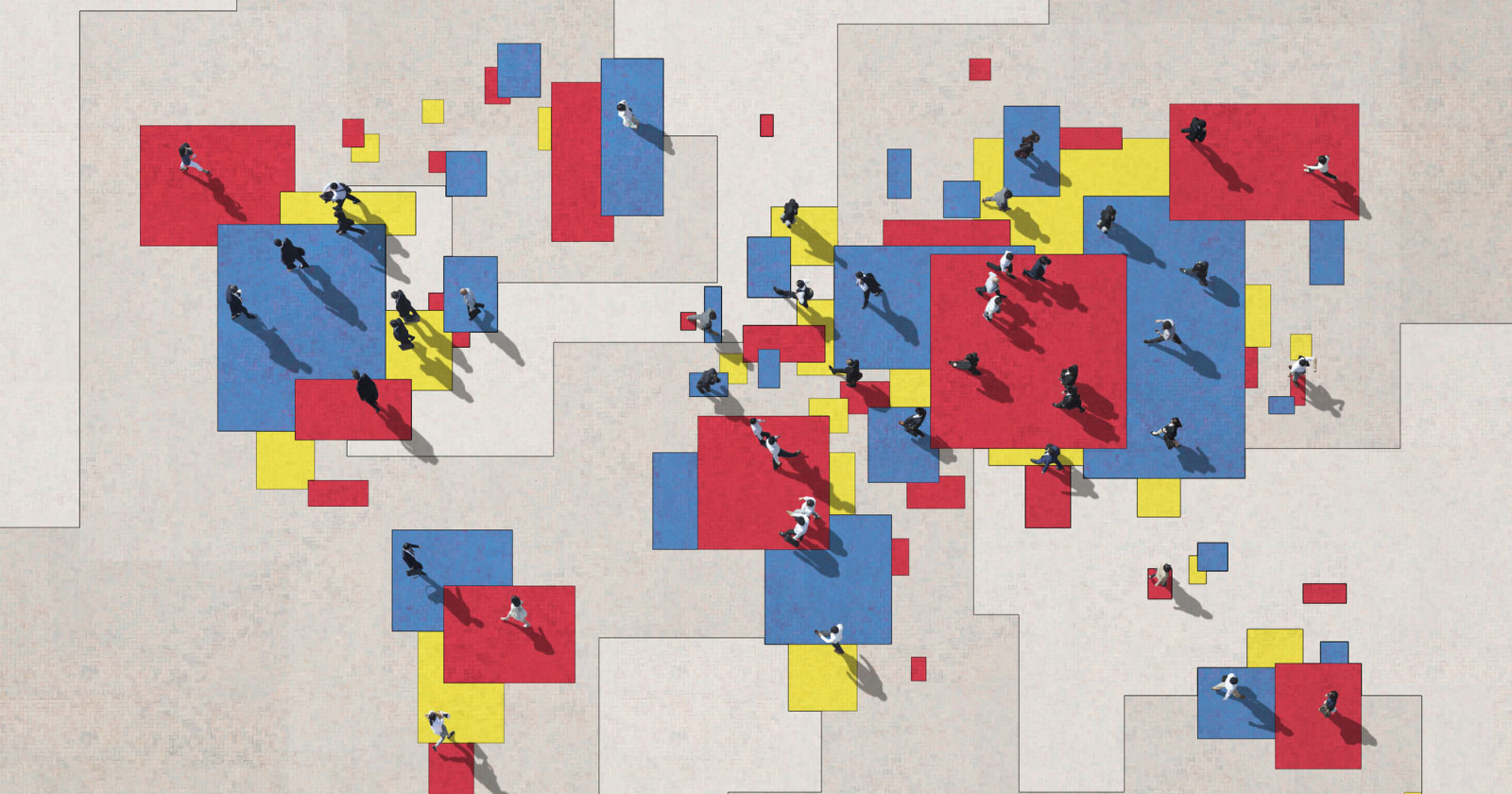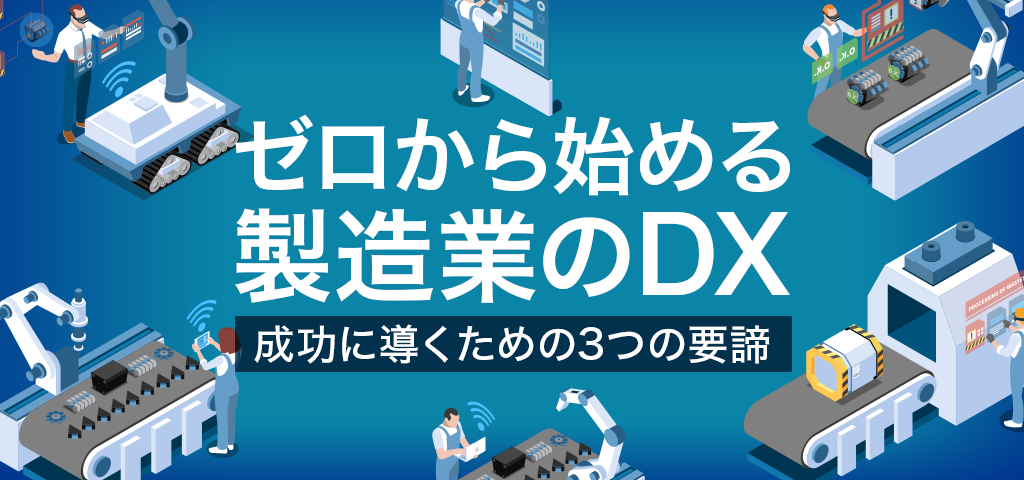デジタルの世界は、「Web3.0」と呼ばれる新たな時代に移行しつつあり、情報を中央集権的に管理するのではなく、個人へ権利を分散させるという流れが起きています。その文脈から新たに誕生した「ヘッドレスブランド(Headless Brands)」という概念が、最近話題になっています。一方ECの世界でも、より柔軟に顧客に寄り添った購買体験の提供を可能とする「ヘッドレスコマース」という手法が登場してきました。こうした新しいムーブメントから、今後のビジネスを考える際のヒントを探ります。
ヘッドレスブランドが象徴する、“脱中心化”とは
これまで、企業が製品やサービスを販売する際には、企業側がブランドイメージや商品・サービスの内容、販売戦略などを設定し、ユーザーに提供するのが一般的でした。つまり、商品・サービスは、企業(ヘッド)からユーザーへと一方的に届けるものだったのです。製品デザインや広告など、そのブランドを形づくるものも全て企業側がコントロールしてきました。
ところが最近、ヘッドレスブランドという新たな存在が現れ、にわかに注目を集めています。2022年3月に開催された、世界最大級のクリエイティブ・カンファレンスイベント「SXSW2022」でも、「The Rise of Headless Brands(ヘッドレスブランドの台頭)」というテーマのセッションが行われました。
ヘッドレスブランドとは、従来のように企業からユーザーへ一方的に商品・サービスを届けるのではなく、コミュニティベースで作り上げていくブランドのことです。ヘッドレスブランドにおいては、ユーザーはただ商品を購入したり使ったりする存在ではなく、プロジェクトの一員であり、企画や開発、広報などさまざまな形でプロジェクトに貢献することで利益を得るのです。
ヘッドレスブランドの例
仮想通貨の「ビットコイン」は、このヘッドレスブランドの代表的な例と言えるでしょう。ビットコインは数ある仮想通貨の中でも、最も世の中に認知されているブランドですが、実は管理者や事業主体は存在しません。その設計や仕組みは不特定多数のコミュニティによってつくられ、発展してきました。そして、ユーザー同士が相互に監視し合う仕組みによって、一定のルールが維持されてきたのです。
他に、ヘッドレスブランド的な存在として注目されているのが「WICKED SUNDAY CLUB」という取り組み。これは、NFTアーティストのTwisted VacancyとIT企業MetaFactory社がコラボレーションしたブランドであり、コミュニティです。メンバーシップパスを購入して会員になると、Tシャツやウェアラブル製品などの特別なアイテムを入手できるだけでなく、専用のチャットに参加でき、そこでアーティストや他の会員とやりとりしながら、Twisted Vacancyの作品をモチーフにした商品を一緒に作り上げることができます。
ヘッドレスブランドが登場した背景
このようなヘッドレスブランドが登場した背景には、昨今のデジタル世界の潮流があると考えられます。現在は、巨大プラットフォーマーが全てのデータを掌握していた「Web2.0」から、ユーザー同士がデータを共有・管理する「Web3.0」と呼ばれる時代に移行する過渡期にあるといわれています。同時に、一部の専門家のみが扱っていたデータを多くの人が活用できるようにする「データ民主化」という取り組みも生まれました。つまり、情報や資産をどこかに集中させるのではなく、多くのユーザーのところに分散させる「脱中心化」が大きな流れとなっているのです。ヘッドレスブランドもまた、こうした「脱中心化」の文脈に連なるものと考えられます。
ECにおける“脱中心化”、ヘッドレスコマースがCXやUXを向上させる

前述したヘッドレスブランドのような「脱中心化」の流れは他分野でも生まれており、その1つがEC業界における「ヘッドレスコマース」です。ヘッドレスコマースとは、ECサイトやアプリなど顧客と接触するフロント部分(ヘッド)と、決済や配送などを行うバックオフィス部分を切り離すことで、さまざまなチャネルで柔軟に顧客体験を提供する、というものです。
これまで、ECサイト、アプリ、外部のECモールといった各種チャネル、すなわち顧客と接触するフロント部分は、バックオフィス部分と一体化していました。フロントとバックが一体化していると、ユーザーの希望や状況に応じてフロント部分の設計を変更したいと思っても、バックオフィスシステムの環境に依存するため、柔軟に、スピーディーに対応しにくい場合があります。
しかし、ヘッドレスコマースではフロントとバックを切り離すことにより、バックオフィスの環境に左右されることなくフロント部分、すなわち顧客とのタッチポイントをスムーズに改善・拡張することが可能。チャネルごと、ブランドごとに見せ方や販売方法を変えることも容易になるでしょう。
自社のECサイトだけでなく、アプリやSNS、ブログ、外部のECモール、さらには実店舗やイベントなど、ユーザーとのタッチポイントが多様化・複雑化し、決済や配送の手段などもさまざまある中で、より便利に、快適に買い物をしてもらうために、フロント部分を状況に応じてスピーディーに改善・拡張していくことは重要です。それは、既存のシステムありきの設計を脱却するという意味で、「脱中心化」の流れの1つとも言えるでしょう。
また、とにかく企業側が売りたいもの、見せたいものを提示するという画一的なアプローチではなく、ユーザーがその時に欲しいと思われるものをリアルタイムに提示するといったインタラクティブな見せ方も可能になるかもしれません。購買体験はより個人に合わせてカスタマイズされ、ユーザーに寄り添ったものとなり、結果としてエンゲージメントや顧客満足度向上にもつながるのではないでしょうか。
さらに、システムによる制約を気にせず「ユーザーにどう知ってもらい、興味を持ってもらうか」というアプローチを考えることに、より注力できるようになることもヘッドレスコマースのメリットです。大手ECプラットフォームなどへの出店は、販路を広げるためには重要ですが、ユーザーによって、あるいは商品によって見せ方を変えるといったことは難しいでしょう。そこで自社ECサイトでは、ヘッドレスコマースによってフロント部分の設計を工夫し、徹底的にユーザーのニーズに合わせたアプローチを行うことが、激化するEC市場の競争で勝ち残る戦略の1つになり得るかもしれません。大手ECプラットフォームに集中していたEC市場の「脱中心化」を進めるための一助にもなるのではないでしょうか。
「ヘッドレス」が生み出す、ユーザーファーストの広告戦略
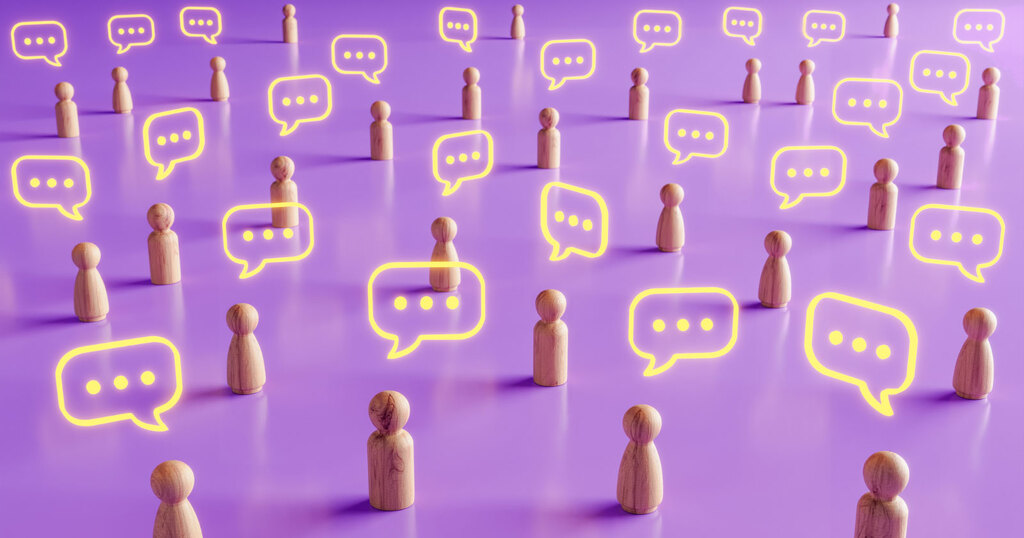
ここまで「ヘッドレスブランド」や「ヘッドレスコマース」について解説してきました。最後に、これら「ヘッドレス」の台頭から見えてくるものを、広告戦略においてどう生かすことができるのか考察していきます。
「脱中心化」が加速していく中では、「ユーザーに一定の権利や選択肢を持たせ、能動的に参加してもらう」という視点が重要になっていくでしょう。しかし、広告がどのように「ヘッドレス」化していくかはまだまだ未知数であり、だからこそ、そこに新たなソリューションやサービス開発の余地が見出せるのではないでしょうか。
例えば、ユーザー同士が自発的に商品・サービスの広告を出すようなケースも増えてくるかもしれません。既にエンタメの世界では「応援広告」といったムーブメントが起きています。これは、アイドルのファンなどがそのアイドルの認知を広げるために、資金を集めて駅や街中の看板、大型ビジョンなどの広告枠を買い取り、独自の広告を掲出するというものです。このような動きは、他の分野でも広がってくるのではないでしょうか。ユーザーの自発的な宣伝の効果によって、多くの人がその商品・サービスを購入するようになれば、価格を下げたり、新商品開発の資金をつくったりすることもできるでしょう。ユーザーにとってもリターンが大きい仕組みを設計することが「ヘッドレス」において大きなポイントになるはずです。
こうした動きが発展していけば、ユーザー自身がターゲットを分析し、いつ・どこで・どのような広告を出すのが効果的なのかを考え、広告戦略を立てていく「マーケター」のような存在になっていくかもしれません。実際に、YouTuberやブロガーのように、コンテンツ制作からマーケティングまでを個人で行う人は増えています。今はSNS広告のような低予算からでも運用しやすい広告があり、無料のアクセス解析ツールなども普及しているため、誰でもマーケターになれる土壌が整ってきているとも言えます。
今後は、マーケティングやブランディングにおいて、いかにユーザーの自発的な行動を促すかという視点も持つ必要があるのではないでしょうか。企業からユーザーへ一方的にブランドメッセージを発信するのではなく、ユーザーコミュニティがブランドマネジメントを支える仕組みを作り上げることによって、広告戦略が根本的に変わっていくかもしれません。
デジタル世界における脱中心化の流れから生まれた「ヘッドレスブランド」と、多様化するユーザーの好みや購買行動に柔軟に対応しようという動きから生まれた「ヘッドレスコマース」。どちらにも共通するのは、ユーザーが主役であること。こうした時代の流れを理解した上で、ユーザー視点のサービス設計や、マーケティング戦略を考えていくことが、新しいビジネスや戦略を生み出すヒントになるのではないでしょうか。