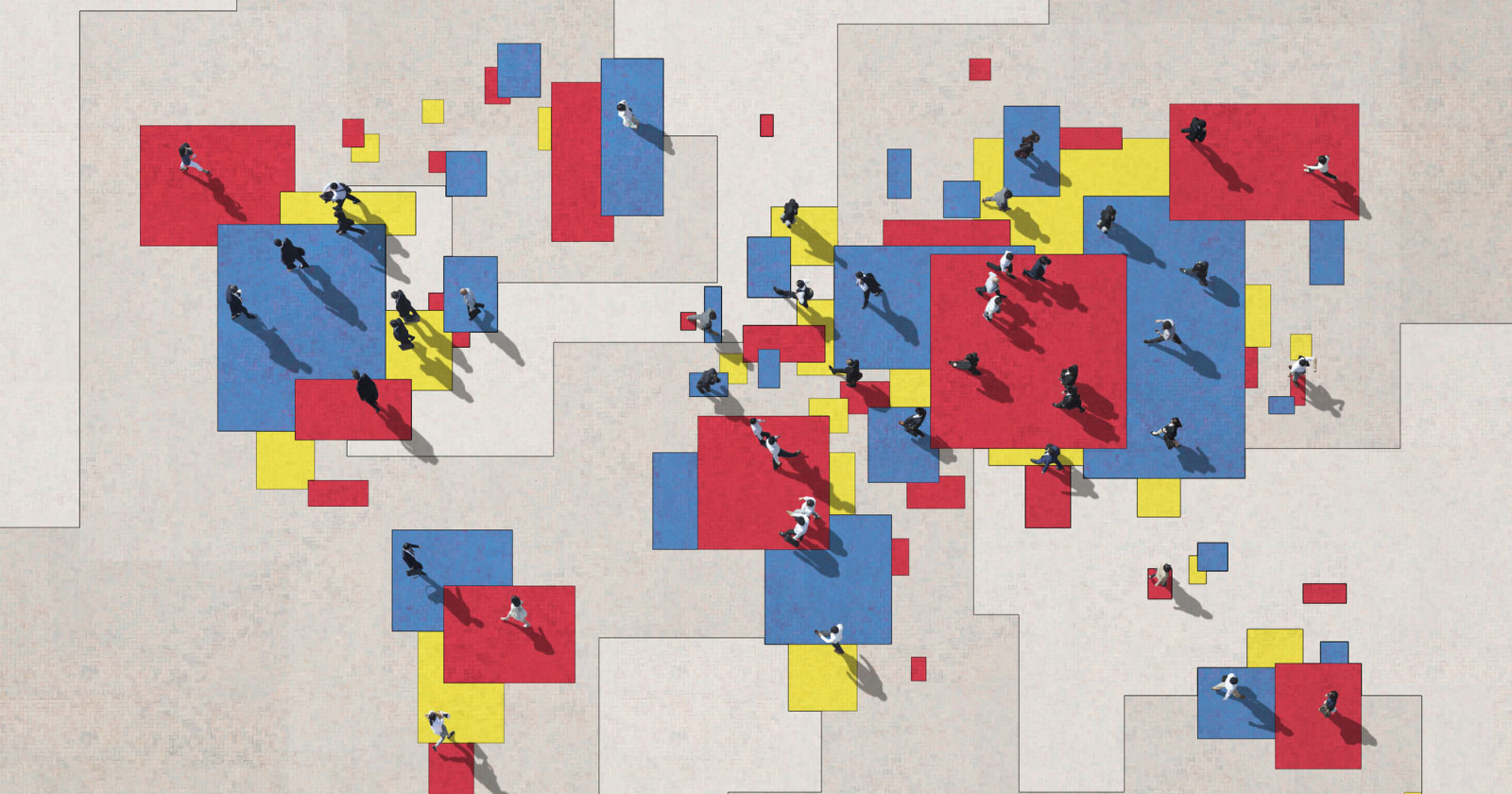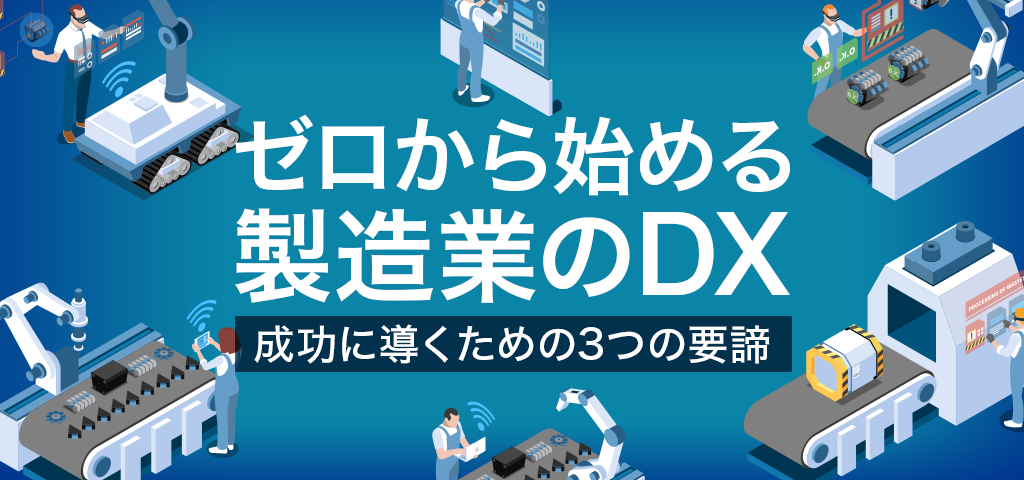昨今、雇用形態が多様化し、さまざまな人たちが関わっている会社が日本でも多くなっていますが、自社のリソースでは対応しきれないような高度な業務をこなすことができるハイスキルなフリーランス人材の活用については、まだまだ生かしきれていないところが多いといわれています。しかし、DX時代に会社が成長するためには、ハイスキルなフリーランス人材の活用は不可欠になるかもしれません。
DX領域において高度な専門性を持つフリーランス人材ネットワークを保有し、顧客企業の課題に応じて最適な人材アサインメントを行ってその解決をサポートする株式会社GNUS(ヌース)の文分邦彦氏に実施した今回のインタビュー。後編では、フリーランス人材を活用する上での注意点や、フリーランス人材それぞれの特性を見極めたアサインメントのポイントなどについて聞きました。「DXを進めたいけれど、自社だけではリソースが足りない」「DX人材がなかなか集まらない」といった課題を抱えているビジネスパーソンには必読の内容です。
フリーランス人材の活用がうまくいかないケースとは

Q.文分さんから見て、フリーランス人材を活用しようとする中で、「うまくいくケース」「うまくいかないケース」があるのではないかと思うのですが、その差はどこにあるとお考えですか。
文分:そうですね、「うまくいくケース」よりも「うまくいかないケース」を見た方がいいかもしれませんね。
フリーランス人材というのは、前編でも申し上げましたが、大企業のしがらみが嫌だったりとか、その企業の事情で生まれる面倒なことはやりたくなかったり、といった思いからフリーランスになっている人も結構います。ですので、そういうタイプのフリーランスの方には「企業内調整」的な性格の強い業務はあまり向いていないのではないかと思います。端的な例で言えば、社内決裁用の資料を作る、とかですね。そういった業務にはモチベーションが上がらないので、うまくいかないケースが出てきます。やはり社内のルール上必要な業務については、社内のスタッフで対応した方がいいのではないでしょうか。そもそも組織にとらわれないでアウトプットを出したいからフリーランスとして活動している人材ですので。
あるいは、表面的な話に聞こえるかもしれませんが、例えば「月に数時間は出社してほしい」といったような条件もあまり相性はよくありません。中には「必ずスーツで出社するように」というようなご要望をいただくこともあるのですが、やはりそういうのは避けたいですね。あくまでも「いいものを作りたい」というモチベーションで仕事をしたい人たちなので、それにあまり関係ないと思われる条件を課されると、能力を発揮しきれなくなる可能性もあります。
フリーランス人材の経歴や適性をしっかり見極め、最適なアサインを実現
Q.実際にGNUSで「ハイスキル・フリーランス」として紹介されている人たちにはどのような人材がいるのでしょうか?
文分:「ハイスキル」と自分たちで言っている以上、実態としてもそのクオリティーを担保できるような環境はしっかりと整えています。まず、私たちのネットワークに入っていただくためにはそれなりの「審査」があり、私たちが求めるものにふさわしいと判断できる方々だけが登録できるようにしています。フリーランス人材と言っても、大きくは「言われたことをその通りにしっかりとやり抜くタイプ」と、「自分からどうすればいいかどんどん提案していくタイプ」に二分できるのですが、私たちが特に重視しているのは後者のタイプです。
面接をする際にはGNUSサイドから2名参加するのですが、適性を見抜くために、そのうち1名は必ず、同様のポジションで活躍しているフリーランス人材に入ってもらい、「同じ専門家」としての目線で見てどう思うか、ということをしっかり見てもらいます。スキルはもちろんですが、仕事への向き合い方や仕事の進め方についてもあぶりだしていくのです。
フリーランス人材も結構な数がいますので、いい人材がいればGNUSのネットワークに加わっていただけるように、積極的にアプローチをしています。私たちの人材マネジメントの方法論で言いますと、私たちの組織でフリーランスのメンバーと一緒に仕事をするポジションには、「プロジェクト担当者」「フリーランス人材担当者」「スタッフィング担当者」の3つのポジションがあります。そのうちのスタッフィング担当者は専任として全案件のスタッフィングを行っており、人材が必要なプロジェクトの内容を見ながら、フリーランス人材担当者に「このプロジェクト用にこういう人材が欲しい」というリクエストをしていきます。スタッフィング担当ではありますが、より最適なスタッフィングを進めるために、「プロジェクト担当者」と連携し、プロジェクトに対する理解を深めながら最適なチーム編成を考えています。さらには、スカウティングにも指示を出しますし、プロジェクトの途中でフリーランスの人材との面談も行ったりします。ただ、仕事のアサインについては、スタッフィング担当者からの指示でアサインするだけではなく、「ジョブボード」で「こういう仕事があるけれど、やりたい人はいますか」と公募する場合もあります。フリーランス人材にはそれぞれの要望やキャリアアップ志向もありますので、こちらからのお願いと、本人の希望を並行して進めている状況です。
現在、GNUSのネットワークでは200名以上のフリーランス人材を保有しており、その人材のスキルや過去のキャリア、実績、職務履歴などを全て把握。さらに、GNUSのネットワークの中でどんな仕事にアサインされ、どんな成果を残したかということも全て記録されています。さらには、実際に仕事をしてフィットしていたかどうか、プロジェクトにおいてどのような点にやりがいを感じているか、どのような点が不満だったか、そういうことも含めて全てフィードバックされます。そうすることで、最適なテーマに最適な人材をアサインできる環境を維持しているというわけです。
Q.これから日本でも、フリーランス人材の活用が定着していくとお考えでしょうか?
文分:個人的な思いとしては、フリーランス人材の活用を定着させることがゴールだとは思っておらず、大事なのは顧客企業がフリーランス人材と一緒にDXを進めていくことができるようになることです。ただ少なくともDX領域においては、自社の人材だけでは推進できないし、新たに採用しようとしてもそんな人材は市場にいない、という現実があります。だからこそ、私たちのように、高いスキルを持ったフリーランス人材を提供する仕組みが必要なのではないかと思っています。
また、私たちの場合、顧客企業の課題に対して、直接的にその課題を解決できるスキルを持つ人材をご提供しています。つまり責任の所在がはっきりしているんです。この領域についてはこの人材が担当して、うまくいったとかいっていないということが明確になっている。プロジェクトが大きくなると、誰がどこを担っているのかが見えにくくなってきます。でも、こちらはフリーランスですから、しっかり実績で評価されないと次につながらない。そういったところをご評価いただけている面もあるのではないでしょうか。
前編でも申し上げましたが、日本ではまだ「フリーランス=ルーティン作業をこなしてくれる安い労働力」と捉えられがちなところがあります。それはフリーランス側からすれば、「大手企業に勤めないと、大きなプロジェクトに携わることができない」という懸念になります。フリーランスであっても、スキルがあれば自分が望む仕事ができる、高い専門性が求められる大きなプロジェクトを遂行できるという環境になれば、労働市場はもっと流動化していきますし、働き方もさらに多様になっていく。日本においても、今後はそのように変わっていくだろうし、変えていきたいと思っています。
「自社の課題を自社だけで解決する」こと自体が困難になっている昨今。企業の側から見れば、自社に限らずさまざまなリソースを活用することで課題解決やビジネス成長を進めていく中で、プロジェクトごとに最適なフリーランス人材を社員として抱えることなしに活用できるのであれば、そのメリットはきっと大きいはずです。そして、働く側から見れば、自分のやりたいことをやりたい環境でやれる時代が訪れる。それは理想的な環境とも言えますし、一方で自分の市場価値を高め続けていかなければいけない環境とも言えます。
ハイスキルなフリーランス人材がいれば、全てうまくいくというわけではありませんが、ハイスキルなフリーランス人材の活用が定着すれば、企業側にとっても働く側にとっても、理想的な労働環境になるかもしれません。そんな時代の変化を見据えながら、「働き方=ライフスタイル」そのものを見直してみるのはいかがでしょうか。