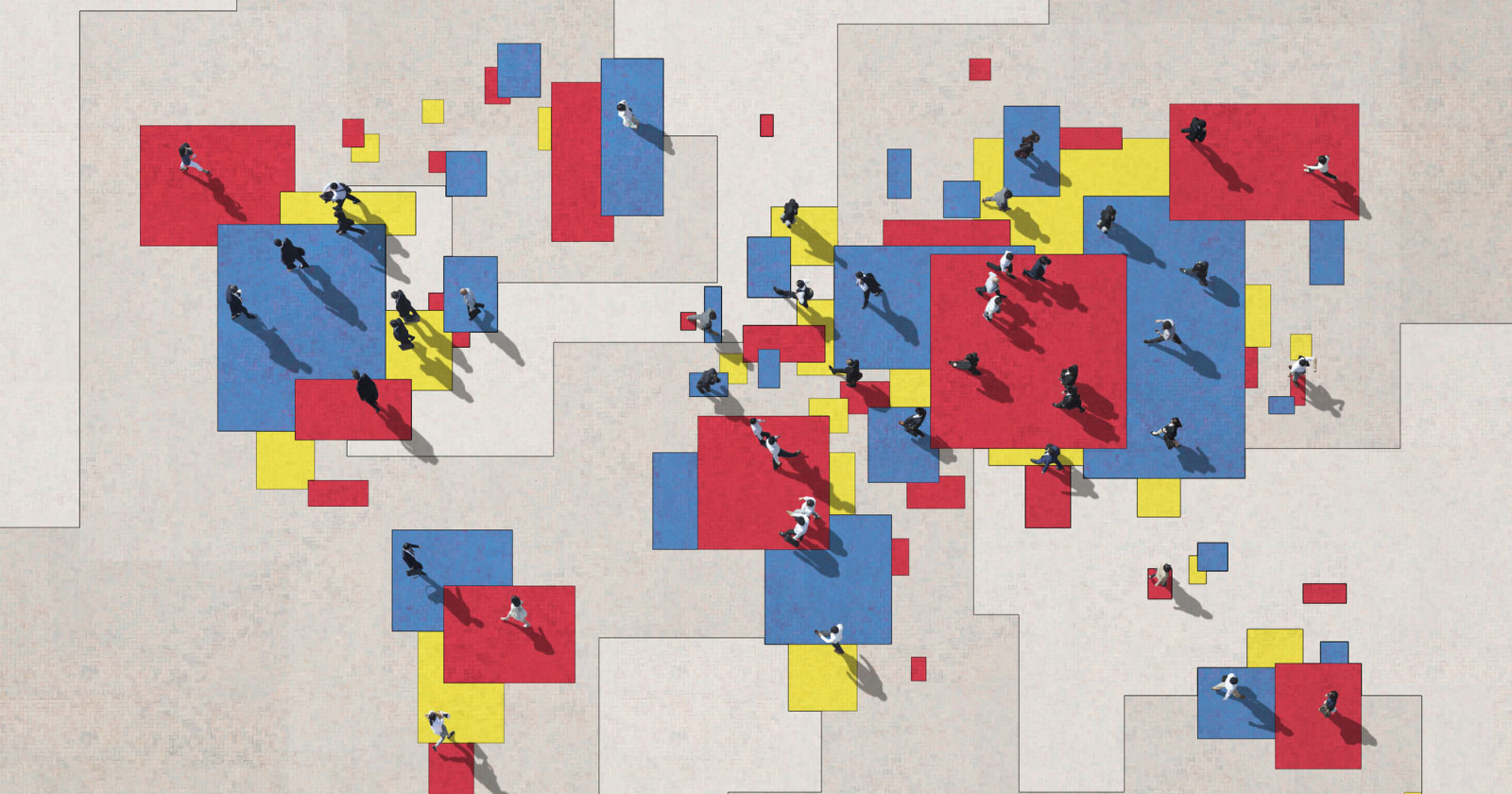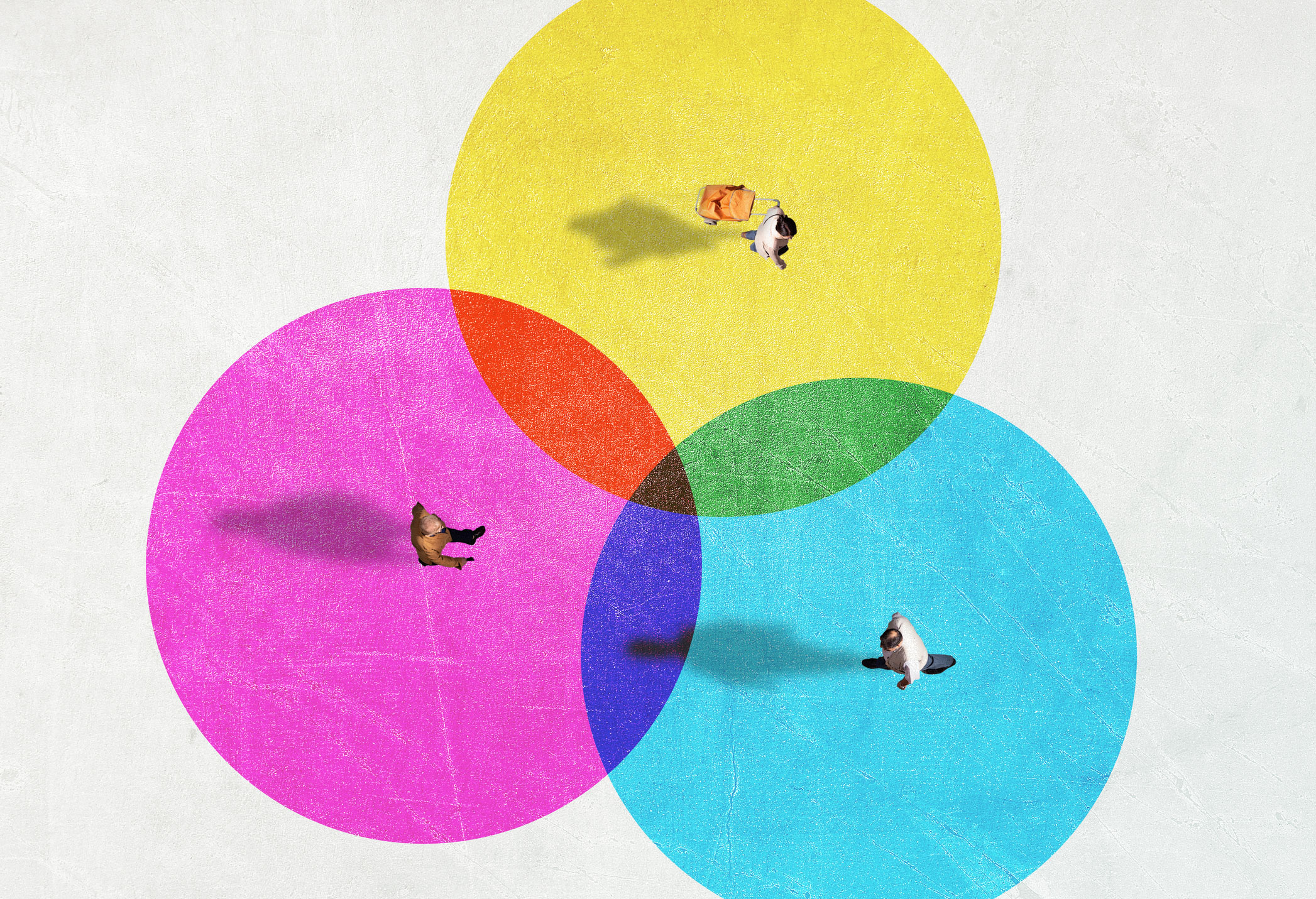「ID-POS」をご存じでしょうか?「POSは聞いたことがあるけど、ID-POSはよく分からない」という人も多いかもしれません。小売業において、データドリブンなマーケティングを実現する上で、非常に重要なデータとなるID-POS。これを分析することで、お客さまのお買い物行動のリアルを把握し、次のアクションへとつなげ、さまざまな施策を考えることが可能となります。
今回は、ID-POS分析の専門家であり、小売・流通業へのコンサルティングはもちろん、メーカーへのプロモーション支援の経験も豊富な、株式会社電通プロモーションプラス(旧社名:株式会社電通テック)の小沼淳氏と、株式会社電通リテールマーケティングの杉本秀樹氏、浅野晋伍氏の3名にインタビュー。前編では、まずID-POSの基礎知識や、その分析の視点、活用方法について杉本氏に聞きました。小売業に携わる方には特に、参考にしていただけるのではないでしょうか。
「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのくらい」「いくらで」買ったのかが分かる

Q.基本的な質問ですが、そもそも「ID-POS」とはどういうものなのでしょうか?
杉本:まず「POSデータ」をご存じでしょうか。店でお買い物をしたときのレシートには「いつ」「どこで」「何を」「いくらで」買ったのか、ということが印字されていますが、それがそのままデータになったのが「POSデータ」です。さらに、そこに「誰が」買ったのか、という情報が付加されたものが「ID-POSデータ」になります。お買い物のときに、会員カードやポイントカードを使えば、「誰が」買ったかが分かりますよね。その購入者のIDが付与されることによって、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのくらい」「いくらで」買ったかが分かるのです。
私の印象では、2006年くらいからいわゆる「ポイントカード」が世の中に出回ってきて、お買い物をしてポイントをためる、というスタイルが定着。それに伴い、「ID付きPOSデータ分析」が行われるようになりました。さらにここ数年前からは、自社のハウスカードだけではなくて、楽天ポイントとかdポイントとか、あるいはアプリのポイントとか、そういった他社のプラットフォームを使ったポイントカードが主流になってきましたね。
Q.ID-POSであれば「誰が」買ったか分かる、とのことですが、この「誰が」というのは、どのくらい詳細なことまで分かるのでしょうか?
杉本:POSデータでは、どれくらい売れたかとか、前年比で上回ったかどうかということは分かりますが、「誰が」買ったかは分かりません。そこにIDが付くことで、どれだけ情報を取得しているかにもよりますが、簡単なところでは年齢、性別、職業、年収などが分かります。加えて、「初めてその商品を買った」新規のお客さまがどれだけいるかとか、「もう一度買った」リピーターがどれだけいるか。あるいは、とにかくたくさん買ってくれる「優良顧客」かどうかとか、今年の購買履歴がない「離反顧客」かどうか、といったことも見えてくる。買い回りの情報を網羅的につかめるというわけです。
お客さまのお買い物行動から、課題とその原因、メスを入れるべきポイントをつかむ
Q.なるほど。では、ID-POSを使って、どのような分析をしているのですか?
杉本:まず大前提として、分析の目的の基本は「お客さまの購買状況を把握する」ということです。1年間に何回来店して、どのくらい買っていただいているのかという、1人当たりの来店頻度や購入金額が基本です。それをさらにロジカルにブレークダウンしていくことで課題発見につながっていきます。例えば、売り上げが落ちてきているとしたら、それは客単価が減っているためなのか、それとも購入者数が減っているためなのか。購入者数が減っているとしたら、それは新規のお客さまが減っているのか、リピートしてもらえなくなっているのか。新規が減っているのであれば、一体何を買わなくなっているのか。そうやって、ロジカルに分析を落とし込んでいって課題を発見します。
もう1つは「0次分析」。フラットに最初の分析をするというもので、どんなお客さまが来ていて何を買っているのかということを、まずはデータでしっかりあぶり出そうという分析ですね。感覚的に売れ筋商品などを分かっているつもりでも、いざデータでしっかり見ると意外な発見や思い込みが明らかになることも多いです。ある外食業で分析したときは、メインとなるメニューだけではなくて、いわゆる「トッピング商品」が売り上げの大きなポイントになることが見えました。そうなると、メニュー構成や店での売り出し方も変わってきますよね。
そして重要なのは、CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)につながっていくような分析です。お客さまを、「ロイヤルユーザー」「ライトユーザー」などにカテゴリー分けし、それぞれどういう買い方をしているのかを見ていく。その中に、昨年は「ライトユーザー」だったのに、今年に入ってから「ロイヤルユーザー」になった方がいる。じゃあそのお客さまはどういう購買行動をしてロイヤルユーザーになったのか。そこに注目すれば、もっと多くのお客さまにロイヤルユーザーになっていただく道筋が見えてくる。そういったところを見つけ出していくのが、私たちデータアナリストの仕事です。
Q.これまでさまざまなデータを分析されてきたと思いますが、業界や業態で、分析の視点などに違いはあるのでしょうか?それとも、どんな業界に対しても同じ視点で分析をするのでしょうか?
杉本:お客さま分析の手法や考え方については、どの業界・業態でも大きな違いはありません。分析そのものは大体同じです。ですが、中には分析の視点が異なるというようなケースはあります。
同じ小売業でも、大型商業施設とドラッグストアの「商圏分析」であれば、ターゲットとなる範囲が変わってきますよね。ドラッグストアの場合、商圏は大体1~2kmで、その辺りの住民が来てくれているかどうかを見ますが、大型商業施設であれば、どれくらいの商圏を押さえられているのか、5kmを超えるところからどれくらい集客できているのか、などを見ます。
あるいは、コンビニエンスストアが分析対象となると、曜日や時間帯で細かく刻んでお客さまの動きを見ていきます。これがドラッグストアだと、曜日や時間帯で売れるものにそれほど大きな差はないことがほとんどですが、コンビニエンスストアは、平日と土日で売れるものが全く違ったりすることがあるんです。さらに店舗がある場所によって、客層も売れ方も全く異なります。ですので、それぞれの時間帯やシーンの特徴を踏まえた上での分析が必要となるわけです。
ID-POSを分析することで、お客さまは「なぜこの商品を買うのか」「なぜ買わないのか」「どういうシチュエーションだと、より買いたくなるのか」といったことが見えてきます。さらに注目したいのは、「優良顧客」と「そうでない顧客」との差を見ることができるということです。そこに優良顧客化を図るヒントや切り口が見えてくるかもしれません。そうすれば、単に「広告」や「特売」で集客するだけではない、さまざまなアプローチの可能性が見えてくるでしょう。後編では、小沼氏、浅野氏を交えてID-POS分析において気を付けるべきポイントや、データ活用のさらなる可能性について聞いていきます。
※株式会社電通テックは2022年4月より株式会社電通プロモーションプラスに社名変更しました。
※所属・役職は掲載当時のものです。