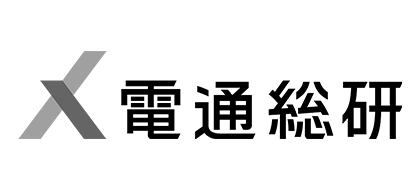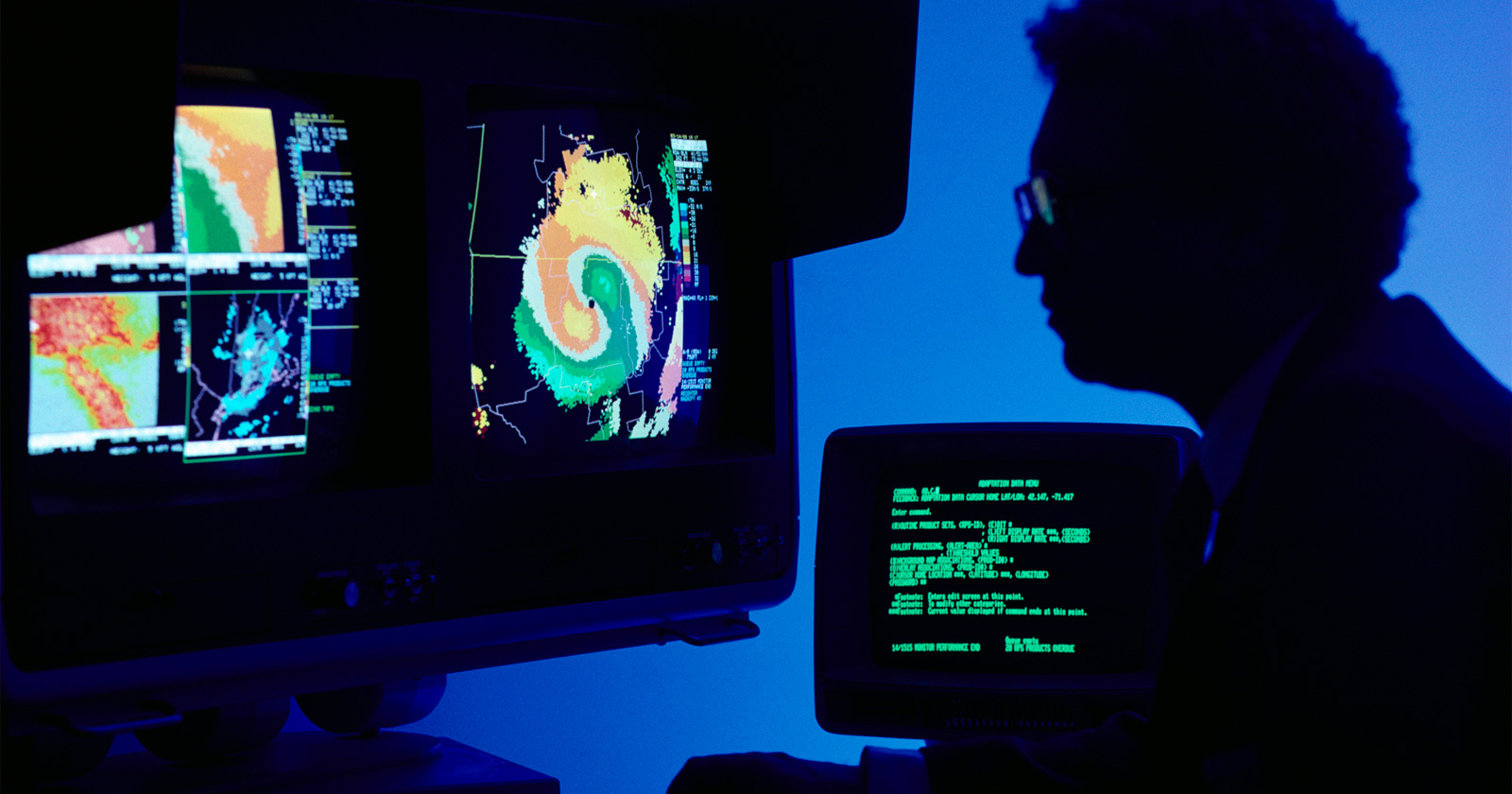「第3次AIブーム」の流れを受け、AI(人工知能)活用がビジネストレンドに登場してから、早いもので5~6年が経とうとしています。2022年現在、いわゆるバズワードとしての「AIブーム」は落ち着いたようにも見えますが、一方でDX(デジタル・トランスフォーメーション)における主要な技術として再び光が当たっています。この記事では、主にマーケティングやカスタマーエクスペリエンス領域でのAI活用について、最新の潮流とトレンド、可能性を考えていきます。
「AIブーム」はその後、どうなった?
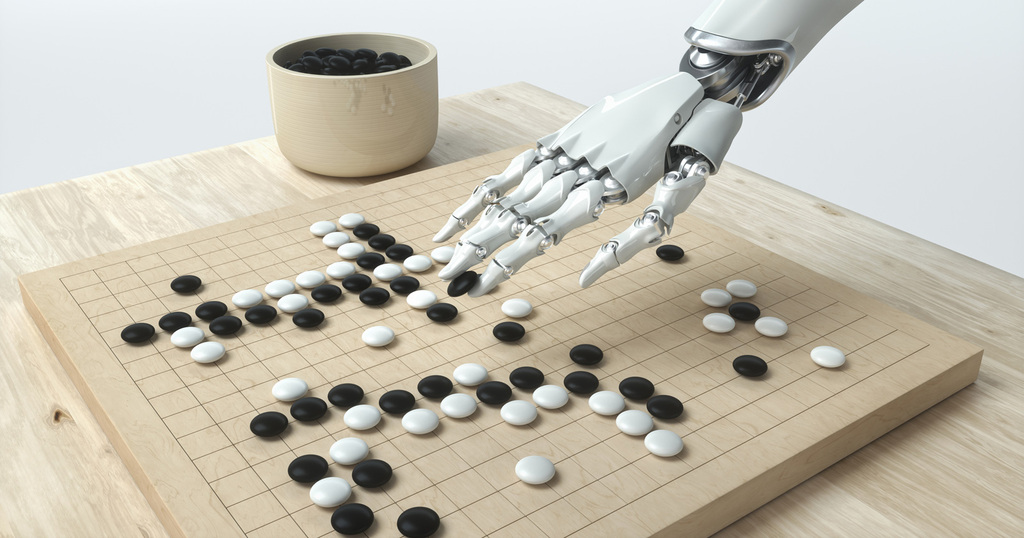
マーケティングについて見ていく前に、「AI活用」そのものの、ここ数年のトレンドを把握しておきましょう。
AI活用に最も興味が集中したのは、2016~2017年ごろ。DeepMind社のAlpha GOが囲碁の世界チャンピオンを打ち破ったニュースを記憶している方も多いでしょう。当時は、さまざまなAIスタートアップが立ち上がり、大企業と共同で実証実験に取り組み、連日ニュースメディアをにぎわせていました。
しかし、2019年ごろから「AI懐疑論」、「AI導入失敗談」が散見されるように。「AIは費用対効果が合わない」「AI活用の落とし穴」など、現実的な目線での情報発信が増えてきました。
このままAIブームは落ち着くのかと思われた2020年、新型コロナウイルスの世界的流行と、それと同時期に発生したDXブームにより、AIは再び脚光を浴びることとなります。手書きや目視などの物理的なオペレーションをAIで代替したり、アバターやチャットボットなどの非接触コミュニケーションで感染者数の抑制に寄与したり、コロナ禍におけるさまざまな場面で、AIは有用だったためです。後に述べる高度な行動データ分析やパーソナライズコミュニケーションもAIの得意領域で、DXブームの中で活用の幅が広がっています。
2022年現在もこのトレンドは継続しているように見えますが、2016~2017年ごろのブームと明らかに異なっている点が1つあります。それは「AIはなんでもできる『魔法の杖』ではなく、適切に使われることでビジネス価値を高める、1つのツールにすぎない」と考えられるようになってきた点です。
良くも悪くも「AIを使った◯◯」というフレーズが価値になっていた数年前と違い、現在は、AIを使っただけでは取り組みそのものの価値や期待値は高まりません。費用対効果、開発・運用体制などビジネス上のさまざまな要素を踏まえて、活用の価値が測られる時代になってきています。
マーケティングにおけるAI活用の現状を概観

こういった時代背景を踏まえて、マーケティングにおけるAI活用の現在地を見ていきましょう。
マーケティングのプロセスを、ここでは大きく以下のステップに分解します。
- 市場・ユーザー理解
- 戦略策定・ターゲティング
- 制作・開発
- デリバリー(顧客接点)
これらの1つひとつにおいて、AI活用の切り口の代表的なものを紹介していきます。
1.市場・ユーザー理解
AIはそもそも、「大量の教師データに基づいて作られた、データを分類したり、予測したりする機械」です。生活者や市場のさまざまなデータを分類・予測したり、今までと違ったアプローチでユーザーの声を集めたりすることで、今まで見えてこなかった生活者インサイトが表層化します。
例えば、人間が普段使用する言語を分析する「自然言語処理」の技術を使用することで、膨大で分析が不可能だったテキストデータ(SNSへの書き込み、アンケート結果など)からトレンドを把握したり、予測したりすることが可能になっています。
事例
・TREND SENSOR
・mindlook
・TexAIntelligence
他にも、市場の動向と自社商品の売れ行きを予測する「需要予測」の分野でもAIの活用が盛んです。需要予測はマーケティングのみならず、生産計画やロジスティクスなどさまざまな分野において応用可能で、DXの大きなテーマとなっています。
事例
・ミチシロウ℠
・AITC(AIトランスフォーメーションセンター)のAI需要予測プロジェクト
少し変わったところでは、対話エージェント(チャットボット)を活用し、従来のインタビュー調査では難しかった「大量のユーザーへのインタビューと定量分析」を可能にするソリューションも生まれています。ユーザー調査の在り方もテクノロジーによって変化しているのです。
2.戦略策定・ターゲティング
「誰にどのようなメッセージを投げかけるか」の戦略策定はマーケティングの核と呼べる部分ですが、ここでもAIが力を発揮します。
最もメジャーなものはユーザーデータ分析やユーザー分類でしょう。CDP(Customer Data Platform)やプライベートDMP(Data Management Platform)のようなデータを収集・管理するためのプラットフォームを導入し、ユーザーの1st Party Dataを保持する企業が増えていますが、それを機械学習させることにより、「より購入確度が高いユーザー」「離脱率が高いユーザー」などを予測し、ターゲットの属性に応じたコミュニケーションを策定することができます。
購入確度や離脱率などのKPIに直結する指標ではなくても、「音楽が好きなユーザー」、「子どもがいるユーザー」、「ビジネスに関心の高いユーザー」などのクラスターを予測するAIを構築し、コミュニケーションの切り口の策定に役立てるケースも増えています。
このようなデータに基づく顧客の予測や分類は、これまでルールベース(例:サイトをx回訪問したユーザーを興味関心層とする)でしかできませんでしたが、機械学習の技術を応用することで、高い精度での分類が可能になっています。
3.制作・開発
デジタルマーケティングにおける落とし穴の1つに、施策を細かく設計すればするほど制作コストが膨大になるため、あるところで、投下する費用やリソースの限界が来る、というものがあります。上記の通りさまざまなデータとAIを駆使し、ターゲティングを細かくすればするほど、クリエーティブやメッセージのパターンも増えていきます。加えてカスタマージャーニーが複雑化し、顧客接点も多様化(SNS、Web、動画、TV、紙媒体……)していることを考慮すると、必要なクリエーティブのパターンは爆発的に増えていきます。
AIによるクリエーティブの自動生成は、この課題を突破するカギになります。コピーライティング、バナー広告、ランディングページなどさまざまなクリエーティブの自動生成ツールが登場し、今までよりも少ないリソースで、多くのパターンのクリエーティブを制作、出し分けることが可能に。全てを自動で生成するだけでなく、リサイズなど、手数がかかっていた作業工程に絞って代替するソリューションも生まれています。
また、制作したクリエーティブの効果を予測するAIもあり、大量に生成するだけでなく、効果が高いものを絞り込むことも可能です。
事例
・MONALISA
ここで重要なのは以下の2点。
1つ目のポイントは、全てをAIで自動化できるわけではないという点です。少なくとも2022年現在では、自動で生成されるクリエーティブは完璧ではありません。言葉に違和感があったり、レイアウトにあらがあったり、100%人間と同じクオリティで生成できるAIは存在しません。そのため、制作・実行プロセスのどこを自動化し、どこを人間が担当するかを見極めて、部分的に取り組みを始める必要があります。
2つ目のポイントは、制作プロセスそのものの最適化です。これらのツールを使いこなすためには、今までの制作プロセスそのものを見直す必要があります。例えば、全てを制作会社に委託するのではなく、一部のツール操作や最終調整を内製することで、飛躍的に業務が効率化する可能性があるのです。あるいは、クリエーティブスタッフにツール活用を促し、利用データが蓄積する制作プロセスにすることで、データが蓄積し、ツールのさらなる改善につなげることができます。AI活用の裏側で、こういったプロセスを進化させていくことで、よりAIの価値は高まると言えます。
事例
・CXAI
4.デリバリー(顧客接点)
ターゲットごとに策定されたメッセージや制作されたクリエーティブを最終的なユーザーに届けるコンタクトポイントでもAIを活用することで、体験がよりリッチになったり、効率的にメッセージを届けたりすることができます。
例えばWebサイト(ランディングページ)上で、データにより導かれた顧客クラスター(似た性質を持つ顧客ごとに分類した集団)によって、提示するメッセージを変えるツールがあります。
事例
・Microscope
従来は細かなセグメンテーションが難しかったマスメディアにおいても、より広告効果を高めるためにAIが活用されています。テレビ業界においては、さまざまなユーザーごとに視聴率を予測し、広告素材を出し分けることで、費用対効果を最適化するソリューションが急速に広まっています。
マーケティングにおけるAI活用の今後
これまで見てきたように、マーケティングプロセスの各領域でAIは活用されていますが、一方でAI技術そのものも日々進化しています。技術の進歩によって、今後どのような変化が起こるのでしょうか。
今後の潮流を、以下の4つの観点から少しだけ予測してみたいと思います。
- 生成系AIの進歩
- バーチャルタレントの登場
- 最適化の進歩
- 倫理的な側面
1.生成系AIの進歩
先の章で、AIによるクリエーティブ生成はまだ十分な精度に達していない、と書きました。しかし先端アルゴリズムにより、この溝はどんどん埋まっています。以下は電通グループで検証したAIによるコピー生成事例ですが、かなり自然な文章になっています。このトレンドが続けば、全自動化もいずれ可能になるでしょう。
<AIによって執筆された文章 例>
〇バウムクーヘンのキャッチフレーズ
・薄皮のバウムクーヘンはふんわりしっとり、じんわり甘いです。
・100%天然素材、100%手作り、100%ふんわりしっとり、日本最高峰のバウムクーヘン技術で作られています。
〇カフェラテのキャッチフレーズ
・上質なミルクを使用した絶品カフェラテです。濃厚なコクと甘酸っぱさがたまらないです。
・美味しいコーヒー豆を使っているため、香りも楽しめる美味しいカフェラテです。
〇レモンティーのキャッチフレーズ
・ほんのり甘いレモンの風味が特徴の茶菓子風レモンティーです。濃厚な香りのブレンドティーと心地よい甘さで、リラックスタイムをより良いものにしてくれます。
・手間暇かけて、じっくりと煮詰めた茶葉と柑橘類の甘酸っぱさが特徴のミックスティーです。
※生成されたキャッチフレーズからブランド名を削除しています。
また、生成する対象も広がっています。例えば人の顔の生成技術は、「ディープフェイク」として有名になっていますが、実在しない人物を生成し、広告素材として活用することで、パーソナライズ・多パターン化と、権利処理の簡易化、撮影や編集などの簡略化など多くのメリットを生むとして期待されています。顔だけでなく動き(モーション)も自然な合成が可能となっていますし、音声合成もかなり自然なレベルになってきています。
これらの技術をかけあわせることで、「各ユーザーに合わせた架空の人物が、ユーザーに最適化されたメッセージを語りかけてくれる動画広告を自動生成・配信する」などといったことも近いうちに可能になりそうです。
2.バーチャルタレントの登場
上記のようなさまざまな生成技術を使うことで、架空の人物だけでなく、実在の人物をバーチャル上で生成することも可能になります。いわゆるバーチャルタレントです。2021年9月には、俳優の加山雄三さんの歌声をAIによって再現した、「バーチャル若大将」が誕生しました。
バーチャルタレントを起用することで、撮影することなく広告素材の制作が可能になったり、従来は難しかった大量パターンの動画広告を生成したりすることなどが可能になります。ここでは深く取り上げませんが、もし「メタバース」のような、全てがバーチャルな世界が一般化するとしたら、こういったバーチャルな人物は、今後のコミュニケーションにおいてより重要になってくるでしょう。
3.最適化の進歩
これまでマーケティングにおいては、投資対効果を最適化するための施策(オンライン・オフライン)の組み合わせ、いわゆる「マーケティングミックス」をいかに行うかが1つのテーマでした。AIが、それをサポートしてくれる可能性はあります。
例えば、非常に細かな特定ターゲットへのリーチを最適化するための、オンライン・オフライン統合プランの自動生成。過去の調査データや経験ではなく、需要の予測とメディア接触予測に基づいて、未来の活動を最適化する。そういったボーダレスな最適化が可能になってくるはずです。
では、今後人間のプランナーやクリエイターは不要になっていくのでしょうか?いえ、マーケティングとはそれほど単純なものではないですよね。いかに限られた予算で、人々の行動や思いの裏をかき、行動を起こさせていくかが本当のクリエーティブです。「平均点のマーケティング」が自動化される時代が来るとしたら、そこから先は再びアイデアの勝負になっていくのではないでしょうか。
さまざまなAIを駆使し、今まで実現できなかったことに取り組んでいく。あるいはAIの裏をかいて、今までにない価値を作っていく。それが「AI時代のクリエーティビティ」と言えるのかもしれません。
4.倫理的な側面
AI活用が浸透するにつれ、倫理的な側面はより重要になってきています。これまでには、AIチャットボットが不適切な発言をして停止に至ったケースや、採用活動において一部の応募者にとって不利な判断をしていて問題になったケースがありました。日本においても、AIによって就活生の「内定辞退率」が予測され、その情報が企業側に通達されたことで、問題になったケースがあります。
マーケティングにおいては、このようなケースを想定してみてください。
- AIが自動で生成したクリエーティブに、差別的な表現・言い回しが含まれていた。
- AIによって差別的要素に基づく分類がなされ、一部ユーザーに不利益があった。
- AIによる予測とパーソナライズがあまりに細かく、ユーザーに不快感を与えた。
AIは人間に代わって予測や判断をするため、こういった好ましくないアウトプットをする危険性と隣り合わせです。AIに関するリスクは開発者だけの責任ではなく、AIを活用する企業にも倫理的な責任が課されます。どういったリスクが存在するのか、リスクをどう未然に防ぐのか、万が一起こってしまった場合にどのように対処するか……。こういったガイドライン策定も同時に、求められてきます。
以上、マーケティングにおけるAI活用の実態と今後について概観してきました。一時期の熱狂は過ぎたとはいえ、いまだ注目され続けるAI。AIの有用性、有用であるがゆえの危険性、そのどちらも正しく理解し、うまく乗りこなしていくことが、業種や規模を問わず、あらゆる企業に求められています。