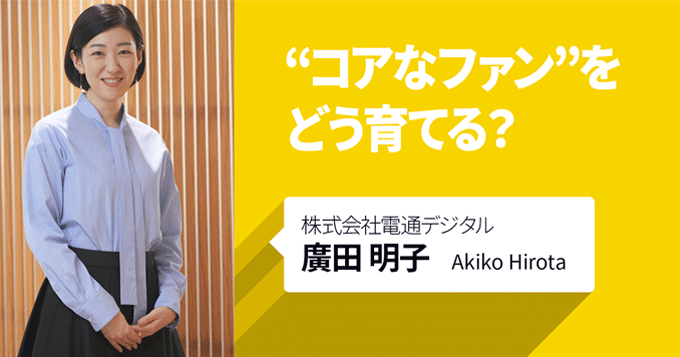コロナ禍で大きな打撃を受けた観光業界は現在、近場で楽しむ小旅行「マイクロツーリズム」を提唱して近隣地域の住人を顧客にし、さらにはリピーターになってもらうためのさまざまな取り組みを行っています。すなわちこれは、マイクロツーリズムを通して既存顧客との関係を深め、1人の顧客から生涯にわたって得られる利益「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)」を高めようという試みでもあるとも言えます。こうしたマイクロツーリズムに見られるリテンション(既存顧客の維持)施策は、他業種にも応用できるのではないでしょうか。
そこで今回は、「マイクロツーリズムにおけるリテンション施策は、他業界においてもLTV向上のヒントとなるか?」をテーマに考察。自社事業において既存顧客のファン化を目指す皆さんとともに、LTVを高めるマーケティングについて考えていきます。
近隣での旅行を楽しむ「マイクロツーリズム」とは
「週末は片道1.5時間のプチ旅行!」と聞いても、「そんな近場で旅行?」と違和感を抱く人はあまり多くないのではないでしょうか。
以前から、日本国内の旅行は「安・近・短(価格が安い・距離が近い・日数が短い)」の傾向が続いていると指摘されていましたが、コロナ禍以降はその流れがさらに加速しています。外出制限や自粛が長期間続いたため、近距離の移動であっても気分がリフレッシュし、旅行のもたらす価値を感じやすくなったとも言えるでしょう。このように近場で楽しむ小旅行は「マイクロツーリズム」と称され、コロナ禍でますます注目を集めるようになりました。
大手旅行関連企業が提唱するマイクロツーリズムの定義は、「自宅から1~2時間以内の範囲で旅行を楽しむ」というもの。陶芸体験や注連縄(しめなわ)づくり、景勝地でのヨガなど、非日常な体験ができるレジャーなどが人気を集めています。さらに、地産地消が促される、地域のお祭りや伝統文化への理解が深まる、地域の人々とのつながりが強化されるなど、地方経済へのポジティブな効果も期待されています。
遠距離移動や海外旅行ができなくても、「心豊かな旅」は地元でできる

なぜ今、日本でマイクロツーリズムがここまで注目されているのでしょうか。その背景について見ていきましょう。
2020年7月、政府による「Go To トラベル」事業がスタートしました。「Go To トラベル」は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって打撃を受けた観光業界を回復させるため、消費者の国内旅行費用を補助するキャンペーンです。他にも、居住する都道府県内や近隣エリアへの旅行を対象にした「県民割」や「地域ブロック割」も開始され、近場の宿泊施設を利用して小旅行を楽しむという旅のスタイルが広まりました。
「マイクロツーリズム」という概念があらためて人々に意識されたのは、このタイミングだと考えられます。コロナ禍では、海外への自由な渡航が制限されただけでなく、国内でも県外への移動に対して自粛要請がなされました。感染症対策の観点から遠距離移動がタブー視され、実家への帰省すらはばかられる方も多かったのではないでしょうか。そんな中、感染症対策と旅行を両立させるために、旅の行き先を居住地県内など移動距離が短い近隣エリアにする、という発想が生まれました。
加えて、そもそも「移動」それ自体が非日常体験となる、ということがコロナ禍によって再認識されたとも言えます。結果として、身近にある鉄道に乗る体験そのものを楽しんだり、近場の温泉地でくつろいだり、近郊のリゾートホテルに宿泊して食事を楽しんだりという日常生活の延長線上にある小旅行の価値が、再発見されたという面もあるのではないでしょうか。
LTVを高めるマイクロツーリズムは、ここがポイント

これまで見てきた通り、コロナ禍では小旅行の価値が再発見されました。ここからは「リテンション(既存顧客の維持)」という観点から、マイクロツーリズムをさらに掘り下げていくとともに、他業界への応用のヒントも探っていきます。
近年、交通インフラの発展などにより遠距離への観光が手軽になり、観光産業は拡大を続けてきました。中でもインバウンドによる市場拡大は目覚ましいものがあり、2019年には、訪日外国人旅行者数が過去最多の3,188万人を記録。同年、日本人出国者数も過去最多の2,008万人に達し、コロナ禍直前の日本を取り巻く旅行は年々スケールアップしていました。
しかし、こうした大規模な旅行は時間も費用もかかるため、リピーターが生まれにくいのも事実。マーケティングにおいては、「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)」という概念があります。これは、1人の顧客が生涯で特定の企業やブランドにどれだけ利益をもたらすかを算出したもの。つまり商品やサービスを一度利用して終わりではなく、いかにしてリピーターになってもらうか、いかにして既存顧客を維持するかを重視した考え方です。海外旅行などの大規模な旅行をこの観点で眺めると「大きな投資で個々の利益を最大化していく」構図となり、LTVの向上には課題があるとも言えます。
一方で、マイクロツーリズムであれば近隣地域の住民による近場の旅行であるため、1年に何回も繰り返し訪れてもらうことも可能でしょう。現地の人口が少なくても、季節ごとに年4回訪れてくれる観光客がいれば、売り上げも4倍になります。
アメリカのある経営コンサルタントは、「新規顧客を獲得するには、既存顧客維持の5倍もコストがかかる」という「1:5の法則」を提唱しています。つまりLTVという観点から見れば、マイクロツーリズムは観光業界における1つの理想形と言えるのかもしれません。
マイクロツーリズムでリピーターを獲得できれば、宿泊施設や交通産業のみならず、関係企業にも大きなメリットをもたらすでしょう。そのためには地域の魅力再発見につながる多彩な体験、訪れる人を魅了する四季折々のイベントや新鮮なアクティビティ、現地の人々との生きた交流機会を提供し、ファンエンゲージメントを深めることが欠かせません。そして実際に、マイクロツーリズムの現場においては、今まで以上に地域の価値を向上しようとするさまざまな試みが実践されています。マイクロツーリズムの具体事例から、顧客のQOLを底上げしながら、関連企業のLTV向上も実現するポイントを見ていきましょう。
事例1:地域密着型体験の提供
地域密着のNPOや都市型観光ホテルでは、地元グルメを客室に届けたり、地元の人がガイドとなって銭湯や飲食店へ案内したり、伝統文化の体験プログラムに参加を促したりと、地域の魅力を再発見できるようなサービスを提供しています。参加した旅行者からは、「おいしいものを堪能できるだけでなく、住民になった気分も味わえる」と大好評。その町のファンになる人が増えれば、リピート率の向上も期待できます。
事例2:デイユースプランの提供
日帰り客を獲得するため、客室での食事や露天風呂などを楽しめるデイユースサービスを提供する「泊まれない温泉旅館」が誕生。宿泊を伴わないものの、高級感あふれる非日常空間で、ゆったりとした時間を過ごすことができます。高嶺の花の高級旅館が、比較的手ごろな日帰りプランを用意したケースです。
事例3:アプリによるリピート客の獲得
自治体が提供するスマートフォンアプリをダウンロードして登録すると、観光情報が見られるだけでなく、飲食店・宿泊施設を利用するごとにポイントが加算。ポイントを使ってお得に買い物ができたり、さまざまな特典を受けられたりするサービスです。旅行後も旬の情報が定期的に配信され、再来訪につなげています。
観光業界に限らず、どの業界にとっても、既存顧客の維持は新規顧客の獲得に勝るとも劣らない重要課題です。地域と企業、自治体が一体となって、逆境をプラスに転換する仕組みを創出すること。顧客視点に立ってサービスを作り込み、「体験」の質を高めること。こうした事例から、他業種にも展開できるLTV向上のヒントが見つかるのではないでしょうか。
コロナ禍によって気運が高まったマイクロツーリズムについて、その背景とビジネス面におけるメリット、具体事例などを詳しく見てきました。マイクロツーリズムによって獲得した顧客とエンゲージメントを深め、リピートを促す施策に果敢に取り組んでいる観光業界。そこからは古くからある手法でありながら、顧客をファン化へと導くユニークな工夫を多数見て取ることができました。彼らが生み出したアイデアをお手本に、皆さんも自社事業においてリピーター獲得とLTV向上を目指してみてはいかがでしょうか。
自社事業や商品のファンをいかに増やし、LTVを向上させるか?電通グループでは、観光業界以外にもさまざまな業種のノウハウを蓄積しています。私たちと一緒にLTV向上にチャレンジしてみませんか?まずはお気軽にCONTACTからご相談を。