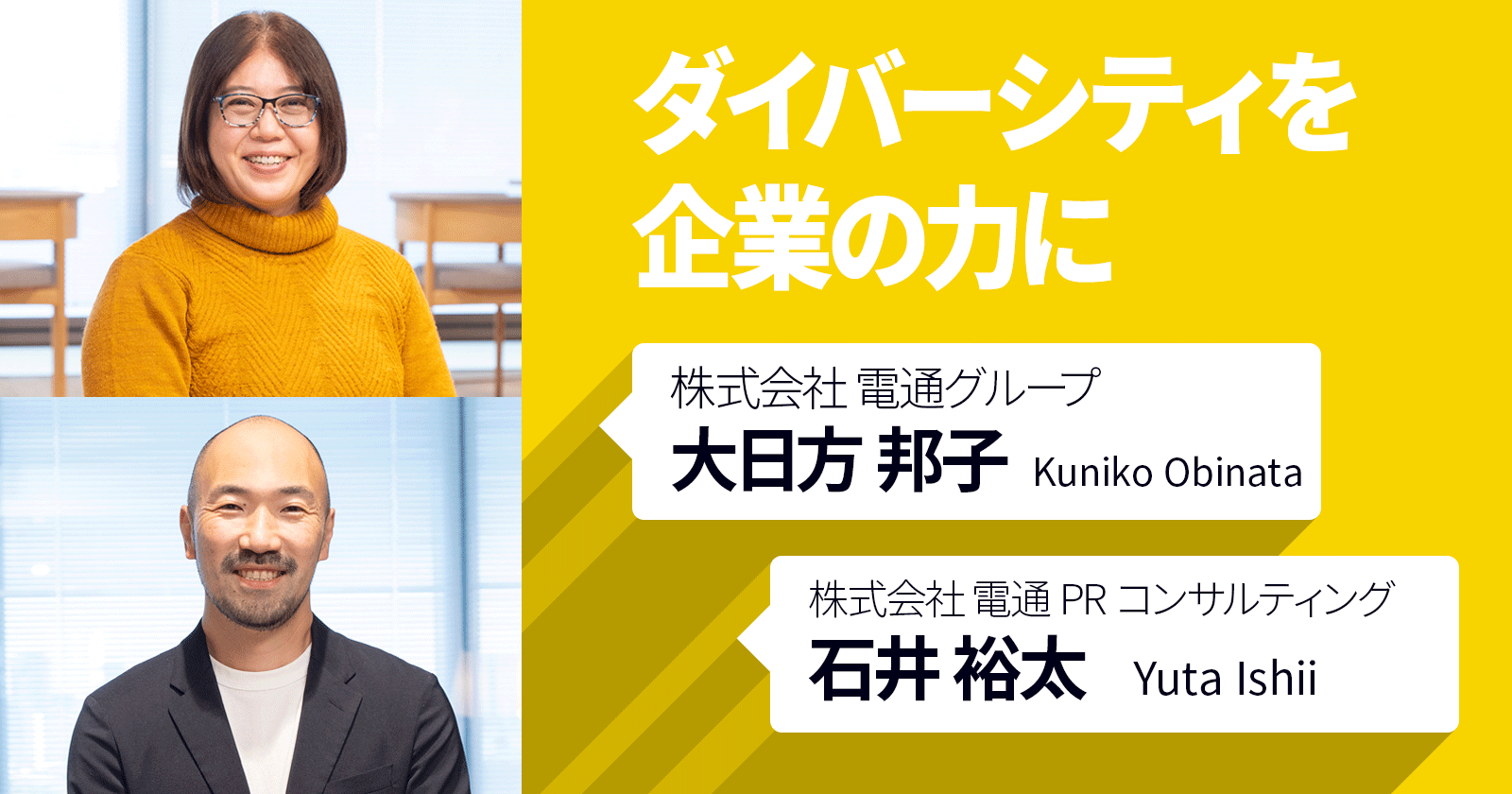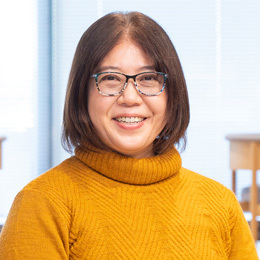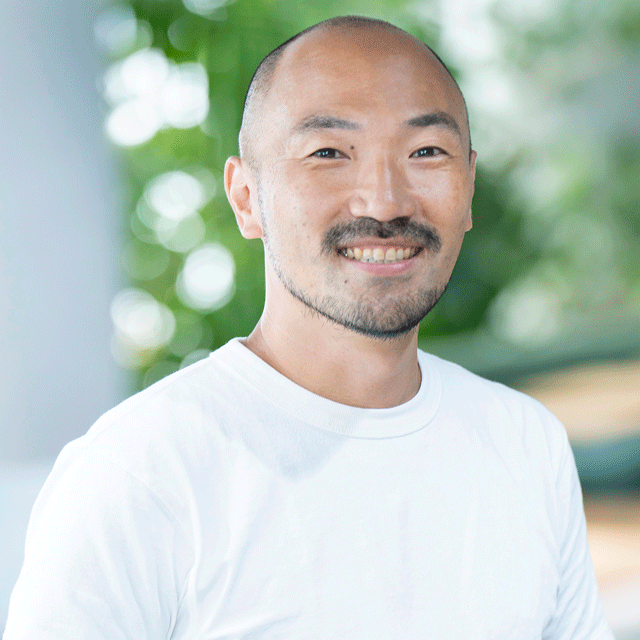企業におけるDE&I(Diversity、Equity&Inclusion)実現に向けた取り組みの重要性は、ますます高まっています。一口にDE&Iといっても、そこにはさまざまなテーマが存在していますが、「障がい者雇用」は重要なトピックの1つです。一定の規模以上の企業では、障がい者の雇用が義務化されていますし、障がい者の方々が職場にもたらしてくれる多様性は、その企業を前に進める大きな力にもなります。
そこで本記事では、株式会社 電通グループ フェロー/電通総研 副所長である大日方邦子氏と、株式会社電通PRコンサルティングの石井裕太氏にインタビューを実施。大日方氏は、1998年の長野パラリンピックで、日本人初となる金メダルを獲得するなど、アルペンスキーの選手として多くの実績を持ち、現在は、一般社団法人日本パラリンピアンズ協会の会長としても活動しながら、日本にパラスポーツを普及させ、パラアスリートを通じた多様性の実現に向け、さまざまな取り組みを進めています。また、石井氏は、電通PRコンサルティングにおいて「サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)」を推進する部署に所属しており、かねてより大日方氏と共に多くの仕事を経験。
パラアスリートの第一人者であり、企業においてもダイバーシティを推進する先頭に立ってきた大日方氏と、共にプロジェクトを進めてきた石井氏に、「障がい者雇用が、企業やビジネスにどのような強さをもたらすのか」について、語ってもらいました。
パラスポーツを続けながらPRカンパニーへ

Q.大日方さんは、チェアスキーヤーとして大活躍されました。冬季パラリンピックには、リレハンメルからバンクーバーまで5大会連続出場し、アルペンスキー競技で合計10個のメダル(金2個、銀3個、銅5個)を獲得。冬季パラリンピックにおける日本人初の金メダリスト(1998年長野大会、滑降)という非常に輝かしい経歴をお持ちです。そんな大日方さんが、「電通PRコンサルティング(旧・株式会社電通パブリックリレーションズ)」という会社に入社されたというのも非常に興味深いのですが、どういった経緯があったのでしょうか?
配属先は東京で、教育番組の制作ディレクターを担当していました。そんな中1998年の長野パラリンピックで、ありがたいことに日本人で初めての金メダルを獲得しました。その時、私の所属元のテレビ局も中継をしていたのですが、「あの大日方ってどこの会社の人?」と、調べたら同僚だったという笑い話があります(笑)。それくらい知られていなかったんです。
そうして競技の実績を積む中で、このままだと仕事もスポーツも中途半端になってしまうのでは、という悩みを感じていました。当時の電通パブリックリレーションズに出会ったのは、そんなタイミングです。テレビ局でメディアとの人脈を築いてきたことや、アスリートであることが強みとなって、会社に貢献できるという点もありましたし、会社からは、スポーツを続けることを応援してくれる、というありがたい話もいただきました。そこで、社会人11年目の節目に転職を決めました。
Q.転職後、すでに電通パブリックリレーションズで仕事をしていた石井さんと出会ったわけですね。

当社は、電通グループの中でもそれほど大きくない会社で、小回りが利く、という良い面を持っています。2007年当時、パラスポーツの現役選手を採用し応援する、という企業は今のように多くはなかったので、「こういう人と一緒に働いたら面白そうだ」というワクワク感で動けるのがこの会社の良いところですし、当時は、まさにそんな判断がされたのだと思います。
Q.大日方さんが入社してすぐ、お2人は一緒に仕事をするようになったのですか?
社会との関わり方や視点が違う人たちと触れることで、物事の本質が見えてくる
Q.2人で一緒にお仕事をされるようになって、今はパラスポーツ支援などを進めていらっしゃるんですよね。
これは「結果」と「成果」の違いとも言えます。例えば、今のDE&I領域の中で重要アジェンダの1つに「女性活躍」があります。その中で、求められる「結果」は、「管理職における女性比率を30%にする」などといった客観的なアウトプットになる。しかし、それ以上に重要なのが「成果」で、これは「女性活躍が進むことで変化した誰かの姿」は一体どうなっているのか、というアウトカムです。つまり、女性活躍が進んだ結果、具体的に誰がどう幸せになったのかという成果を、私たちは身をもっていろいろと実体験してきたのではないかと思います。
パラアスリートだって、聖人君子ではありません。「障がいと付き合いながら頑張っている」ということで、立派な人として描かれるケースも多いですし、そういう側面もあるとは思いますが、それでも1人の人間としては、もっと多様な側面も持っている。石井がパラアスリートたちの素顔を見る中で、理解が進んでいるのが分かります。
「本音」で向き合えるかどうかが、ダイバーシティを推進するカギ
Q.お2人は、有識者と連携したダイバーシティに関する研究を進めていらっしゃると伺いました。
これまでいろんな議論をしてきた中で、「触媒」となる人が重要だ、ということが分かってきました。しかし、究極的に言えば、その役割が必ずしもパラアスリートである必要はない、ということも見えてきています。「障がい者だから」「パラアスリートだから」ではなく、チームにおけるダイバーシティを推進できる人かどうか、ということが重要なのだと。
Q.なるほど、確かに「本音」は大事だと思いますが、難しいですよね。「正論」は何となく分かりますし、それこそ誤りではないのでしょうが、「本音」となると、その発言が命取りになる、というケースも現代では数多く見られます。
パラアスリートの多くは、自分の中に強い芯を持っていて、周囲の人の発言や行動に揺らがない強さを持っている人が多い。私自身もパラアスリートとして、大切にしている価値がありますし、謙虚な気持ちは大切にしながらも、自信を持って生きていきたいと思っています。
以前、ボッチャの選手へのインタビューを調整するお手伝いをして、福祉面ではなく運動面にトップアスリートとして大きく掲載されたのですが、その時、選手と選手のご家族が非常に喜んでくださって、「これは宝物だ!」と言っていただいたんです。それだけ喜んでいただける仕事って本当に尊いなとあらためて思いまして、そんな仕事に巡り合うことができたのは、大日方やいろいろな人たちと出会えたからだと思います。こういった実績をいろいろな仕事につなげていきたいと思っています。

「障がい者雇用」と「DE&I」というテーマに対し、当事者として向き合ってきた大日方氏。非常にリアリティに溢れた、貴重な話でした。障がい者と向き合うことで、新鮮な気付きがあり、物事の本質が見えてくる、という指摘は非常に重要な視点ではないでしょうか。
「ダイバーシティ」をどんなに意識していても、やはり1人の人間で考えられる領域には限界があります。いろいろな人がいて、それぞれの視点があるからこそ、自分だけでは気が付かなかった新しい視点・重要な発見にたどりつける。「VUCAの時代」と言われる現代において、いかなる状況にも対応できる力をつけるためには、企業の内部にダイバーシティを担保することが重要です。大日方氏や石井氏は、ダイバーシティが企業にもたらす強さを、リアルに語ってくれたのではないでしょうか。
電通グループは、DE&Iをはじめ、多様性に富んだ社会を実現するための、さまざまな知見を持っています。そんなムーブメントを、共につくっていきませんか?お問い合わせはCONTACTから。