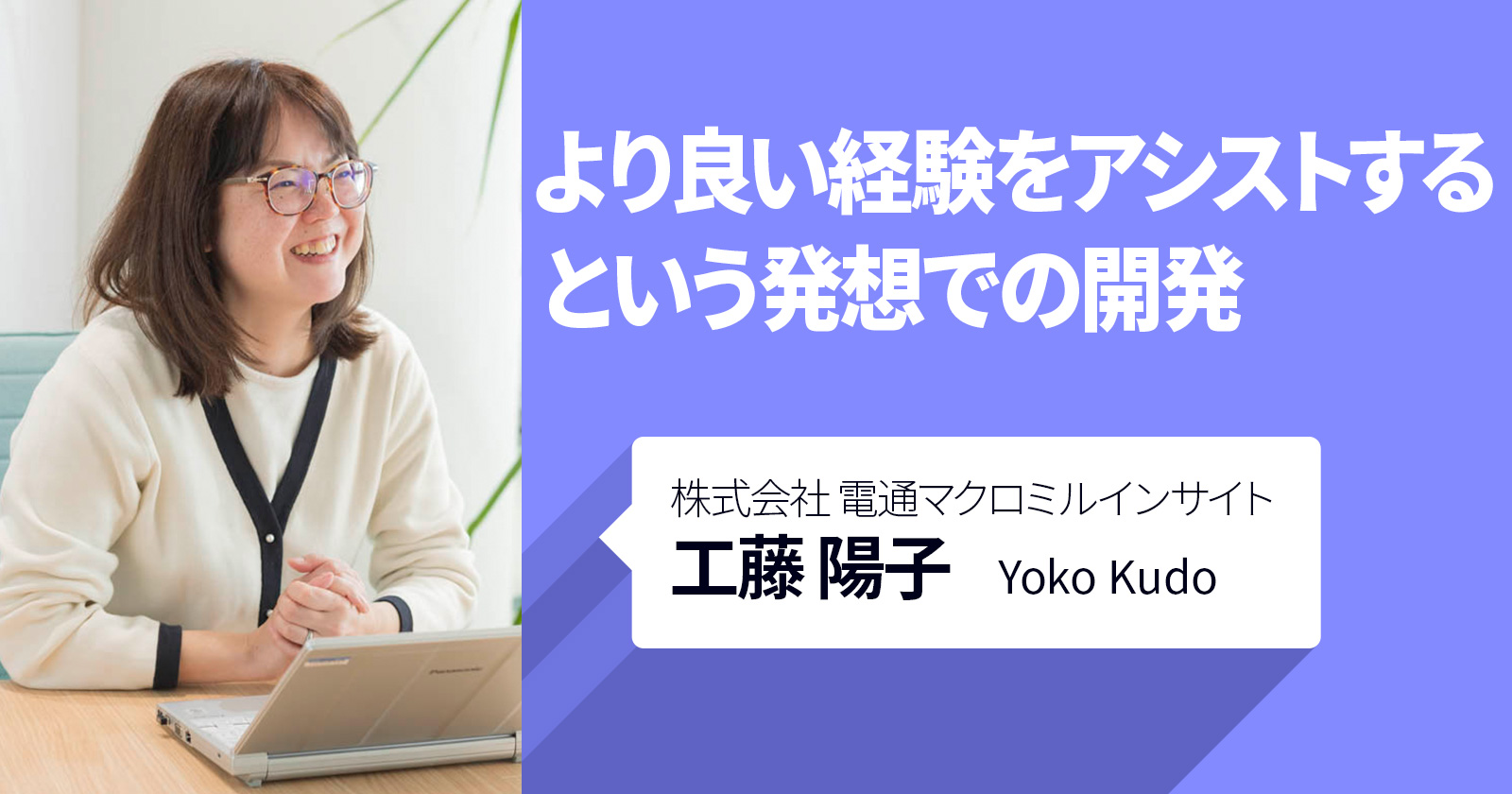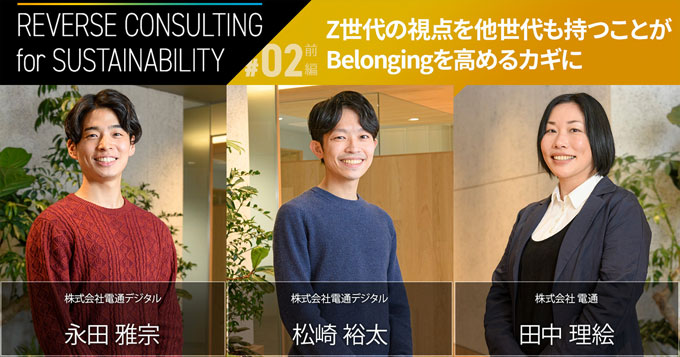株式会社 電通マクロミルインサイト(以下、DMI)の組織「人と生活研究所」では、マーケット理解・予測を目的とした「トレンド予測」「未来予測」と、生活者インサイト理解を目的とした「ウェルビーイング研究」「欲求研究」を2本柱に、調査・研究を行っています。前編では、そのうちの「ウェルビーイング研究」の活動内容について、「人と生活研究所」の工藤陽子氏に話を聞きました。
インタビュー後編では、ニューロサイエンスを基に開発した「Happy Brain Card」と、その活用法について深掘りします。
“脳内ハッピー”が起きる状態を可視化する
Q.ウェルビーイング研究の第3弾研究発表によると、ウェルビーイングな商品・事業開発を促進するための「Happy Brain Card」を開発したそうですが、これについて詳しく教えてください。
例えば、睡眠。現在、睡眠をサポートするアイテムやサプリもいろいろと販売されており、よく眠れることや睡眠の質をあげたいニーズは高いと思います。脳的ハッピールールとしては「朝浴びたセロトニンが夕方になるとメラトニンに変わり、良質な睡眠を得られる」があります。体に摂取するものなどで改善していく方向もありますが、朝から太陽の下で活動してセロトニンを浴びるような行動を促進していく、そんな経験をギフトしたほうがより良い1日につながるかもしれません。
このように、脳的ハッピーを導ける行動ルールを30個ほどピックアップしてツール化したものが「Happy Brain Card」です。

Q.ニューロサイエンス観点から作成したということは、生体反応に基づいて「幸せ」を定義しているということでしょうか?「趣味に没頭できて幸せ」とか「好きなゲームができて幸せ」といった主観的な幸せについて、脳科学や生理学の観点からその現象の原因と言われているポイントを活用し、カードに落とし込んだということですよね。
これを踏まえると、商品やサービスを提供するときも、「何が飛び出すか分からないドキドキ」と、「好奇心をそそるワクワク」みたいなものをセットにすれば、その状態に近くなる可能性があります。
Q.「吊り橋理論」という心理学の実験がありますが、あれは不安や緊張から引き起こされたドキドキする感覚を、恋愛感情と錯覚するために起こる心理的現象ですよね。「Happy Brain Card」を用いた商品・サービス開発も同じように、生体反応を応用するような展開を目指しているということでしょうか。
最近では、クライアントとのワークショップの中でも「Happy Brain Card」を活用いただけるケースが増えてきました。アイデア出しの刺激剤として使っていただいています。
ウェルビーイング研究は組織開発にも応用できる
Q.これまで、研究発表を第4弾まで出されていますが、ウェルビーイングの研究を通して見えてきたことや、手応えを感じた部分はありますか?
当社のメイン事業はマーケティング&リサーチですが、組織開発や、人材を資本として捉えてその価値を最大限に引き出す「人的資本経営」といった領域もサポートできるのではないかと思っているので、今後はそちらの方面にも挑戦していきたいと思っています。
Q.マーケティングのソリューションが、組織開発に応用できるというのは面白いですね。
ただ、いわゆる「施策ありき」の取り組みは、上からトップダウンで実行するよう言われても「ああ、なんかめんどくさいな……」「なんかやること増えたな」という空気になってしまいがちなことも多いのではないでしょうか。それよりも、毎日幸せに働ける方法を社員自ら考えていく方が、ウェルビーイングが高まりやすいのではないか。HR戦略に詳しくないいち従業員でも、「幸せの方向性9因子」という方向性と「Happy Brain Card」のヒントがあれば、職場のより良い慣習づくりの施策を思いつくヒントに役立つのではないかと感じました。

「良い経験」を得られるような商品・サービス開発を
Q.今後、追究していきたいウェルビーイングのテーマはありますか?
市場がコモディティー化してしまっていて、新商品を開発することの意味を見失いつつある企業もあるように感じています。そのような企業に対して、単純に企業活動のサイクルとして新商品を開発する、だけでなく、良い体験を得られたり、良い1日を過ごせたりするような商品を考えていきませんか、といった提案ができればいいなと思っています。
例えば、調味料を開発しているメーカーなら、「食体験」や「1日の行動」というふうに視野を広げて考えて、生活者にとって良い経験をデザインしていく。そのような商品・サービスを開発するために伴走していけたらいいですね。
Q.「この商品を売るために」といった従来型のプロモーションではなく、もう少し長いスパン、広い視野で、未来をどうデザインするか提案していくということですね。
人生100年時代と言われる今、長い人生をより良く、ウェルビーイングな暮らしを実現することに注目が集まっています。個人的体験や感覚に基づく「幸せ」を可視化し、マーケティングや企業活動に生かそうとする「人と生活研究所」の取り組みは、時代のニーズにもマッチしており、今後の研究にも興味を惹かれます。
電通マクロミルインサイトでは、専門性の高いリサーチャーやアナリストが豊富なデータ活用と独自メソッドを生かし、生活者インサイトとビジネスを力強くブリッジすることで、クライアントビジネスを成功へと導きます。withコロナを踏まえた「生活者予測」や、人の幸せの類型を描く「ウェルビーイング研究」をベースにしたソリューションについて詳しく知りたい方は、CONTACTよりお問い合わせください。