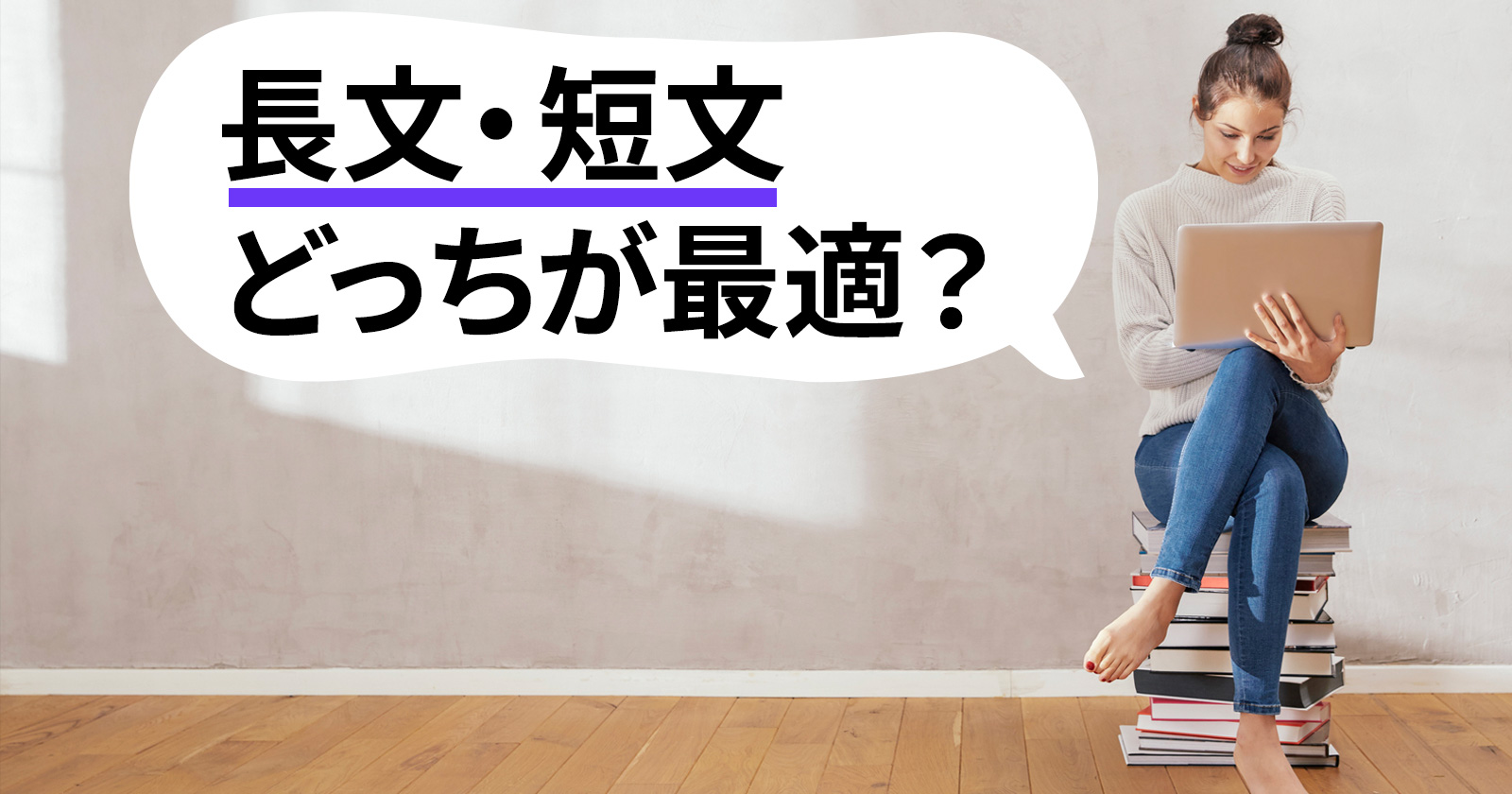ここ数年、SNSをはじめとしたわずか数秒で理解できるマイクロコンテンツが人々のスタンダードになる一方で、ロングフォームコンテンツがトレンドとして浮上しつつあります。変化が目まぐるしいコンテンツの世界において、最適なボリュームを見極めるにはどうすれば良いのでしょうか。
今回は、「ターゲットに好まれるコンテンツのボリュームを知りたい」「自社が発信するコンテンツのボリュームは、本当に適切なのか?」という課題意識を持つ皆さんに向けて、コンテンツの長短を判断するヒントをお届けします。「ロングフォームかマイクロか。最適なコンテンツの長さを見極めるモノサシとは?」をテーマに、コンテンツの最適な長さを考えていきましょう。
マイクロコンテンツからロングフォームへ。コンテンツのトレンドが回帰している?
SNSの投稿文や記事を3行に要約したコピーなど、現在、ボリュームの少ないマイクロコンテンツがインターネット上にあふれています。こうしたコンテンツに慣れ親しんだ感覚からすると、この記事ですら長く感じてしまうかもしれません。しかしその一方で、近年、とてもボリュームのある長文コンテンツを目にする機会も増えてはいないでしょうか。
例えば、マイクロコンテンツの代表格とも言える某SNSでは、1回の投稿の上限文字数が140文字と決められており、限られた文字数でいかに要点を伝えるかが重要となります。その端的でスピード感あふれるコミュニケーションこそが魅力であり、ユーザーの時間を奪うことなくメッセージを伝えられる点が、最大の武器と言えるでしょう。
そんな中、そのプラットフォームにおいて新たな機能のテストがなされました。ブログのように最大2,500文字の文章と画像から成るコンテンツを投稿できるというものです。これまで長文を投稿するには、長文メモのスクリーンショットを貼り付けたり、スレッドをぶら下げたりする必要があるなど、短文を売りにしてきたSNSが、なぜ、このような試みを行ったのでしょうか。この長文へのトレンド回帰ともとれる動きによって、コンテンツの長さに関する議論が活発化しています。
コンテンツの長さのトレンドは、時代とテクノロジーの進化によって変遷してきた
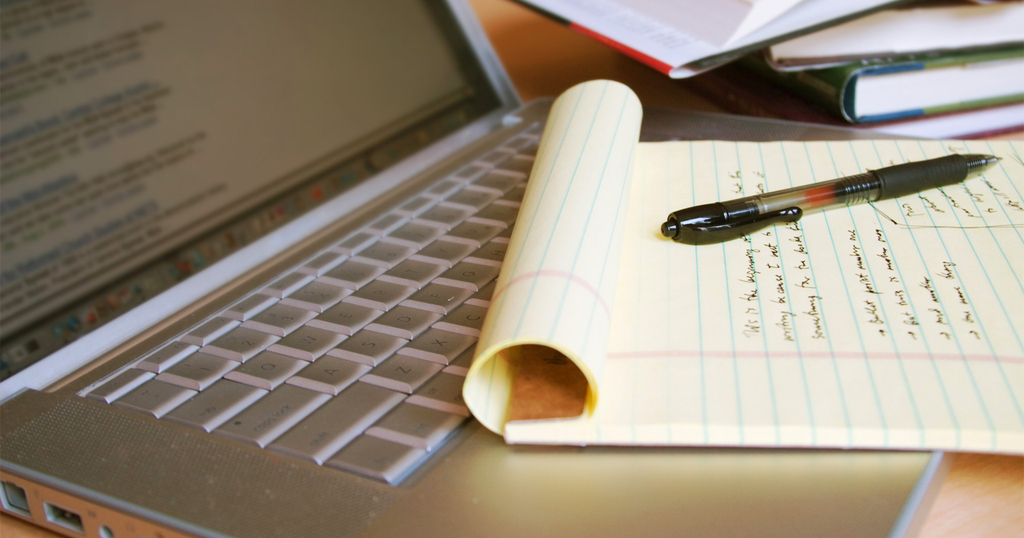
コンテンツのボリュームは、果たしてどれくらいが適量なのでしょうか。それを探るにあたって、まずはコンテンツの長短を巡るこれまでの歴史を振り返っていきましょう。
コンテンツを提供するメディアは、本からテレビ、パソコン、スマートフォン等へと広がり、時代とともに多様化してきました。テクノロジーとインターフェースが進化すれば、メディアのトレンドも移り変わっていきます。その都度、最適なコンテンツの形式やボリュームも変化してきたのです。
1990年代にインターネットが登場してからは、マーケターは「どのようなコンテンツがターゲットに最も読まれるか」「訴求効果の高い文章量とはどのくらいか」と、試行錯誤を繰り返してきました。また、検索エンジンのアルゴリズムが変化すれば、検索上位に表示されるコンテンツも変わります。検索エンジンに正しく評価されるために行うSEO対策も、コンテンツのトレンドに影響を与えてきました。
デジタルメディアでは、長きにわたって「SEOに効果がある」という観点から長文コンテンツ、いわゆるロングフォームコンテンツがリーチ獲得において有利とされてきました。しかし、近年ではSNSの流行により、「コンテンツは短い方がリーチする」「画像をメインにした方が伝わりやすい」「動画も短くコンパクトに」という方向へトレンドが変化。こちらの記事でもご紹介しましたが、動画コンテンツを倍速視聴するなど、タイムパフォーマンスを重視する特定世代において、時間を奪わないマイクロコンテンツが隆盛になるのは当然と言えます。
では、なぜ今、ロングフォームコンテンツが再び注目を集めているのでしょうか。その変化には、「テキスト発信型メディア」の影響もあるようです。
例えば、企業がテキスト発信型メディアをプロモーションに活用する場合、商品・サービスの開発プロセスや製作者インタビューなど、自社サイトでは伝え切れない舞台裏をメイキングのようにテキストにまとめて発信することも。また、海外発の同型メディアは、論評やアイデアなど独自の情報を共有するプラットフォームとしてユーザーを増やしています。
これは、発信する情報に価値があるからこそ、長いテキストが求められる。あるいは、情報に価値を持たせるために、ある程度のコンテンツの長さが必要とされるということでしょう。つまり、発信する情報の価値が、コンテンツのボリュームに影響を与えているのです。
コンテンツの長さに制限が少ないこうした自由なプラットフォームでは、発信者が思うままにテキストをつづることができ、それが読み手の支持を集めています。ロングフォームコンテンツは、発信側・読者の双方にとって短文のマイクロコンテンツにはない魅力を持っていると言えるでしょう。
カギとなるのは「適材適所」の視点。コンテンツ設計を起点にすれば、適切なボリュームが見えてくる

このように、情報の価値はコンテンツの長さに影響を与え得ることが分かりました。この点について、さらに別の角度から考えていきましょう。
SNSを好む若い世代は、タイムパフォーマンスを重視する一方、消費行動においては「イミ消費」へとシフトしつつあります。イミ消費とはブランドなどのストーリーや世界観に共感し、そこに価値を見出す消費行動のこと。例えば、東日本大震災などの災害やコロナ禍によって機運が高まった「応援消費」も、その一環と言えます。
こうした消費傾向とロングフォームコンテンツは、相性の良い組み合わせと言えるのではないでしょうか。誰もが自由に情報を発信できるユーザー発信型プラットフォームの誕生により、現代は「ストーリーを売る時代」になりました。ストーリーの価値が見直され、テキストによるコミュニケーションへの回帰が注目を集めていると捉えることもできるでしょう。
思い返せば1995年に、多くの人々が日常生活の記録をインターネット上の掲示板に公開する、ある日記のプロジェクトが存在しました。日付を軸に、多くのユーザーによって生み出される文章の集合体は、プロジェクトの価値そのもの。つまりそこには、「テキストの量=価値」という図式がありました。
何をもって情報の「量」を適切とするかは、唯一の正解があるわけではないため非常に難しい問題です。しかし、伝えたい内容に対して過不足がないかどうかを判断することは、比較的容易と言えます。すなわち最も重要なのは、「何を伝え、受け手の態度や行動にどのような変容を促すか?」という視点に立ったコンテンツ設計。コンテンツの長短は、そこから自ずと導き出されるものではないでしょうか。
ではこのことを、小説を例に考えてみましょう。星新一作品をはじめとするショートショートのように、短いストーリーテリングの中で驚きと感動を与える小説は、短時間で娯楽を享受できるのが特徴です。他方で、京極夏彦作品などの超大作は、娯楽を享受するには多くの時間を要するかもしれませんが、それだけの物量があるからこそ届けられる価値もあります。
つまり文章の長さと価値の大きさは比例せず、どちらも「感動」という価値を得られることには変わりありません。このことから、判断のモノサシはケースバイケースであり、表現したい内容に応じて器を選ぶという「適材適所」の考え方でコンテンツを作るべきであることが見えてきます。
「どのボリュームのコンテンツが最も読まれるか」というターゲットの行動分析は、時によってはコンテンツ制作の指針の1つとして役立つこともあります。しかしより本質的には、訴求する内容はどのような形で表現すべきか、コンテンツの価値とメディア特性を考慮し、適材適所の考え方でそのボリュームを設定する視点が不可欠であると言えそうです。そういった視点に立った上で、ロングフォームコンテンツへのトレンド回帰に注目してみると、適切なボリュームを導き出すためのヒントが見えてくるかもしれません。
コンテンツの長短をめぐる歴史を振り返りながら、ロングフォームとマイクロコンテンツ、それぞれの特徴と背景について見てきました。コンテンツのボリュームは、「ロングの方が正解」「マイクロの方が価値が高い」などと二者択一で語ることはできません。適材適所の視点を持ち、訴求する内容に応じて柔軟に使い分ける、届けたい価値から逆算して長短を決めるという発想が何より大切ではないでしょうか。
「媒体に合わせてコンテンツボリュームを使い分けるにはどうすればいい?」「受け手の行動変容を促すコンテンツづくりのコツは?」そんな課題をお持ちの皆さん、私たちと一緒にユーザーに「刺さる」コンテンツを作っていきませんか?お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。