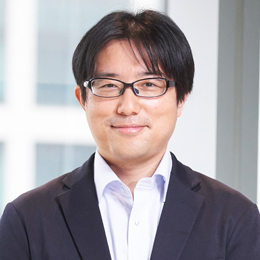今や、データの分析・活用はビジネスの成長に不可欠です。しかし、取得したデータをビジネスに生かしきれていないケースも散見されます。「手元にデータはあるが、活用できていない」「CDP(Customer Data Platform:顧客データを収集・統合し管理するシステム)を構築中だが、有益な使い方が分からない」という悩みを抱える企業も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、データ活用によるビジネス・コンサルティングを推進している株式会社電通デジタル ビジネストランスフォーメーション(BX)部門 データストラテジー事業部の小西良太氏にインタビュー。小西氏は、個社に対応するセミナー「AIワークショップ」を開催。データに基づくビジョン策定、AI・機械学習による営業効果向上を支援しています。
「データを起点にすることでビジネスが進化していく」ということはなんとなく分かるけれど、その具体的な道筋はイメージができない、という人も多いのではないでしょうか。前編では小西氏が所属するチームの特徴や、データドリブンな戦略策定について聞きました。
データに基づき、ビジネスの理想像を設計
Q.小西さんは、電通デジタルのBX部門データストラテジー事業部で、どのような役割を担っているのでしょうか。
中でも、私が深く携わっているのが個社別セミナー「AIワークショップ」です。クライアントさまから「こういうことに困っている」「こういうことを教えてほしい」という声を伺い、個別にカスタマイズしたワークショップを行って、ご相談に応じています。
また、データ利活用の構想策定も行っています。「どうすればデータを利活用できるのか」「集めたデータをどう利活用すれば、収益アップにつながるのか」というご相談に対するサポートをする他、データの集計・分析も行います。

Q.ひと口にデータと言っても、アンケート、ユーザーの会員情報などさまざまなものがあります。小西さんが言う「データ」とは、何を指しているのでしょうか。
例えば、インタビューでユーザーの声を集める場合、一度に多くの人に話を聞くのは困難です。聞けたとしても、数人から数十人でしょう。ですが、データとして数百、数千、数万というファクトを積み重ねていけば、そこからさまざまなことが読み取れます。今何が起こっているかが分かってきて、それを分析することで、今後どうなるかが見えてくる。そういったものがデータではないかと思います。
Q.データを使ったコンサルティングについて教えてください。企業からの相談に対し、どのようなソリューションを提供しているのでしょうか。
そこで起点になるのが、先ほど申し上げた「データ」すなわち「ファクト」です。どのようなファクトを基にして、戦略や施策を打ち出すのか。施策を実現するには、どんなデータ分析環境、IT環境が必要なのか。データ起点でビジネスの理想像を設計していきます。データの分析自体は、機械学習ツールに詳しくなくてもできますが、何をインプットするのか、出てきたアウトプットをどう利活用するのかを考えるのは人の力。そこをメインにしているのが、私たちデータストラテジー事業部です。
ビジョン実現のために、必要なデータを提案
Q.AI・機械学習に興味はあっても、まだ活用法が分からない企業もたくさんあると思います。小西さんのところに寄せられる相談としては、どのようなものが多いのでしょうか。
その上で、私たちとしては、データ利活用構想策定の割合を更に増やしていきたいと考えています。データ利活用構想策定は、クライアントさまが抱えている抽象的なwishを、「データを使うと、こういう未来が待っている」と提示しながらGOAL設定を明確化していくところから始まり、それを具現化させるためのIT環境要求整備やデータ解析事項の設計、実装までのロードマップ作りを行うものです。クライアントさまが集めたデータを基にビジョンを描いたり、ビジョンを実現するためにデータをそろえたりすることを担っていきたいと考えています。「ビジョンを描く」というと他社でもサービスを提供していると思いますが、私たちの部署では、電通グループならではの、クライアント業界の半歩先の未来や顧客体験設計から来る定性的な初期仮説設定と、AI/機械学習をはじめとした定量解析で可能となる世界観を組み合わせたアプローチでビジョンメイキングしており、そこが他社との違いになっていると考えています。
Q.策定したビジョンを実現するには、クライアントさまが既に保有しているデータだけではなく、新たなデータが必要になることもありそうです。そういうケースでは、必要なデータの取得を提案することもあるのでしょうか。
大事なのはそこからです。私たちは「こういうデータをそろえると良いのでは」というご提案はできますが、実際にデータを取得するのはクライアントさまのタスクになります。そこで、目的に応じて「一般的にこういうデータの取り方があります」「アンケートでこういうデータを取りましょう」「こういう企画にすると、データがよりリッチになりそうです」といった選択肢をご提示した上で、何が最適なのか、一緒に考えていきます。
また、既にクライアントさまが収集しているデータを加工することも提案します。私たちは「合成変数」と呼んでいますが、既存のデータであっても、何かと掛け合わせることで新しいものが見えてくるかもしれません。
新規でどのようにデータを取るか、そして既存データをどう生かすか。この2点はご相談をいただいたら早いうちに、アイデアとして提案しています。
Q.データを利活用するプロジェクトにおいて、うまくいく・うまくいかないの分水嶺はどこにあるのでしょう。

「AIワークショップ」で、各社に適したAI活用テーマを発見
Q.これまでのお話から、ビジョンメイキング、その実現のためのデータ利活用が大事だと分かりました。そこにAI・機械学習はどのように関わってくるのでしょうか。
Q.「AI勉強会」というテーマだけで言えば、他にも似たようなものが数多く開かれているとも言えます。小西さんの「AIワークショップ」の特徴や強み、高く評価されている点についてお聞かせください。
次にフリートークセッションを行い、クライアントさまが抱えるビジネス課題を自由に話し合い、提案につなげていきます。ただセミナーを聞いていただくだけでなく、フリートークによって自社にとってのビジネスの課題を洗い出し、新たな価値観を生み出すことが、私たちの「AIワークショップ」の特徴です。
「データ利活用」と聞くと、手元にあるデータの分析・利活用を思い浮かべますが、それだけではありません。データを基にビジョンを策定すること、実現のための環境づくりも重要であり、それを包括的にサポートするのがデータストラテジストの役割と言えるでしょう。こうしたデータ利活用の第一歩として、小西氏のチームが開催しているのが「AIワークショップ」です。後編では、「AIワークショップ」の詳細、活用事例について掘り下げていきます。
データを利活用する前に、ビジネスを通して何を実現したいかというビジョンが大事です。小西氏の役割は、データサイエンティストとビジネス部門をつなげることであり、データを使ってどんなことができるかを伝えるエバンジェリストでありたい、といいます。そんな小西氏が携わる「AIワークショップ」にご興味のある方はもちろん、AI・機械学習に関する最新の知見や活用法について知りたい方は、CONTACTよりお気軽にお問い合わせください。