日常業務において「調査データをすぐに参照したいが誰に聞いたらいい?」「広告効果を確認するためには担当者に連絡を……」と些細なプロセスが業務を圧迫していたり、必要な情報がスムーズに活用できないストレスを感じたりすることもあるかと思います。
DXやデータドリブン経営の重要性が叫ばれる昨今、関連ワードとして「データ民主化」という言葉を耳にするようになった方も多いのではないでしょうか。これまでビッグデータの分析・活用を行うのは、データアナリストやデータサイエンティストなど一部の専門家に限られていました。しかし今、誰もが必要な時にデータを利活用できるデータ民主化が求められています。そこで今回は、「これからの時代、データ民主化は事業成長の必須条件か?」という問いを持ち、データ民主化によって得られる成果と実現に向けての課題を整理。企業がデータ民主化を成功に導くための道筋を描きます。
激変するビジネス環境に即応するために、「データ民主化」がなぜ必要なのか
顧客行動の多様化、現場業務の複雑化、製品ライフサイクルの短縮化……。近年、ビジネス環境は目まぐるしく変化しています。こうした中、必要性が高まっているのが、データに基づいて経営戦略を構築する「データドリブン経営」です。経験や勘に基づく従来型の意思決定に頼ることなく、収集したビッグデータをいかに分析・活用して経営に役立てるか。激動の現代においてはデータに裏打ちされた経営戦略が、企業の競争力を大きく左右する要因の1つになります。
データドリブン経営において、欠かせないのが「データ民主化」です。データ民主化とは、「企業活動において、誰もがデータを主体的かつ自律的に使える状態を実現すること」。これまで企業が収集したビッグデータは、データサイエンティストなど一部の専門家のみが扱っていました。しかし、それでは迅速かつ精度の高い意思決定を行い、急激に変化するビジネス環境に即応することはできません。専門知識を持たない社員でも、それぞれの現場において自由にデータを扱える基盤を構築することは、急務と言えるでしょう。
せっかく企業がデータを蓄積しても、社員が必要なときにアクセスできなければ宝の持ち腐れになってしまいます。例えば、マーケティング部門なら「商品投下のタイミングを計るために顧客行動の分析データが欲しいのに、自部門からは希望のデータにアクセスできない」、経営層なら「経営における重要な判断を今すぐ検討したいのに、必要なデータの準備に時間がかかる」といったデータに関する困り事が頻発していないでしょうか。こうした問題を解決するためにも、組織内で多くの社員が容易にデータを取り扱えるようにするデータ民主化が必要なのです。
とはいえ、データ民主化を達成できている企業はごくわずかかもしれません。大半の企業では、データ活用を推進しつつも民主化までは至っていないのではないでしょうか。データ民主化を目指すべきゴールとした場合、現在その前段階にいるという企業が多いでしょう。少数のデータサイエンティストが自社データを管理し、限られた目的のために利用している状態か、あるいはデータドリブン経営自体に着手していない状態か、どちらかではないでしょうか。
データ民主化を実現できれば、データサイエンティストを含めた全社員が、日々の業務でデータをフル活用できるようになります。必要なインフラさえ整備できれば、専門知識を持たなくても、全社員がデータを最大限に活用した意思決定を遂行できるようになるのです。実際に、Google社のような海外の先進企業のほか、日本のITベンチャー企業でもこうした体制を整えつつあります。
BI(ビジネスインテリジェンス)によって、仕事はこう進化する

では、データ民主化を実現する体制には何が必要なのでしょうか。データ民主化には、さまざまな手法やツールが用いられますが、その中核を担うのが「BI(ビジネスインテリジェンス)」ツールです。多くの企業では、顧客情報を管理するCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理システム)や、営業活動を支援するSFA(Sales Force Automation:営業支援システム)、顧客開拓を管理するMA(Marketing Automation:マーケティング活動支援システム)などによって、膨大なデータを収集・蓄積しています。BIツールは、こうしたビッグデータを統合・集計・分析し、経営戦略の意思決定をサポートするシステムです。
BIツール導入のメリットは、さまざまな場所に散在するデータを簡単に検索・アクセスできるようになることや、データの分析結果を誰が見ても分かるように可視化・ビジュアル化すること。その結果、次のような状態を実現することができます。
1.全社的なデータ統合によるデータドリブン経営
BIツールにより社内のデータを一元化し、部署を横断して共有できます。データ活用に関して全社員の理解が促進し、全社を挙げてのデータドリブン経営が可能になります。
2.意思決定スピードの向上
誰もがデータにアクセスし、理解できる環境をつくることで、専門家の分析を待たずとも迅速に意思決定ができます。目まぐるしい環境変化の中でも確度の高い分析結果を得て、即応性が高いチームを編成することができるでしょう。
3.ニーズを先取りした製品・サービスの提供
顧客情報を一元管理・分析することで、市場の潜在的な可能性をいち早く発見することができます。こうした分析情報を基に、顧客のニーズを先取りした製品・サービスをリリースすれば、企業としての競争力も高まります。
データ民主化成功のカギは、「ガバナンス」「社員の育成」「現場のニーズ」
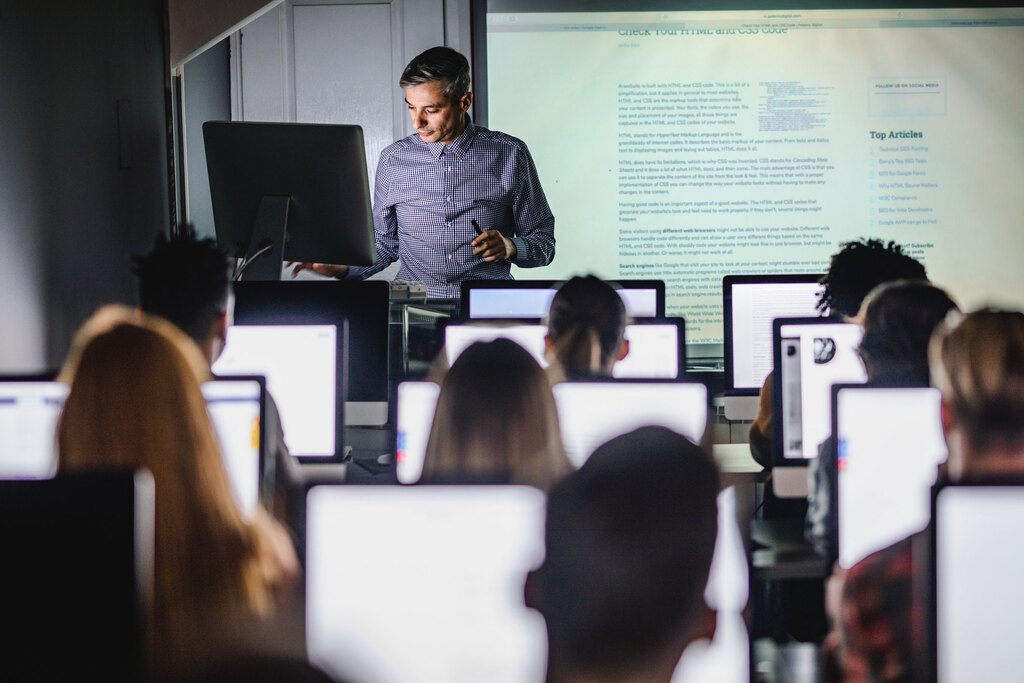
ここまでデータ民主化によって得られる成果を見てきましたが、いざ着手するにあたって、陥りやすい失敗についても見ておく必要があるでしょう。データ民主化には、誰もがデータにアクセスできる環境の整備が欠かせません。しかしながら、BIツールを導入して組織に蓄積されたデータを社員に開示しただけで、データ民主化を実現できるわけではないのです。では、どのような点に配慮すれば良いのか。よくある3つの失敗例から、データ民主化とBIの課題について学んでいきましょう。
失敗例1:ガバナンスが不十分なため、現場の使い勝手を考慮できていない
データ民主化を阻む理由の1つに、不十分なガバナンス体制が挙げられます。データを適切に統制管理できていなければ、データの取得元が分からない、データ形式が統一されていない、データの検索性が低く必要なデータが見つからないといった問題が発生します。データ活用に対して全社を横断した意識統一をするとともに、各部門のニーズや課題に即したデータガバナンス基盤を設計することが必要です。
→[クリアしたい課題]データ活用に対する全社を横断した意識統一/部門ごとのニーズ・課題の設定と環境整備
失敗例2:データを扱う社員のスキルやリテラシーが不足している
誰もがデータにアクセスできる環境を構築しても、データを読み解き、分析・活用できなければビジネスに役立てることができません。専門家レベルの知識を持つ必要はありませんが、データ民主化にはデータを適正に扱うための最低限のスキルやリテラシーが不可欠です。そのため、社員の教育・育成も重要課題の1つです。
→[クリアしたい課題]社員の教育・育成
失敗例3:データの公開範囲が限定的で、現場のニーズに合わせた有用なデータを利活用できない
データには機密情報などが含まれるため、アクセス権を限定することもあります。しかし、データは単体で活用するより、複数を掛け合わせることで大きな価値が生まれるものです。公開範囲を厳しく限定し過ぎると、データを十分に利活用できない可能性があります。職位や職責に応じてデータアクセス権を適切に設定するとともに、フレキシブルに運用することが重要です。
→[クリアしたい課題]職位や職責に応じた、データアクセス権の設定
さらに最近では、データ民主化による成果をいっそう高めるものとして、BIとAIを掛け合わせたツールも登場しています。AIによって提示された消費者インサイトと未来予測をBIがビジュアル化すれば、CRM活用はもとより、データ民主化という観点でも大きな効果が得られ、企業・ビジネスの成長加速にもつながるでしょう。
また、AIは、人間に代わって膨大なデータを処理・分析できる上、データから何らかのパターンを見つけることが得意。データの分析結果から、どのような意思決定をすべきかサジェストすることもできます。近い将来、重要度の低い判断はAIに委ね、高度な意思決定はBIの分析結果を基に人間が行うといった使い分けが進んでいくかもしれません。そうなると、人間による高度な意思決定のスピードが速くなり、企業の事業成長もより速く大きくなることが期待できるでしょう。
全社員がデータを扱えるようにするデータ民主化は、企業のこれからの事業成長に欠かせないテーマと言えます。データガバナンスの確立、データリテラシーの向上、現場のニーズをくんだデータの運用といった課題をクリアすることで、DX、データドリブン経営を大きく加速させることができるのではないでしょうか。スピーディーな意思決定を実現するための手段として、企業のDX化においては、データ民主化も同時に推進すると効果的かもしれません。











