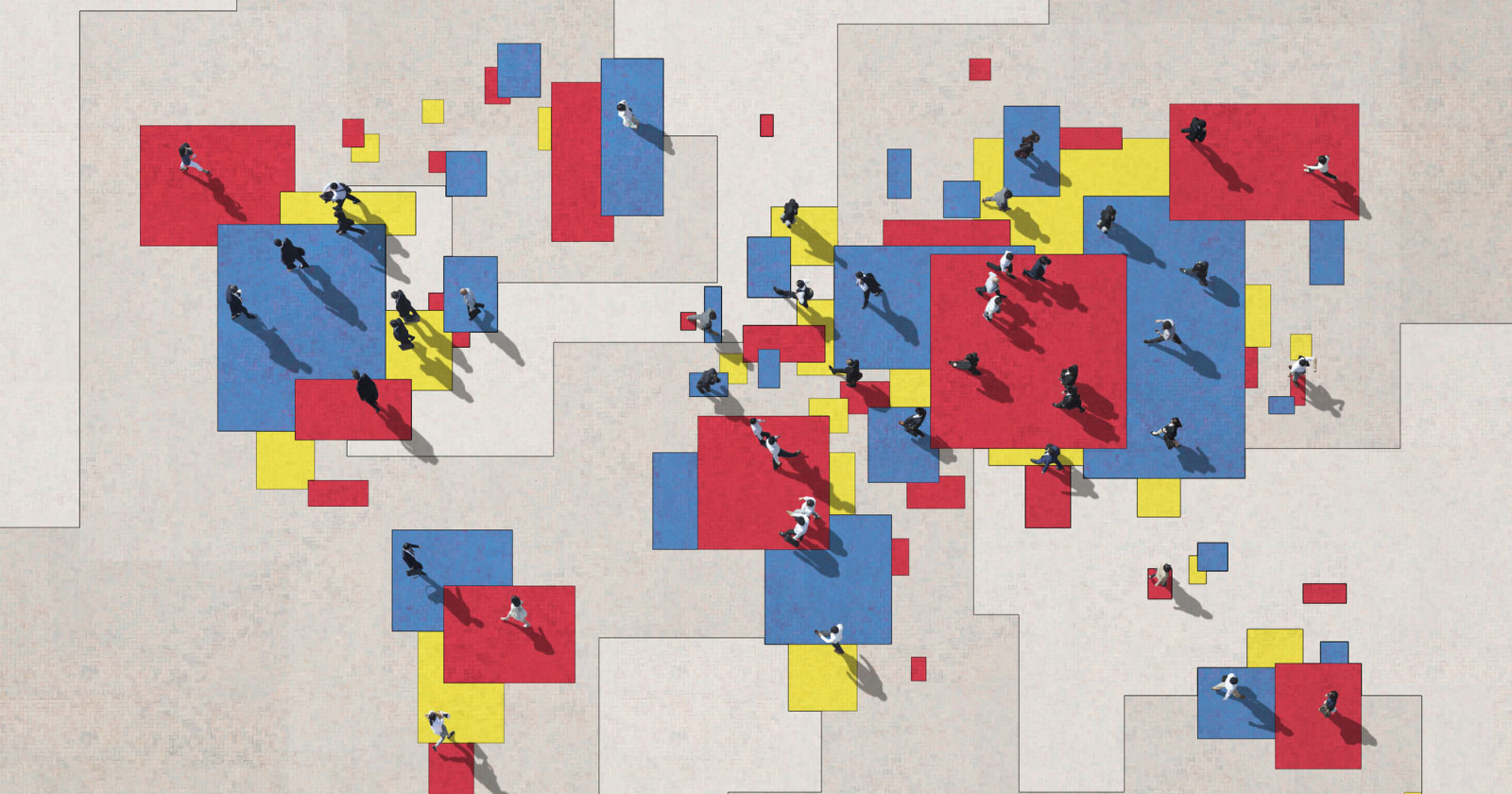コロナ禍やスマートフォン利用者の増加もあり、近年、EC市場が活性化しています。とはいえ競争が激化した分、そこで勝ち抜いたり、新規参入したりすることは難しいと感じている事業者の声を聞くことも少なくないのではないしょうか。そんなECへの参入障壁をぐっと下げてくれるサービスの1つが複雑なEC業務を一括で請け負う「フルフィルメントサービス」です。ここでは、「EC市場の活性化を支えるフルフィルメントサービスは、ビジネス活性化のきっかけになり得るか?」という観点から、フルフィルメントサービスの価値や、活用する意義について掘り下げます。
受注からアフターフォローまで、フルフィルメントサービスはECをシームレスにサポート
Amazonがハイテクを駆使した実店舗「Amazon Style」を2022年後半にオープンさせることを発表し、話題になりました。陳列された服のQRコードをスマートフォンのアプリで読み取ることでサイズや色の確認ができ、決済ボタンを押せば購入完了。試着したい場合は、ボタンをタップすれば、その服が数分で試着室に届けられます。試着室の中では壁のタッチパネルを使って追加の買い物をすることも可能。もちろんECサイトとも連携しており、インターネットで注文した商品を店舗に送り、試着することもできるようになるといいます。
このような今までにない買い物体験には、Amazonの物流拠点「フルフィルメントセンター」の技術が生かされています。フルフィルメントとは、通販やECにおいて商品の在庫管理から注文受付、梱包、発送、受け渡し、クレーム対応やアフターフォローまでを含めた一連の流れのこと。Amazonでは自社の事業のために最先端のテクノロジーを活用して構築してきたフルフィルメントの仕組みを、他の企業にもサービスとして提供しています。こうした受注からアフターフォローまでの一連の作業を請け負い、ECをシームレスにサポートするサービスがフルフィルメントサービスです。日本の企業でも同じように、大手運送会社や大手EC企業が、自社で培ってきたノウハウや技術を結集した、さまざまなフルフィルメントサービスを提供しています。
フルフィルメントサービスは、ワンストップのサービスで顧客満足度の向上に貢献

EC市場が活発化する中で登場した、フルフィルメントサービス。では今、注目されるようになったのはなぜでしょうか。ここからはその背景や、従来の物流業務アウトソーシングとの違いを解説します。
近年、EC市場の拡大とともに、新規参入を考えている事業者は多いようです。とはいえ、自社で倉庫やコールセンターを用意し、システムを組んで自前でEC事業を始めるのはハードルが高いのも事実。最近は決算手法が多様化し、決済処理や管理が非常に煩雑になっています。インターネット通販が定着したことで顧客の要望も高まっており、問い合わせや返品の要望、さまざまなご意見にも丁寧に対応しなくてはなりません。そのため、EC業務の全てを自社で行うとなると、大きなコストと人材が必要になります。さらには競争の激化とともに、EC事業者はより付加価値が高い商品を開発した上で、コストは削減し、同時に顧客満足度を高めていく必要があります。このような課題を解決するものとして注目され、活用が広がってきたのがフルフィルメントサービスなのです。
ちなみに、フルフィルメントサービスが登場する以前から、物流業務をアウトソーシングする「3PL」(Third Party Logistics)というサービスがありました。さらに、最近は3PLにロジスティック策定の企画などのコンサルティング要素を加えた「4PL」(Forth Party Logistics)という言葉も使われるようになっています。ただし、基本的に3PLや4PLは、物流に特化したサービス。一方、フルフィルメントサービスは、物流業務だけでなく受注や梱包、決済、顧客対応まで、ECにまつわるバックヤード業務をワンストップで対応するサービスです。極端に言えば、フルフィルメントサービスを活用すると、事業者は商品さえ用意すればすぐにECビジネスを始めることができるというわけです。すでに何らかの商品を製造したり販売したりしている企業であれば、わずかな初期投資でビジネスを拡大することも可能です。
さらにフルフィルメントサービスの活用は、EC業務の人的負担やミスを減らし、顧客満足度を上げることにもつながります。煩雑な決済処理や問い合わせ、返品対応やクレーム対応など、会社の信用に大きく関わる業務を、それぞれのノウハウを蓄積したプロに託すことができるからです。
加えて、例えばAmazonのフルフィルメントサービスでは、最先端のテクノロジーによって極限まで最適化、効率化を追求しており、スケールメリットによる物流コストの削減も行われていますから、自社で倉庫やコールセンターを持つよりも、低コストでEC事業を始められるでしょう。このように、今までECに取り組んでこなかった企業や、EC業務に慣れていない企業、資金力に不安のある企業もEC事業に参入しやすくなったのです。
つまり、ECへの新規参入を考える企業が増えたことや、ECにまつわる業務の複雑化などがフルフィルメントサービスに注目が集まる要因になったと考えられます。フルフィルメントサービスを利用することによって、より効率的に、品質の高いサービスを提供し、顧客満足度を高めていくことも可能になるでしょう。
煩雑な業務を一括アウトソースすることで、自社のコアバリューに専念できる

ここまで紹介してきたフルフィルメントサービスの価値は、煩雑な業務を一括で外部に委託できることによって生まれています。バックヤード業務を徹底的に効率化できれば、自社のリソースを、より付加価値の高い製品の開発や顧客満足度の向上など、自分たちにしかできないコアバリューに集中させることもできるでしょう。
フルフィルメントサービスに見られるような「徹底した効率化」や「一括管理によるワンストップ化」の流れは、EC業界に限らずあらゆる分野で起きています。ビジネスにおいてはマーケティングやセキュリティー関連でもさまざまな業務を1社で全て請け負うサービスが登場。一般消費者向けでは、引っ越し関係の手続きなどをワンストップで行うサービスなどが広がっています。さらには、かつては役所に行って、1つひとつ申請書などを提出しなければいけなかった行政手続きなども、デジタルを活用したワンストップ化が進みつつあります。「複雑なものをひとまとめにして効率的に行いたい」というニーズは、今後も大きなトレンドであり続けるでしょう。
このような時代の流れとともに期待が集まっているフルフィルメントサービスですが、もちろんデメリットもあります。例えば、受発注からアフターフォローまで一連の業務を全て外注することで、顧客との直接の接点が減ってしまうことです。クレーム対応やカスタマーサポートは顧客の生の声を聞き、関係性を深めるという点で非常に重要です。それができないのは、事業を成長させる上で弊害となる可能性があります。
しかし、こうしたデメリットも、工夫次第で解消することはできます。SNSやWebサイトのアンケート機能を活用し、顧客の声を吸い上げる。あるいは、ライブコマースやイベントなどを組み合わせた新たな顧客とのコミュニケーションを図るなど、今までとは異なる方法で新たな接点を持つことはできるでしょう。フルフィルメントサービスを利用しつつ、重要な顧客対応のみは自社で行うという方法もあります。
また、フルフィルメントサービスの利用には、それなりの利用料が発生することや、社内にバックヤード業務のノウハウが蓄積されないことなども、デメリットになり得ます。ですから導入にあたっては、自社で力をかけるべきところと効率化すべきところを見極め、将来的にEC事業をどのような規模やスタンスで展開していくのか、しっかり検討しておく必要があります。
他方、経営戦略という観点から考えると、ECビジネスにおける「守り」であるバックヤード業務をフルフィルメントサービスに託すことで、安心して「攻め」の業務に自社のリソースを割くことができると捉えることもできます。自社リソースを、顧客を引きつける商品企画や、広告戦略、顧客とのコミュニケーションなどに専念させる。つまり、経営の「核」となる領域に注力し、自社のコアバリューを磨くことで、さらなる事業成長を目指していくのです。それこそがフルフィルメントサービスの有効な活用法であり、大きな意義と言えるでしょう。
EC参入への障壁を下げてくれるフルフィルメントサービスですが、導入にあたっては、力をかけるべきところと効率化すべきところを見極めて検討することが必要です。そうすることで、より効果的な導入方法が見えてくるはずです。さらには、複雑な業務を一括管理し効率化を図るアウトソースサービスの導入は、特定業務の効率化にとどまらず、事業自体を活性化させ、自社が成長するきっかけにもなるでしょう。