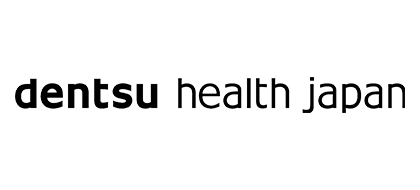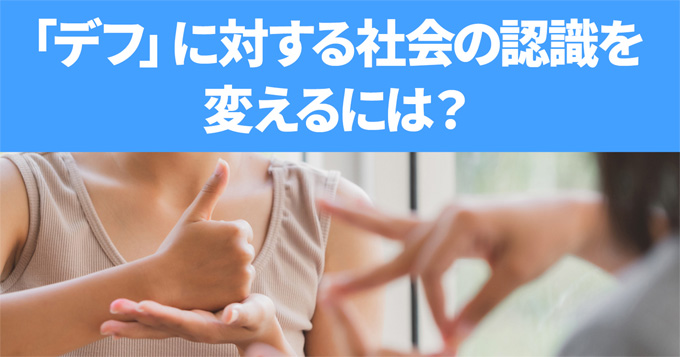2023年4月6日、株式会社 電通の専門組織「電通ダイバーシティ・ラボ」と、株式会社電通メディカルコミュニケーションズが協同でサービス提供を発表した「GAP MIKKE(ギャップミッケ)」。これは、主に発達障害と診断された子どもとその保護者の視点の違い(=ギャップ)を可視化するためのツールです。
第1弾の記事では、「GAP MIKKE」が具体的にどんなツールなのか、また、ツール開発の裏側やその思いなどを開発プロジェクトメンバーにインタビューしてお届けしました。第2弾となる本記事では、株式会社電通メディカルコミュニケーションズ代表取締役社長の林剛氏、電通ダイバーシティ・ラボの代表を務める林孝裕氏、プロジェクトメンバーの高橋大氏、クリエーティブを担当した和田佳菜子氏に、発達障害という領域に着目した理由や、チームメンバーが社会に果たしていくべき役割をどう考えているかなど、より深く話を聞いていきます。
コミュニケーションを通して、患者に寄り添う医療へ

Q.「GAP MIKKE」は、電通ダイバーシティ・ラボと、電通メディカルコミュニケーションズがタッグを組んで開発したツールです。なぜ電通メディカルコミュニケーションズがこのプロジェクトに参画することになったのか、その背景を伺えますか?
また、医療では、「EBM(Evidence-Based Medicine)」といって、科学的な根拠に基づいて、患者さんに最も適した医療を提供することが重要でした。しかし最近では「NBM(Narrative-Based Medicine)」の考え方も加わる傾向にあります。NBMとは病を薬で治すだけでなく、患者さん1人ひとりの「ナラティブ=物語」に寄り添いながら、その人の人生をより良くしていくことに軸足を置く考え方です。
これはすなわち、電通グループが得意なコミュニケーション領域とも言えます。そのような中、今回「GAP MIKKE」で発達障害のお子さんだけでなく、ご家族を含めた周辺の方々との意識や考えの違いを見える化することは非常に意義深いと感じ、またそれらの考えの違いを理解するための施策は電通メディカルの強みを生かせるとも思い、参画することとしました。
Q.「発達障害」というテーマに関してはどのように思われたのでしょうか?
そのような状況に対して「GAP MIKKE」を用いることで、発達障害の方々の特性をより良く理解し、社会に広め、発達障害のご本人だけでなく、周辺の方々が理解でき、さらに生きやすい社会を作る一助になるのではないかと思いました。当社は専門知識を生かし正しい情報を分かりやすく伝えるノウハウを持っているので、この領域に参画する意義は大きいと感じています。
課題を「見える化」することから、社会との溝を埋めていく

Q.電通ダイバーシティ・ラボとして、発達障害に着目してサービスを展開しようと考えたのには、どのような背景があるのでしょうか?
発達障害はいわゆる疾患とは異なり、治療そのものもそうですが、それ以上に社会への適合、生活や仕事における他者との溝を埋めることなどが大きな課題となります。われわれが課題の全てを解決できるわけではありませんが、周囲との関係性をどう考えていくかということを前提として、さまざまな企業や自治体、広くは社会全体に課題を共有していくことで何か寄与できるのではないかと考えました。

当事者のQOLを上げるためには、社会的な変革が必要
Q.社会に課題を共有していくというところが、大きな特徴なのだなと感じましたが、どのようなゴールを目指しているのでしょうか?
われわれは発達障害を社会モデル化していくことに意義があると考えています。それはつまり「その人たちだけの課題にしない」ということです。当事者やその周辺の人たちが抱える困り事に対して、例えば子どもの勉強のことであれば、ステーショナリーメーカーができること、家での生活のことであれば生活商材を扱っているメーカーや商社ができることは何だろうと、生活を取り巻く全ての企業や団体や組織などが、解決に役立つ価値提供を考えて実践していければ、社会的な動きになって、社会全体で当事者のQOLを上げることができるのではないでしょうか。
参画障壁を良い意味で下げることが社会モデル化には必要で、われわれがその入り口を設計することによって、それが加速するといいなと思うのです。

発達障害は、その特性上、地域社会による理解と、医療や福祉を超えた、さまざまなサービスや商品の重要度が高いもの。そして、それが整った社会モデルをつくることが当事者の生活の質を上げるカギになりそうです。後編ではさらに、発達障害の現在地や「GAP MIKKE」のチームメンバーが社会に果たす役割について掘り下げていきます。
新しい社会モデル構築のため、自社にできることを探している担当者の方。「社会の困りごと」と「自社事業」とがどうつながるのか、どんな可能性があるのか、一緒に考えてみませんか。CONTACTからのお問い合わせをお待ちしています。