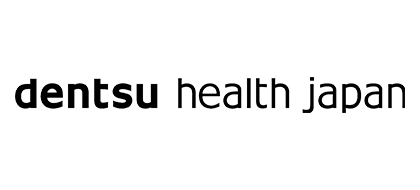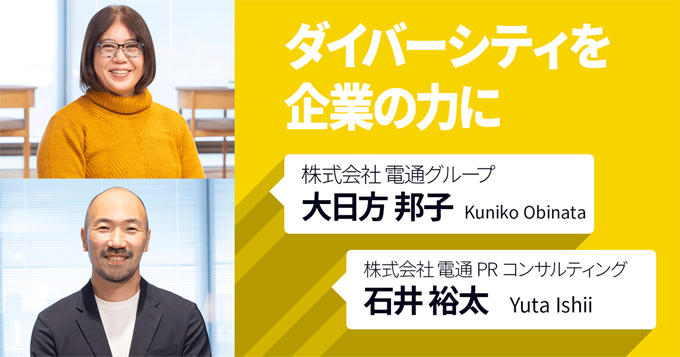株式会社 電通 で「多様性」に関する課題に取り組む専門組織「電通ダイバーシティ・ラボ 」と、株式会社電通メディカルコミュニケーションズ は、2023年4月6日に課題発見支援ツール「GAP MIKKE (ギャップミッケ)」を共同開発したことを発表しました。
これは、発達障害の診断を受けた子どもの保護者や、子どもの発達が気になる保護者を対象に実施した調査結果をもとに、子どもとその保護者の視点の違い(=ギャップ)を可視化したツールで、社会全体が発達障害への理解を深めること、また、発達障害の特性を起点に課題発見やソリューション開発を促すことを支援するものです。
今回は、電通ダイバーシティ・ラボの代表を務める林孝裕氏、「GAP MIKKE」のクリエーティブを担当した和田佳菜子氏、同プロジェクトのリーダーである海東彩加氏、そして株式会社電通メディカルコミュニケーションズの川村章子氏に、開発の目的や過程、今後の展開などについてインタビュー。「GAP MIKKE」が社会に対して果たす役割とは何なのか、話を聞きました。
発達障害と診断された人は全国に48万人以上。当事者と、周囲の人との視点の違いを可視化 Q.「GAP MIKKE」とはどのようなツールなのか、あらためて教えていただけますでしょうか。
川村: 2016年に厚生労働省が行った「生活のしづらさなどに関する調査」によると、発達障害の診断を受けた人は国内に48.1万人いるといわれています。発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達の仕方に偏りがあることで起こる障害で、言語や行動、情緒などに特性が認められるものです。発達障害には大きく3つのタイプがあります。1つはASD(自閉スペクトラム症)で、こだわりが強い、コミュニケーションや対人関係が苦手、といった特性があります。2つ目がADHD(注意欠如・多動症)。じっとしていることや待つことが苦手、集中できない、気が散りやすいなどの特性があります。3つ目がLD(学習障害)で、読み書きや計算などが苦手といった特性が見受けられます。
株式会社電通メディカルコミュニケーションズ 川村 章子氏 林: 「GAP MIKKE」という名の通り、「ギャップを可視化する」ことを目的としているので、まず子どもの発達状態が気になると感じているご家族にアンケートやヒアリングを実施しました。当初、われわれは「発達障害の困り事を可視化しよう」というコンセプトでプロジェクトを進めようとしていましたが、多くのご家族にアンケートやヒアリングを重ねる中で、絶対的に困り事と言えるものばかりではないこと、親にとっては困り事でも子どもにとって同様とは限らないことが分かってきました。1つの事象に対して、それぞれの視点で見え方が違う。それをギャップと捉えて視覚的に見せていくことが、さまざまな理解を促進するのではないかという気付きがあり、そのツールを開発する取り組みへと進化していきました。
株式会社 電通 林 孝裕氏 和田: 私自身も子育てをしているのですが、発達の特性がある・ないにかかわらず、どうしても大人の視点から物事を見てしまい、子ども側の視点は見落とされがちだと感じています。ですから、1方向からの視点だけでなく、双方向での視点で可視化するということに大きな意味を感じているところです。
海東: 子どもと保護者の間での感じ方や捉え方、考え方の違い(=ギャップ)が、「おうち」の中のさまざまな場面に存在することが見えてきたので、リビング・寝室・お風呂など部屋ごとのシチュエーションに分けて、発達に特性のある子どもと、その保護者との視点のギャップを可視化しました。視覚的に理解しやすい「マップ」と「カード」に落とし込んで完成したツールが、「おうち育児 GAP MIKKE」です。
見落とされがちな子どもの視点も含めて、フラットなビジュアルに落とし込む Q.発達に特性のある子どもとその保護者の間にあるギャップとは、具体的にはどのようなことがあるのでしょうか?
海東: 例えば、「何度言っても散らかしっ放し。片付けてくれない」というのが保護者視点ですが、それに対して子どもは「どこに何があるか自分では分かっているから、片付けなくてもいい」と感じている。ここにギャップがありますね。あるいは、「食事に集中しない。ご飯もたくさんこぼれて大変」という保護者視点に対しては、「おもちゃやゲームをやりながら、好きに食べたい」という子ども視点が存在します。その双方の視点をどちらも大事にしてビジュアル化したいという思いがありました。
株式会社 電通 海東 彩加氏 Q.家の中で起こるいろいろな事象に対して、実は同じ事象でも子どもと保護者ではこんなに捉え方や考え方が違って、それが行動につながっているんですよ、といったことを見せていくのですね。その際、デザイン表現はどのように考えましたか?
和田: 林さんがお話ししたように、当初は「困り事」を可視化するつもりでしたが、調査を経て、家庭に存在するのは「困り事」というよりも、保護者側と子ども側の視点の「ギャップ」だと分かりました。そこで、クリエーティブのディレクションにあたっては、ネガティブな表現にならないよう、あくまでフラットに、子ども側の視点が持つ豊かな発想も感じられるようなデザインにしようと考えました。
「おうち育児 GAP MIKKE」デザイン(マップ&カード) 和田: 必ずしもカードに書かれた特性が、全ての発達障害と診断された子どもに当てはまるわけではなく、それぞれに特性が違います。ですから、このツールは「診断につなげるためのものではない」んです。そこが大事なところで、同じお風呂場のシチュエーションでも人によってはビジョンが違っていて、そうした余白を持たせているところが、このツールを広く活用してもらうための重要なポイントだと思っています。
株式会社 電通 和田 佳菜子氏 ギャップがあるのは悪いことではなく、尊重し合うことが大切 Q.「GAP MIKKE」をこんな風に使ってほしい、こんなシーンで役立ててほしいなど、どのような利用を想定しているのでしょうか?
川村: 発達障害という言葉は、最近よく耳にするようにはなったものの、まだまだ正しく理解している人は少ない状況だと感じます。発達障害は周囲の方の正しい理解と適切なサポートが重要です。まずは知ってもらうこと、そこで起こっていることの背景に存在する意識のギャップに気付いてもらうこと。「GAP MIKKE」はそんな役割を果たすことが大事かと思っています。
海東: 具体的には、企業向けにGAP MIKKEを活用したワークショップを実施することで、発達障害の特性の理解に役立て、さらには課題解決につながるソリューションを一緒に生み出していくといったことを想定しています。
和田: 今回、発達に特性のあるお子さんがいる保護者にインタビューをした際、ほとんどの方が何かしらの悩みを抱えていたんです。そうした悩みを親子間だけで抱え込まず、社会全体で考えて解決していこう、という形にできたらベストですよね。
林: 今回は「おうち育児」というテーマで制作しましたが、発達障害がある就労者とその周囲の人など、親子に限らず2者間での視点のギャップを可視化してほしいといった要望もいただいています。さまざまな立場や環境における、相互理解に生かしていきたいと考えています。
和田: ギャップを解消することができれば、それはもちろんベストで理想的だとは思いますが、開発チームの中でいつも話しているのは、「ギャップがあること自体は悪ではない」ということ。ギャップを埋めたり縮めたりすることだけを目的にせず、ギャップがあったままでも、お互いがお互いの視点に立つこと、尊重することで関係性に変化が生まれたらいいなと思います。
海東: さらに、このツールを活用することで、多くの人にとって役立つソリューションを生み出せる可能性もあると感じています。
発達障害と診断される人が国内だけでも48万人以上いるとされる中でも、特性が理解されていない現状があります。だからこそ、その現状に着目し、さらには双方向での視点のギャップを描いた「GAP MIKKE」は、相互理解を促し、発達障害当事者を含む多くの人がより生きやすい社会をつくる可能性を秘めています。後編では、ツール開発の裏側や今後の展開などについて、さらに詳しく話を聞いていきます。
社内外のダイバーシティ促進に寄与したい、インクルージョンを深めたい……など、企業・組織文化づくりやさまざまな組織改革に関するお悩みをお持ちの方。自社だけで取り組むのではなく、外部の知見や刺激を取り入れながら、多様なパートナーと共に向き合っていくという方法論もあります。CONTACTからお問い合わせください。
https://transformation-showcase.com/articles/345/index.html
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。