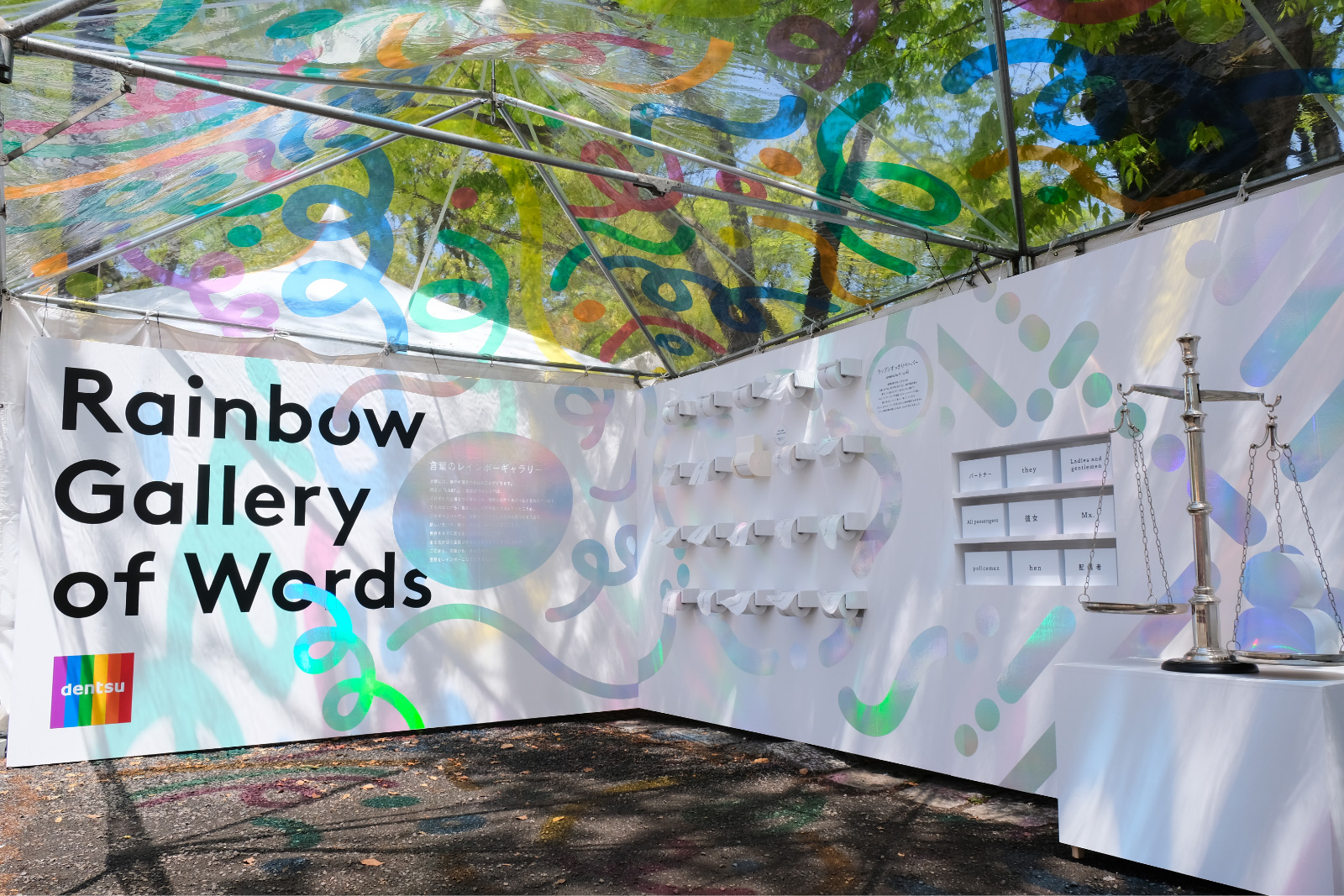国際女性デーである3月8日、株式会社 電通におけるDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)の専門組織「電通ダイバーシティ・ラボ」が、ジェンダー・ギャップ問題の解決に向けた施策の1つとして、アイデア発想を支援するツール「ジェンダー課題チャート」をリリースしました。「ジェンダー・ギャップ指数2021」によると、日本は全156カ国中120位(2021年3月時点)と、G7の中では最下位となり、また、男女間賃金格差ではOECD(経済協力開発機構)に加盟する全38カ国中、ワースト3位(2020年時点)になっています(※1)。まさにジェンダー・ギャップ問題の解決は日本社会が抱える大きな課題の1つと言えます。
そこで今回は、ジェンダー課題チャートをリリースした電通ダイバーシティ・ラボのメンバーである國富友希愛氏と岸本かほり氏にインタビュー。「ジェンダー課題チャート」開発の背景や、効果的な活用方法について聞きました。
「ジェンダー平等」は、企業価値そのものを左右する重要な視点。本記事を参考にしていただきながら、「ジェンダー課題チャート」を活用して、企業の現状認識や今後の取り組みを見直したり、議論したりするきっかけにしていただけると幸いです。
ジェンダー・ギャップ問題を定量的なファクトとともに概観できる、「ジェンダー課題チャート」
Q.今、いかなる企業においても、ジェンダー平等への取り組みは、企業の成長やサステナビリティを支える重要な指針となっていると思います。一方で、「取り組まなければならないことは知っているが、具体的にどのような問題があるのかまでは知らない」「問題認識が漠然としていて、具体的に何をどう変えればいいか分からない」という人もいるでしょう。あるいは、問題を自分ごと化しにくい人もいるかもしれません。そんな中、「ジェンダー課題チャート」を開発した背景には、どのような思いがあったのでしょうか?
岸本:大きくは、3つのポイントがあります。まず1つ目は、近年、企業や自治体などさまざまな方面からジェンダー関連のお問い合わせやご相談が増えてきたことです。電通の中にも知見はあるのですが、それらの情報が一元化されておらず、お問い合わせを受けるたびに担当者がゼロから情報を集めていく状況が続いていました。すると、お問い合わせをいただいても、お答えするのに時間がかかってしまいますし、担当者によってご提供するものの質が変わってしまうということもあります。そういった経緯があり、お問い合わせに対して、すぐにご提供できる「ジェンダー問題のファクトやデータの集積」をまとめることで、迅速な対応が可能となり、多くの方々のお役に立てるのではないかと思い、さまざまなテーマから俯瞰することができるチャートをつくろうという動きになりました。
2つ目は、ジェンダーの問題は、「個人的な思い」と思われがちという点です。例えば、ジェンダー問題の1つに「女性の睡眠時間が短い」というものがあります。仕事と家事の両立に励む女性にはタスクが多く、結果的に睡眠時間が短くなり、健康維持が難しくなっています。しかし、このテーマを聞いたとしても、「一部のハイキャリア層だけなのではないか」「専業主婦は違うのではないか」といったように、個人のライフスタイルの問題で「社会的に解決すべき問題」とは感じない人も多いのではないでしょうか。しかしマクロな視点で見ると、OECDの調査では「日本の女性の平均睡眠時間は、調査国中で最も短い(2021年現在)」というファクトがあるのです(※2)。
また、「街中でハラスメントを受けやすい」という事実もあります。「自分の周りには、そのような経験がある人はほとんどいない」と思っている方もいるかもしれません。しかし、「#WeToo Japan」の調査データからは、「女性の70%が、電車や道路で何らかのハラスメントを経験している」ことが分かりました。こういったことは、たとえ実際に嫌な思いや怖い思いをしていたとしても、他者に共有しにくく、表面化しづらい背景もあり、「社会として向き合うべき問題」として捉えられにくいのです。このように、「定性的に感じられるような問題」について、「定量的なファクト」を重ねることで、これが「女性個人の主観的な問題」ではなく、「日本社会全体が直面している問題である」ということを可視化したい、という思いがありました。
そして3つ目のポイントは、3月8日の「国際女性デー」のタイミングで国内外の企業が女性に関する社会課題について何らかの意思表明をしたり行動をとったりすることが当たり前のトレンドになりつつあるという点です。私たち自身が、企業で働く者として何らかの取り組みを可視化していかなければいけないという課題意識も手伝い、この「ジェンダー課題チャート」をリリースする動きにつながりました。
國富:このジェンダー関連のトピックは、専門家や興味がある方には情報が集まる一方で、全ての人が自信をもってジェンダーについて語り合う、という空気が生じにくい気がします。しかしこれらの問題は、誰もが共通に知っておいてほしいことです。これからのビジネスをリードしていく立場の方は、特に「標準装備」として知っていなければいけないことでもあるのではと思っています。
女性が直面する問題について積極的に発信する人を、SNSでは「フェミ」と呼んで揶揄するような状況が伺えます。このようにジェンダー関連のトピックは、賛成する人と反対する人の二項対立に陥りやすい構造になってしまっています。しかし、客観的にファクトで確認すると、問題に対する印象や意見が変わったり、二項対立で終わらない対話が生まれたりするかもしれません。ジェンダー問題を、二項対立や分断で捉えない方法を模索したいと思っています。
他者になって考えることで、問題解決の扉が開く

Q.この「ジェンダー課題チャート」ですが、どんな人にどう使ってほしいと思っていますか?
岸本:まずは一度目を通してほしいのですが、女性も女性以外の人も、いろいろな状況に置かれた女性の存在を認識してほしいと思っています。
ひとくちに「女性」といってもいろいろな方がいますよね。結婚している人もいれば、していない人もいる。子どもがいる人、いない人、働いている人、そうでない人。それぞれの状況・立場によって見えている世界が全く違います。女性だからと一括りにするのではなく、さまざまな状況・立場の女性が存在することを理解し、できる限りそれぞれの視点から見える世界を知ってもらえるといいと思います。
セカンドステップとして、その女性が直面する問題を抽出し、そこに対してどういったソリューションがあるのかを考えてみていただきたいです。この「ジェンダー課題チャート」は、あらゆるジェンダー問題を一目で俯瞰できるのが特徴です。なぜなら、ジェンダーの問題は、ひとつひとつが独立して起こっているわけではなく、いろいろな問題が複雑に絡み合っているケースが多いからです。何か1つの問題だけを見て、それを商品やサービスで解決する、というのは少し短絡的なのではないかと思います。もっと女性の人生を点ではなく面として見て、その中でどういう問題に直面しているのかを実感していただき、解決策を考えるということができれば長期的な視点にはなりますが、より本質的な問題の解決につながるのではないかと思っています。
國富:多面的に考え現状を知れば、行動も変わり、ジェンダー平等に近づくことができるかもしれません。「ジェンダー課題チャート」のあるテーマを対話することで、変化のきっかけになれば幸いです。
例えば「日本は子宮頸がんなどを予防するワクチン(HPVワクチン)の接種率が低い」という問題があります。あまり知られていないかもしれませんが、厚生労働省の調査によると、日本におけるHPVワクチン接種率はなんと1.9%(2019年度、3回接種した人の割合)に過ぎません。では、なぜ日本はこんなに低いのか。そこから、いろいろな対話が始まってほしいと思っています。
「問題を自分ごと化しにくい方にこそ、読んで考えてほしい」と思うのは、企業のマネージャークラスの人たちが、いろいろな悩みを抱えていることも聞こえてくるからです。男性のマネジメント層が、部下の女性のことが分からなくて悩む、という状況がある場合、これはその個人個人の知識不足の問題だけではなく、男性が上司で、女性が部下であるケースが多いという社会構造と、性教育が浸透していないという問題に起因していると考えています。
きちんと女性の健康についての知識や、リプロダクティブ・ヘルス/ライツを知ることで、マネジメント問題が解決できる可能性があります。女性の妊娠出産や更年期などについて、体調はどうなっていくのか、加齢とともにどのような変化があるのか、企業やマネジメントにどのような対応が求められるか。網羅的に知ることによって、企業内のコミュニケーション問題の解決につながるかもしれません。そして、「興味を持って知る」ことが、自らのマネジメント上の悩みを解決することにつながるかもしれない。そう感じてもらえるといいですね。
女性が直面する問題は、男性が抱えている問題の裏返しでもある
Q.確かに、女性にとっての問題は、同時に「それを知らないことで出口もなく悩んでいる男性の問題」という側面もありますよね。企業内の現状の意思決定者やマネージャーにこそ見てほしい、その通りだなと思いました。
岸本:「ジェンダー」というと、「女性の問題」と捉えられがちです。そうなってしまうと、女性でなければ語ってはいけない、女性でなければ分からない、とされてしまいます。しかし、これは女性だけが直面している問題ではなく、女性のみで解決できるものでもありません。社会全体の問題である以上、女性も女性以外も一緒に興味を持ち、知識を得て考え続けていくべきと考えています。
「誰かが悪い」「誰かが敵だ」というのではなく、みんなが自分ごと化して変えていかなければいけない、と発信し続けたいと思っています。
國富:「女性活躍」という言葉を良く聞きますが、「保育士」や「看護師」、また教職の中でも特に「小学校の教員」は、女性比率が多い職業で「非正規雇用で働く女性」は男性の3倍といわれています。就労の場以外で、家事・育児・介護などの無償の労働をしている人もいます。つまり、ずっと社会で活躍しているのです。
なぜ、「これからは女性活躍を推進しなければいけない」という掛け声が起こっているのでしょうか。今は本当に「女性の活躍が足りない」社会なのだろうか。男性だけが活躍しているように“見えやすい”社会なのではないだろうか。そのようなことをジェンダー課題チャートの制作中に考えていました。
同時に、本当の意味で女性が活躍している実感が得られる社会とはどういうことか、共に考えていきたいと思っています。
岸本:ジェンダーの問題は男性も直面している問題が多くあるでしょうし、そもそも「性別」という捉え方自体が、徐々に時代遅れになりつつあるのかもしれません。それでも「ジェンダー平等」は数ある社会課題の中でも大きなテーマの1つですし、この問題が解決されないことによって苦しんだり窮屈な思いをしたりしている人が多く存在していることも事実です。
「ジェンダー課題チャート」は、1つの「入口」でしかありませんが、このような「入口」が、日本社会全体が前進していくきっかけになればいいな、と思っています。
SDGsやESG投資が広がっている中で、企業内外でジェンダー関連の問題を解決することは、企業が存続し続けるための重要なポイントとなりつつあります。一方で、日本は世界的に見ても、この領域に対する対応が遅れていることは否めません。
ジェンダー関連の問題が生まれている大きな原因の1つは、「それが問題だと認識されていないこと」ではないでしょうか。この「ジェンダー課題チャート」を見ていただければ、「事実として」問題がそこに存在していることが分かります。問題を問題と認識するためには、「感情的に共感する」ことも重要ですが、「客観的な事実として知る」ことも、社会を変える大きな一歩になるのではないでしょうか。
また、今回のインタビューでは、「女性が直面している問題」の裏側には、「男性が直面している問題」もある、という指摘がありました。同時に、「女性」「男性」という2分類そのものに苦しさを感じている人たちがいることも紛れもない事実です。このような問題は、全ての人が興味を持って向き合わない限り、解決への道のりは遠くなってしまいます。「自分ごと化されない」と思っている人こそ、相手の立場を知り、その人になり切って考えてみる。この考え方は、ジェンダー関連の問題に限らず、あらゆる問題解決を実現する上で、重要な考え方と言えるのではないでしょうか。
※1 「ジェンダー・ギャップ指数」「男女間賃金格差」の順位は、記事執筆時(2022年5月時点)までのものです。2022年「ジェンダー・ギャップ指数」のデータは、2022年6月末に、世界経済フォーラムのサイトにて公表される予定です。
※2 出典:OECD「Gender data portal 2021」