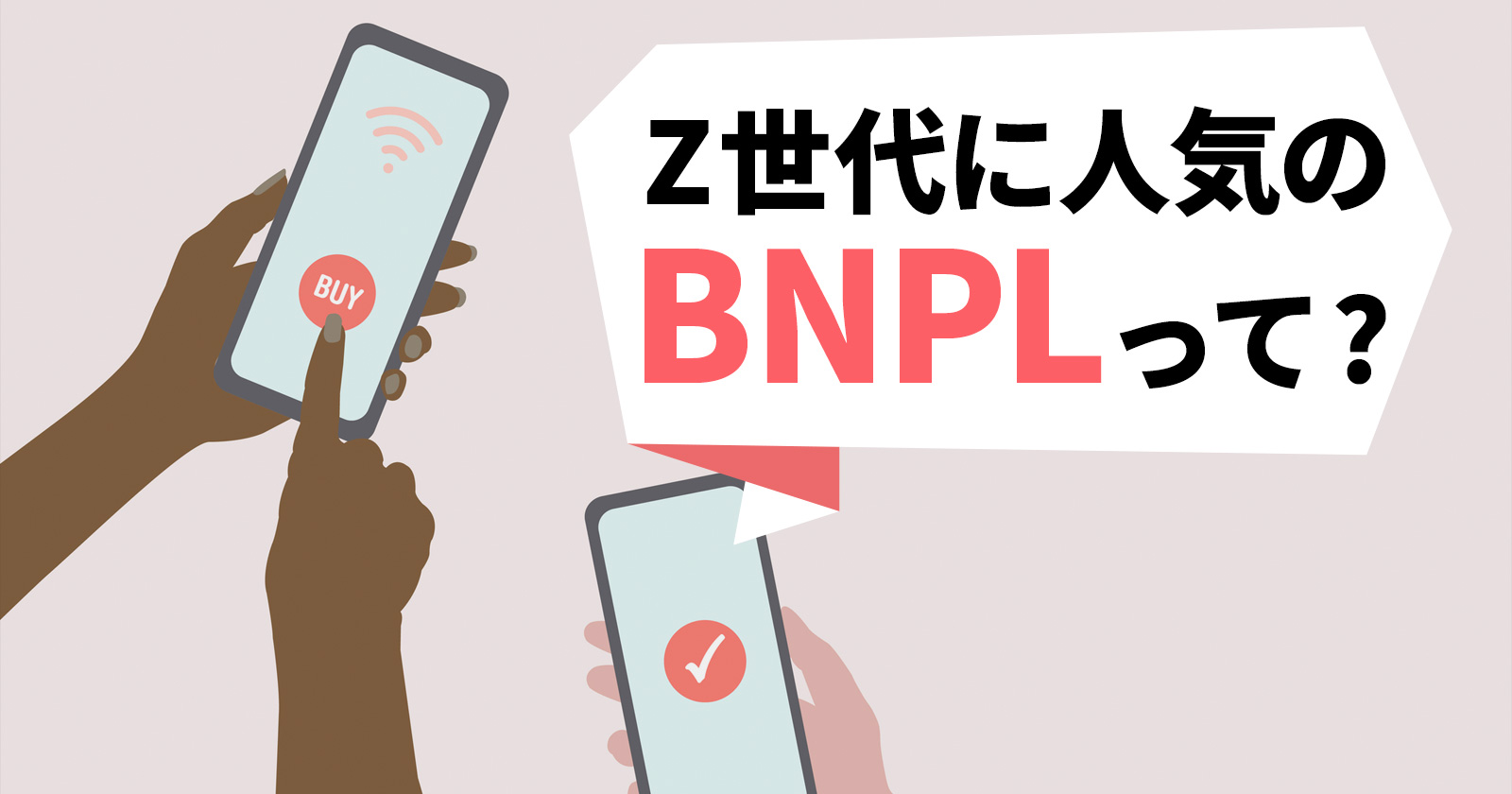いつの時代も、若い世代の意識や行動を把握することは非常に重要です。特にZ世代/ミレニアル世代(2022年現在、10代後半〜30代前半頃)と呼ばれる若い世代は、生まれた時からインターネットサービスに日常的に触れてきた「デジタルネイティブ世代」と呼ばれ、たびたび、それ以前の世代とは大きく異なった傾向があると指摘されています。
そんな中、株式会社電通デジタルは、「デジタルネイティブ世代の消費・価値観調査 '21」を実施・発表しました。調査結果は既出の記事で掲載しましたが、今回は、この調査結果やその分析にさらに一歩踏み込むべく、調査を実施した同社の松崎裕太氏と安部茜氏に話を聞きました。前編、後編の2回にわたってお届けします。若い世代にアプローチしたいと考えるマーケターやプランナーには、ヒントの多い内容となっているのではないでしょうか。
コロナ禍により変化が見えてきた、デジタルネイティブ世代の購買行動
Q.まずはあらためて、「デジタルネイティブ世代の消費・価値観調査 '21」の実施目的について教えてください。
松崎:私たちは電通デジタル内のデジタルネイティブ特化型マーケティング専門チーム「YNGpot. ™️(ヤングポット)」のメンバーです。このチーム自体がデジタルネイティブ世代だけで構成されており、デジタルネイティブ世代のインサイトや情報取得・購買行動・ビジネストレンドに立脚して、サービス開発の支援や、マーケティングソリューションの提供をしています。
その中で、デジタルネイティブ世代のインサイト変化をつかむために2020年から定期的に実施しているのが「デジタルネイティブ世代の消費・価値観調査」です。定点調査として実施を始めましたが、2020年の調査では「コロナ禍になって、デジタルネイティブ世代の消費・価値観にどのような変化が起こったか」ということをメインテーマに調査を行いました。そして、最新の定点調査を実施したのはコロナ禍になってから2年近くが経過した2021年の10月になります。
最新の調査で着目したのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて生まれた、色々なライフスタイルの変化についてです。例えば、オンライン会議ツールやフードデリバリーサービスのように、新たなデジタルサービスが急激に普及しましたし、リモート飲みやリモートデートといった、新たなムーブメントも生まれました。一方で、こうした変化の中で「社会に普及し、定着したもの」と「一時的には普及したが、社会に定着しなかったもの」の差も徐々に出てきたタイミングだったと思います。具体的には、感染症が広がった直後はリモート飲みが一気に増えましたが、それも現在では行う場面が限られてきたな、とか。逆に、フードデリバリーサービスは今でも利用されており、社会に定着したな、と。
そこで改めて、コロナ禍による変化を経て定着したもの/定着しなかったものの差に着目することは、これからのサービス開発や、マーケティング・コミュニケーションを考える上でとても重要なのではないか、と考えました。しかも、デジタルネイティブ世代は、デジタル機器を使いこなし、情報を先取りする能力に長けているわけですから、今回のコロナ禍を経て、デジタルネイティブ世代が、どういう価値観を持って消費行動を取るようになったのかを明らかにしよう、という点も、大きな実施目的の1つでした。
以上のような背景から、2021年の調査では「コロナ禍を経て、次のスタンダードはこうなっていくのではないか」ということをあぶり出していこう、という狙いの下、実施することにしました。
ますます強まる、デジタルネイティブ世代の「自己表現消費」傾向

Q.調査結果を見たときの、最初の印象はいかがでしたか?
松崎:まず、調査結果からデジタルネイティブ世代の消費行動を考察してみたときに、コロナ禍でリアルのコミュニケーション機会が減ったこともあり、買ったものをSNSに投稿して、自分の趣味嗜好を表現したりアピールしたりすることで、「人とつながったりコミュニティに入っていったりするきっかけにしている」という特徴がより強く出ているな、と思いました。商品も、単なる機能として求められ、購入されているわけではないということです。また価値観の面でも、いろいろなことに挑戦していきたいけれど、リアルな接点が限られるために不安も大きい、といった心境も見えてきて、コロナ禍の影響を垣間見たように思います。
さらに、調査を実施するにあたって、仮説を立てるために、デジタルネイティブ世代にあたる電通デジタルの新入社員へ「ブランド観」について話を聞いてみたんです。すると、この世代では他の世代と比較しても、企業の「ブランド」の源泉が今までと違っていることを強く感じました。今まで企業の「ブランド」とは、その企業が何を発信しているか、どんなイメージを作り上げようとしているかが源泉となっていたのですが、最近はそこが大きく変わり、どんな人が使っているか、使っている人たちがどのように思い、発話しているかという、その企業を取り囲む「コミュニティ」が、若い人たちにとっての「企業ブランド」の源泉になっていたのです。まさにその変化の要因を考えると、デジタルによってインタラクティブなコミュニケーションが当たり前にできる環境で育ったことが、背景にあるのではないでしょうか。
また、モノの売れ方にも興味深い特徴があると感じました。例えば、ある美容グッズが「発売数日の間に店頭で売り切れること」があるのですが、その現象がどのような流れで起こるのか、についても話を聞いてみました。すると、まず最初は美容情報に明るいインフルエンサー起点で発売前からSNSで発信され、次にそのフォロワーである「美容ファン」が、商品発売日にお店に駆けつけ購入。さらに、その美容ファンたちが購入したことをSNSに投稿することで、さらに拡散され、美容コミュニティ全体に広まっていき、結果、店頭で売り切れるというメカニズムが見えてきました。これは、「美容」というくくりのコミュニティがベースとなって、そこから情報が拡散しているために発生しています。そのような現象が起きるのは、デジタルネイティブ世代にとって、いつ何を購入したかをSNSに投稿することは、自分の「好き」を表現し、同じ趣向を持つ人同士でつながる上で、非常に重要だからです。
上記に挙げたコミュニティは、美容というジャンル以外にも多種多様に存在していて、その中で情報交換が起こり、特定の情報が拡散されていく、という動きはたくさん見られます。もちろん、今でもマスメディアの力もありますが、昔と比較すると、情報番組やテレビドラマが起点となってというよりも「SNSコミュニティが起点となって」広がっていく、という動きがスタンダードになりつつあるのです。
ここまで説明してきた「コミュニティ」とは、デジタルネイティブ世代を説明する上で非常に重要なキーワードではないかと思っています。かつては、「地元」や「学校」、「会社」などの「リアルの場」がコミュニティの源泉でした。仲の良い友人は「同じ学校」でできるものであり、よく飲みに行く人は「同じ職場」の人が多かった。でも調査結果からも見えてきたのが、デジタルネイティブ世代にとっては、コロナ禍によるリアルの喪失も相まって、「好き」がコミュニティの源泉になる傾向がより強くなったように感じました。それはスマホ1台さえあれば、「このインフルエンサーが好き」「この野球チームが好き」「この景色が好き」など、「同じ趣向を持つ人たち」がSNSで簡単につながることができるからです。年齢も性別も職業も、住んでいる場所も関係ありません。
こうした中で、デジタルネイティブ世代の多くが「自分らしさを表現」したいと思っていることも、調査結果から分かっています。でも一方で、「じゃあ自分らしさってなんだろう?」「それって、他の人とずれていないだろうか?」という不安も感じることも分かってきました。だからこそ、同じ「好き」で人とつながることで安心できる。それがリアルなつながりでなくても、SNS上で行うことができる。これがデジタルネイティブ世代の何よりの特徴だと思います。中には、複数のアカウントを使い分けて、いろんなコミュニティを持っている人もいます。「美容好き」な私、「キャンプ好き」な私、「アイドル好き」な私。多様な自分がいて、それぞれがコミュニティで「〇〇好き」な自分として活動することで、各所で自分らしさを表現しているのです。
デジタルネイティブ世代が持つ、「利用シーンを生み出す力」
Q.これまでデジタルネイティブ世代について調査を続けてきた中で、彼らの消費行動や価値観のどんなところに注目していますか?
安部:私も、デジタルネイティブ世代にとって、「自分がどんな商品やサービスを使っているか」が人格の表現やコミュニティ参加につながる、という特徴が面白いなと思いました。一方で、ドライで合理的にものを選ぶ側面もあるようです。
彼らは多角的な視点から購入決定の判断をしており、「環境保全に取り組んでいるか」「ブランドとしてのビジョンやパーパスを持っているか」「リセールバリュー(再販価値)があるか」といった、ある意味で非常に理性的な判断基準も持っています。つまり、これを買うことで「こういう人格として見られたい」という「憧れ」的な要素と、非常に合理的に判断をする側面と、その2面性があるところが何より面白いなと感じました。
もう1点注目しているのは、デジタルネイティブ世代は、おそらくその商品・サービスを作った人が想定していなかったであろう使い方を生み出していく能力がある点です。
以前耳にして面白いと思ったのは、ある位置情報共有アプリのケースです。このアプリでは、今現在の自分の位置情報を仲間と共有できます。これにより「友達がこの場所にいるから会いに行こう」なんていうことができるわけですが、一方で自分の居場所が常に知られてしまうので、一見、賛否両論ありそうなサービスです。おそらくサービス開発側は、若い世代が友達や恋人同士で登録して、遊びに誘いやすくするといった使い方を想定していたのだと思います。しかし実際には、そうした使い方に加えて、スキー場や野外フェスのようなイベント中に「お互いの位置を確認して合流する」という使い方もされているようです。このような利用シーンを発見し、広げていく力は、デジタルネイティブ世代ならではだと思います。
コロナ禍におけるデジタルネイティブ世代の行動や考え方の変化を調査した「デジタルネイティブ世代の消費・価値観調査 ’21」 。この調査をひもとくと、彼らの「モノ」に対する意識が、他世代とは大きく異なっていることが分かります。彼らにとって、モノは機能を求めるだけの存在ではなく、彼ら自身の自己表現や仲間とのつながりにも関わる、重要な要素となっていたのです。後編では、デジタルネイティブ世代の消費行動や価値観をより深く掘り下げるため、彼らがモノを購入するまでの流れや購買決定の判断基準について聞いていきます。
デジタルネイティブ世代の価値観と行動を知ることは、「未来のビジネス」を想像することにつながります。彼らを理解し事業戦略の最善を考えたい。あるいは、この記事でもご紹介した調査結果をもっと深く知りたい。そんなときは、ぜひページ下部「CONTACT」から私たちにお声がけください。