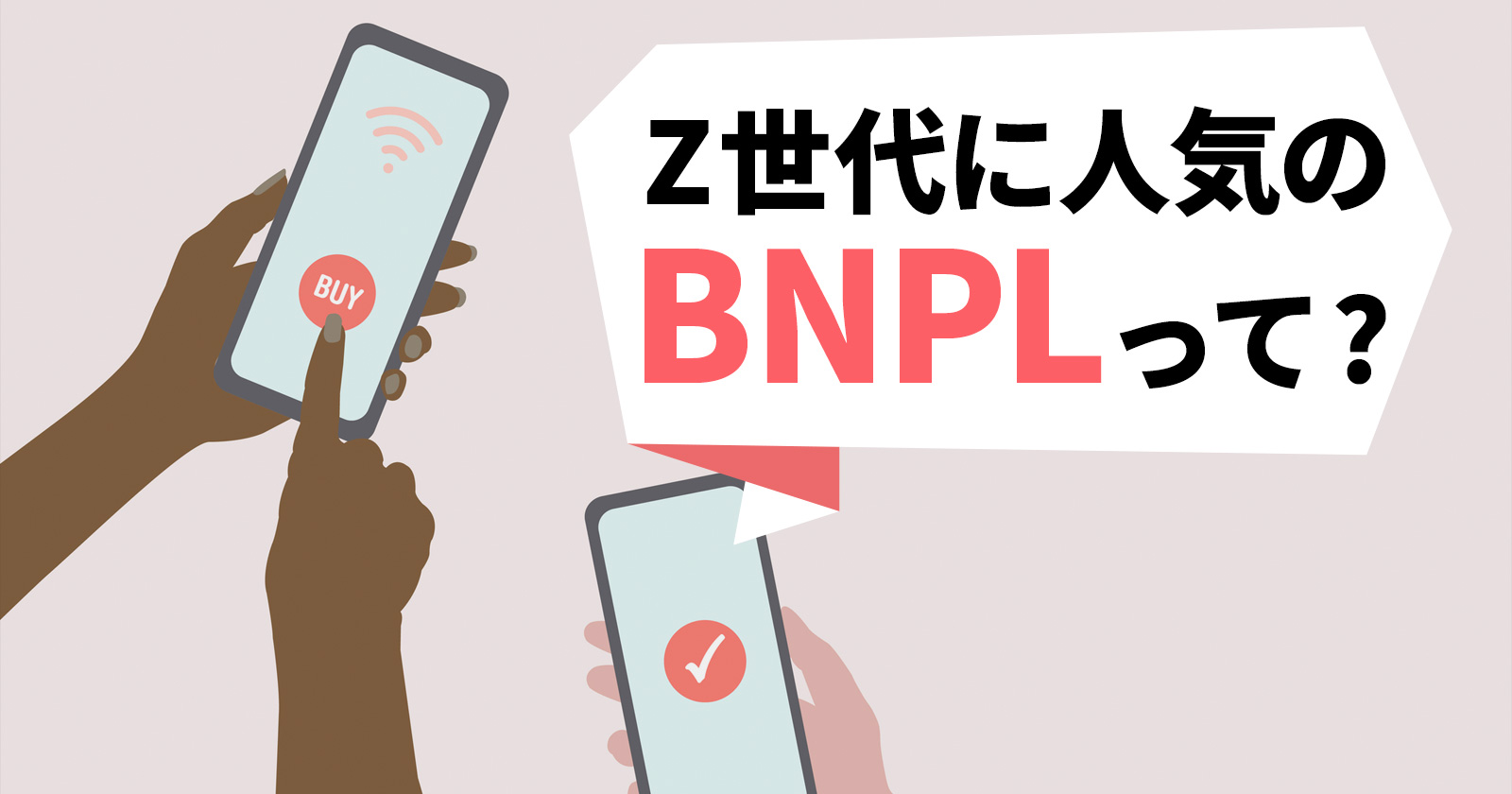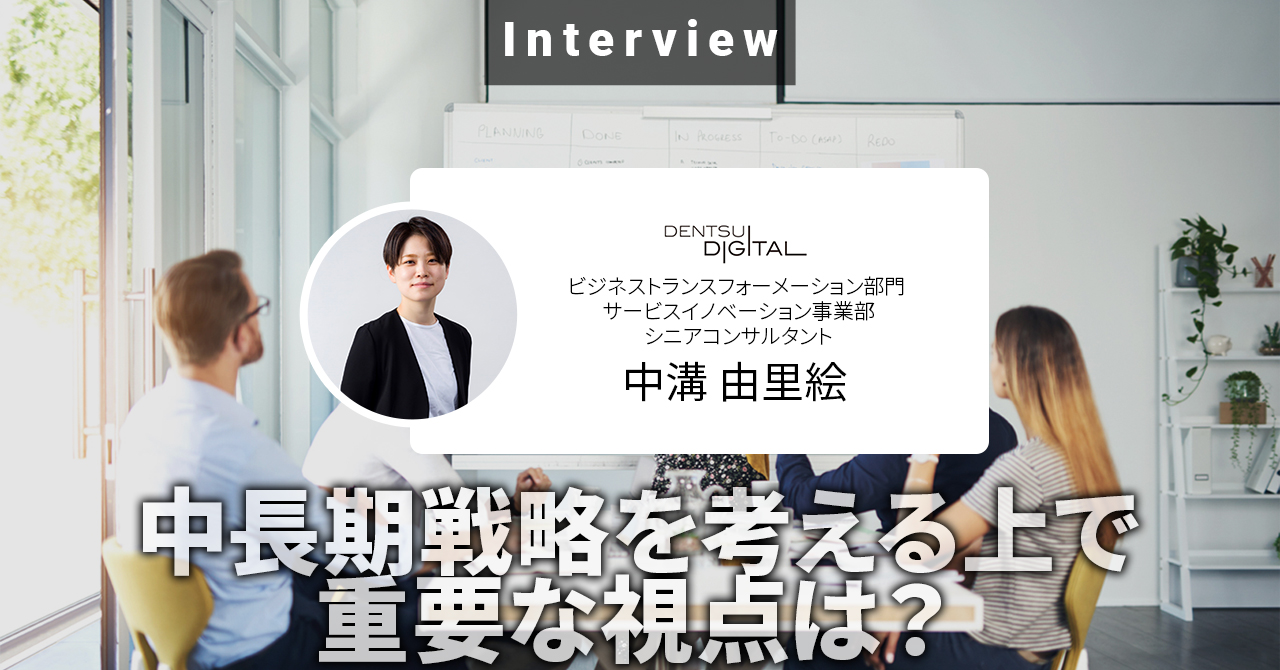株式会社電通デジタル内のデジタルネイティブ世代に特化したチーム「YNGpot. ™️(ヤングポット) 」は、コロナ禍によってデジタルネイティブ世代の意識や行動にどのような変化が起きているのかを分析し、次のスタンダードを探るため「デジタルネイティブ世代の消費・価値観調査 ’21」を実施しました。前編では、調査の目的や、その結果から見えてきたデジタルネイティブ世代の消費の傾向についてYNGpot. ™️メンバーの松崎裕太氏と安部茜氏に語ってもらいました。続く後編では、デジタルネイティブ世代がものを購入するまでの流れや購買決定の判断基準について詳しく解説してもらうとともに、オンラインでの消費が隆盛を極めている今、リアルな店舗がどうあるべきかについても迫っていきます。
デジタルネイティブ世代の「自己表現消費」における3つの購買フェーズとは

Q.前編で安部さんがおっしゃっていましたが、今回の調査を通じて、デジタルネイティブ世代の購買行動のスタイルが見えてきました。ニュースリリース記事にも「デジタルネイティブ世代の『自己表現消費』における3つの購買フェーズ」として記載されていますね。あらためてこちらについて詳しく教えていただけますか。
松崎:私たちは、デジタルネイティブ世代特有に見られる、消費行動にも自分らしさを求める行動のことを「自己表現消費」と名付け、その消費行動を「日常フェーズ/商品検討フェーズ/購入決定フェーズ」の3つのフェーズに分けて、それぞれの特徴を明らかにしました。
この「3つのフェーズ」の捉え方ですが、いわゆるファネルやカスタマージャーニーとはちょっと違う捉え方をしています。カスタマージャーニー的な捉え方だと、例えば「商品・サービスを知って、それに興味を持って、購入する」という段階的なステップを踏むイメージがありますよね。でも、デジタルネイティブ世代の消費行動を見ると、日常的にSNSで情報収集をしたり、店頭で見た商品の口コミをSNSで調べたり、階層的というよりも、グルグルといろんな段階を回っているように見えるんです。ですから、今回の分析の際にも「3つのフェーズ」という捉え方をしました。各フェーズについて、それぞれ簡単にご説明します。
日常フェーズ
デジタルネイティブ世代は、普段から「暇つぶし」的に、「何かいいものはないか」とSNSを中心に、情報を探している状態です。その中で「いいな」と思うものがあれば、それをSNSの保存機能やスクリーンショットを撮って記録。特徴としては、脳内ではなく、デジタルデバイス上に保存します。この一連の流れから、カスタマージャーニーとのニュアンスの違いを感じていただけるでしょうか。「まずは商品の存在を認知して、段々と興味を持ち、そこから詳しく調べて……」と段階的に進んでいくというよりも、「日常の情報収集の中で、ふと気になったらとりあえずスクショして手元に置いておく」というイメージです。翌日には忘れてしまっているかもしれないけれど、でもふとスクリーンショットを見返しているときに、目に飛び込んできて思い出す、なんてこともあるかもしれません。
商品検討フェーズ
とにかく情報過多な時代ですから、ある商品を買おうと思い立った時、同じカテゴリの商品を全て調べることはまず不可能です。同様に「口コミをチェックする」といっても、ネット上には口コミも大量に溢れているので、その全てを確認することはできません。しかも、デジタルネイティブ世代は口コミの中には、ステルスマーケティングが含まれていることがある、なんてことも知っていますから。さらに信憑性のある情報を選抜して、情報収集しなければいけません。他にも、レストランを探そうと思っても、グルメ情報サイトだけでも多くの種類がありますし、グルメ系サービス以外でも、例えば、地図サービスに直接お店の名前を打ち込んで出てくる情報もある。つまり、この「商品検討」のフェーズにおいては、大量にある情報の中から効率的に情報収集するためにも、事前にある程度絞り込まれている情報の中から検討していく必要があるのです。
その絞り込むための方法の1つが、「日常フェーズ」におけるSNS保存機能やスクリーンショットなどの「ストック情報」です。ストックしていたものの中から情報を引き出して、その中から選ぶ。他にも「既に誰かによってまとめられている情報」から選ぶ方法もあります。「こういう人は◯◯を買っている」というまとめ情報であったり、どこかのアプリが提供してくれている人気ランキングであったり、あるいはSNSコミュニティの情報であったり。デジタル上には、色々な切り口でキュレーションされている情報がたくさんあるので、それを活用することも多いようです。
「日常的に、自分の気になったものをストックしている情報の中から選ぶ」か、あるいは「どこかのキュレーション情報の中から選ぶ」か。いずれにしても、これらの「絞り込み」の中にエントリーできていなければ、その商品が購入検討されることはないと言っても過言ではないでしょう。
購入決定フェーズ
最後の意思決定をする段階においては、特にデジタルネイティブ世代に見られる「5つのフィルター」に私たちは注目しました。もちろん単純に「安い」「便利」「カッコいい」など、普遍的とも言える基準はこれまで通り存在していますが、加えてこの世代特有のポイントがあることも分かりました。それがこの5つのフィルターです。
- 壮大なビジョンやパーパスがあるかどうか
- SDGsや社会貢献性など、世の中の役に立つかどうか
- これは「自分たちの世代にとって使いやすい」と感じられるかどうか、つまり自分たちのことをよく考えてくれていることへの共感、仲間意識が感じられるか
- 「こんなに多くの人が良いと言っている」という購入者の生の声
- リセールバリュー(再販価値)、つまり使わなくなったら中古品市場で高く売れるかどうか
もちろん、世代の中でも重視度は異なりますが、購入決定時には、これら5つのポイントも重視しながら、多角的な判断をしていることが分かりました。特に、デジタルネイティブ世代においては「1.壮大なビジョン」を持っていたり「2.社会貢献」していたりするブランド・商品を選択することで、自身もそのビジョン・社会貢献コミュニティへの共感・所属を表現したいという想いがあるようです。
Q.カスタマージャーニーではなく「3つのフェーズ」で捉えているところが面白いですね。
安部:決してカスタマージャーニーを否定しているわけではありません。例えば、メインターゲットがはっきり決まっている場合であれば、そのターゲットのジャーニーをしっかり追いかけていくことは有効です。しかしデジタルネイティブ世代をターゲットとする場合、多くの顧客を獲得するためには、複数のコミュニティにアプローチしていかなければならないケースも増えてくるのではないかと思います。
「デジタルネイティブ世代全体」みたいなターゲティングはおそらくほとんど意味がなくて、「デジタルネイティブ世代の中でも、いくつかのコミュニティの中にいかに入り込んでいくことができるか」が重要になるのではないでしょうか。その時に全てのコミュニティのジャーニーを描くのはなかなか難しいでしょうし、さらに言えば「日常生活における情報収集」の中に入っていかなければ、選択肢に入ることもできません。ならば、それぞれのコミュニティの日常フェーズの中で、きちんと情報が拡散されているかを見ていくことが重要では、と私たちは考えています。
加えて、Google社が提唱している「パルス消費」(24時間いつでもスマートフォンを操作している中で、突発的に物が買いたくなり、商品を見つけ、購入まで終わらせるという消費行動)や、SNSがEC連携を行う中で、コンテンツを見てそのままECに飛んで買う、といったスタイルが、デジタルネイティブ世代の新たな消費行動となってきています。そうなると、いわゆる「認知から購入まで」という従来のカスタマージャーニーは必ずしも当てはまらず、「見た瞬間に買う」ということが起こっているのでジャーニーが一瞬で終わってしまうこともあるのです。もちろん、「認知してから調べてじっくり考える」というケースも引き続き存在していますが、このように購買のスタイルが多様化しているので、従来のカスタマージャーニーでデジタルネイティブ世代の購買行動を描き切るのは難しくなってきているのではないかと思います。
ですから、購買に至るまでのプロセスを「3つのフェーズ」に分けて考える、そして購買決定の判断基準になる「5つのフィルター」を押さえる、以上の2つが重要ではないかと考えました。
デジタルネイティブ世代の購入決定を左右する5つのフィルターとは
Q.先ほど紹介いただいた、購入決定に影響を及ぼす「5つのフィルター」ですが、この5つの中でも特にこれが重要とか、最も影響力が大きいのはこれだ、というものはあるのでしょうか?
松崎:まず大前提になるのは、「5つの中でもどれが特に大事」というわけではなく、「個々の商品・サービスによって、またその購買フェーズによって、どの要素が機能しやすいか」ということではないでしょうか。
例えば、「4.購入者の生の声」というのは、もはやデジタルネイティブ世代に限らず、どの世代でも重要な要素になっていますよね。そして、特に価格の高いものを買う時には、「5.リセールバリュー」が重要になってきます。先にフリマアプリを見て、まずは「そもそも新品で買う必要があるのか」を考える。そして、その商品が安く大量に売られていると、「これは価値がないんだな」と判断されてしまうこともある。逆に高く売られていれば、仮にその商品を買って失敗したなと感じたり、使わなくなったりしても「すぐに売ればいいや」となるので、購入を迷っている人は背中を押されますね。
また、先ほどもお伝えしましたが、やはり「1.壮大なビジョンやパーパス」「2.社会貢献」の2つは非常に重要です。SDGsのゴールは2030年。デジタルネイティブ世代にとっては、まさに自分たちが社会の中心になっているタイミングですし、SDGsは教育現場などでも頻繁に取り上げられるテーマなので、より身近な課題として感じられているのでしょう。コロナ禍という社会的な課題に直面したことも、より社会を身近に感じるきっかけになっていると思います。
これらのフィルターに関して、注意しなければいけないのは「社会に貢献しているからこのブランドの商品を買う」など、エシカルな姿勢が評価されて購入につながる以上に、「社会に悪影響のある商品である」「この企業のやり方は良くない」といったネガティブな情報に接した途端、継続購入していた方が購入をやめるきっかけにつながったり、最初の時点で購入検討の候補から外れてしまうという、マイナスな判断の基準になり得るということです。商品を購入することは、その商品を応援していたり、自己表現することに繋がる世代だからこそ、商品にネガティブな声が付いているだけで即座に購入検討候補から外されてしまい、情報収集しようという気すら起きなくなってしまう。デジタル上に情報が全て残る時代、こうなってしまうと、リカバリーは本当に大変です。
デジタルネイティブ世代にとって、「リアル」はどのような意味を持つのか
Q.インターネットで何でも買えることが当たり前のデジタルネイティブ世代にとって、リアルの店舗はどう映っているのでしょうか?
松崎:確かに、今はたいていの情報はインターネットで集められますし、思い立ったらその場ですぐに買える、という環境にあります。とはいえ、デジタルにも「商品の実物に触れられない」「他商品と見比べられない」というような弱点はあるんです。インターネットでみんながいい商品だと言っている、でもやっぱり自分で実物を見て確かめたい。そういったニーズは確実に存在していますので、むしろ「ネットで先行して情報を仕入れてはいるけれど、本当にその通りなのか、自分で確かめたい」という思いに応える場としての環境づくりをしっかり行うと、マーケティング効果が高まるのではないかと考えています。
安部:リアル店舗のもう1つの価値は、やはりセレンディピティではないでしょうか。SNSで自分が好きなコミュニティに入って、好きな人をフォローしていく、そういった中で、入ってくる情報がどんどん「好きなもの」で最適化されていくと、それ以外の情報を自然と得ることが難しくなってしまいます。でも、例えばTikTokは、「おすすめ」のページで自分の好きな領域以外のコンテンツもフィードに上がってくるような、ランダム性を取り入れたアルゴリズムになっています。ですから、デジタルネイティブ世代にとってTikTokは「自分の知らないものを知ることができる」という点で支持されているのです。
このように、デジタル上で起こる最適化に対抗するように、デジタルサービスの提供側があえてセレンディピティを導入しているような状況ですから、リアルな店舗ならではのセレンディピティは非常に重要なのではないかと思います。
松崎:前編で、デジタルネイティブ世代は複数アカウントを持つケースが多いという話をしましたが、これはデジタル最適化が生み出した負の側面に対する、若者なりの対応策でもあるんです。例えば、好きな芸能人のSNSばかり見ていると、そのSNSのタイムラインが同系統の芸能人の投稿で埋め尽くされ、友達の投稿が埋もれて追えなくなってしまったりする。だから、「芸能人の投稿を見るアカウント」と、「仲の良い友達とやりとりするアカウント」を分けて使いますし、例えば就活するときには、専用のアカウントを作成する人も多くいます。このように、アカウントを複数持つことは、自分が必要な情報を収集し続けるためのノウハウなのです。
このようにデジタルネイティブ世代は、元々は想定していなかった、商品・サービスの新しい使い方・楽しみ方を生み出したり、広げていったりする力があります。普段からSNSでいろんな情報を見ている中で、情報がどんどん流れていってしまうから、覚えておきたい情報はスクリーンショットでストックするという習慣が自然に生まれた。そうしたらSNS側も保存機能や履歴機能をつけるようになっていった。先ほどご紹介した例も、まさにこれに当てはまると思います。だからこそ、「これからのスタンダードを考える」にあたっては、デジタルネイティブ世代がどのような行動をしているのかを注視することが大事だと考えています。
24時間いつでもどこでも手元のデバイスで情報収集ができる。これがスタンダードになっていることから、デジタルネイティブ世代における情報収集から購買決定までの流れは、それより上の世代とは大きく異なると考えられます。例えば、「保存されることで候補に入る」というのは1つの典型的なパターンであり、逆に言えば「保存されるような情報発信が必要」であるとも言えます。こういった視点から自社のマーケティングを見直すことで、次の一手が見えてくるのではないでしょうか。
また、デジタルネイティブ世代が、複数のアカウントを使い分けながら、さまざまなコミュニティとつながっているというスタイルも注目したいポイントです。ターゲットを「コミュニティ」と捉えたときに、そのコミュニティに入り込みやすい情報設計や発信方法が導き出されるのかもしれません。
そして同時に、購入そのものがコミュニティ参画の手段ともなっています。あなたが提供している商品やサービスは、いったいどのようなコミュニティをつくり上げているでしょうか。「モノを売る」のではなく、「モノを核としたコミュニティをつくる」と考えると、商品設計そのものの改善点が見えてくることもあるでしょう。あらためてデジタルネイティブ世代の立場に立ち、自社のビジネスを見つめ直してみてはいかがでしょうか。