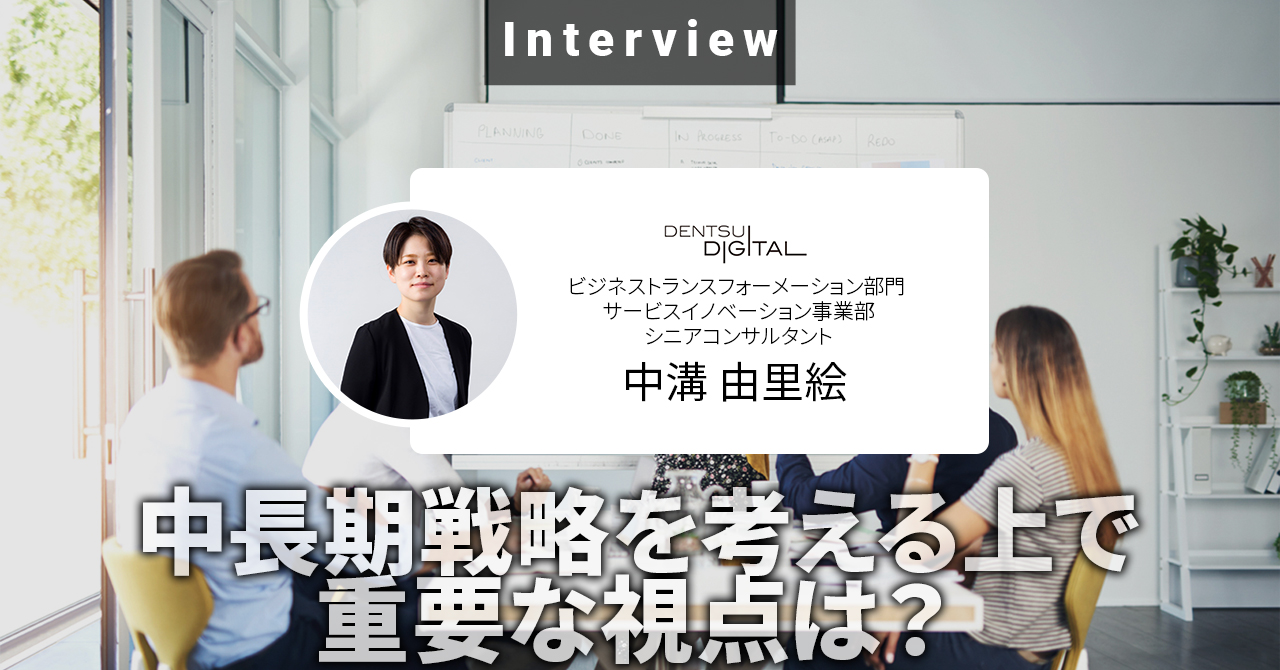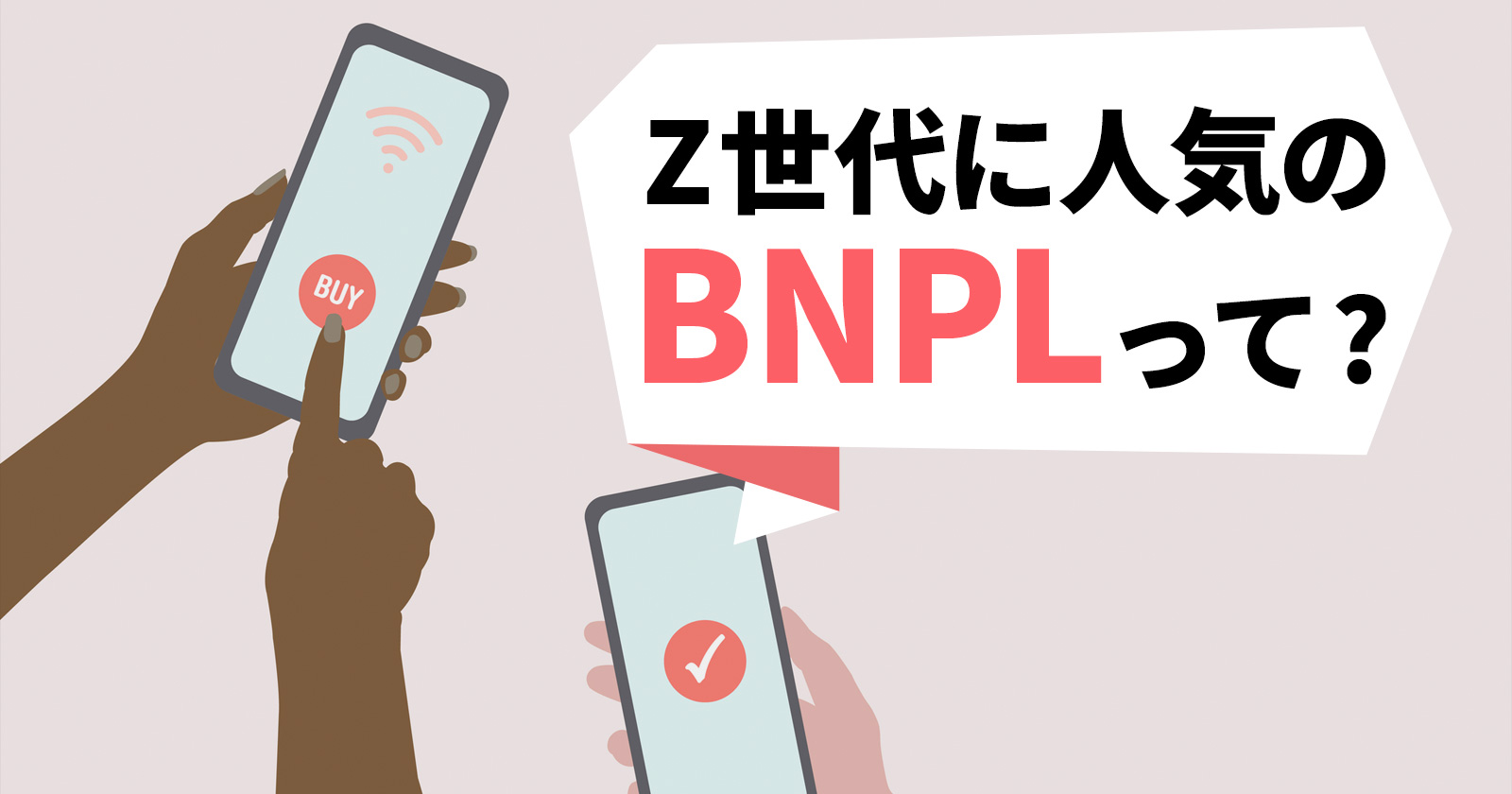先行きが不透明で予測が難しい時代。どのように会社の未来像を描き、事業を展開していけばいいのか。そんな迷いを抱える経営者は多いのではないでしょうか。2010年代頃から、社会情勢を表すのに「VUCA(Volatility=変動性、Uncertainty=不確実性、Complexity=複雑性、Ambiguity=曖昧性)」という言葉が用いられるようになりましたが、その状況は、誰もが想像さえしていなかった新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって、さらに混沌を極めています。
今回は、株式会社電通デジタルで、多くのクライアントのビジネストランスフォーメーションに携わっている中溝由里絵氏に、電通デジタルならではの中長期戦略の組み立て方について、話を聞きました。
「少し先」ではなく「もっと先」を見据えた戦略が求められている

Q.中溝さんが現在の部署に所属するまでのご経歴を、簡単に教えていただけますか。
中溝:私は新卒で電通グループのデジタルマーケティング会社に入社しまして、営業としてキャリアのスタートを切りました。少しずつプランナーのお仕事を任せていただけるようになったタイミングで、電通に出向し、ダイレクトマーケティング関連の経験を積みました。
電通デジタルに入社したのは、社会人6年目のタイミングです。入社当初から「できる業務の幅を広げたい」と上司に伝えていたのですが、ある日突然、某トイレタリーメーカーへの出向を提案された時は、驚きました。メーカーに出向すると、これまで私が担当していた領域とは異なる、データサイエンスを扱う部署に配属されたので、当初は戸惑いも大きかったですが、電通デジタルの立場では見えなかったモノ、コト、考え方に触れることができた貴重な経験だったと思います。2年間の出向を終え、電通デジタルに戻ってからは、クライアントの新規事業の立ち上げ支援などを担当させていただいています。現在の部署に異動したのは、2021年の1月ですね。
Q.さまざまな企業の新規事業の構想支援やソリューション開発支援を行っているとのことですが、最近はクライアントからどのような相談を受けることが多くなっていますか?
中溝:現在、多くの企業が「既存の事業がこの先成り立たなくなるのではないか」という課題意識を抱えているように感じます。以前は3、4年くらい先の未来を見据えて新規事業を立ち上げるなど、中期的な戦略を求められることが多かったのですが、今は、「もっと先、10年後、20年後、さらには50年後と、長期スパンでの事業構想を一緒に考えてほしい」という依頼が増えてきています。会社自体もそうですが、10年後、20年後に業界がどうなっているのか、存続しているのか。そんな危機感に駆られている企業が多い印象です。
それは新型コロナウイルスの感染拡大によってさらに加速したと思います。世の中がよりデジタルへと舵を切り始め、「もっと早く変化しなくては」「描いていたシナリオを見直さなくては」という声が数多く届くようになっています。
Q.多くの企業が不安定な世の中で事業戦略の見直しを迫られている中、陥ってしまいやすい落とし穴としては、どんなものがあるのでしょうか。
中溝:まず1つは、長期スパンで考えるからこそ「どこを目指すのか」という芯の部分が曖昧になりがちです。人によって見ている未来が全く異なることもあるので、社員1人ひとりが同じところを見据えることが非常に重要だと思います。トップと担当者の意識の相違があるケースもあったりします。担当者や担当部署だけで取り組むのではなく、全社で一丸となってやっていく意識を根付かせることも大切ですね。
そのために我々が提案して実施しているのが、社内のステークホルダーへのインタビューや自社資産の棚卸しです。事業構想をする上で、自社の資産をしっかりと把握することで、必然的に「これを扱うのであれば、それに対応できる部署はありますか」とか、「こういうふうにするのなら、このあたりの人たちを巻き込んでいきましょう」というように、全社的に取り組める状態に導いていくことができます。それに加えて、その企業について、業界について、膨大なリサーチをして、関わってゆく私たち自身が未来に対する認識を擦り合わせていくことも、大きく意識している部分です。
数字だけにとらわれず、生活者のフィルターを通して「ワクワク」を届ける提案を
Q.中溝さんが所属するチームのコンサルティング手法は、いわゆる一般的な「戦略コンサルティング」と比べてどのような特徴がありますか?
中溝:以前、ある会社で「2050年の未来を描く」という事業構想に参画していた際に言われたのが、「電通デジタルさんって、ハッピーなアイデアを出してくれるよね」という言葉でした。一般的な戦略コンサルティングは、数字をベースに考えた「硬いアイデア」が中心になるけれど、電通デジタルは「ワクワクするようなアイデアを提供してくれる。だからお願いしたいんだ」と言っていただいて、大きな自信につながったことがあったんです。
私たちはデータだけを見ていくのではなく、未来の生活者を洞察しながら「生活者ってどういう気持ちになるだろう」とか「生活者ってどんな行動をとるだろう」とか、そういった思考を踏まえて、「だったらこういうビジネスができるんじゃないか」「この市場が動くんじゃないか」と発想を展開します。そこにクライアントの強みを掛け合わせてアイデアを提案するので、クライアントとしてはイメージしやすいし、ワクワクすると感じてもらえるのだと思います。
Q.マーケットの推移を見ながらも、そこでどんなことが起こり得るかということを具体的に形にして、描いていくというのが特徴なんですね。
中溝:はい。数字で理詰めしていって、それを戦略に落とし込んでいく「戦略コンサルティング型」のアプローチをする会社もありますが、私のいる電通デジタルのビジネストランスフォーメーション部門は、それとは異なるアプローチをしています。キーワードとしては「未来志向」「生活者視点」「ビジネス視点」「エンジニア視点」を掲げたコンサルティングという感じですね。
数字ベースで考えていくと、「市場や業界はこう変わるから、こういうアイデアが必要だよね」という発想になりますが、私たちは「人はこの時にこういう気持ちになるだろうから、こうしたらワクワクするだろう」という考え方をしています。生活者視点を取り入れて分かりやすく、イラストや絵や写真など、ビジュアル的なツールも使いながら具体的なアイデアを提案していく。さらに、ビジネスとエンジニアの視点も加え、事業として成り立ち、実現でき得るものにしていく。それが、私たち電通デジタルの特徴であり、魅力だと思います。
数字やデータのみに依拠せず、生活者視点で戦略を立てていく。そうすることで納得感と具体性のある事業構想が生まれていきます。そうしたアイデアを生み出す取り組みの1つとして、電通デジタルと株式会社電通コンサルティングが共同で開発した「未来曼荼羅」という発想支援ツールの活用があるといいます。後編では、この「未来曼荼羅」についても、詳しく話を聞いていきます。