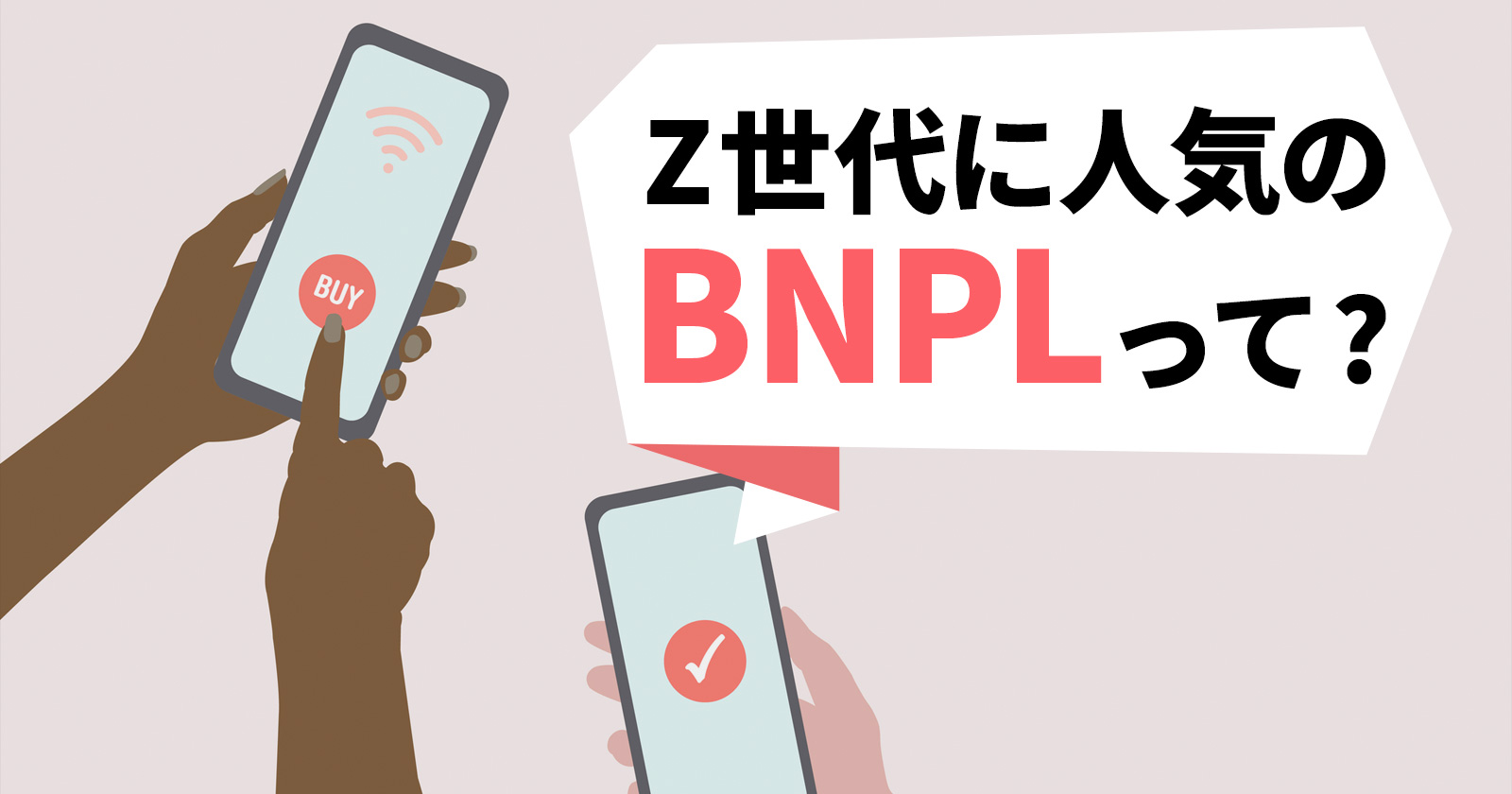デジタル化の進展は、あらゆる業界に構造的な変化をもたらしています。Transformation SHOWCASEでは、さまざまな業界においてどのような変化が起こっているのか、そしてその変化の中にはどのような「次のチャンス」が生まれ始めているのかをレポートしていきます。
エンターテインメント業界も、その1つ。デジタル化によってビジネス構造が変わり、新たな動きが生まれています。その中でも、本記事では音楽業界に注目し、株式会社電通ミュージック・アンド・エンタテインメント(以下、DME)の保坂秀氏、殿村陽子氏、富樫祐輔氏にインタビュー。デジタル化が進む中で、変革と向き合う音楽業界のリアルな現状について話を聞きました。前後編の2回にわたりお届けします。
「広告マーケティング」領域における音楽ビジネスの変化
Q.まずは基本的なことですが、DMEとはどのような事業を展開する企業なのでしょうか。音楽業界の企業でありながら、いわゆる「レコード会社」や「レーベル」と呼ばれるような、アーティストを自社で抱えたり楽曲をリリースしたり、という会社とは異なっているようですが。
富樫:DMEは音楽にまつわるさまざまな事業に取り組んでいますが、その中でも特に大きい事業の1つが、アーティストや楽曲とCMをはじめとした企業広告とのマッチングを行う「広告ビジネス」。もう1つが、自ら著作権者となって、楽曲の著作権の管理や契約、新たなコンテンツへの投資、アーティスト活動の支援などを行う「権利ビジネス」です。以上の2つがDMEの事業の2本柱になっています。音楽の権利を守る機能を持ちながら、音楽と企業とをつないで新しい価値を生む「広告ビジネス」も事業の柱としている、という点はDMEの特徴と言えるかもしれません。
「広告ビジネス」についてご説明しますと、基本的には企業がテレビCMなどの広告活動を展開するときに必要な広告音楽に関するあらゆるソリューションを行うのですが、中でもアーティストとのタイアップは重要な要素の1つです。企業のニーズに対して、アーティストが持つイメージやファン層を踏まえた上でマッチング。企業にとっては、アーティストと組むことでマーケティングの上で大きな力となる。一方でアーティストにとっても、CMなどを通じてメディア露出が増えるのはメリットが大きい。こういったWin-Winの関係を成立させることが私たちの仕事になります。
Q.広告マーケティングの世界において、アーティストタイアップは以前から行われていた手段だと思いますが、最近の傾向やトレンドとしてはどのようなものがありますか?
富樫:従来は「CMタイアップ」と言えば、認知度が高いメジャーなアーティストに対するニーズが高く、またテレビやラジオなどマス媒体を中心とした展開が主流でした。しかし、最近では企業の広告キャンペーンも、テレビCMだけではなくWeb上での展開にシフトしてきています。それによって、企業に提案するアーティストの幅が広がってきているのを感じます。メジャーなアーティストだけではなく、特定のターゲットに人気の高いインディーズのアーティストも、タイアップの候補として挙がるようになってきました。SNSのフォロワー数やYouTube動画の再生数などが「拡散力」の指標となり、ターゲット効率の観点から、「特定の世代やジャンルでバズっている」とか「TikTokで人気」など、よりターゲットの世代やカテゴリーにリーチできるアーティストが評価されるケースも増えてきたなと。
一方で、アーティスト側の変化もあります。かつては「テレビCMがどれだけ流れるか」など、マスメディアでの露出量が確約されていなければ、楽曲提供や出演するメリットが少ないのでタイアップが成立しない、というようなケースもありました。しかし最近はWeb展開だけのキャンペーンであっても、それがアーティスト自身のプロモーションにとっても重要だという認識が広がってきていて、タイアップが成立しやすくなってきたという流れも起こっているのではないかと思います。実際、特に若い人たちの間ではネットやSNSの音楽文化が浸透し、音楽の情報収集をする手段がWebメディアやSNS中心になってきていますので、アーティストにとっても、それらを使ったプロモーション展開が重要になりつつあります。
保坂:デジタルへの対応という点では、音楽業界は動きがとても速かったのではないでしょうか。音楽配信サービスなどの台頭によって、「聴き方」がデジタル化しているのはもちろん、アーティストの生まれ方や育ち方も大きく変わっています。動画共有サイトでオリジナル曲を発表したり、ボーカロイド曲の作曲をしていたりした人が、デビューしてメジャーアーティストになったケースもありますよね。今では「DIYアーティスト」などと呼ばれていますが、自分たちで曲を作って、Webにアップして、オンラインで販売までやってしまう。SNSを駆使したプロモーションで多くのファンを集めるアーティストもいます。こうなってくると、そもそも「メジャーデビューする」ことの意味が希薄になってくるかもしれません。デビュー前からフォロワーをたくさん抱えているアーティストがどんどん出てきています。以前はメジャーデビューして、CDやDVDの売り上げが伸びて人気アーティストに育っていく、という流れが王道でしたが、今はとにかくファンがどれだけいるか、ということが重要になっている。この傾向は3~4年前から顕著になっていたのではないかと思います。
映像と音楽のマッチング。「シンクロビジネス」とは何か

Q.なるほど、デジタル化によって音楽の「聴かれ方」や「売れ方」が変わっているような気はしていたのですが、「アーティストの生まれ方」まで変わってきている。それに伴って、企業のマーケティングに求められるアーティストの特性も変わってきている、ということですね。殿村さんは、広告と音楽のマッチングビジネスに携わっているとのことですが、具体的にどのようなお仕事をしているのか、教えていただけますか?
殿村:私たちの業界では、「シンクロビジネス」と呼んでいる領域があるのですが、これは「映像」に対して「音楽」をシンクロさせる、つまりマッチングさせるという仕事になります。例えば、映画に音楽をシンクロさせるとか、ゲームに音楽をシンクロさせるという形で、そこに何らかの「映像」があり、その映像には「音楽」が必要だ、という状況はいろんなところにありますよね。その中でも私は、「広告」という映像素材に対して音楽をシンクロさせる、というビジネスを専門にやっています。
「映像にマッチする音楽を付ける」という点では、それが映画でもゲームでも、広告でも同じと言えるのですが、その中でも「広告のシンクロ」はちょっと特殊なのではないか、と個人的には思いながら仕事をしています。というのも、広告には「広告主」つまりクライアント企業の存在があり、企業として狙っていきたいターゲットとか、消費者に訴求したい企業イメージやブランドイメージがある。そういった部分を全てくみ取った上で、一番マッチすると思われる音楽をシンクロさせていくわけです。これが例えば「映画」であれば、映画監督や音楽監督といった「作り手」の想いをストレートに音楽にも乗せていけばいいのですが、広告の場合は、広告主の想いや、キャンペーン全体との関係といった要素も考慮しなければなりません。
一方で、同じ楽曲でも、特定の映像に乗った場合、その性格が変わったように見えるということもあり得ます。楽曲にも人格があり、それを作ったアーティストにも想いがあります。単に使用料を払えば何でも使える、というものでもありません。そういった事情も理解して音楽をシンクロさせなければならないので、単純に映像に合った楽曲を選べばいいというわけではないと思っています。アーティストに対してもきちんと交渉して、こちらの使用意図を伝え、納得してもらった上で契約に至ります。その権利関係の契約処理も含め、アーティスト側との通訳的なポジションを専門的に務めています。
Q.殿村さんが「シンクロ」を進めるときに、特に重視している点はありますか?
殿村:私たちのスタンスとしては、基本的には「押し付けない」ということを重視しています。私たちは音楽を取り巻く世界で仕事をしてはいますが、あくまでも顧客企業の要望にお応えするプロとして仕事をしています。特に広告というものは、多種多様な方々の想いが込められているものであることがほとんどです。広告主であるクライアント企業はもちろん、その対象となっているプロダクトやサービスを開発した人、広告制作のクリエーティブ担当者など、本当に多くの人が関わって、紆余曲折を経ながら作り上げていく。そういったことを踏まえて、私たちとしては、もちろんレコメンデーションはしますが、「これがいいです」と押し付けていくのではなく、いろんな人の想いに柔軟に応えながら、何がベストかを考えていくことが大切なのではないかと思っています。
急速に進むデジタル化によって、過渡期を迎えている音楽業界。今後の音楽ビジネスを考える上では、音楽の「聴き方」だけではなく、アーティストの生まれ方や育ち方まで変わってきている、という現状を踏まえる必要があるようです。さらに、広告マーケティングにおける音楽の在り方にも、新たな動きが生まれてきています。続く後編では、デジタル化による音楽業界の変化や、「シンクロビジネス」の現状について、さらに深く掘り下げていきます。