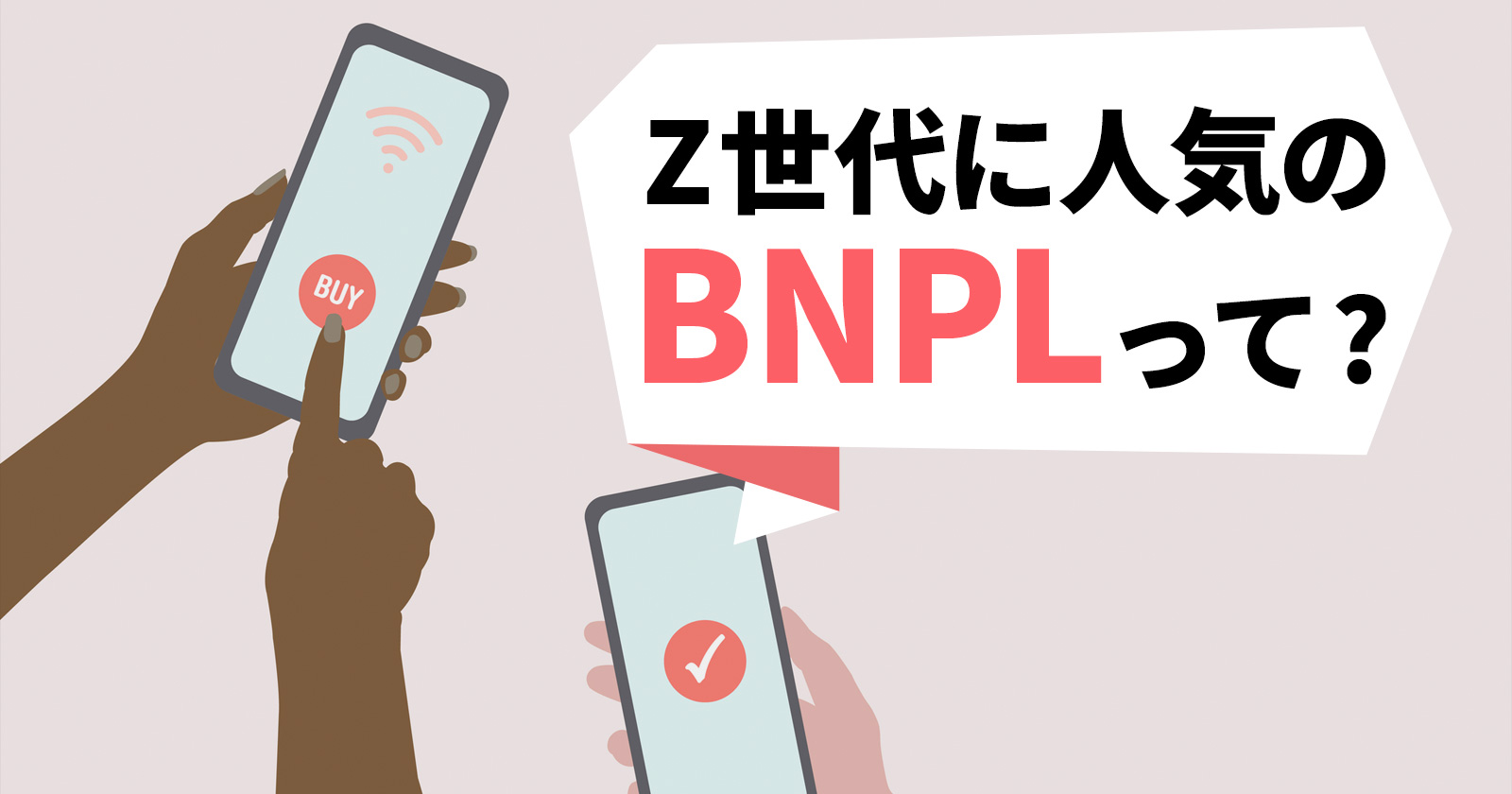今や、あらゆる分野でデジタル化が進んでいますが、中でもその影響を大きく受けている業界の1つが音楽業界ではないでしょうか。音楽の「聴かれ方」や「売れ方」が変わっていく中で、音楽ビジネスも変革の時を迎えています。そうした音楽業界の現状から、新しいビジネスのチャンスを探るのが本記事。音楽業界で「広告ビジネス」や「権利ビジネス」を軸とした事業を展開している、株式会社電通ミュージック・アンド・エンタテインメント(以下、DME)の保坂秀氏、殿村陽子氏、富樫祐輔氏の3名にインタビューしました。後編では、音楽業界の今後や、映像と音楽をマッチングさせる「シンクロビジネス」について、より具体的に聞いていきます。
デジタル化によって音楽業界はどのように変化したか

Q.「広告ビジネス」と「権利ビジネス」を事業の2本柱にするという、業界の中でもユニークな特徴を持ちながら、これまで音楽ビジネスを展開してきたDMEの皆さんは、デジタル化に伴う音楽業界の変化をどのように感じていらっしゃいますか。
保坂:これからの音楽業界も、そして私たちDMEの将来性を考える上でも、「デジタル&グローバル」というのがキーワードだと考えています。今、「&」と言いましたが、「デジタル=グローバル」と言った方がより正確かもしれません。
もともと音楽とか映像は、CDやDVDとしてパッケージ化して販売する、というビジネスが主流でした。しかし、それらがインターネット上に一気に解放されたことで、どこでも誰でも楽しめるようになった。ちょっと前までは、アメリカの動画配信サービスが、世界各国で視聴されるなんて考えられなかったわけです。プラットフォームはアメリカのサービスでも、世界中で同じものを見ることができる。もちろん言語の問題はあるので、それぞれの国・地域の言語に対応する必要はありますが、それさえクリアすれば同じコンテンツをどこでも見たり聴いたりできるようになりました。つまり、音楽ビジネスというものは、昔はある国や地域の中だけで成り立つ、いわば「ブロック経済的」なものだったわけですが、デジタル化によって一気にグローバルなものになったのです。考えようによっては、誰もがアーティストとしてグローバルに活躍できるようになったとも言えます。
音楽ビジネスの規模でいうと1位がアメリカ、2位が日本という時代が長らく続いています。ですが、アメリカのアーティストはグローバルに売れている一方、日本のアーティストの多くは日本市場だけで売れている。それなのに日本が世界2位の市場規模を誇っていることは非常に特徴的です。それでもかつては、音楽ビジネスがブロック経済的なものでしたから、それでも良かったわけですが、今では例えば韓国などがグローバル市場を狙っていろいろと仕掛けてきている。そんな中で、日本の地位は徐々に脅かされています。日本の音楽業界も今後は、もっとグローバル市場のことを考えながらやっていかなければいけないのではないかと思っています。
さらに成長が見込める「シンクロビジネス」マーケット
Q.これからの音楽ビジネスを見据えたときに、特に皆さんが注目しているのはどのような分野でしょうか。
保坂:全世界の音楽市場の推移を見ると、2000年代に入ってからCDやDVDの販売は低下しており、一方でストリーミング配信による売り上げは2010年頃から増加し続けています。結果として、トータルで見ると音楽市場全体は拡大し、2021年には3兆円を超える規模へと成長しました。そしてその音楽市場の中で、前編で殿村さんが説明した「シンクロビジネス」による売り上げは、全体のわずか2.1%。さらにその中身を見ると、ほとんどがハリウッドを中心とした映画における音楽使用にまつわるものになっています。企業の広告・マーケティング活動に関連したシンクロビジネスが展開されているのは世界でも日本だけと言っても過言ではないくらい、非常に特殊なビジネスが成立していると言えるのです。
しかし一方で、このマイナーなシンクロマーケットには、今後大きな可能性があるのではないか、と私たちは考えています。デジタル化が進み、動画配信サービスやSNSなどのデジタル・コミュニケーション・プラットフォームが多数生まれたことで、デジタル動画の数は爆発的に増えています。そこに動画があれば動画に音楽をプラスしていきたい、という人たちもどんどん増えてきます。動画配信サービスに投稿するための映像を作ると、そこに音楽を入れたい。でも、音楽の知識は専門的なので、素人にはどうしたらいいか分からない。だからプロに相談したい。そういったニーズが広がっていくのではないでしょうか。これまでは、映像を作って発信するのは大手企業が中心でしたが、今や個人でも発信できますし、インターネット上でビジネスを展開している人もたくさんいます。音楽というのはますます求められるコンテンツになるのではないでしょうか。
Q.広告マーケティングと音楽との「シンクロビジネス」が成立していることは世界的に見て珍しい状況だ、というご指摘がありました。なぜ日本ではこのようなビジネスが成立しているのでしょうか?
保坂:いろんな理由があるとは思いますが、私が個人的に感じているのは、日本とそれ以外の国々との「広告の作り方の違い」が1つの要因になっているではないか、ということです。
というのも、日本の場合、広告というのはどちらかと言うと「クライアントのもの」という考え方が主流で、何をするにしてもクライアントの許諾が必要となります。しかし、アメリカを中心としたグローバルな広告市場においては、「広告にも著作権があり、その版権は広告代理店や制作会社にある」という考え方が主流です。そしてクライアントは、広告の制作費を払うというよりは、その使用料を支払う、という構造になっています。
そういったベースがあるので、特に海外においては、広告やCMの制作は、広告代理店や制作会社が「訴求ポイントを軸に、自分たちの作品を作っていく」という考え方で進んでいきます。そこに有名な楽曲が使用されるとか、アーティストがタイアップ的に起用されるというのは、それこそ「スーパーボウル(アメリカンフットボールプロリーグの優勝決定戦)」のような国民的イベントのCMでもない限り、本当に珍しいケースとなります。このことは、海外の広告を見ていただければお分かりになるかと思います。
一方で、日本における広告、とりわけCM制作は、企業の商品サービスに結び付く接点として、有名タレントやアーティストを起用する文化が定着しています。これは、単一民族である日本人の特徴として、消費者に共有された共通のイメージしやすいアイコンが求められて来たのではないかと考えています。その結果、国内外の有名アーティストの楽曲が、他の国と比較して顕著に広告表現で使用されることとなり、日本の広告における音楽の「シンクロビジネス」の発展につながったのではないかと思っています。
殿村:現場で仕事をしていて感じるのは、海外のメジャーアーティストでも「日本のCMであれば許諾する」という人が多いように思います。彼らの間でも「日本のCMのクオリティ」を認識しているように思う事例を何度も経験しています。アメリカのスーパーボウルのように本当に特別なものでなくとも、日本のCMはそのような音楽を受け止めるクリエーティビティが非常に高い、ということを見てきているのでOKが出やすい土壌はあるように感じます。また、そこにシンクロビジネスが成立していることも知っていますから、安心して楽曲を提供できる、という状況になっていると思います。
Q.今後の音楽業界について、皆さんはどのような展望を持っていらっしゃいますか。
保坂:音楽と一口に言っても、本当にいろんなタイプのものがあります。もちろんプロフェッショナルが作る音楽もありますし、今では楽譜なんてなくても、作ろうと思えば誰でも簡単に作れてしまいます。さらに、音楽はそれ自体が主役のコンテンツにもなりますし、脇役的に映像を引き立てたり、リアルな空間を演出したり、というような役割も担うことができる。音楽というと、特定の楽曲やアーティストを取り上げて「こういうものが流行る」とか「あのアーティストの音楽はいい」とか、そういった世界が思い浮かぶかもしれませんが、実はもっと身近なものですし、生活のありとあらゆる領域に溢れているものでもあります。映像でも必要、スポーツの試合でも必要、レストランでも必要、と本当にいろんな場面で必要とされる。そこに、音楽とのマッチングに対するニーズがありますし、このニーズはますます拡大していくのではないか、と期待しています。その観点で言えば、私たちは今まで「広告」という領域で音楽のシンクロをやってきたわけですが、この「シンクロ」を拡大していく領域は他にもたくさんあるのではないか、と考えています。
同時に、やはり音楽に携わって仕事をしている以上、「音楽の感動を広げたい」という想いはずっと持ち続けています。そして、その出口は何であってもいい。「広告」という出口だって、音楽の感動を広げる大きなきっかけになっているのではないでしょうか。このような「出口の方向を探る」というのも、自分たちのミッションではないかと。これからますますコミュニケーションが多様化する中で、私たちがシンクロビジネスで培ってきた専門性が生かせればいいな、と思っています。
今回のインタビューでは、音楽業界の変化とともに、DMEのユニークネスともいえる「シンクロビジネス」についても話を聞きました。
「CDが売れなくなった」と言われて久しくなっています。日本国内のCD(12cm)の販売数は、1998年に過去最高の3億291万3,000枚を記録しましたが、その後売り上げは急速に減少し、2018年には1億3,720万5,000枚と、20年間で半分以下にまで縮小しました(一般社団法人日本レコード協会「音楽ソフト 種類別生産数量推移」より)。しかし一方で、ストリーミング配信など「新しい音楽の楽しみ方」を加えると、世界的には音楽市場そのものは拡大している、ということもまた事実です。そして保坂氏が指摘したように、デジタルコンテンツが増加することで「音楽が必要とされるシーン」はむしろ増えています。メジャーアーティストによるビッグセールスが減った一方で、音楽というビジネスそのものはむしろニーズもマーケットも拡大している、ということは重要な事実。つまり、音楽業界はむしろ大きなチャンスの真っただ中にあるとも考えられるのです。
今回はDMEの皆さんに、音楽業界の変化について聞きましたが、ここで視野を広げれば、この音楽業界が示しているものは、デジタル化によってビジネス構造改革が起こり、既存のプレーヤーが課題を抱える一方で、確実に新たなニーズやチャンスも生まれるという、どの業界にも起こり得る「トランスフォーメーション」そのものではないでしょうか。「変化と課題」は、「新たなチャンスと成長」の入口でもあります。もしあなたが何らかの課題に直面しているとしたら、その裏側に次の成長につながるヒントが隠されているかもしれません。