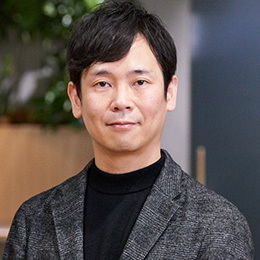2023年1月5~8日、全米民生技術協会(CTA)が主催するテクノロジーショー「CES(シーイーエス)2023」がアメリカ・ラスベガスで開催されました。1967年から続く「CES」は、世界最大規模のテクノロジー見本市。コロナ禍以前よりは減少したものの、今年は3,200社以上が出展し、最新テクノロジーの展示が行われました。
2011年以降、毎年CESを定点観測してきた株式会社 電通 未来事業創研ファウンダー 吉田健太郎氏による今年の概況、テックトレンドの分析をお届けします。
今年のテーマは「Human Security for all(人間の安全保障)」
Q.吉田さんは、2011年から「CES」を見続けているそうですが、「CES 2023」の率直な感想をお聞かせください。
また、かつて「CES」は「Consumer Electronics Show」、つまり家電ショーという名称でした。ですが、2015年に主催団体がCEA(Consumer Electronics Association:全米家電協会)から、CTA(Consumer Technology Association:全米民生技術協会)へと名称を変更し、イベント自体も2016年から「CES」が正式名称になりました。それに伴い、家電ショーからテクノロジーショーへとコンセプトが変わり、2020年ごろから社会貢献・環境貢献というテーマを強く打ち出すようになりました。素晴らしい流れではありますが、風呂敷を広げすぎたため、方向性が少しぼやけてしまったようにも感じます。

Q.2020年ごろから社会・環境貢献の重要性を強く打ち出すようになったとのことですが、その流れで言うと今年の「CES 2023」の目玉は環境対応テクノロジーだったのでしょうか。
また、今年は「Human Security for all(人間の安全保障)」も大きなテーマでした。例えばフードセキュリティ(安心安全な食事)、ヘルスケアなどですね。2050年には世界人口が約20億人増えると言われています。人口100億人時代に向けて、フードセキュリティを担保するためには食糧生産の効率化が必要であり、そのためのテクノロジー開発が急務です。他に命の安全を保障するテクノロジーもトレンドですね。先進国では高齢化が進んでいるため、単身の高齢者が急増しています。何かあったときにすぐに反応するセンサー、生体情報を常時取得するデバイスなども見られました。
基調講演に農機メーカーが登壇。「環境貢献と事業成長の両立」を訴える
Q.「CES 2023」で、押さえておくべきトピックやテクノロジーはありましたか?

Q.2023年はどなたが登壇したのでしょうか?
Q.キーノートでは、どのようなメッセージを伝えたのでしょうか。
ですが、ジョンディア社がまずアピールしたのは、「テクノロジーを使うことで、農家のコストが下がり、収穫量が増える」という点でした。環境貢献をしながら、さらに事業成果も上がると明確に示したわけですから、他の業界にとっても1つのモデルケースになりますよね。
これからの企業にとって重要なのは、社会貢献と事業成長を両立させてサステナブルにしていくこと。大量生産・大量消費を促すばかりでは地球環境を悪化させますし、自社の価値も下げることになります。社会貢献を第一義にしつつ、サステナブルに収益化しようというメッセージをテクノロジー業界が訴えかけることに大きな意義があると思いましたし、個人的にも深く共感しました。
SDGsやサステナビリティへの意識が高まり、テクノロジーによる社会課題や環境問題の解決をテーマに掲げてきた近年の「CES」。今やテック企業にとって、社会・環境貢献の視点は欠かせないものとなっています。これまで環境価値と経済価値はトレードオフの側面があると捉えられてきましたが、今年の基調講演では「環境貢献と事業成長の両立」がアピールされ、テック企業が目指すべき未来があらためて明確になったのではないでしょうか。後編では、吉田氏が「CES 2023」で特に注目したテック領域、マーケターへのアドバイスをお届けします。
吉田氏が創設した電通の「未来事業創研」では、企業が目指す未来を可視化し、実現に向けたプログラムを提案しています。未来のライフスタイルや最先端のテクノロジーにご興味のある方は、ぜひCONTACTからご連絡ください。