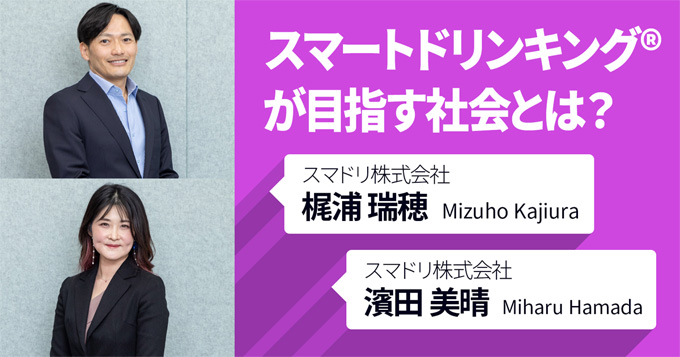次なる市場の担い手として、消費をけん引していくと期待されているZ世代。デジタルに慣れ親しみ、多様な価値観を持つ彼らの存在を抜きにして、今後のマーケティングを考えるのは難しいでしょう。
株式会社電通プロモーションプラス内で組織された「若者消費ラボ」は、若手メンバーを中心とした企画調査型ユニット。Z世代当事者も多く、世代ならではの視点で若者向けの販促課題のソリューションを提供しています。今回は、所長を務める五十嵐響介氏、若手メンバーの高橋ひなの氏、齋藤晃平氏の3名にインタビューし、若者消費ラボの取り組みなどについて詳しく話を聞きました。
若者の買い物体験を設計するプランナー集団
Q.若者消費ラボの中で、五十嵐さんは所長というポジションを務めていますね。まずは「若者消費ラボ」とはどのようなチームなのか、立ち上げの経緯について教えてください。
Z世代やミレニアル世代は、消費の次期コアであると言われています。さらに、近年は「多様性」もキーワードになっている。多様性あふれる社会で、特定の商品やサービスを買っていただくためにはどうすればいいのか。そうした視点から、若者の買い物体験を設計し、企業が抱える販促課題を解決するソリューションを提供するチームとして活動しています。

Q.立ち上げ当時は数名のチームだったとのことですが、現在は、どのようなメンバーで構成されているのでしょうか?
チーム内は「ユニット」で担当領域が分けられていて、現在は「SNS×店頭」「食」「コスメ」「アイドル」「コンテンツ」「SDGs」の6つがあります。食やコスメはZ世代にとって買いやすい消費財ですし、SDGsもまた、Z世代と切っても切り離せないキーワード。そしてアイドルやコンテンツが持っているパワーも強く、Z世代に響いていますよね。「自分たちがやりたいことは何か」という視点で、メンバー同士がフラットに話し合い、集まった意見をラベリングした結果がこの6つの領域だったのですが、結果的に若者消費ラボが扱うテーマとしてふさわしいものになったと思っています。
事例収集や自己分析を通して、Z世代の購買体験を調査
Q.齋藤さん、高橋さんは現在、入社2年目とのことで、まさにZ世代に当たりますよね。若者消費ラボの中では、どのような役割を担っているのでしょうか?

SNS購買自己分析とは、Z世代である自分がSNSをタッチポイントにして、実際に購買につながった体験を、カスタマージャーニーを描くような形で資料化するというもの。私自身の購買体験を振り返って、「こういうところが購買に至ったポイントじゃないか」という、リアルな分析をしています。
例えば、私が実際に服を買った時のフローを挙げると‥‥‥
①SNSでフォローしているインフルエンサーの投稿を見て「こんなブランドがあるのか」と興味を持つ
②ブランドのアカウントを見に行くも、購買にはつながらなかった
③後日、そのブランドの服を店頭で発見
④フォロー中のインフルエンサーの投稿で見掛けた、というタッチポイントの記憶から、その場で衝動買いした
このフローにおけるポイントは、そのブランド自体を知らない人は「投稿したインフルエンサー」=「その服のブランド力」と認識するという点です。私はそのブランドについて他の情報を持っていませんでしたが、好きなインフルエンサーが着ているということだけで十分な購買の理由となりました。そこで、商材によっては「インフルエンサーも着ています」という店頭POPや投稿画像をディスプレーして、SNSと店頭を連動させるのも効果的では、と分析しました。こういった形で定期的に、各々の購買体験についてまとめ、ソリューションとして生かせるようにしています。
Q.そこから実際の提案・実践にその知見を生かしていくような活動をしているのですね。高橋さんは、どのような活動をされていますか。

「食」ユニットについてお話すると、実際の食に関する販促施策の事例を取り上げて、その概要や「プロモーションの反応としてどういう結果があったのか」「この施策が若者に刺さるポイントはどんなところだったか」などを言語化して、実際の案件へのブリッジができるように日々情報収集に励みながら、「次の施策」に生かせるポイントを抽出しています。その上で、実際に食に関するご相談を頂いた際には、先ほどのインプットを踏まえて、若者に刺さるプロモーションをご提案できるよう業務を進めていきます。
Z世代やミレニアル世代のメンバーを中心に構成された若者消費ラボ。当事者としての目線や実際の体験から、若者のインサイトを捉えた販促課題の提案を行える点がチームの特長です。後編では、そんな若者消費ラボが現在、注目しているという「エモ販促」について深堀りしていきます。
価値観の多様化が進むZ世代の複雑化したインサイトを捉えるのは難しく、企業として若者に向けたマーケティングでお悩みの方は多いのではないでしょうか。「Z世代の来客数を増やしたい」「SNSを活用した販促を強化したい」などご要望があれば、CONTACTよりお気軽にお問い合わせください。
※本記事の記載内容は2023年3月取材当時のものになります。