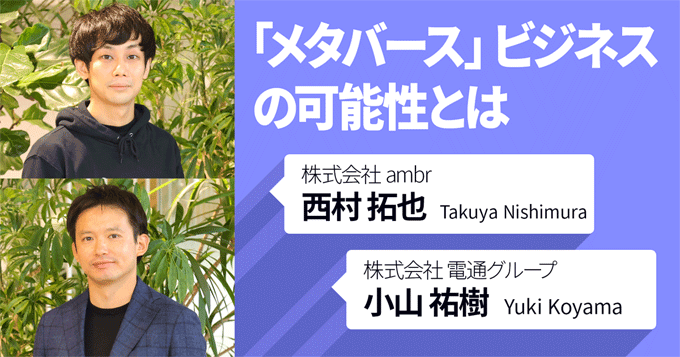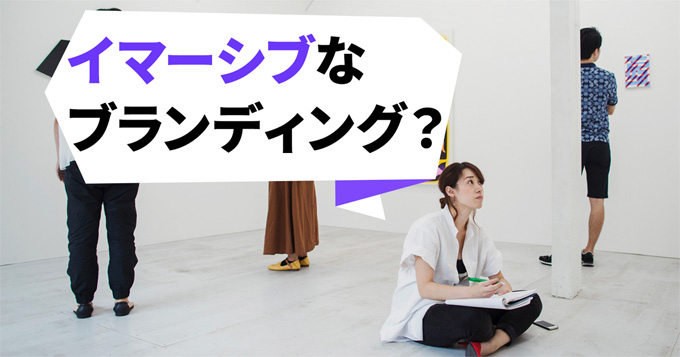街の交差点に点在する画面、駅通路の巨大モニター、ライブ会場の大型スクリーンなど、ここ数年で映像の活用領域は驚異的な速度で進化を遂げ、日常・非日常を問わず人々の生活に浸透しています。そうした中、株式会社IMAGICA GROUPと株式会社電通ライブという、クリエーティビティとテクノロジーを兼ね備えた2つのチームがタッグを組み、あらゆる空間において映像表現による新たな体験を創造するソリューション「UN-SCALABLE VISION」(アンスケーラブルビジョン)の提供をスタートしました。
テクノロジーの進化によって、「空間」はこれからどのような可能性を発揮するのか。今後どのようなビジネスが期待できるのか。IMAGICA GROUPの中でも映像体験設計分野に特化した株式会社IMAGICA EEXの諸石治之氏と、電通ライブの前澤克文氏に話を聞きました。前編では、「UN-SCALABLE VISION」立ち上げの経緯を中心にお届けします。
コロナ禍で急激に進化したテクノロジーが新たなメディアを生み出した
Q.「UN-SCALABLE VISION」に携わった両社は、どちらもこれまで数多くの映像コンテンツを創出してきた実績がありますよね。それぞれどういった強みがあるのかをお聞きしたいと思います。まずは、IMAGICA GROUPについての概要と、諸石さんのご経歴からお話しいただけますか?
私自身は、元はテレビの映像制作会社で、音楽やアート、科学番組の制作や高精細メディアを活用したコンテンツのディレクションをする仕事をしていました。その中で、メディアの進化や拡張の可能性を感じており、映像コンテンツをテレビ以外の分野で展開することに関心を持つように。以降は、博覧会などの大型イベントのコンテンツプロデュースなどを手掛け、やがてIMAGICA GROUPに参加することになりました。現在は、2020年7月に立ち上げたグループ会社のIMAGICA EEXで、エンターテインメントとテクノロジーを掛け合わせた事業に取り組んでいます。

Q.IMAGICA EEXについてもう少し詳しく教えていただけますか。2020年7月といえばまさにコロナ禍であったと思いますが、その時期にエンターテインメントの新しい会社を立ち上げられた、ということでしょうか。
映像と通信の力を合わせたエンターテインメントで社会課題に向き合うことを目標にスタートして、最初はライブ配信が主な事業。そこでXRやヴォルメトリックキャプチャ(撮影した画像から3Dデータを構成する技術)などを活用して、映像だからできる新しいライブエンターテインメントを打ち出していきました。見てくださった方々も、新しいライブ体験として感じてくださいました。最近では、メタバースやデジタルツイン(物理的な空間をデジタル上に再現すること)などの概念を取り入れつつ、新たな体験価値の提供を進めています。
Q.前澤さんは、電通ライブでどのような仕事をされてきたのでしょうか。
そういう仕事に取り組んでいると、「大画面で何か表現したい」「スペースに合った変形画面にコンテンツをつくりたい」といった問い合わせが次々とやってくるようになりました。これは「空間×演出×映像」という新しいソリューションが必要かもしれない、と考え始めたところで、諸石さんと出会ったんです。これが「UN-SCALABLE VISION」の発端と言えますね。
IMAGICA GROUPさまとは以前から一緒に仕事をする機会があって、映像編集や配信技術の高さがトップクラスであることは実感していました。それにIMAGICA EEXは、コロナ禍を経てさらにチャレンジングな取り組みで、エンターテインメントを進化させようとしていたので、ぜひ協業したい、とお声掛けしたというわけです。

スタート時点から総合的な完成図が共有できるオールインワンチームの強み
Q.まさにお互いの強みとニーズが合致しての今回のソリューションチームの結成に至ったのですね。続いて、「UN-SCALABLE VISION」の画期的なポイントを教えていただけますか。
電通ライブに寄せられる、大型化・多様化する映像制作のニーズの高まりと、IMAGICA GROUPが取り組む最新のテクノロジーを導入した新たな映像表現への挑戦が融合することで、今までにない空間演出創出への期待が高まります。後編では、「UN-SCALABLE VISION」リリース後の反応や、具体的にどういったソリューションとして役立つのか、といった点を中心にひもといていきます。
展示会やイベントで大型映像を用いた印象的な演出を取り入れてみたい企業の方や、自社の所有するビルやスペースを活用したいと考えている企業の方。ぜひお気軽にCONTACTよりお問い合わせください。