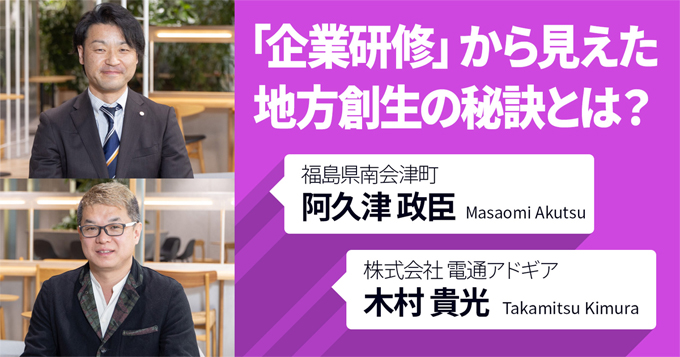持続可能な社会を実現するために、必要な視点や発想とはどのようなものなのか。そのヒントを得るために、企業のサステナブルなビジネス創造をサポートする株式会社 電通 サステナビリティコンサルティング室のメンバーが、次世代のオピニオンリーダーを訪ねてお話を伺う本企画。第2回は緑と調和した都市「ガーデンシティ」を掲げるシンガポールで、実務と教育の両視点より活躍されるランドスケープアーキテクトの遠藤賢也氏に、サステナビリティコンサルティング室の南木隆助氏がインタビューしました。前後編の2回にわたって、お届けします。
「自然と対峙する」のではなく、「自然をいなす」まちづくりへ
南木:遠藤さんは長年、ランドスケープアーキテクトとしてシンガポールを中心に自然環境と調和したまちづくりに取り組まれ、現在はシンガポール国立大学の建築学科で講師を務めています。実は私と中学時代からの友人なんですよね。私は建築系の学部出身で、電通でも設計建築系のプロジェクトに関わってきました。商業施設や学校空間の設計、幼稚園などの建築のディレクションを行い、サステナビリティコンサルティング室でもまちづくりや駅開発のプロジェクトに携わっています。遠藤さんの仕事と重なる部分もあり、今日はお話を伺うのをとても楽しみにしていました。まずはランドスケープアーキテクトとはどのような仕事なのか、教えていただけますか。
遠藤:皆さんがまずピンとくるのは公園や広場,庭園など、水や緑があって、人々が自由に楽しめる屋外空間を設計する人のことではないでしょうか。日本では造園家という言葉に相当するかもしれませんね。ただ、ここ最近20年近くの中で考え方が変わってきて、サステナビリティやエコロジーの観点を重視し、自然が持つ多様な力をうまく取り入れて都市開発を行う潮流が生まれてきました。そのため、単に屋外空間を設計するだけではなくインフラ整備、中長期的なまちづくりとの融合といった視点が不可欠になり、私の仕事もどんどん複合的に、多様な要素を考えなくてはならないものになってきています。

南木:かつて都市開発は、自然と切り離して行われてきましたが、現在の都市開発は自然との融合、自然をうまく活用することを目指していると言うわけですね。そのような変化を遠藤さんは、「自然との対峙から自然を“いなす”方向へ」と表現されていますよね?
遠藤:私の研究テーマがランドスケープと防災であるため、結果的にそのような表現となりました。これまでの都市開発というのは元々の自然環境をリセットして、例えば河岸をコンクリートで固めることをしてきました。でもそのような場所は変化もなくてつまらない、そしていつか自然界から大きなしっぺ返しがやってくることに気付きます。都市開発もインフラ作りも、災害などの転換点を経て、「自然との対峙から自然を“いなす”方向へ」シフトし始めるのではないかと思います。今は開発に資金を提供する国際金融機関も、レジリエンスやサステナブルの観点を重視しており、自然と調和するデザインを評価するようになってきています。開発余地が多く、めまぐるしい早さで開発が進む東南アジアの都市では、日本や欧米などの先進国とは別の、いわば最初からサステナブルな観点を重視した開発を進めていくと思っています。こうした潮流に日本も遅れをとってはまずい、という危機感を感じています。
国際競争力をつけるためのブランディング戦略としての「ガーデンシティ」
南木:シンガポールでは、国家主導で1960年代から「ガーデンシティ」を掲げ、都市の緑化を進めてきましたね。屋上緑化や壁面緑化による、緑と建物が融合した美しい景観が何よりの魅力です。
遠藤:シンガポールは世界で最も緑被率の高い都市の1つと言われています。ガーデンシティ構想の初期は、都市の見栄えを良くする対外的な狙いが大きかったようです。とにかく都市の緑の量を増やすことが目的だったのですが、90年代くらいから質の追求へとフェーズが変わっていきます。単に景観として緑が多いだけでなく、市民が緑と触れ合い、潤いを感じたり、心豊かに暮らせたりする空間づくりへ移行していきます。今はさらにそこから、自然が持つ摂理を都市に取り入れる方向へ進化しています。例えば道路沿いの街路樹なども、背の高いものから低いものまで自生種を混ぜて植えることで、多様な生物が行き交う「コリドー」が生まれます。あるいは、コンクリ三面張りの都市河川をいわゆる「多自然型」に改修するプロジェクトもそうですね。生物多様性に寄与しながら、不必要なメンテナンスを減らし、ヒートアイランド現象の緩和にもつなげる。そのように複合的なベネフィットが得られるよう、自然界のシステムをうまく取り入れることが最近のトレンドです。シンガポールは、冒頭のフレーズを上手に実践している国なのかもしれません。

南木:「ガーデンシティ」は、今やシンガポールのシンボルであり、そこで暮らす人のアイデンティティーにもなっているようですね。このような自然と調和したまちづくりは、そもそもどのような目的で行われてきたのでしょうか。
遠藤:シンガポールは資源の少ない国なので、リーダーたちはいかに都市としての国際競争力をつけるかに、ものすごい危機意識を持っています。「人が資源」なので世界から優秀な人材を集めるために、シンガポールという都市の魅力をいかに上げるか。そのための知恵を常に絞っているのです。シンガポールのまちに緑や水をうまく取り入れ、それらを身近に感じられる環境をつくることも、その一環なのだと思います。つまり「ガーデンシティ」はシンガポールの成長戦略であり、ブランディングであるとも言えます。
トップダウンで実験的な緑化プロジェクトを行うシンガポール
南木:シンガポールでは、自然が持っている機能をどう都市に取り込むかを、ある種実験しながらやっているというのも、すごく面白いですよね。

遠藤:それができるのは、シンガポールが機動力のある都市国家であるからではないか、と私は思います。そのため、官主導でリスクのあるビッグプロジェクトも大胆に行うことができるのではないでしょうか。実は屋上緑化1つとっても、どんな土壌や植栽が適しているのか、それによってどれくらい熱環境が改善され、開発者にどの程度のベネフィットがあるのかは、まだまだ分からないところも多くあります。シンガポールではそのようなプロジェクトも実験的にどんどん進め、そこからフィードバックを得て、次のプロジェクトにつなげていく。そのようないい意味での試行錯誤が行われているように見られます。
南木:実験を重ね、精度を上げていくことで、より魅力的な都市をつくっていくのが、シンガポールのサステナブルな開発なのですね。
遠藤:ランドスケープアーキテクトは開発ありきの職業です。単に自然環境を保護することではありません。デザインを行う人、精度をモニタリングする人、計画を進める政策立案者など、サステナブルな考えを持つことは、ランドスケープの視点から都市開発を考えることと大差ないと考えています。人口減少が問題になっている日本にいると忘れがちですが、世界のほとんどの国々はまだ開発途上であり、東南アジアでもまだまだ開発は必要ですし、今後も続くでしょう。その中でサステナブルに開発を進めていくにはどうしたらいいのかを考えていくために、ランドスケープアーキテクチャの重要性も高まっているのだと思います。
前編では自然と対峙するまちづくりから自然を“いなす”まちづくりへの変化や、「ガーデンシティ」を掲げるシンガポールでの自然と調和した都市開発、実験的な緑化プロジェクトについて伺いました。後編ではこれからのまちづくりや企業のサステナブルな取り組みで大事なポイントを、遠藤氏に伺います。
シンガポールで行われている、自然の力を上手に取り入れた持続可能な開発は、日本の地方創生や地域活性化にもさまざまなヒントを与えてくれます。電通ではさまざまな企業などと連携しながら、サステナブルなまちづくりの支援もしています。ご興味のある方は、CONTACTよりお気軽にお問い合わせください。