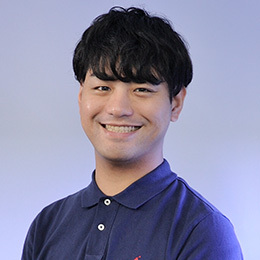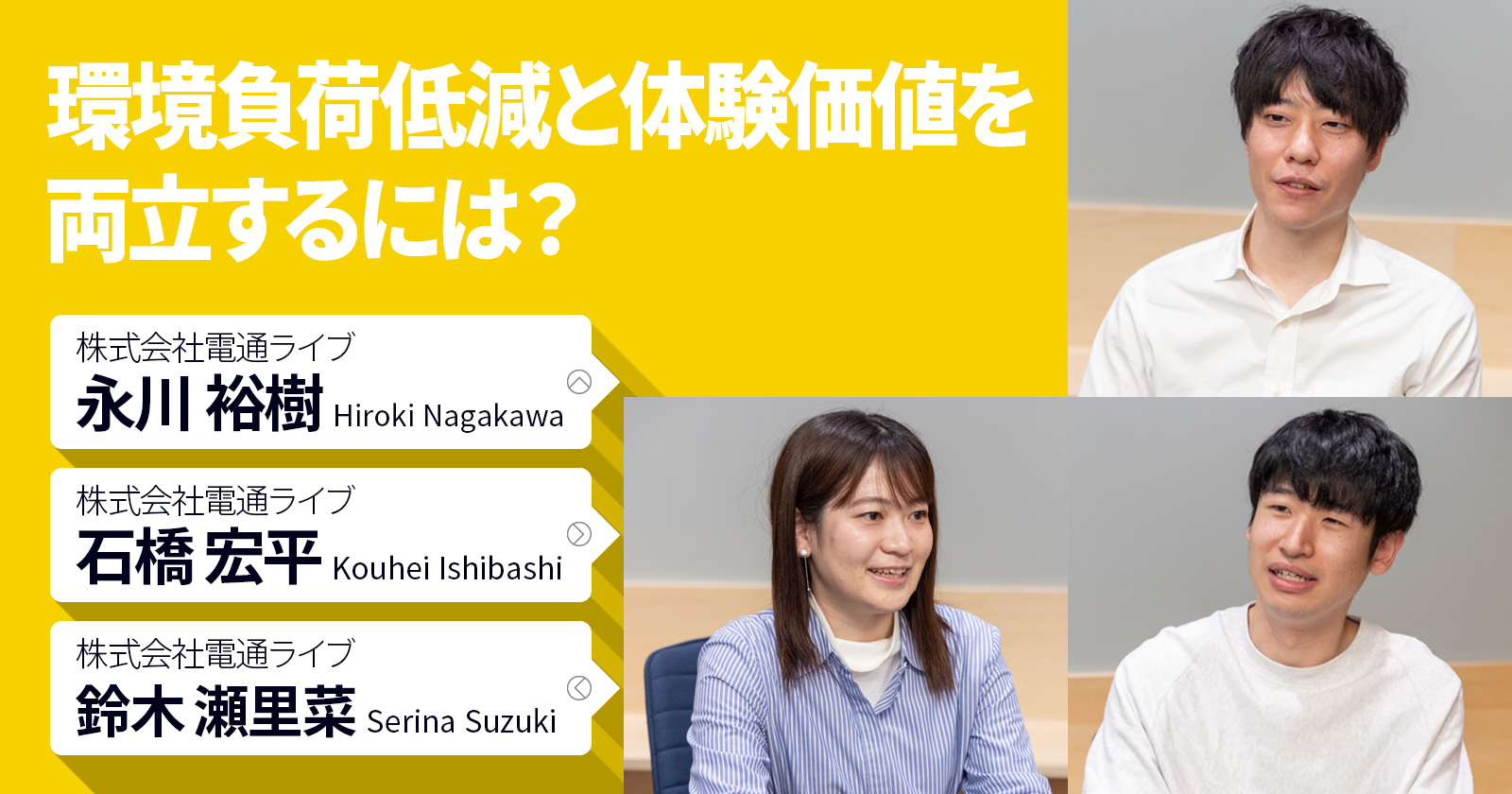これからのサステナビリティビジネスにおける課題は何なのか。新しい技術やソリューションにはどのようなものがあるのか。本シリーズでは株式会社 電通においてサステナビリティ視点での企業変革・事業変革推進をサポートする専門組織「サステナビリティコンサルティング室」のメンバーが、この分野のオピニオンリーダーを訪ね、お話を伺います。
第1回は環境移送技術というユニークな技術で「100年先も人と生物が共生していける社会」を目指す、株式会社イノカCOOの竹内四季氏に、サステナビリティコンサルティング室の澤井有香氏がインタビューしました。前後編の2回にわたり、お届けします。
自然の海をそのまま切り取り、陸上に再現する「環境移送技術」
澤井:サステナビリティコンサルティング室として、さまざまな企業をご支援する中で、環境保全と企業活動を両立させる上では、まだまだ新しい視点やイノベーションが必要だと感じています。とりわけ「生物多様性」という分野は気候変動問題などと違い、数値化しにくいため、そもそも現状を把握できていない企業も少なくないようです。そういった意味で、海洋環境を人工的に再現し、「海を見える化」するイノカさんの事業には非常に興味を抱いていました。まずは、イノカさんがどんな事業を展開されているのかから、紹介していただけますか。
竹内:イノカは2019年に設立され、現在、5期目を迎えています。もともと東京大学でAIを研究していた、現CEOの高倉と、独自に海の生態系を研究し、サンゴ礁を育てていた増田の2名で創業した会社です。今はインターン生を含めて社員は30人ほど。事業は研究開発事業と教育イベント事業の2軸で、そのバックボーンにあるのが独自開発した環境移送技術です。

澤井:環境移送技術とはどのようなものなのでしょうか。
竹内:自然環境を水槽などの閉鎖空間内に再現し、複雑な環境パラメーターを制御・モニタリングすることで、自然環境をモデル化する技術です。まるで自然界の海を切り取って、そのまま陸上の室内空間に持ってきたような再現レベルを目指しています。海の中に差し込む太陽の光や波の中に含まれている物質まで、人工的な機材を組み合わせて再現しています。例えば、光は沖縄の海の光のスペクトルを測定し、波長や強さを調整した上で、日の出から日の入りまでの変化も再現しています。波にはサンゴやさまざまな生物が成長するのに必要な栄養塩、カルシウムやマグネシウムが含まれています。

澤井:そのように、水槽の中にリアルな海を再現することにはどのような意義やメリットがあるのでしょうか。
竹内:一番のメリットは、自然界の海では取得できないようなデータを取り、研究に活用できることです。自然の海で環境データを取るには、毎日海に出かけて、同じ地点でセンサーを確認するなど、大変な労力がかかります。データを取りにくい場所があったり、天候の変化でデータが乱れたりすることもあります。ところが、環境移送技術によって海の環境を再現した水槽であれば、そのような手間がかからず、欲しいデータに応じて、光などさまざまな条件を調整して実験を行うことができます。つまり、欲しいデータを少ないコストで取ることができるようになるので、研究の大幅なスピードアップが可能になります。
また、環境改善に役立つ物質を特定するために、海に直接化学物質を投与するような実験は、本物の自然環境ではやりづらい面がありますよね。でも当社の水槽を使えば、企業の生産活動で生じるさまざまな副産物などを安心して試すことができます。環境移送技術を使うことで実験の幅が広がり、海洋問題のメカニズムの解明や生物多様性の保全に貢献できると考えています。
また、環境改善に役立つ物質を特定するために、海に直接化学物質を投与するような実験は、本物の自然環境ではやりづらい面がありますよね。でも当社の水槽を使えば、企業の生産活動で生じるさまざまな副産物などを安心して試すことができます。環境移送技術を使うことで実験の幅が広がり、海洋問題のメカニズムの解明や生物多様性の保全に貢献できると考えています。
10万種の生物に影響を与えるサンゴ礁は、生物多様性の中心的存在
澤井:海の環境を再現するという取り組みの中でも、特にサンゴ礁の再現に力を入れてきたとお聞きしました。その理由を教えていただけますか。
竹内:サンゴ礁自体は海の面積の0.2%ほどを占めるに過ぎない存在ですが、そこに25%の海洋生物、10万種弱が暮らしています。ですから、もしサンゴが全て死んでしまうと、10万種弱の海洋生物が影響を受けることになります。サンゴ礁は海の中の生物多様性の中心的な存在で、生物多様性を計測する物差しになるのです。

澤井:サンゴは、海の生物多様性を見る上で、重要な存在なのですね。そんなサンゴが、あと20年ほどで70〜90%死滅するかもしれないと言われていますよね。
竹内:はい。気候変動によって海の温度が上昇すれば、サンゴ礁は甚大な影響を受けるでしょう。そもそもサンゴは繊細な生き物で、わずかな環境変化ですぐに死んでしまいます。だからこそ、人工的に飼育することがすごく難しいと言われてきました。そんな中、当社の増田はただただ生き物が好きで、自宅の水槽で趣味としてサンゴ礁の再現に取り組んでいました。サンゴを飼育する水槽の環境を微妙に変え、ひたすらPDCAを回す。そんな地道で職人的な試行錯誤の結果、サンゴの飼育に成功し、それが環境移送技術につながりました。サンゴをこんなふうに育てられる人は、おそらく日本でも数えられるほどしかいないはずです。増田は、「CAO(Chief Aquarium Officer:最高アクアリウム責任者)」という肩書きで、イノカの生態系技術の根幹を担ってくれています。イノカは2022年2月に世界初となるサンゴの人口産卵実験にも成功しましたが、現在はこうした技術にIoTやAIを組み込み、より汎用性あるソリューションとして提供しています。
自社製品が生態系へ与える影響を図るニーズが増加
澤井:サステナビリティ経営を掲げる企業は増えていますが、今まではどちらかというと、気候変動問題や脱炭素などを意識した取り組みが多かったように思います。ですが最近では、ビジネス界でも生物多様性への取り組みに関する気運が高まっていると感じます。さまざまな企業からの相談も増えているのではないですか。
竹内:そうですね。気候変動問題においては、2015年に「TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)」という国際的な組織が設立されました。これは、企業が気候変動に対してどのように取り組んでいるのか、CO2排出量などを具体的に開示することを推奨するタスクフォースです。これに続く流れとして、2021年には企業活動が自然資本や生物多様性に与える影響を開示するように働きかける「TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:自然関連財務情報開示タスクフォース)」の動きが始まっており、企業も対応を迫られています。そのため、当社にも「TNFDに対応するために、自社製品の生物多様性に対する影響度を測定したい」といった相談をよくいただくようになり、実際にTNFDのデータアナリストという立場で企業をご支援することが増えています。TNFDに関するさまざまな企業事例を聞き取り、動向を把握しながら、企業が生物多様性に関するグローバルスタンダードに対応するためのサポートをさせていただいています。
澤井:弊社にも生物多様性へのご相談が増えてきている一方で、どういった取り組みをすべきか具体的なイメージが湧かないといった声もあります。企業との協業や共同研究の具体的な事例としては、どのようなものがありますか。

竹内:例えば、皆さん海水浴を楽しむときには、当たり前のように日焼け止めクリームをお使いになると思います。ですが、この日焼け止めクリームがどれくらいサンゴ礁に影響を与えるのか、ということは、実はほとんど研究実績がありません。そこで、日焼け止めクリームがサンゴに与える影響をきちんと調べるというプロジェクトを、ある企業と提携して取り組んでいます。他の業界に対しても、サンゴに対する影響を適切に評価して開示し、ルールを作ることが企業価値の向上につながるという提案をさせていただいています。
また、鉄鋼会社と連携して、製鉄の過程の副産物として生まれる物質を海に投与することで、サンゴの生育を良くしたり、環境を浄化したりするような研究も行っています。
また、鉄鋼会社と連携して、製鉄の過程の副産物として生まれる物質を海に投与することで、サンゴの生育を良くしたり、環境を浄化したりするような研究も行っています。
澤井:自社製品が海にネガティブな影響を与えないかという観点だけではなく、海や海洋生物が新たな産業を生み出す可能性にも注目が集まっているのですね。
竹内:そうですね。海洋に関連した経済活動は「ブルーエコノミー」と呼ばれていて、今後の市場規模のポテンシャルは500兆円になるとも言われています。特に日本に強みがある領域が海洋生物多様性資源です。これは新たな素材開発や創薬につながります。次に「ブルーカーボン」に関連した市場も、まだまだ大きいと考えています。ブルーカーボンとは、藻や海洋生物が取り込む炭素のこと。ブルーカーボンを吸収・貯蓄できるという海洋生態系の仕組みを活用することで、大気中のCO2を取り込ませ、地球温暖化対策に役立てようという取り組みが進められています。
また、今日本でも洋上風力発電の建設が進められていますが、これが再生可能エネルギーを生み出す一方で、海の生態系にどのような影響を及ぼすかはまだよく分かっていません。そのため、その影響を最小化するための技術開発も同時に求められており、この点でも私どもがお役に立てることがあると考えています。
また、今日本でも洋上風力発電の建設が進められていますが、これが再生可能エネルギーを生み出す一方で、海の生態系にどのような影響を及ぼすかはまだよく分かっていません。そのため、その影響を最小化するための技術開発も同時に求められており、この点でも私どもがお役に立てることがあると考えています。
澤井:お話を伺って、海とビジネスの接点がさまざまなところにあることが分かりました。とはいえ、まだ「海」や「海洋生物」は自社の製品・サービスとは縁遠いものと感じている企業が多いのではないでしょうか。
竹内:おっしゃる通りだと思います。ただ、サプライチェーン全体で見ると、事業活動に関わるものが何らかの形で海に流れ込んでいることはよくあります。ですから、海や水の生態系と、自社はどんな関係があるのかを一度しっかりと考えていただきたいと思います。私どもがやりたいことは、ただ「海を守れ」と主張することではなく、海を守りながら産業も発展させることです。ぜひ多くの企業とポジティブな関係で、オープンイノベーションを進めたいと考えています。
前編ではイノカが提供する「環境移送技術」の概要や、企業活動にとってもこの技術が有益なこと、さらにはイノカとの協業による可能性について伺いました。後編では、日本における海の多様性の維持や海洋研究の重要性、イノカのもう1つの柱である教育事業についても伺います。
多くの企業にとってサステナビリティが重要な課題となっている中、自社のビジネスが環境にどのような影響を与えるのか、あらためて見つめ直すことが求められています。生物多様性をはじめとしたサステナビリティにまつわる企業変革や事業変革に課題を感じている方は、ぜひCONTACTよりお気軽にお問い合わせください。