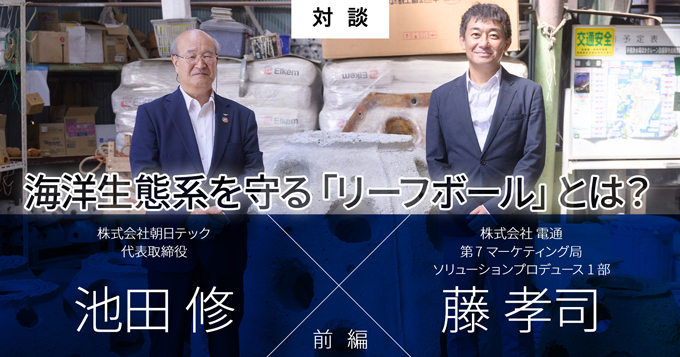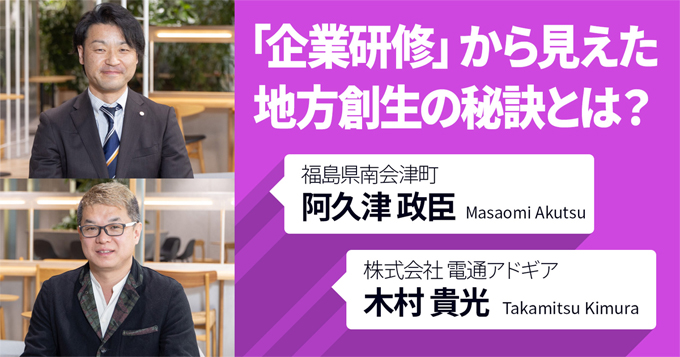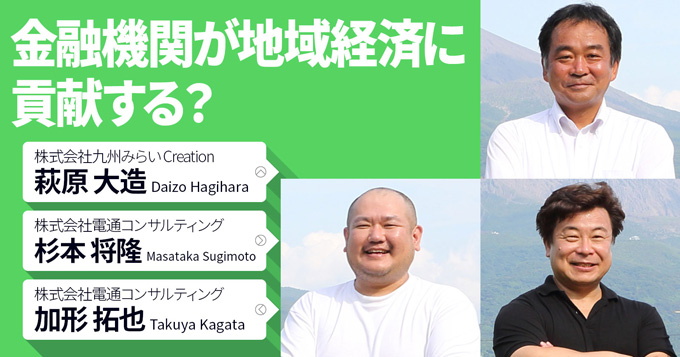日本でカーボンニュートラルのためのさまざまな取り組みが行われています。その中でも注目されているのが、海洋生態系によって炭素を取り込んでいく「ブルーカーボン」です。地球温暖化対策と海の豊かさの保全を同時に行える対策として、海に囲まれた日本でも関心が高まっています。
Transformation SHOWCASEでは、ブルーカーボンにおける取り組みの1つとして、大きな可能性を秘めた人工礁「リーフボール」に注目し、それを普及しようと取り組んでいる方々への取材記事をお届けしています。第1回の記事では、アメリカで開発されたリーフボールを日本に持ち込んだ、長崎県の株式会社朝日テック 代表取締役の池田修氏にお話を伺いました。その池田氏と二人三脚で普及に取り組んでいるのが、一般社団法人マリンハビタット壱岐 代表理事の田山久倫氏です。そこで、第2回の記事では、生まれ育った故郷・壱岐市でリーフボールの実証実験などを行う田山氏の活動に焦点を当て、株式会社 電通の藤孝司氏がお話を伺います。
地元貢献への思いとリーフボールとの出会い
藤:田山さんが、リーフボールに積極的に関わるようになったのは、どのようなことがきっかけだったのでしょうか?

田山:私は今年で32歳になるのですが、30歳の年の年始を迎えた時に、「故郷の壱岐に何か貢献しなければいけないのではないか」という強い思いが生まれました。その当時は、長崎の諫早市というところにある清掃用具販売の会社に勤めていたのですが、2017年から個人的に入会した諫早の青年会議所でさまざまな地域活動に参加していた流れもあって、「自分の故郷にも何かしたい」という思いが急に高まったのです。
そして、環境を変えないと自分も変えられないと思い、先のことは一切考えず、まず「会社を辞める」ことだけ決めてしまいました(笑)。会社にもしっかり貢献して辞めようと、これまでになく積極的に飛び込み営業を重ねている中で、たまたま池田社長の朝日テックに伺ったのです。そこで、池田社長に壱岐出身であることをお伝えしたら、「ちょうど壱岐市長と話してきたところだ」と、リーフボールの話を伺いました。これはすごいものだと思い、その日のうちにリーフボールを広めていくお手伝いをしようと決めたのです。
そして、環境を変えないと自分も変えられないと思い、先のことは一切考えず、まず「会社を辞める」ことだけ決めてしまいました(笑)。会社にもしっかり貢献して辞めようと、これまでになく積極的に飛び込み営業を重ねている中で、たまたま池田社長の朝日テックに伺ったのです。そこで、池田社長に壱岐出身であることをお伝えしたら、「ちょうど壱岐市長と話してきたところだ」と、リーフボールの話を伺いました。これはすごいものだと思い、その日のうちにリーフボールを広めていくお手伝いをしようと決めたのです。
藤:池田氏と出会ったその日に決めてしまったのですか?
田山:はい。池田社長と意気投合して、その日の夜の飲みの席でいろんなお話をしました。リーフボールを使って日本の海をどう再生するかといった話を伺い、これは一刻も早く壱岐の人たちに伝えなければいけないと思いました。壱岐はもともと沿岸漁業が盛んで、海藻を食べて育つウニやアワビ、サザエなどの貝類が重要な水産資源です。そんな壱岐で磯焼けが起こって海藻が育たなくなってしまい、これらの生物も衰退。漁師の収入も激減するという状況になっていました。それに何とか対応したいと思っていたのです。
そこで、平日は会社勤めを続けながら、土日に壱岐でリーフボールのことを伝えて回るという活動を始めました。故郷の父や叔父にまず相談して、リーフボールの実験を引き受けてくれる人はいないか探していき、地元の漁師の皆さんに集まっていただいて説明会を開いたり、池田社長にお越しいただいて説明してもらったりと、活動を進めていきました。
そこで、平日は会社勤めを続けながら、土日に壱岐でリーフボールのことを伝えて回るという活動を始めました。故郷の父や叔父にまず相談して、リーフボールの実験を引き受けてくれる人はいないか探していき、地元の漁師の皆さんに集まっていただいて説明会を開いたり、池田社長にお越しいただいて説明してもらったりと、活動を進めていきました。
リーフボール実証実験で海藻の育成の成功
藤:実験の協力者はどのようにして得られたのでしょうか?
田山:私がリーフボールの説明をして回っていたのは4月ごろでしたが、この4月というのは海藻であるアカモクが胞子を出す時期になります。ですから、4月のタイミングにリーフボールを使った実験ができなければ、また1年後の4月を待たなければいけなくなりますので、どうしてもこの時期に実験を決めたかった。とにかく費用とリーフボールはこちらで用意するので実験に協力してほしいとお願いして回ったのですが、私が壱岐にいるのは土日だけということもあり、なかなか密なお話をする時間が十分に取れず、理解を得られない状態が続いていました。
そんな日曜のある日、壱岐でアキレス腱を切るという大けがをしてしまいました。ですが、けがをしたおかげでというのも変なのですが、その結果、翌日の月曜日に諫早に戻らなくてもよくなったのです。どうせ壱岐に残っているならと思い、父親と共に松葉杖をつきながら、ある漁業協同組合に伺ってリーフボールの話をしたところ、ご理解いただけまして、もともと藻場再生の実験をされていた場所にリーフボールも設置することを許可してくださいました。そのおかげで、4月中にリーフボールの実験を開始できることになったんです。
そんな日曜のある日、壱岐でアキレス腱を切るという大けがをしてしまいました。ですが、けがをしたおかげでというのも変なのですが、その結果、翌日の月曜日に諫早に戻らなくてもよくなったのです。どうせ壱岐に残っているならと思い、父親と共に松葉杖をつきながら、ある漁業協同組合に伺ってリーフボールの話をしたところ、ご理解いただけまして、もともと藻場再生の実験をされていた場所にリーフボールも設置することを許可してくださいました。そのおかげで、4月中にリーフボールの実験を開始できることになったんです。
藤:ドラマチックな展開ですね(笑)。その実験の結果はどうだったのでしょうか?

田山:1年後には、リーフボールを覆うくらいの海藻が見事に育ちました。魚に食べられないようにしっかりと網で囲って実験していただいたので、食害にも遭わずに結果を出すことができました。この実験をどんどん続けて、リーフボールの力を1人でも多くの人に知っていただき、広めていきたいと思っています。今はまだ実験を続けている段階なので、理解していただける人を少しずつ増やしていっているような状態ですね。
他の実験場では、設置した海域とリーフボールのサイズがマッチしておらず、台風で流されてしまったということもありました。そうなると「やっぱりリーフボールではダメだ」となってしまいますし、実験も簡単なことではありません。今は壱岐だけでなく、隣の対馬市でも実験をやってもらっていますので、壱岐・対馬でしっかりロールモデルを作っていきたいと思っています。
他の実験場では、設置した海域とリーフボールのサイズがマッチしておらず、台風で流されてしまったということもありました。そうなると「やっぱりリーフボールではダメだ」となってしまいますし、実験も簡単なことではありません。今は壱岐だけでなく、隣の対馬市でも実験をやってもらっていますので、壱岐・対馬でしっかりロールモデルを作っていきたいと思っています。
故郷の壱岐でリーフボールの普及活動を行う田山氏は、地道な活動や実証実験こそが、理解していただける人を少しずつ増やしていく事につながると語ります。後編では、ビジネスとして取り組む田山氏の覚悟や、実証実験のレポートをお届けします。
電通グループでは、サステナブルなソリューションを数多く提供しています。自社の事業に環境への配慮の必要性を考えている方は、ぜひCONTACTよりお気軽にお問い合わせください。