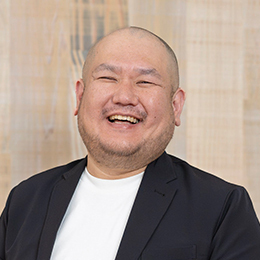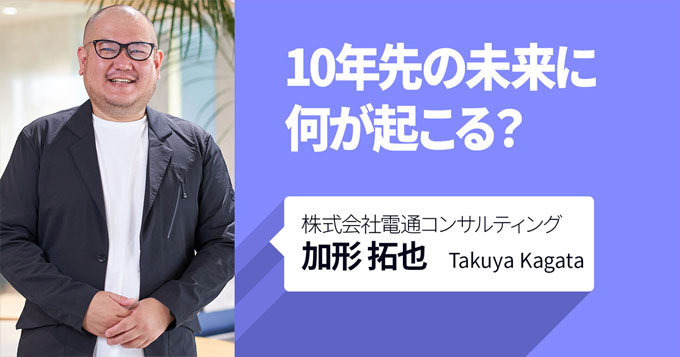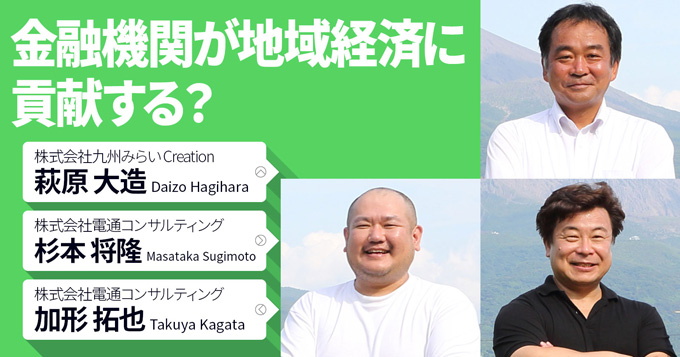https://transformation-showcase.com/articles/537/index.html
2024年3月、国内電通グループ6社(株式会社 電通、株式会社 電通東日本、株式会社電通デジタル、株式会社電通コンサルティング、株式会社電通総研、株式会社 電通マクロミルインサイト)は、「電通未来曼荼羅2024(以下、未来曼荼羅2024)」の提供を開始しました。「未来曼荼羅2024」とは、2030年までに起こり得るトレンドテーマをまとめ、経営戦略立案や新規事業開発に活用できる未来予測ツールです。提供開始に伴い、新規事業創出に悩みを抱える企業を対象に、ワークショップも実施しました。
今回の記事では、「未来曼荼羅」の編集およびワークショップに携わった電通コンサルティング 加形拓也氏、電通デジタル 高橋朱実氏にインタビューを実施。2024年度版で注目すべきトレンドテーマ、ワークショップの効果について話を聞きました。
22のトレンドテーマを刷新。中でも注目すべき3テーマとは
Q.2010年に開発された「未来曼荼羅」ですが、このたび2024年度版がリリースされました。近年の動きについてお聞かせください。
 株式会社電通コンサルティング 加形 拓也氏
株式会社電通コンサルティング 加形 拓也氏加形:変化が激しいVUCA時代には、企業も狭い業界に閉じこもっていては未来のビジネスを生み出せません。こうした中、未来を広く見渡してトレンドを予測するために開発が始まったのが「未来曼荼羅」です。当初は数年に一度アップデートしていましたが、コロナ禍以降は世の中の変化がさらに加速したため、1年に一度、内容の更新を行っています。
また、2022年度には中国版、2023年度にはインド版の編集・運用も始まりました。中国やインドは日本以上に変化が激しいため、あらゆる未来を想定して可能性を考えるアプローチは非常に有効だと思います。
高橋:近年は、新規事業開発担当者だけでなく、マーケティング担当者やシステム開発者からも「『未来曼荼羅』を使って、バックキャストであるべき姿や状態を考えたい」という相談を受けています。VUCA時代には足元の課題やトレンドがすぐに移り変わるため、視線を先に延ばそう、未来から現在を見つめようという考え方が広く根付きつつあると感じています。
Q.2024年度版では、2023年度版から22のテーマが刷新されました。新しく追加されたもののうち、注目のテーマを教えてください。
高橋:特徴的なテーマは3つあります。まず、「多死社会、死生観も関連ビジネスも変わる」です。
加形:社会の高齢化が進むことを見据え、「未来曼荼羅」ではこれまでにも60歳代以降のシニアの生き方をトレンドテーマとして取り上げてきました。それが2024年度版では、いよいよ「死」を正面から取り上げることに。高齢社会が成熟し多死社会の到来が予測され、「より良い人生の終え方」というような終活をビジネスにする企業も現れはじめ、私たちの未来予測も変わってきました。
高橋:次に「時間資源の貨幣化によるシン経済圏」。こちらも、生き方や価値観の根底を揺るがす変化だと捉えています。タイパの追求が進めば、お金よりも時間の価値が重視されます。その結果、個人の可処分時間を奪い合う経済圏が形成されるはず。その一方で、時間に追われることなくゆっくりと時を過ごすサービスも増えるのではないでしょうか。時間資源を取り合うマーケティング活動が活発になるのではと予測しています。
加形:最後は「国家・自治体の財政悪化とEBPM(Evidence-Based Policy Making)の加速」です。政府の財政逼迫が続く中、EBPMと言われる客観的データに基づく合理的、論理的な政策評価/立案プロセスが標準化され、エビデンスがない政策は廃止されるのではないかと見ています。
「未来曼荼羅」は、民間企業の新規事業創出に活用するツールですから、数年前ならこのテーマは選ばなかったでしょう。ですが、ここ数年で社会の分断が進み、さまざまなレイヤーでの意思決定、合意形成をどう行うべきかが大きな問題になっています。また、インフラ維持など、もともと行政が行っていた領域が民間企業に委託される動きも加速しています。そのため、国の政策に関する未来予測も、今年のトレンドテーマに組み込むことにしました。
2035年の未来予測への挑戦
Q.3月に行われたワークショップでは、「2030年前半入居予定の新築マンションの住まいアイデア開発」をテーマに、新規事業のアイデアを考えました。このテーマの選定理由と、参加者に感じていただきたかった気付きについてお聞かせください。
 株式会社電通デジタル 高橋 朱実氏
株式会社電通デジタル 高橋 朱実氏高橋:生き方や暮らし方など全方位に考えを巡らせていただきたくて、衣食住にご近所付き合い、ライフイベントや資産と多面的に捉えられるマンションをテーマにしました。ワークショップの狙いは、「未来曼荼羅」からのインプットをベースに、自分自身の中から仮説や課題を引き出す体験をしていただくことです。また、各グループで討議しながら複数人で考察を深め、仮説の課題を精緻化していただきたいという思いもありました。
加形:以前は、マンション造りと言えば不動産デベロッパーの領域でしたが、今では自動車メーカー、家電メーカーなど多くの業界が生活者の暮らし全般に関わる事業を展開しています。野心的にいろいろなアイデアを考えていただくのに、最適なテーマだと思いました。
Q.今回のワークショップに参加された方には、この体験をどのように生かしてほしいと考えていますか?
高橋:ぜひ社内でも、今回のような取り組みを実施してほしいと思っています。日々の業務では、同じチームの方が同じ課題に向き合い、解決を図っています。ですが、「未来曼荼羅」によって未来の視点を取り入れることで、何か違うものが見えてくるかもしれません。ワークショップで得た思考のエッセンスを生かしていただければと思います。
Q.最後に「未来曼荼羅」の今後の展開についてお伺いします。2024年度版は2030年を射程圏内に捉えて編集していますが、今後はどう発展させていこうと考えていますか?
加形:2つ考えがあります。これまでは、より解像度高く未来予測をするため、2030年という短射程で未来を見据えてきました。ですが、最近は2040年、2050年の未来を予測するプロジェクトも増えています。そこで、いよいよ来年は2035年の未来予測に取り組みたいと考えています。少し足を伸ばしつつ、でも手触り感がある未来を引き続き予測し、仮説や議論を巻き起こしていきたいですね。
もう1つは、BtoB企業へのアプローチです。これまではBtoC企業からの引き合いが多かったのですが、技術に強いBtoB企業からの注目度も高まっています。BtoB企業の多くは「最終的に生活者の変化はどこに向かうのか」と予測して商品を開発していますが、それと同時にクライアント企業が未来をどのように見ているのかも考慮しなければなりません。プロセスがもう1つ加わり、応用編のプロジェクトになっていくでしょう。こうしたBtoB企業の方々に、「未来曼荼羅」をより広く知っていただくための活動も広げていきたいです。

「未来曼荼羅」を活用した新規事業開発では、未来の生活者視点でアイデアを広げていきます。その過程では、既存の事業領域以外にも知見が広がり、共にプロジェクトに取り組むメンバーについての理解も進むはずと加形氏は話します。未来の事業を柔軟に考えるキックオフツールとして、「未来曼荼羅」を活用してはいかがでしょうか。
変化の激しい時代、どのようにして生活者のニーズに合った新しいビジネスをつくっていけばいいか、悩まれることもあるでしょう。「未来曼荼羅」を活用した新規事業開発に興味をお持ちの方は、ぜひCONTACTよりお問い合わせください。
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。