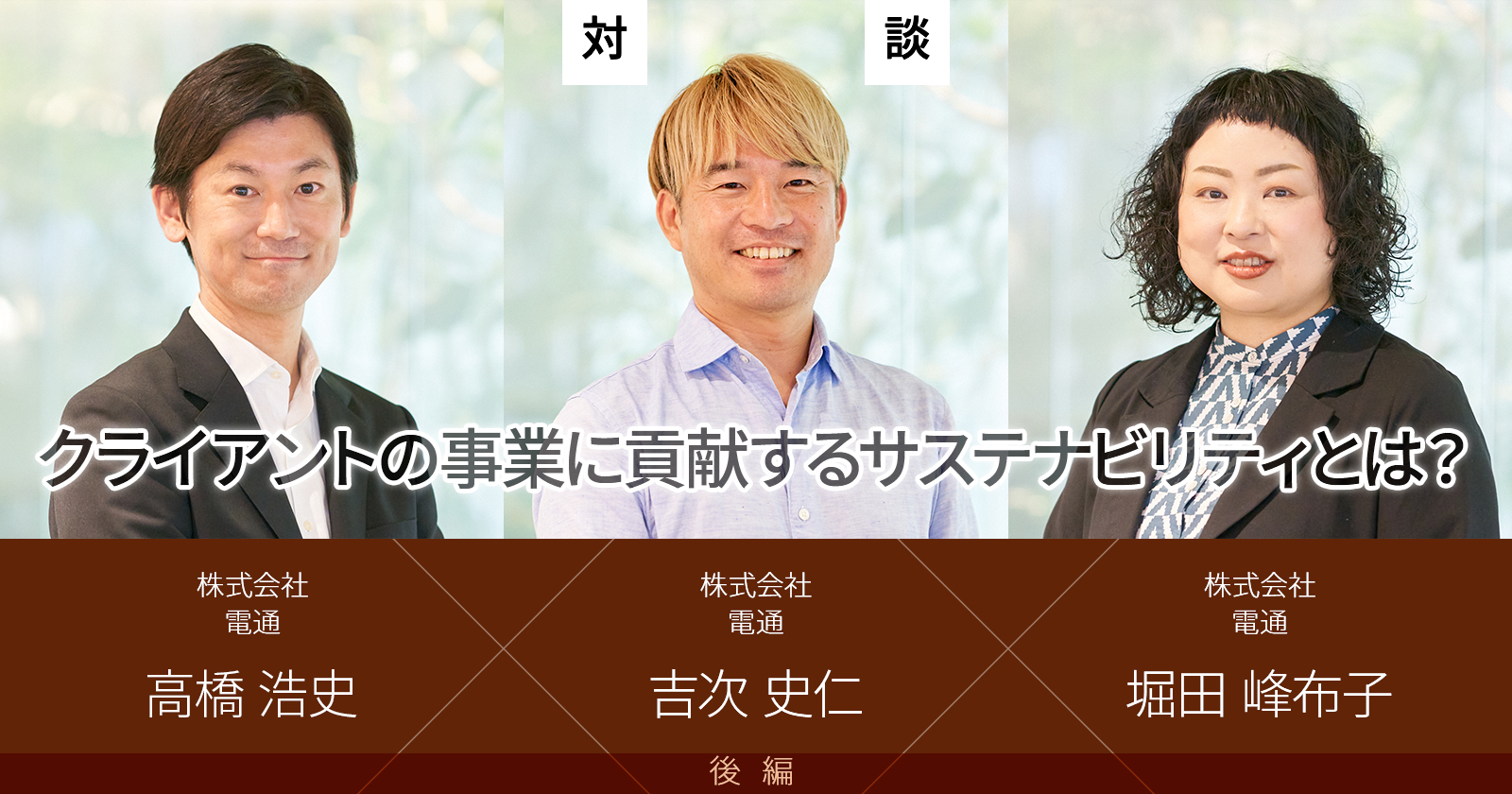国内電通グループ2社は、空容器などの「回収・リサイクル」に、クーポン・ポイントなどの「販促」を組み合わせ、循環型社会の実現を目指す「で、おわらせないPLATFORM」を開発しました。2024年1月末まで実施した実証実験には、株式会社 明治、株式会社ローソン、株式会社ナカダイホールディングスが参画。
実証実験へ参画した各企業の担当者が実証実験を振り返った前編に続き、後編では株式会社 電通でそれぞれ明治、ローソンを担当するビジネスプロデューサー(BP)の高橋浩史氏と吉次史仁氏が登場します。循環プラットフォーム構築の旗振り役となった、サステナビリティコンサルティング室の堀田峰布子氏を進行役に、プロジェクト立ち上げの背景や実現に至るまでの経緯、電通グループだからこそ具現化できること、今後の展望などについて話を聞きました。
サプライチェーンの上流から下流まで。社会課題解決の新たな手立てに
堀田:まずは、私から「で、おわらせないPLATFORM」を立ち上げることになった背景をお話させていただきますね。これまで企業は、商品やサービスを作って売るところまででビジネスが完結していたのが、昨今は資源の回収・リサイクルまでを担うことが企業の大きな責任となっています。ただ、回収・リサイクルにはコストが掛かり、収益につながらないことが課題。だからこそ、多くの企業が頭を悩ませています。
そうした背景も踏まえて、電通グループは、「B2B2S(Business to Business to Society)」を経営方針として掲げています。マーケティングやデジタル領域の強みを生かして、社会と生活者の意識・行動変容を促す仕組みを発信できないか。そうした思いから、製造メーカーなどの動脈産業、回収・リサイクルを担う静脈産業、そして消費者をデジタルでつなぐ「で、おわらせないPLATFORM」を開発しました。
2023年6月、この実証実験に参加する企業を募るリリースを出したところ、社内から明治さま担当の高橋さんと、ローソンさま担当の吉次さんが名乗りを上げてくれました。なぜこのプラットフォームをクライアントさまに提案しようと思ったのでしょう?
そうした背景も踏まえて、電通グループは、「B2B2S(Business to Business to Society)」を経営方針として掲げています。マーケティングやデジタル領域の強みを生かして、社会と生活者の意識・行動変容を促す仕組みを発信できないか。そうした思いから、製造メーカーなどの動脈産業、回収・リサイクルを担う静脈産業、そして消費者をデジタルでつなぐ「で、おわらせないPLATFORM」を開発しました。
2023年6月、この実証実験に参加する企業を募るリリースを出したところ、社内から明治さま担当の高橋さんと、ローソンさま担当の吉次さんが名乗りを上げてくれました。なぜこのプラットフォームをクライアントさまに提案しようと思ったのでしょう?

吉次:ローソンさまをこれまで担当する中で、これまでも社会課題解決型のキャンペーンや取り組みを推進してきました。そうした中でも、このプラットフォームはリサイクル活動に販促の要素を加える、今までにない新しい視点だと思いました。「これはもしかしたら、社会課題を解決しながらも、売り上げ向上につながるすごい仕組みかもしれない」と思い、すぐにローソンさまへ提案をさせていただきました。
高橋:私は20年ほど明治さまを担当させていただいているのですが、明治さまは元々カーボンニュートラルの実現に向けて、GHG(温室効果ガス)をどう減らすかという課題を抱えていらっしゃいました。明治さまのGHG排出量のうち約85%は「Scope3」が占めています。「Scope3」というのは、サプライチェーンにおける排出量のうち、事業活動の上流における原材料の調達や製品の輸配送に伴う排出、下流における製品使用や廃棄による排出など、間接的な排出を指しますが、明治さまの場合、その大部分を生乳の調達に関わる排出量が占めています。これは酪農業界ならではの課題といえます。酪農は、CO2だけではなく、牛のゲップやふん尿の処理などから出るメタン(CH4)や一酸化二窒素(N2O)の温室効果への影響が大きく、明治さまでは餌を工夫するなどして上流側のGHG削減の取り組みを行っていました。
それに加えて、下流側の消費者との連携まで取り組みを広げた方がいいのではという提案をまさに議論していたところ、今回の実証実験参画企業を募集するニュースリリースが目に留まりました。まさにこれまで議論してきたことに当てはまる取り組みだと思い、すぐに明治さまへ提案した次第です。
それに加えて、下流側の消費者との連携まで取り組みを広げた方がいいのではという提案をまさに議論していたところ、今回の実証実験参画企業を募集するニュースリリースが目に留まりました。まさにこれまで議論してきたことに当てはまる取り組みだと思い、すぐに明治さまへ提案した次第です。
B2B2Sの実現に向け電通グループ自身が汗をかき、単発ではなく長期的な取り組みに
堀田:今回の実証実験では、クライアントさまへの提案だけでなく、電通グループ自身が資源循環のプラットフォームを構築した点が新しいチャレンジでした。実証実験に関して、電通グループだからこそ実現できたことは何だと思いますか?
高橋:クライアントさまにサステナビリティ関連の提案をするとき、よくぶつかる壁があります。プロジェクトに取り組む社会的意義は理解できるものの、企業としてサステナブル関連活動へ先進的に取り組むべき動機付けと腹落ち感です。それに対して今回、電通がグループ会社の電通プロモーションプラスも巻き込んで、プロジェクトとして推進し、プラットフォームを構築したというのは、多様な専門性を有する電通グループだからこそできたことなのではないでしょうか。
こうしたサステナブルな取り組みは、1社で成果を出せるものではなく、時には競合他社とも協力し、業界の垣根を越えて共創しなければ実現できません。電通はグループ会社も多く、たくさんのクライアントさまを巻き込める可能性があります。
こうしたサステナブルな取り組みは、1社で成果を出せるものではなく、時には競合他社とも協力し、業界の垣根を越えて共創しなければ実現できません。電通はグループ会社も多く、たくさんのクライアントさまを巻き込める可能性があります。

吉次:まさに、電通は「ハブ」ですよね。クライアントさまにはメーカーも流通もいらっしゃいますし、業界を問わずさまざまな企業を巻き込めるのは、電通グループならではだと思います。それに、調査からコンサルティング、クリエイティブ、コミュニケーション、デジタルまで、さまざまな領域を得意とするグループ会社を持つ電通ならば、最後まで実行してくれるだろうという安心感・信頼感を得ていただきやすい。だからこそ、ローソンさまもすぐに企画に賛同してくださったのかなと思っています。

明治、ローソン、ナカダイホールディングスと一緒に、普段はあまり表に出ない電通グループのロゴが並んだことが印象的だったと言う
堀田:一方、実証実験を実現するまでに苦労した点や、抱いた課題はありましたか?
高橋:苦労まではいきませんが、サステナブルな取り組みに対して、クライアントさまに過度な期待を抱かせないということは、初期の段階から心掛けていました。もちろん、資源回収率もクーポン償還率もしっかり確保して、事業に貢献することが目標ではありましたが、この期間限定の取り組みにおいてそれが達成できなかったとしても、原因を探り、アップデートしていくことが大事だと考えていました。こういった活動は単発でやってみて結果が出なかったらといって、すぐにやめてしまってはいけません。消費者が紙パックを洗って、開いて、乾かして、店舗に持っていくのは、ペットボトルのラベルをはがして捨てるよりも手間がかかりハードルが高い。それをきちんと説明して、まずはやってみて、アップデートしながら継続していきましょう、と繰り返しお伝えしていました。
吉次:参加者を増やすための仕組み作りというのは、次への課題になりましたね。今回、実証実験を行ったローソンさまの3店舗はいずれも、都心の店舗でした。前編でローソンさまもおっしゃっていましたが、それが回収率が上がらなかった1つの反省点であると感じています。今回の取り組みを1回で終わらせるのではなく、継続することで参加者が増えるという共通認識ができたことは、良かったなと思います。
クライアント事業の持続的な成長に貢献するサステナブルな取り組みとは
堀田:そうした収穫から、より成果を上げていくためにどうしたいか、またこのプラットフォームを活用してどんな施策を講じていきたいかなど、今後の展望をお聞かせください。
吉次:実施する店舗の選定はもちろん、例えば「住宅街の近隣の3店舗で実施する」など、プロモーションの効率が上がるやり方を考えながらやっていきたいですね。そうして、店舗の数を増やしていく。また、今回は紙パック+プラスチック製キャップのみの回収でしたが、回収する資源の種類を増やしたいですよね。それによって参加者が増え、販促につながる。そういった良い連動を生み出したいです。

高橋:今回の実証実験で得られたものとして、ロイヤルティも高く、なおかつ回収・リサイクルにも参加するいわゆる「サステナブルカスタマー層」の出現を実感したことが大きかったです。そういった層を新たなマーケティングターゲットとして育てていくためにはどうすればいいか。店舗数の増加など規模を拡大するのはもちろんのこと、クーポン取得といった金銭的なインセンティブ以外に、これまでとは違った価値を提供できないだろうかと考えています。例えば、自治体やコミュニティー内で、リサイクルの取り組みに参加することで非金銭的な価値を得られる構造を作れないか、とか。それによって、サステナブルカスタマーが増えていくのが、理想的ではないでしょうか。
堀田:電通グループとしても、このプラットフォームは新しい取り組みです。今回、担当クライアントさまと向き合ってみて、社内の他のBPへ向けて発信したいポイントやマインドセットがあれば、教えてください。
吉次:BPはどうしても数字に追われて、短期的に収益が上がるか上がらないかの視点になってしまいがちです。しかし、クライアントさまの長期的なパートナーになるという視点で考えると、このプラットフォームは、より良い関係性を築く一助になると思います。どの企業にもサステナブル経営が求められている状況下で、長期的な視点を持って提案できることは、BPとして大きな価値になるのではないでしょうか。
高橋:中長期的な視点でクライアントさまの利益を考えることの重要性は、まさにその通りだなと思いました。少し別の視点で言うと、海外では、環境保護の観点から動物性のミルクに対しての風当たりが強いんです。でも私は、「明治おいしい牛乳」がすごく好きで、どうしたら明治さまが主とする事業の課題を解決できるかを、ずっと考えてきました。消費者に酪農における課題を理解してもらった上で、牛乳がもたらす価値についても再認識してもらい、企業だけが頑張るのではなく、社会を巻き込んで課題を解決していきたい。そういう思いが、実証実験参加の背景にはありました。
社会貢献という文脈だけではなく、クライアントさまの本業に対する、「こうあってほしい」「こう持続してほしい」という思いを大切に、サステナビリティを考えてみても良いのでは、と思います。
社会貢献という文脈だけではなく、クライアントさまの本業に対する、「こうあってほしい」「こう持続してほしい」という思いを大切に、サステナビリティを考えてみても良いのでは、と思います。
堀田:ロングタームで考えることや社会や生活者を巻き込みながら共創していくこと。どれも電通社内の話に限らず、企業がサステナブルなプロジェクトを実現するために必要なことですね。電通グループが目指すIGP (Integrated Growth Partner)への新たなアプローチになったのではないかと思います。

あらゆる垣根を越え、手を取り合って協働すること。1度で終わらせることなく、アップデートしながら継続していくこと。それが、社会課題の解決には欠かせない条件です。電通グループならではの強みを生かし、多くの企業を巻き込んだ取り組みを、今後も展開していきます。
サステナブル経営やSDGsへの関心が高まる中、事業と社会課題解決を両立したいという企業の方や、「で、おわらせないPLATFORM」にご興味を持った方は、CONTACTからお問い合わせください。