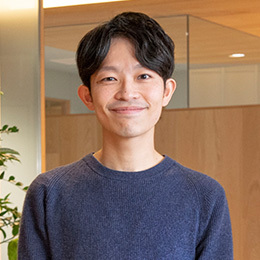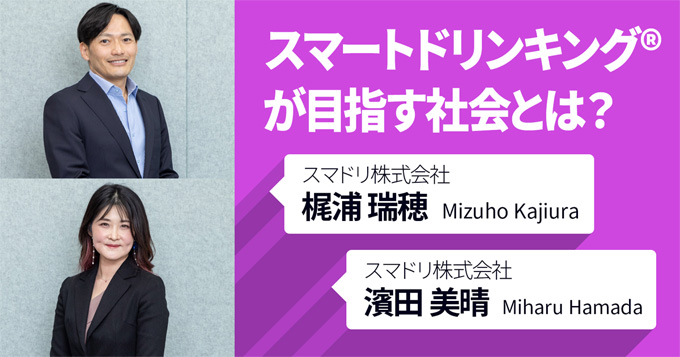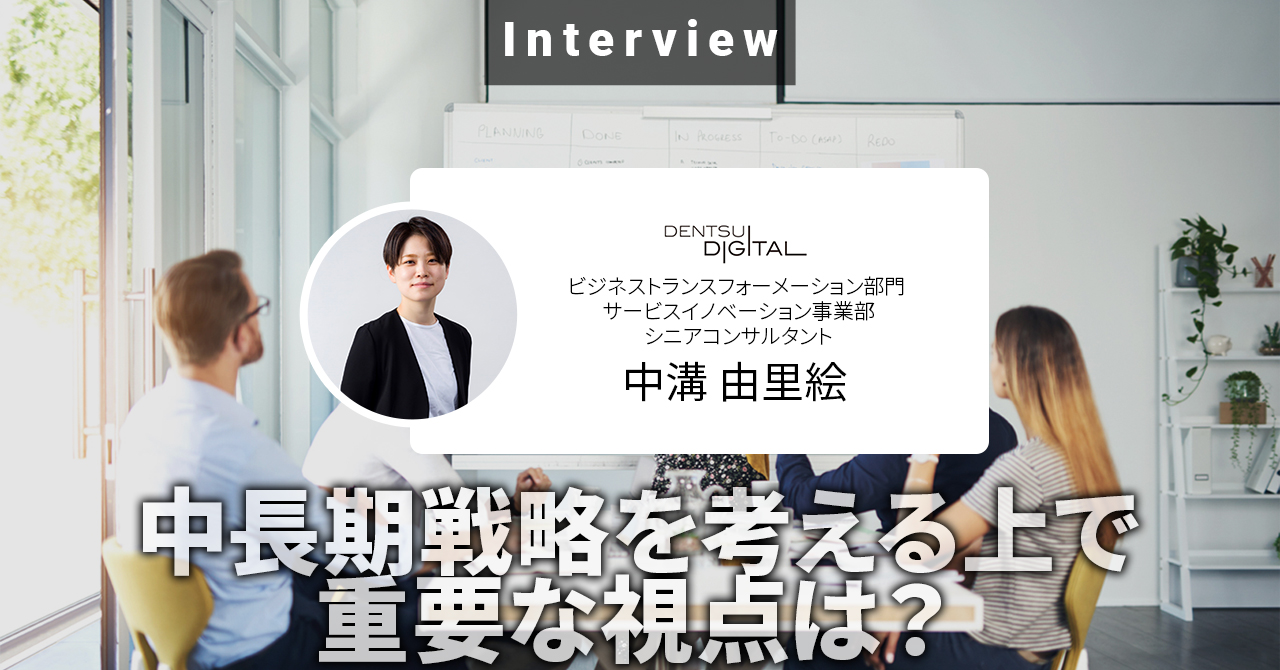https://transformation-showcase.com/articles/289/index.html
環境、人権の意識が高まる中、あらゆる企業にとってサステナビリティの推進は、避けては通れない経営課題です。電通ジャパンは、サステナビリティ・ネイティブと呼ばれるZ世代とともに企業のサステナビリティを推し進めるサービス、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY 」をリリースしました。Z世代との共創をする上で重要なポイントについて、Z世代のトレンドを発信するNEW STANDARD株式会社代表取締役の久志尚太郎氏、株式会社電通デジタル でデジタルネイティブルームを設立した松崎裕太氏、そして株式会社 電通 サステナビリティコンサルティング室 ディレクターで、電通Team SDGsコンサルタントの田中理絵氏が語り合います。
前編ではサービスの概要やZ世代とサステナビリティの関係について紹介。後編となる今回は、事例解説とともに、Z世代との共創をする上で重要なポイントについて取り上げます。
リバースメンタリングに必要な「形式知」 田中: 前編で、海外でリバースメンタリングの普及が始まったという話をされましたよね。日本での普及には、どういったことが必要なのでしょうか。
久志: これはDXの普及においても同じなのですが、DXの本質はユーザー起点の問題提起です。さまざまな人が持ち寄った課題を、みんなで共有してアジャイルに解決していけばいい。全てを自分たちで考え実行することは、どんな天才でもすごいチームでも限界があります。年長者や経験者が答えを全て持っているわけでもありません。社会の当事者として、若い世代だからこそできる問題提起だってあるはずなんです。若手をリーダーに抜てきしたり、意見を出してもらったりことは、企業自身のサステナビリティにとって、大切だと思います。
NEW STANDARD株式会社 代表取締役 久志 尚太郎氏 田中: 形式知で意思決定プロセスがオープンになっていると、誰もがリーダーになりやすい。Z世代の視点を取り込みながら、組織のインクルーシブを推進していくことにつながりますね。
松崎: そもそもZ世代の視点で考えると、「サステナビリティ」って言葉を声高に口にすることにも少し違和感があるかもしれません。おそらく、ソーシャルグッド・ソーシャルバッドという対立概念もない。なぜなら、「企業は社会を良くするためにあるべきでしょう」という大前提を持っているからです。現在の企業にとって、サステナビリティは「義務」とか「やらなくてはならないこと」になりがちですが、Z世代にとってのサステナビリティは「当たり前」だし、「楽しいもの」という位置付けなんですよね。
田中: デジタルネイティブも、デジタルを当たり前で楽しいものとして使いこなしてきましたよね。頭でやらなきゃと考えるだけではなかなか動けない人も多いのではないかと思いますが、「こうなれば、みんな喜びそう」と思えることであれば、きっと自発的に動ける人が増えるのではないでしょうか。久志さんがおっしゃった自分だけで背負い込まないでみんなで解決しようというのは、まさに、コレクティブインパクトの精神ですよね。「ユーザー起点」は一見、人間本位でサステナブルに感じにくいアプローチに見えるかもしれませんが、大きくて複雑な社会課題こそ、1人の視点・当事者意識で捉え直すと、その解決にさまざまな視点や技術が集まってくる。デジタルで起こったのと同じアプローチですね。
新たな文脈をひも付けて、当事者意識を生む 田中: 久志さんはZ世代との共創で、これまでさまざまな事業やサービスを開発されてきましたよね。幾つかご紹介いただけますか?
久志: 象徴的なのは、2022年5月に発売された、大手飲料メーカーの新しいアルコールドリンクの開発に関わったことですね。これまで、アルコールには「酔っ払う」という文脈が強くひも付いていました。けれど、アルコールは人の心を豊かにすることだってできます。特にコロナ禍で心を満たしづらいという状況が続いたこともあり、「飲むこと」に新しい価値を生み出したかった。そこで、若い世代がお酒に対して持っていた「お酌しないといけない」「権威を感じる」といった文脈を取り払い、お酒にひも付く文脈を「エモい」や「チルい」といった、若者にとって身近で、価値を感じてもらいやすいものに置き換えたんです。
田中: 商品にまつわる文脈を変え、若者にとって価値あるものにしたんですね。
久志: そうですね。人は文脈によって物事を理解するので、商品の価値を創造する上で文脈はとても大切な要素だと思います。
田中: サステナビリティに関連する事例はありますか?
久志: 2022年11月に開催した企画展「
わたしがはじまる、出発展〜滋賀のSDGsに触れる旅〜 」は滋賀県が主催し、NEW STANDARDが運営するメディア「TABI LABO」がコンテンツ制作・監修を担当しました。Z世代のフォトグラファーが滋賀を旅する中で、普段の生活の中に、SDGsがたくさん詰まっていることを発見する様子を、写真などのコンテンツで追体験していく取り組みです。
田中: いいですね。サステナビリティを「新しいことを始める」と捉えるとハードルが高くなりがちですが、今までやってきたことを見直す、というアプローチなら受け入れやすくなりますね。
株式会社 電通 田中 理絵氏 久志: 自分に近いものを体験してもらうことで、当事者意識が育つんです。観光旅行に限らず、例えば、サステナブルなものづくりをしている工場を訪れるのもいいと思います。自分の生活の中に、当たり前のようにあるSDGsとかサステナビリティを実感してもらうようなアプローチがこれからは重要になってくるのではないでしょうか。
田中: エコツーリズムも、生物多様性への注目の中でビジネスチャンスになる領域ですね。先日、大阪から石垣島への修学旅行の話を聞いたのですが、アクティビティとして海岸のごみ拾いが選ばれ、その満足度が高かったそうです。旅行や社員研修で、Z世代とサステナビリティの視点を入れてサービス開発すると広がりそうですね。
「購入」で終わらないカスタマージャーニー 田中: 松崎さんの取り組まれたサステナビリティの事例もご紹介ください。
松崎: ユニクロが展開するチャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」で、TikTokerの方と協業して映像コンテンツ(※1~3)を制作しました。プロジェクトの概要としては「世界の平和を願ってアクションする」という目的に賛同する著名人がデザインしたTシャツを販売し、その利益を全額、3つの人道支援団体に寄付するというものです。今回は、その映像コンテンツを企画。フォロワーが600万人を超えるTikTokerのレミたん(元ハンドボール日本代表主将・土井レミイ杏利)さん、車椅子生活をしながらTikTokerをされているみゅうさんらと共に、支援先である特定非営利活動法人国連UNHCR協会やセーブ・ザ・チルドレン、プラン・インターナショナル・ジャパンを訪れ、どんな課題に向き合っている人たちにどんな支援を行っているかなど、できる限り現場について取材しました。今の若い世代には、リアリティのないものは受け入れられにくいと思います。ですから、彼らと同じ目線で手触り感を持って伝えるべく、TikTokerと協業し取材するという形式をとりました。
株式会社電通デジタル 松崎 裕太氏 田中: Tシャツのチャリティーで支援団体を知る、という体験ができるのがいいですね。Tシャツを買う意義が、素材・デザインなどのモノを超えていると思います。
松崎: もちろんTシャツ自体にも商品としての価値がありますが、買ってもらうことがゴールではなく、Tシャツをメディアとした一連のプロジェクトなんです。そこからインフルエンサー経由で社会課題の現場を知ったり、動画のコメント欄でユーザー同士が意見を交換したりといったところにつなげていくことができる。そこに可能性を感じています。このようなプロジェクトの場合、カスタマージャーニーが、購入で終わってしまうのはもったいないですから。
田中: なるほど。買った後の生活や、事業に関わる人々の背景をどう伝えていくかは「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」でも肝になりますね。今後もサステナビリティに関するビジネスを、「やらなきゃというより、そもそもなんでやっていないんだろう」という軽やかなZ世代の感覚で捉え直し、世の中を面白く書き換えていきたいですね。
Z世代に意見を出してもらう仕組みは、企業自身のサステナビリティに大切。その際ボトルネックになる暗黙知を形式知に変える経営努力が必要。解決のカギは1人ひとりの視点を集め、みんなで解決に向かうコレクティブインパクトの姿勢。また、Z世代と共創するサステナブルな事業は既存の文脈を捉え直し、消費はゴールではなく1過程として、その後の生活やつながりに満足の力点が置かれていくことが大事。3人の間ではそんなトピックが語られていましたが、読者の皆さんはどのようにお感じになったでしょうか?
「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」はサステナビリティ対応を機会と捉え経営戦略に反映するために、Z世代の視点で既存の枠組みを捉え直し、将来世代のマイナスをプラスに変え、それが収益に結び付くよう事業の再構築をするコンサルティングソリューションです。
本記事を読み、事業構想立案に当たっての新たなアプローチや、Z世代との対話やアイデア共創などに関心を持っていただいた方は、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせはCONTACTから。
※1 チャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」映像コンテンツ①(レミたん氏) チャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」映像コンテンツ②(みゅう氏) チャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」映像コンテンツ③(レミたん氏)
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。