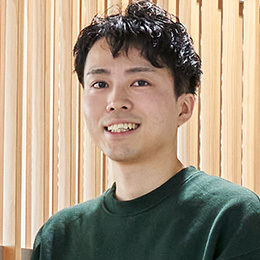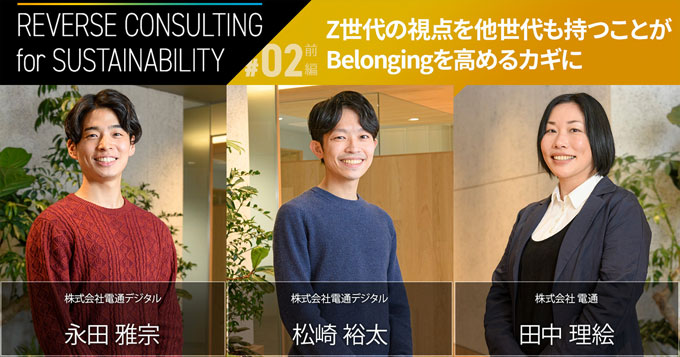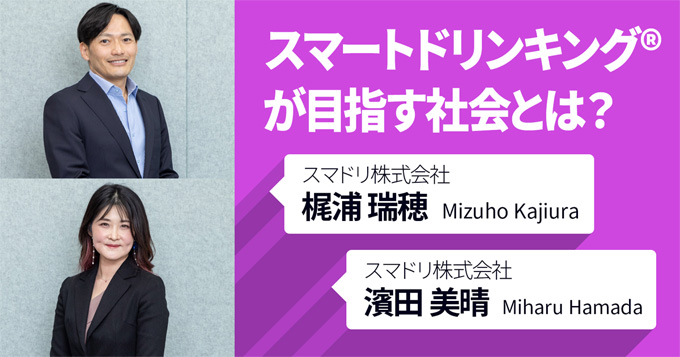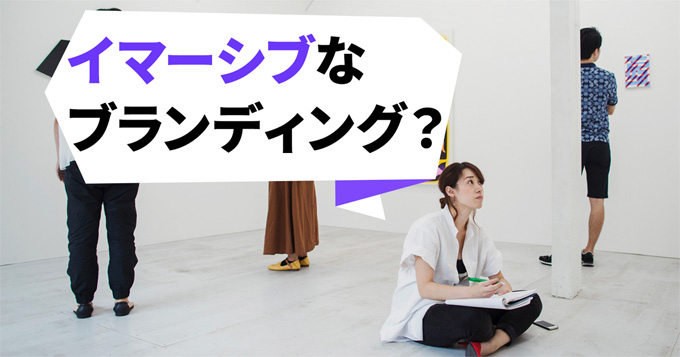電通ジャパンでは、サステナビリティ・ネイティブと呼ばれるZ世代とともに企業のサステナビリティを推し進めるサービス、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」をリリースしました。コンサルティング体制の中で異彩を放つのは、株式会社電通プロモーションプラス内のユニット「若者消費ラボ」のメンバーです。今回は同ユニットの五十嵐響介氏、大木佳奈氏、馬場理彩子氏を迎え、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」をリードする田中理絵氏とともに、Z世代当事者から見たサステナビリティの捉え方について語ります。
義務感よりワクワクを。「となりのSDGs」とは?

田中:まずは2022年に立ち上げられた「若者消費ラボ」について、簡単にご紹介いただけますか。
五十嵐:若者消費ラボは電通プロモーションプラスに在籍する、ミレニアル世代(1980~1995年生まれ)、Z世代(1996~2015年生まれ)で構成されているユニットです。若い世代向けの商品・サービスを対象に、当事者の視点を取り入れながら、販促・プロモーション領域の課題解決に取り組んでいます。
田中:メンバーはどうやって募ったのですか?
五十嵐:若年層をターゲットとしたプランニング部門は以前からあったのですが、もっと下の世代が中心となって活躍できる場をつくりたいと思い、若手社員1人ひとりに声を掛けました。当事者であるZ世代がメンバーにいることは不可欠だと感じましたし、若手社員もそうした場があれば、より生き生きと活動できると考えたんです。また、会社全体の課題としてプロジェクトを実行していくプロデューサーが多く、企画を立てるプランナーが少ないことも感じていたため、「若手のプランナーを増やす」という裏テーマもありました。
田中:プロデューサーになるには、それなりに経験が必要ですものね。
五十嵐:そうですね。だからといって、みんなが現場の数をこなして経験値を上げるのを待っていては組織としては硬直してしまう。それでは駄目だと思って、若手が活躍できる場の創出について考えるようになりました。
田中:若者消費ラボが誕生したことについて、馬場さんたちはどう思いますか?
馬場:五十嵐は新入社員研修で講師をしていて、そのときにも「プランナーの数を増やしたい」「底上げしていきたい」と言っていたのですが、そんなふうに若手の活躍の場の創出に尽力している先輩がいることがすごくうれしかったですし、心強い存在だと思っています。

田中:若者消費ラボの中にはSDGsユニットもあるのですね。
五十嵐:それまでは案件ごとにケースバイケースで動いていたのですが、所属メンバーの関心が強く、かつ消費との連動性の高いものをカテゴリー分けして、大きく6つに分けることができたので、今はそれぞれのユニットチームごとに活動しています。
田中:馬場さん、大木さんはSDGsユニットのメンバーですよね。
馬場:はい。普段からお客さまと接する中で、「自社のビジネスにSDGsをどう絡めていけばいいのか分からない」という声を聞くことが多かったので、このトピックをもっと掘り下げていきたいと考え、SDGsユニットへの参加を決めました。
大木:このユニットでは、Z世代にSDGsをもっと身近に感じてもらいたいという思いから、「となりのSDGs」という活動方針を掲げています。企業が発信しているSDGs活動となると少し「お堅い」イメージもあるので、それをある意味でベンチマークとして、「手に取りやすいSDGs」を目指しています。
サステナビリティはこれからもっと「当たり前」になると思いますが、だからといって義務感だけで遂行するのは難しい。じゃあどうすればみんなが率先してサステナブルな取り組みを行えるようになるのか。そこにはサステナビリティ以外にも「商品やサービスを利用したくなる理由」が必要なのではないでしょうか。その商品を買うこと、サービスを利用することに対してワクワクできるかどうかはとても大切。そこに「サステナビリティ」が後からついてくるのが理想的だと思います。
サステナビリティはこれからもっと「当たり前」になると思いますが、だからといって義務感だけで遂行するのは難しい。じゃあどうすればみんなが率先してサステナブルな取り組みを行えるようになるのか。そこにはサステナビリティ以外にも「商品やサービスを利用したくなる理由」が必要なのではないでしょうか。その商品を買うこと、サービスを利用することに対してワクワクできるかどうかはとても大切。そこに「サステナビリティ」が後からついてくるのが理想的だと思います。
田中:確かに、「環境にいい」の手前に、その商品の「デザインが好き」とか、「おいしい」「楽しい」みたいな気持ちが持てないと、なかなか買いにくいですよね。
五十嵐:Z世代は、SNSで不特定多数の人とつながって、場面ごとに異なる立ち居振る舞いをすることにも長けているし、社会との距離の保ち方も心得ていますから、自分にとっての「ワクワク」と、社会や世の中にとって良いことである「サステナビリティ」「SDGs」とのバランスもうまく取れているように思います。自分にとっての楽しみを大事にしつつも、地球の未来や環境を守ることが価値観として形成されているのではないでしょうか。
Z世代視点を取り入れる提案のポイント
田中:若者消費ラボは「for Z」、Z世代をターゲットとしたプロモーションを考える現場対応のチームですが、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」のコンサルティングサービスは経営者向けの「with Z」、つまり、Z世代と一緒に新しいビジネスをつくっていくもので、少しスタンスが異なります。Z世代視点を取り入れながら、組織内外のサステナビリティ推進にアプローチし、課題を解決していく。そこに、若者消費ラボがプロモーションを通じて得たリアルな知見を生かしていくことは、インプットだけでなくテストマーケティングを成功に導く際も、コンサルティングの厚みになると考えています。Z世代向けのプロモーションの最近の傾向を教えていただけますか。
五十嵐:まず、デジタルコミュニケーションが基本ですね。ECも店頭も、現状のコミュニケーションは、まだZ世代に最適化されていないと感じます。新しいテクノロジーも取り入れられつつありますが、その技術を使ってZ世代に刺さる型・パターンを確立できているところはまだ少ない。今は、各企業やプレーヤーがさまざまなやり方を模索している、過渡期なのではないでしょうか。

田中:Z世代視点で事業の勘どころを押さえることは大事ですよね。ただ、経営側がより長期的な視点でサステナブルな事業について考え、事業ポートフォリオを見直し、新事業に投資すると決めたとしても、テストマーケティングをしないとうまくいくか分からない。現場は忙しいし、売り上げに対する責任もあるので、手堅く既存路線になりがちです。Z世代視点でビジネスを見直すことを既存の事業部門内でやっていくことは、思いのほか難しいのではないでしょうか。
大木:実際、さまざまな企業さまの事業やコミュニケーションを見ていて、Z世代目線では「もっとこうしたらいいのに」と感じる場面もあります。それでも、いろいろな縛りがある中で提案しないといけなかったりすることはありますね。

田中:「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」は「forZ(Z世代向け)」ではなく、「with Z(Z世代と一緒に)」なので、むしろそういった「こうしたらいいのに」という意見に価値があると思います。もちろん、経験則によってうまくいくこともあると思いますが、バイアスブレイクしていかないと現場経験値の豊富なベテランの価値観で判断されて、結果的にビジネスとして後れを取ることになってしまうかもしれません。
良いアイデアがあっても、組織の壁とか、事業の壁みたいなものに阻まれて通らない、というケースはありますか?そういう時はどうやって壁を乗り越えていくのでしょうか。
良いアイデアがあっても、組織の壁とか、事業の壁みたいなものに阻まれて通らない、というケースはありますか?そういう時はどうやって壁を乗り越えていくのでしょうか。
五十嵐:事業や組織の壁というほど大きくはないですが、提案を通していくためには、3つの大事なポイントがあると思っています。1つ目は、理想を語ること。2つ目は、KPIなどの数字を設定して現状とのギャップを示すこと。そして3つ目は、具体的なイメージを提示することです。
例えば、若年層向けのキャンペーン企画でVTuberの起用を提案する際、理想を伝えた上で、そのVTuberにどんなことを話してもらえれば企業の魅力が伝わりやすいか、それによってKPIをどう達成できるかを、具体的な数字やアウトプットイメージを見せながら説明することで、理解を得ることができました。
例えば、若年層向けのキャンペーン企画でVTuberの起用を提案する際、理想を伝えた上で、そのVTuberにどんなことを話してもらえれば企業の魅力が伝わりやすいか、それによってKPIをどう達成できるかを、具体的な数字やアウトプットイメージを見せながら説明することで、理解を得ることができました。
田中:「いけそう」と感じていただけるかどうかが大事ですよね。プロモーションも、未来への投資の1つですから。理想と、数字による現状ギャップの提示、そして具体イメージの3つのポイントはどんな場面でも、誰を相手にするときにも信頼を得られそうです。
Z世代ターゲットのプロモーションを企画・実行する中で、それを推進する企業の課題も見えてきたと言う、若者消費ラボメンバー。後編では、Z世代の間で具体的に最近どのようなことが流行っているのか、そして、それらを分析することで得た知見を生かし、「REVERSE CONSULTING for SUSTAINABILITY」でどのようなことを実現するのか、深掘りしていきます。
Z世代の視点を取り入れた新しいビジネスを成功させるには、「Z世代当事者の目線」と「専門家の知見」をうまく融合させることが不可欠。電通グループは、Z世代の感性やスキル、ビジネス・マーケティングに関する幅広い知見を有しています。話を聞いてみたいという方は、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。