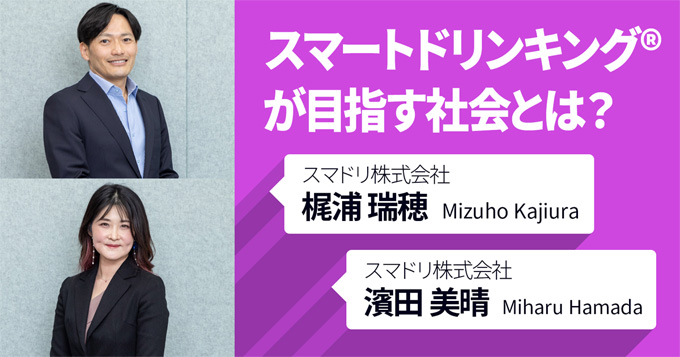マーケティングリサーチなどを通じてビジネス課題の解決に貢献する株式会社 電通マクロミルインサイト(以下、DMI)。同社内の組織である「人と生活研究所」がリリースした『「ありたい、ちょっと先の未来」調査』では、若者世代がマーケティングの中核を担いつつある中、コロナ禍を経たことで、若者世代を含む生活者の価値観や消費行動が大きく変容していることが明らかになっています。
この調査のファインディングスについて「人と生活研究所」和田久美氏へ聞くインタビューの後編。今回は、研究結果から見えてきた未来予測や同研究所が着目する「ウェルビーイング」について聞いていきます。
若者世代ではプラントベースを選択することが「当たり前」に

Q.前編でご紹介いただいた『「ありたい、ちょっと先の未来」調査』のファインディングスの中で「プラントベース(植物由来の原料を使った食品、またはその食品を生活に意識的に取り入れる食への考え方)」というキーワードが出てきましたね。確かに、最近は多くのスーパーマーケットで大豆ミートやオーツミルクなどが販売されるようになりましたが、このあたりのトレンド浸透度については、どのようにお考えですか?
もちろん肉や乳製品も食べますが、その時の気分や体調によっては、プラントベースの食品を選んだり、野菜中心の食生活を送ったり、あるいは家族みんなで食物アレルギーにケアしたメニューを選ぶなど。こうした価値観は、今後ますます浸透していくことが予想されます。
「没入」や「熱狂」がウェルビーイングに寄与する
Q.その他に、Z世代や高感度層が注目しているトピックとしてはどのようなものがありますか。
そのような状況を背景に、今後大きなテーマになってくると予測されるのが「メンタルのモニタリング」です。今後は、メディテーション(瞑想、または精神を集中させる練習をすること)やコーチング・アドバイスなどに代表されるメンタルケアサービスの浸透、そして自分の気持ちや好みに合う商品をAIが提案してくれる「パーソナライズ化」が進んでいくのではないでしょうか。生体データをモニタリングするウェアラブル端末の進化もこれを後押しし、メンタルとモニタリングを掛け合わせたソリューション提案が、2025年に向けて増えてくると考えています。
ちなみにDX化に関して進んでいる国の1つとして、韓国は注目に値するのではないでしょうか。都市部の単身者や共働き世帯を中心に掃除や洗濯、サプリメント、生理用品に至るまで、定期購入サービスが定着している。こういった動きが参考の1つとなって、日本でも今後はさまざまな日用品のサブスクリプションサービスが出てくるだろうと予測されます。
Q.なるほど。ウェルビーイングに対するアプローチも、変化の途上にあるわけですね。ここ2〜3年で「推し活」というワードが一般化したと思いますが、推し活も“オキシトシン的な幸福”と言えるでしょうか。
推し活を含め、コミュニケーションの場は、リアルからSNS、そしてバーチャル空間へと移り変わってきています。特に、若者層・高感度層では、メタバース空間でのコミュニケーションの機会が爆発的に増えていくのではないか、と言われています。例えば、ハンディキャップのような事情があったり、地理的な理由でイベントに参加できなかったりする若者の中には、メタバース空間に対して「活力をもたらしてくれる場所」といった感覚を抱いている人もいるようです。このような背景もあり、2025年頃までに「バーチャル空間でのブースター(没入・熱狂)消費」がキーワードとして広がってくるのではないかと予測されます。
マクロからn=1に迫る部分まで。生活者をストーリーごと理解する
Q.「未来予測」や「Z世代研究」については、さまざまな研究機関がそれぞれのやり方で調査を進めていると思います。「人と生活研究所」では、マクロ環境や世の中の兆候のようなファクトを集めた上で、さらに生活検証を加えて予測の精度を上げていますよね。その点が強みでありユニークネス、ということでしょうか?

そのような分析のベースがあると、例えば「こんなヒット商品がありました」と言われた時に、「世の中の価値観がこのように変わってきたから」「世界的にこういう動きがあるから」と、さまざまな事象を線としてつなげて説明することができます。単なる思い付きではなく、確かな仮説を元にした分析や検証ができるのです。
また、調査の中でさまざまなキーワードや兆しが見えてきたら、未来予測の確度を上げるために、定量・定性調査を重ねて検証するのも、「人と生活研究所」ならではの取り組みだと思います。例えば、20代が多く反応している項目であれば、該当する20代の人を集めて行動観察やディテールドインタビューを行い、インサイト仮説を具体的に補強していきます。このように、マクロからn=1に迫る部分までデータを取りに行く点が、われわれの強みであり、ユニークネスだと思いますね。
「トレンドやデータ収集は行っているけれど、各々がバラバラで構造化できていない」「ファクトの整理が戦略につながらない」。そんな課題に対して、生活者理解を深めるさまざまなアプローチを組み合わせ、さらには次なる戦略策定や商品開発のためのドライバーを提示することまでをカバーするようにしています。
Q.今回ご紹介いただいた『「ありたい、ちょっと先の未来」調査』は、今後も継続して実施されるのでしょうか?
気分や気持ちといった不確かなものをデータで捉え、世の中の動きをいち早くキャッチして、クライアントへのソリューション提案に生かしている「人と生活研究所」。ミレニアル世代やZ世代の「新感覚層」が旧世代の人口に迫り、トレンドが目まぐるしく移り変わる今、従来のやり方が通用しなくなってきたと感じている人も少なくないのではないでしょうか。「人と生活研究所」が提供する研究成果は、そのような課題を解決する一助になり得るかもしれません。
オフライン、リアルな体験が再注目され、人々の嗜好が新たな方向へと舵を切ろうとしている現在。電通グループには「人と生活研究所」を筆頭に、時代の変化に合わせた人々のインサイトを的確に捉え、マーケティングをサポートする知見が取り揃えられています。新しい時代への対応を前に、何から手を付ければいいか戸惑っている担当者の方は、ぜひ下のCONTACTからお問い合わせください。