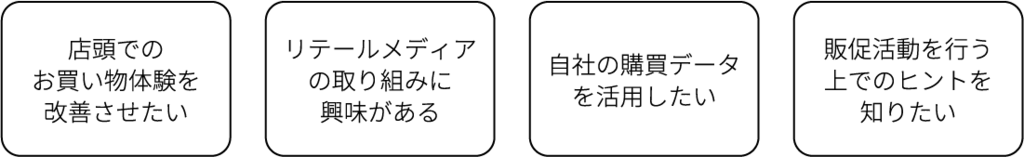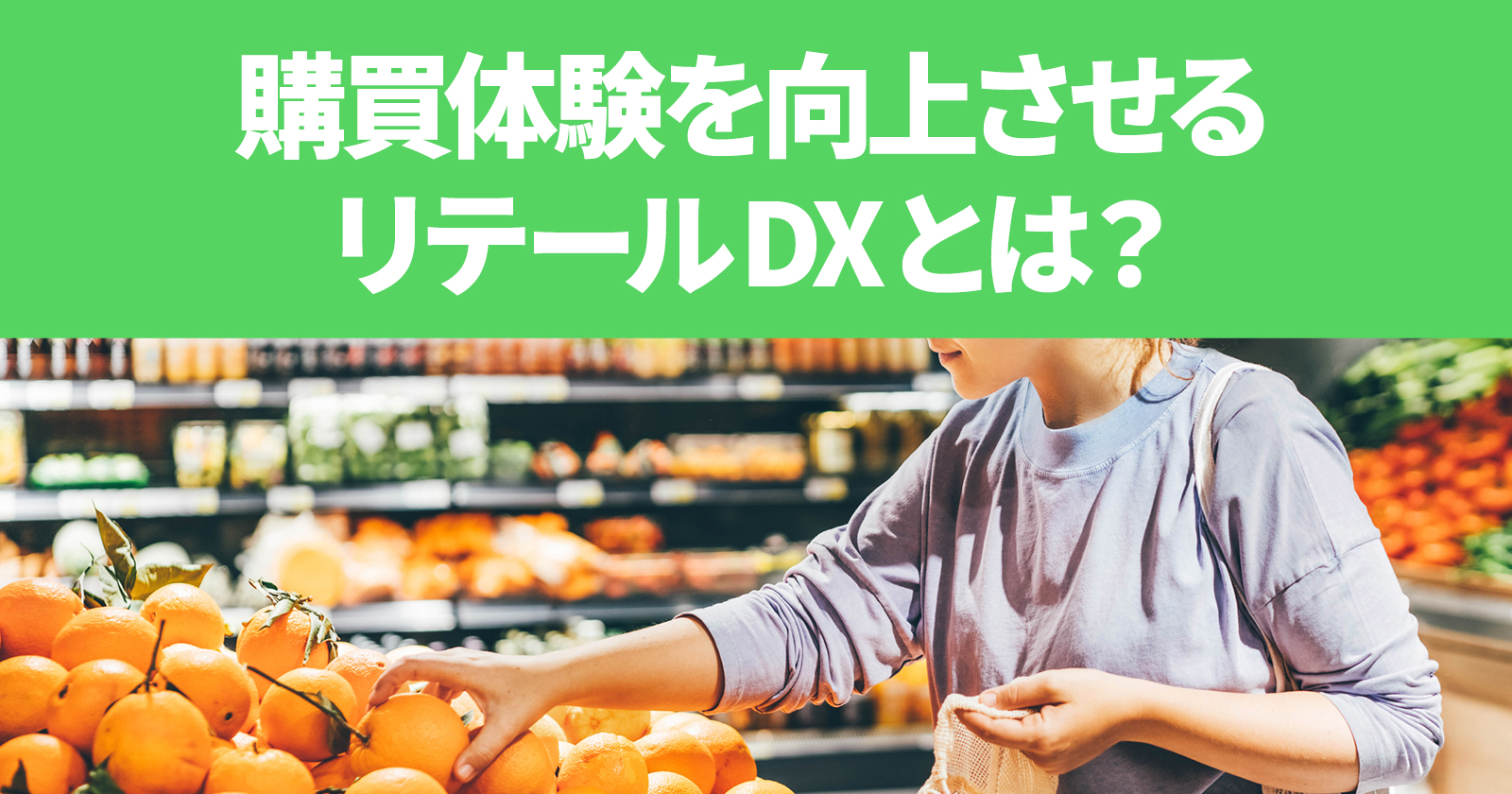小売が持つ購買・行動データなどの1stパーティーデータを活用して、ECサイトのオンライン広告や、店舗内に設置されたサイネージといった媒体を通じて広告やクーポン配信を行う、いわゆる「リテールメディア」の手法が近年注目を集めています。
なぜ今リテールメディアが注目されるのか、その本質的な価値とは何なのか。2022年11月、リテールDXの強化を目的に業務提携した、株式会社電通プロモーションプラスと、リテールテック企業・株式会社フェズ、両社のリテールソリューション担当者が、リテールメディアの現状と、未来について対談しました。
失われたお買い物体験と、高まる購買データ活用の需要
Q.まずは前提となる、ここ数年の小売業界の現状、動向についてですが、コロナ禍以降、リアル店舗の在り方や、生活者の消費行動はどのように変化してきていると感じられていますか。
白銀:コロナ禍で変化したというよりも、それまで内包していた課題が新型コロナウイルスという強制的な外部要因によってはっきり表面化したという印象がありますね。
井本:そうですね。
 株式会社電通プロモーションプラス 白銀 拓氏
株式会社電通プロモーションプラス 白銀 拓氏白銀:お客さまは人口減少で減ってきているし、人手不足だし。そういった課題に対応するには、広い意味でのDXしかないよね、というのは誰もが感じていたことなんですけれど、目の前の課題に追われて、皆さん二の足を踏んでいた。
そこに来たのが、コロナ禍でした。お店に足を運べなくなったことで、リアル店舗の本質的な価値というものに、生活者も、小売企業も、メーカー企業も気付き、DXに取り組むことになったというのが、ここ2〜3年の潮流なんじゃないかなと考えています。
井本:僕も白銀さんと同意見です。人口減少が進む中で、メーカーさんや、小売のバイヤーさんがマーケットを拡大していくためにはどうすればいいかと考えた時に、1つの答えとして「価値ある商品を、価値ある価格で売る」ことを目的に突き進んできたのが、ここ5〜6年の動きでした。
 株式会社フェズ 井本 悠樹氏
株式会社フェズ 井本 悠樹氏井本:ところが、コロナ禍で、人々がお店に行かなくなった、購買頻度も滞在時間も減った。試食もテスターもなくなり、お買い物体験が悪化していく中で、それでも店頭で価値訴求をしていくにはどうすればいいかが、大きな課題となっていった。その課題に対する1つの分かりやすい手法が「デジタル活用」であり、近年盛り上がってきている「リテールメディア」だったんだと思います。
白銀:弊社でもここ数年、クライアントさまから自社で蓄積した情報資産の活用を、本格的にやっていきたいというオーダーを多数いただくようになり、まさにリテールメディアで必要となる購買データ活用に対するニーズの高さを、肌で感じていたところでした。
リテールメディアが小売とメーカーの共通認識を生み出す
Q.購買データ活用がこれほどまでに求められる理由は何なのでしょうか。
白銀:例えば、僕がある店で某社のミネラルウォーターを20本、1カ月の間に買っていたとしますよね。となると、この人は次の来店時にも同じ水を買うだろうということが容易に想像できるわけで、メーカーさんとしては、僕に対して今後どのようなコミュニケーションをしていけばいいのか、具体策がおのずと導かれていきます。というように、1つのIDにひも付けて生活者の購買行動を把握できるということは、マーケティングの設計をする上では有無を言わさぬ強い武器となるわけです。

井本:そういう意味では、購買データを活用したコミュニケーションは、圧倒的に「効率がいい」と言えますよね。メーカーさん側の観点となりますが、原油高、原材料高、円安といった苦境に見舞われる中、ボトムラインを守るために、どうしても削られがちなのが広告費。そうなると、メーカーさんとしても、いかに効率良く広告を打つか、いわゆるROI(投資利益率)を上げることが命題となりますから、購買データの活用が求められる一因かと思います。
白銀:効率化という視点はまさにおっしゃる通りですね。これまではというと、まず広告を打って、お客さまに来てもらったところを刈り取るというフォアキャスト的な発想でマーケティングが設計されてきたのですが、どちらかというと、今効率がいいとされているのは、マーケティングファネルでいうところの購買の部分から逆算してマーケティングを設計するバックキャスト的なやり方。そのバックキャストの起点となる「購買」のデータに関心が集まるのは、自然な流れと言えるでしょうね。
井本:もう1つ、メーカーさんの視点からデータ活用が注目されるようになった背景としてあるのは、ここ1〜2年で、ECサイト上での広告運用と同じことが、オフラインでもできるようになってきたということ。メーカーさんのEC化率は6~7%、コロナ禍以降でも8%と、オフラインビジネスが圧倒的に主流なので、ここにリテールメディアの手法がハマったんだと思います。
白銀:加えて、昨今のCookie規制の流れにも触れておきたいですね。従来の3rdパーティーデータを活用したWeb広告の手法が通用しなくなっていくという未来が待っている中で、小売企業が持たれている1stパーティーデータに注目が集まっているというのも、特に個人情報保護の意識が高い海外に関しては購買データ活用に関心が持たれる大きな要因となっています。
Q.そういった小売が持つ1stパーティーデータを活用した「リテールメディア」の手法が昨年から注目を集めているわけですが、小売側からすると、自社のデータを開放することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
井本:もちろんデータを提供することが営業外収益につながるというメリットはあるのですが、それよりも小売さんが期待しているのは、お客さまに対して的確な商品情報を提供できるようになることで、お買い物の機会ロスを減らす、といったような、カテゴリーマネジメントへの活用だというふうに、僕は捉えています。

白銀:そうですね。それに付け加えるとすると、僕がリテールメディアの本質的なメリットだと感じているのは、小売さんとメーカーさんが、お買い物をするお客さまに向けて共にメッセージを送れる、ということなんです。というのも、これまでは小売さんとメーカーさんって分断されていたというか、店舗の売り上げを上げなければいけないバイヤーさんと、自分たちの商品を何とか棚に置いてほしいメーカーさんとで、ある種の敵対的緊張感があったと思うんですよね。
でも、店舗に来店され商品を買ってくださるお客さまは、小売・メーカーどちらにとっても本質的な顧客であることには変わりないので、このお客さまの体験価値をどう上げていくかという最終ゴールに向かって、一緒に販促活動をした方が絶対に効率はいいはずなんですよ。リテールメディアは、それができるツールですし、そのツールを通じて小売さんとメーカーさんが共通認識を持てるのが、リテールメディアの本質的な価値なんじゃないかと思います。
細分化された小売を横断した取り組みができるか
Q.リテールメディアの国内・海外動向についてお聞きできますか。
白銀:日本のメガ流通企業の1つであるセブン‐イレブン・ジャパンさんが2022年9月に「リテールメディア推進部」を立ち上げて、社としてリテールメディアに取り組んでいく姿勢を見せたというのが印象的でした。日本にもいよいよ波が来たという、シグナルのような出来事だったかと思います。
井本:具体的なトピックではないのですが、メーカーさんとお付き合いする中で感じるのは、ここ2年くらいの日本国内のトレンドとして、小売さんに対するマーケティングの予算を持つ企業さんが増え始めているな、という印象はあります。

白銀:一方で、海外動向に関しては、やはり世界でも大きく先行しているのはアメリカなので、リテール事業においてはアメリカの動向をチェックすることは必須となってきます。しかし、気をつけなければいけないのは、生活者の購買行動は日本とアメリカでは全く違うということです。日本はいわゆる狭小商圏ビジネスであって、安心安全を求めるため、生活必需品のお買い物は9割がリアル店舗で行われているのが実態なんです。なので、日本のリテールビジネスに適したリテールメディア運用というのを、しっかりやっていかないといけないとは思っています。
井本:マーケットの違いという点には、僕も今思考を注ぎ込んでいるところでして、リテールメディアの観点からすると、日本のマーケットと、アメリカのマーケットの大きな違いは、小売さんがどれくらい細分化されているかということなんですよ。例えばアメリカのフードリテールは、マーケットのうちウォルマートが25%を占め、その次のクローガーは12〜13%で、この2社だけで40%近くにもなります。つまりより多くのお客さまを内包できるということで、メーカーさんとしては、会社ゴト化してリテールメディアを動かすだけの価値を感じられます。

井本:かたや日本は小売さんがたくさんいてマーケットが細分化されている状況なので、1個のリテールメディアを構築してもリーチできるお客さまが少なく、メーカーさんとしても、なかなか1つの小売さんに向けた「販促施策」の枠組みを抜けられず、会社ゴト化しにくいという課題がある。なので、細分化された小売さんたちをつなげて、いかに規模感があり、拡張性・汎用性のあるリテールメディアにしていくか、というのが今後一層求められてくるでしょうね。
白銀:まさに僕も同じことを今日言おうと思っていたのですが(笑)、いや、本当にその通りで、だから僕らの本質的なチャレンジというのも、本来であれば競合同士の小売さんたちをいかにつなげていけるかということ。これが勝負だなと思っていて。それこそが、今回フェズさんと僕らが手を携えた大きな理由でもありますしね。
井本:ええ。
白銀:リテールメディアの進展によって今後リテールビジネスも、狭い範囲でお客さまを取り合うっていう構図から、もうちょっと大きなエリアマーケティングのような考え方におそらく変わっていく。その地域内での生活者のお買い物体験をどう豊かにしていくか、という動きに自然と集約されていくと思うんですよ。
井本:まさに、その通りですね。

白銀:ちなみに、日本とアメリカの違いという点でお聞きしたいことがありまして、日本ではお買い物の際に、店頭でアプリを見ながらお買い物をするという習慣はまだ少ないのかなと思っていて、ここはリテールメディアとして1つの課題ではないかと感じているのですが、井本さんはどう思われますか?
井本:確かに、店頭でアプリを見ながらお買い物をするという習慣はあまりないかもしれません。ただ実際のところ、アプリの利用はすごく増えてきていますよね。コロナ禍で「目的買い」が増えたことで、事前に小売さんのサイトを見たり、メーカーさんのSNSをチェックしたりといった下調べが一般化してきているんです。なので、店頭でアプリを活用してもらうだけに限らず、例えば事前の情報収集としての活用を促進することで、アプリを店頭での購買動機につなげるなど、日本なりの効果的な方法があるのではないかと僕は思っています。
Q.最後に、今回、電通プロモーションプラスがフェズと業務提携をするにあたって、お互いに期待されていることを教えていただけますか。
白銀:やはり圧倒的な数の購買データをお持ちであるということは大きな魅力ですよね。それに加えて、今フェズさんが力を入れて取り組んでおられるという、購買データから、その人の行動DNAのようなものを抽出して、このブランドにとって本当に親和性の高いお客さまってどういうお客さまなんだろうということを分析、アプローチしていくという、まさにバックキャスト型のマーケティングというものを、一緒にやらせていただきたいと思っています。
井本:ありがとうございます。われわれの側としては、マーケティングファネルの中に、いかにショッパーメディアを入れ込んでいくかというチャレンジを、ご一緒できるのではないかという期待感もあります。例えば、店舗にあるサイネージって、ある種のショッパーメディアだと思うんですけど、これってまだまだ小売さんのメディアにとどまっていて、マーケティングメディアとしての活用はなされていないと思うんです。ブランド側が期待している広告メディアとしての価値が生まれていない。そこで、電通プロモーションプラスさんが持たれているショッパーメディアの知見と、われわれの持っている購買データを融合させることで、フルファネルで、ショッパーメディアも融合させたような大きなソリューションを描けるのではないか、そう思っています。
白銀:ぜひ、やりましょう!今日はどうもありがとうございました。

これからの日本のリテールビジネスのカギとなるのは、細分化された小売を横断し、より多くの生活者を内包したリテールメディアを構築するという挑戦。その実現に向けた取り組みの第1弾として、電通プロモーションプラスとフェズは2023年2月から、放送局や小売企業と連携し、テレビと店舗の売り場が完全に連動したエリアマーケティングの施策を展開していきます。
お買い物体験の向上という意味では、生活者の側からも期待が持てるリテールメディアの取り組み。今後ともリテールメディアの動向、データ活用した新しいリテールDX施策に注目です。
本記事で取り扱った話題以外でも、下記のような疑問や課題、ニーズをお持ちであれば、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。
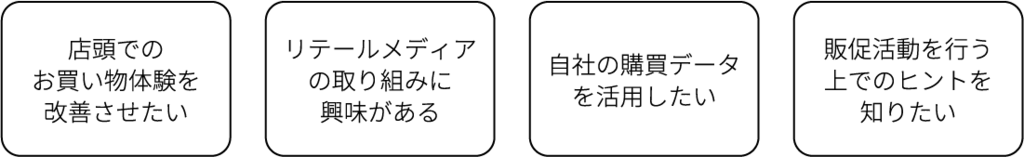
※ プロモーショントレンドメディアBAEは、世の中の潮流、最新テクノロジー、クリエーティブ領域などのプロモーションのヒントになる情報を配信しています。
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。