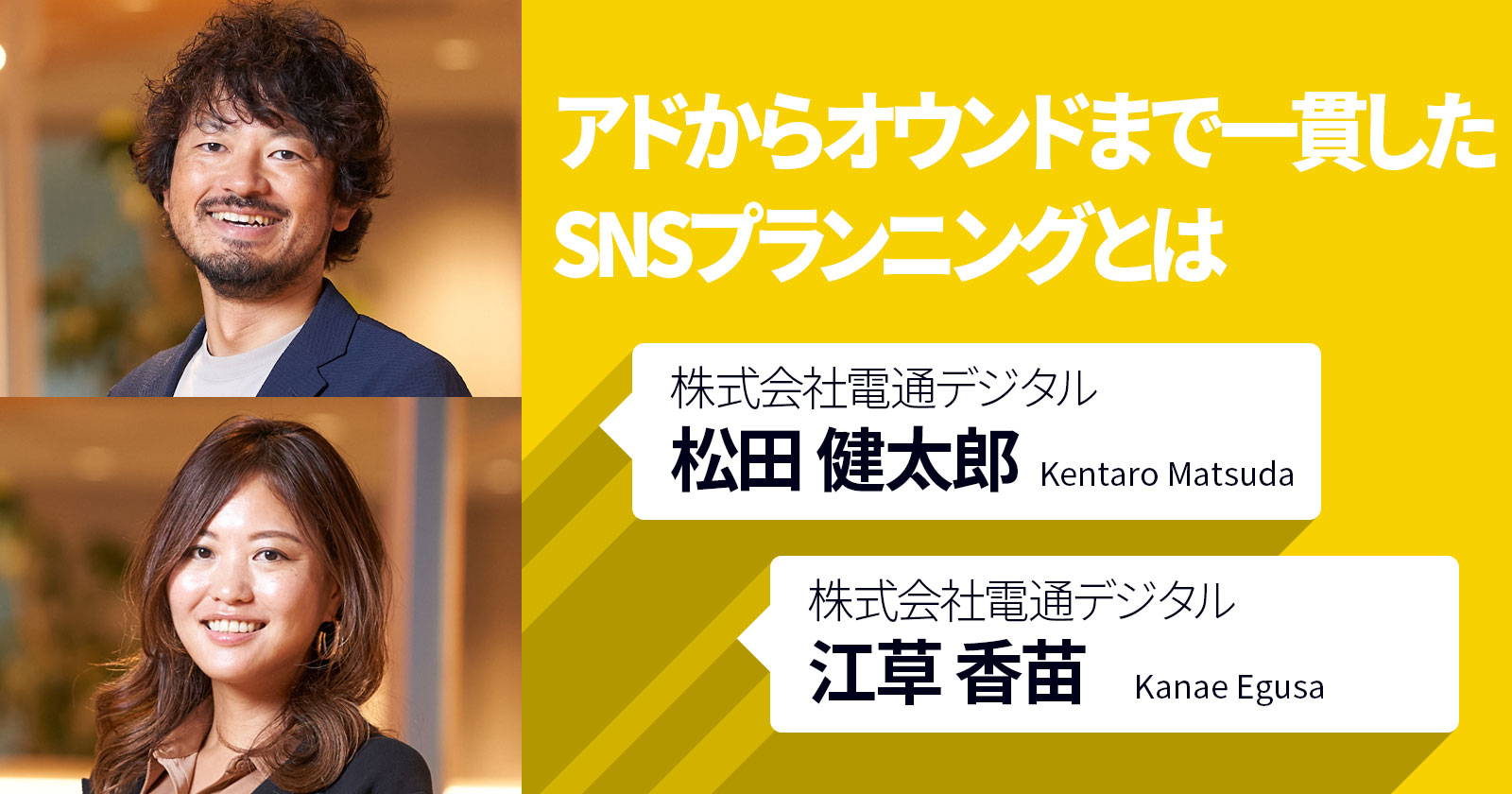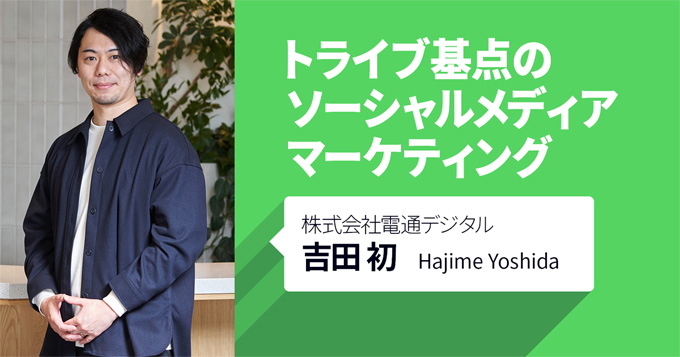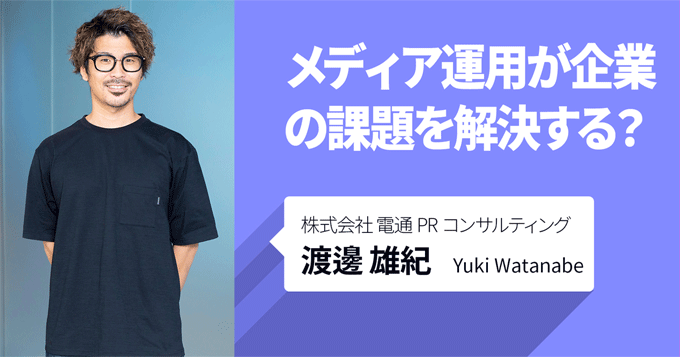企業にとって、Instagram、X(旧:Twitter)、TikTokなどのソーシャルメディアを活用したマーケティングは今や欠かせないものになっています。とはいえ、「SNS広告で商品・サービスの認知は広がったものの、自社のファンは増えない」「ブランディングがうまくいかない」といった悩みを抱える企業も多いようです。
こうした中、2023年1月、株式会社電通デジタルに「Social Connect Group」が発足しました。同チームでは「ソーシャルメディアにおけるアドとオウンドの接合」をテーマに、企業のSNS活用をトータルでサポートしています。
本記事では、「Social Connect Group」の中核メンバーである電通デジタルのプランナー・江草香苗氏と、ソーシャルメディアのプラットフォーム各社と向き合う電通デジタルの松田健太郎氏にインタビューを実施。このチームが誕生した背景や、独自の強みなどを前後編の2回に分けてお届けします。
分断されがちなSNSのアドとオウンドをつなぐ
Q.まず、「Social Connect Group」とはどのような組織なのか説明をお願いします。

Q.SNS領域のアドとオウンドをつなぐと言っても、これまでどこに問題があったのか、なぜつなぐ必要があるのかと疑問を抱く方も多いと思います。クライアント企業さまのどのようなニーズに応えるためにこの組織を立ち上げたのか、背景を教えていただけますか?
その一方で、クライアント企業さまの中でも、アドとオウンドとでは領域や担当者が異なり分断されている、というケースもよくあります。そこで、電通デジタルではアドからオウンドまで一貫したプランニングができる組織として「Social Connect Group」を発足したのです。
Q.SNS広告から新規ユーザーが流入してきても、そういった方々の期待に応える情報やコンテンツをオウンドで提供できていないケースが多いのでしょうか。
最近のユーザーは、SNSを何かしらチェックしています。そこで認知を広げても、さらにファンになってもらうための動線が明確に引けていない企業さまも多く存在しています。その一方で、各マーケティング企業も「Instagramが得意」「TikTokが得意」と、それぞれ得意なプラットフォームが違います。そのため、ソーシャルメディアの垣根を越えたコミュニケーション設計や、各SNSに最適化したプランニングを行えるチームがあれば、きっと多くのクライアント企業さまのお役に立てるだろう、と見えていたので、それをチームのミッションと定めました。
SNS広告は企業のファンを育てるブランディングにつながる
Q.松田さんは、チームの中ではどの領域を担当しているのでしょうか。

ソーシャルメディアは本来ユーザー同士がコミュニケーションを取る場であり、企業とのつながり方もプラットフォームによって異なります。そこに広告を発信すれば、商品やサービスの認知はされますが、そこから先につながっていくためには、それぞれのソーシャルメディアならではのコミュニケーションスタイルがあります。しかも最近は、1人のユーザーがSNSごとにいろいろな人格を使い分けている傾向にあり、それぞれのSNSで最適なアプローチを行うには、プランニング寄りの発想が必要です。だからこそ「Social Connect Group」のように、アドとオウンド、双方の知見を持つ部署の連携が不可欠だと考えています。
Q.前にも触れましたが、クライアントとなる企業さまの中には、アドとオウンドで担当者が違うケースも多いのではないかと思います。そうなると、クライアント企業さま側においても、これまで以上に連携が必要になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
さらに言えば、そもそもソーシャルメディアの使い方に悩んでいる企業さまはたくさんいます。「アド計画を見直したい」「オウンドの集客が弱い」など、さまざまな立場での課題に対し、入り口を示す役割も果たしていきたいです。
Q.アドを強化した先に、オウンドメディアの改修が必要になるケースもありそうです。とはいえ、そこまで大掛かりになるとは想定していない企業も多いかもしれませんね。全体のコンセプト設計を見直す必要があると、いかにご理解いただけるかがカギになりそうです。
とあるSNSで広告を見たユーザーが、これいいな、と思ってアクセスしたら、その先のオウンドメディアは全然雰囲気が違っていて、気持ちが下がってしまってすぐ離脱した。あるいは、アドで気になった商品が、オウンドではどこにあるかすら分からず、探しているだけでイライラしてくる。そんなケースは結構あるのではないでしょうか。こうした齟齬を防ぎ、ソーシャルメディアを最適な形で活用するとともに広告効果を最大化するのが「Social Connect Group」の役割だと分かってきました。後編では、電通グループならではの強み、今後の展望について話題を広げていきます。
電通グループは、企業のソーシャルメディア活用について豊富な知見を持っています。SNS運用にお悩みを抱える企業の方は、ぜひCONTACTよりお気軽にお問い合わせください。