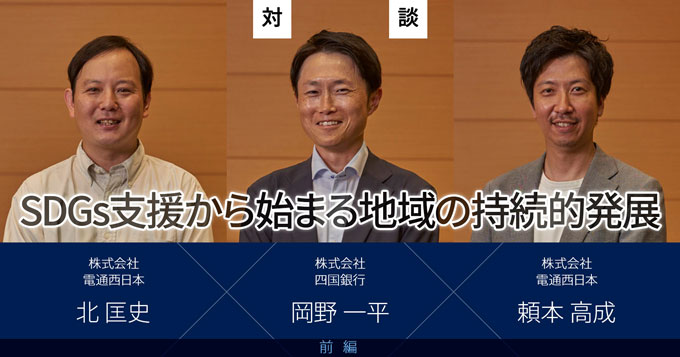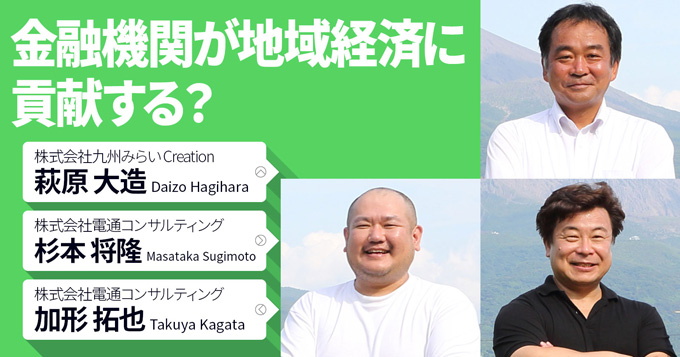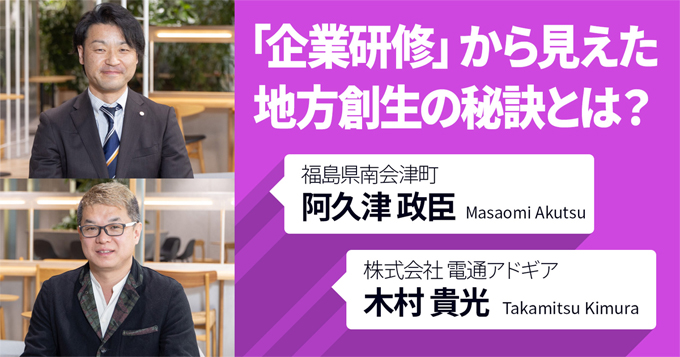地域の持続可能な発展を目指す取り組みが注目を集めています。Transformation SHOWCASEでは、エリア特性を生かした独自のビジネスモデルの構築や、エリア経済の活性化に資する活動事例を紹介する連載をスタートします。
第1回として取り上げるのは、2020年に始動した金沢大学とdentsu Japan(国内電通グループ) による産学連携プロジェクト。このプロジェクトでは、金沢大学の学生や地元企業と協力して地域課題を解決する新たなアイデアを生み出し、その社会実装に挑戦しています。
今回は、プロジェクトを推進する金沢大学の堤敦朗教授、株式会社 電通西日本 北陸支社の広松京子氏、株式会社 電通 BXクリエイティブセンターの森口哲平氏にインタビューし、地方創生に産学連携で取り組む意義や、地域のより良い未来を実現するために必要なアプローチについてご紹介します。
アカデミアとの協業。産学連携でデザインするエリア経済活性化 とは Q:最初に、金沢大学とdentsu Japanが協業し、産学連携プロジェクトを始めた経緯についてお聞かせください。
堤: 私が身を置くアカデミア(研究職)の世界では、社会課題は“暗い話題”として捉えられがちです。もちろん真面目に向き合うことは大切ですが、だからといって面白さや遊び心が欠けてしまうと、閉じられた世界のままで広がりを生み出せないのでは……という課題感を持っていました。
金沢大学 堤 敦朗氏 広松: その後、2020年に産学連携プロジェクトを始動させ、最初は地方の社会課題をテーマに金沢大学で授業を行い、学生たちに課題解決のアイデア出しやプレゼンテーションをしてもらうところからのスタートでしたね。
森口: 私は、2022年に金沢大学に融合学域観光デザイン学類が新設されたタイミングで、先輩社員に誘われて学内で実施されたワークショップに参加しました。そこで堤先生や広松さんと出会いまして、当該学部の1年生向けの「アントレプレナー基礎講座」に講師として招いていただき、産学連携プロジェクトに関わるようになりました。
Q:その観光デザイン学類は、具体的にはどのような学問分野を扱っているのですか?
堤: 「観光」には、人を呼び込むためのマーケティングや優れたホスピタリティの追求などさまざまな側面があります。観光デザイン学類では、新たな観光産業や地域の仕事を自ら生み出し、社会変革につなげるマインドセットを持った人材育成を目標としています。ビッグデータ解析などを経て、社会科学と自然科学を組み合わせる“文理融合型の学びの場”であることも特長です。
森口: 電通としても、これまでマーケティングや広告コミュニケーションの分野で培ってきたクリエイティブの力を、事業開発やブランドづくりへ広げていきたいと考えていました。観光デザイン学類が扱う領域と私たちの目指す方向性には、共通する部分が多くありますね。
Q:ビジネスの観点から見て、アカデミアと協業することの意義はどこにあるのでしょうか?
森口: 市場が成熟して豊かになった現代では、企業がユーザーのニーズに応えるのはますます難しくなっています。言い換えると、企業やブランド側が、商品やサービスを新しく出さなければいけない明確な理由が必要とされているのではないかと思います。一方でこうした地域それぞれの社会課題に目を向けると、そこには人々の抱える「痛み」が明確にある。それに寄り添って、そこにこそ「理由」を見つけていくことこそがこれからのビジネスの核になっていくと思います。
学生の発想を生かした、地域課題解決型のビジネスデザインとは Q:産学連携プロジェクトで取り組んでいる具体的な事例について教えてください。
株式会社 電通西日本 広松 京子氏 広松: 最初の本格的なプロジェクトとして始めたのが、2021年に金沢大学、電通西日本、地元テレビ局が共同で立ち上げた「ソーシャルデザイン北陸」です。地元企業と連携した特別講座を開講し、学生のアイデアを社会実装することに挑戦しています。
堤: また、直近のプロジェクトとしては、2024年に「観光プロジェクト演習」を開講しました。使われていない蔵を宿泊施設にリノベーションする「The Bath & Bed Team」(電通と株式会社エンジョイワークスの協業プロジェクト)と、金沢大学が共同で開設したカリキュラムで、街とつながる観光ビジネスについて実践的に学ぶ場となっています。
森口: 金沢は観光地として知られていますが、他の地方都市と同じく、遊休不動産が多く存在していて、蔵もいくつも存在します。それらを活用し、旅行者と街の有機的なつながりやその土地ならではの体験を生み出す仕掛けとして、学生たちとともに宿泊施設づくりを進めています。
株式会社 電通 森口 哲平氏 Q:こうした取り組みに対して、学生からの反応はいかがですか?
堤: 「社会課題について考えて終わり」ではなく、実際に行動に移せるのが面白いという声は多いですね。
Q:一方で、地元企業にとって学生と協働するメリットはどんなところにあるでしょうか?
広松: 現在、地方企業では人材確保に苦戦している企業も多いと伺っています。学生と協働しながら社会課題に取り組むことで、企業が自らの姿勢やソリューションを学生に直接アピールできる点は大きなメリットになると考えています。
地域が輝く、より良い社会を構築していくために Q:産学連携プロジェクトが始まって今年で5年目、プロジェクトを進める中での気付きや今後の課題がありましたらお聞かせください。
堤: 地域活性化は一筋縄ではいかない、というのが率直な感想です。特に産学連携となると、企業と大学、それぞれの組織が持つミッションや優先事項が異なる点に難しさがあります。企業は収益性を重視しなければならないし、大学は研究や教育への貢献が大前提になる。地域活性化という共通テーマを持って集まったとしても、それぞれの目的を達成するための最適解を見つけることの大変さを実感しています。それでも今回、大学と企業が共同で授業を開講するという、これまでにあまり前例のない産学連携の形を実現できたことは大きな一歩でしたね。
Q:産学連携プロジェクトの今後の展望については、どのように描いていますか?
堤: 今メインで進めている「The Bath & Bed Team」では、金沢にある蔵の候補を見つけて宿泊施設として再生し、プロジェクトに参加してくれた学生たちにとっての1つの成功体験をつくることが具体的な目標となっています。一方で、地域活性化は長期的な取り組みなので、あまり短期的な成果ばかり追い求めず、継続していくことを大切にしたいです。10年経ってようやく目に見えてくる変化もあるはずですから。
The Bath and Bed teamによる蔵のリノベーション例(The Bath and Bed Hayama) 森口: 大都市圏で生まれた事例を地方にあてはめるのではなく、地方ごとにカスタマイズして考えることの重要性を今回のプロジェクトで、強く感じました。リアルな課題に直面する地方でこそイノベーションは起こる。それを証明できるよう、地域に根を張り、地域独自の産学連携の成功事例を1つでも多く生み出していきたいです。
ビジネスを考える上で、地域の社会課題に目を向け、解決に向けて取り組むアプローチはますます重要に。産学連携の取り組みからは、大学が持つ専門性や若者ならではの視点、企業が持つクリエイティブの力が組み合わさることで、地域課題をより面白く、多角的な視点で解決に導ける可能性が見えてきました。そのためには、教育機関と企業の両者がフラットな関係を築き、困難を率直に共有しながら、お互いの経験や知見を生かすことが成功のカギと言えそうです。
dentsu Japan(国内電通グループ)では、地域経済活性化を目指した取り組みをさらに強化しています。地域課題の解決や地方でのビジネスの可能性を模索中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。